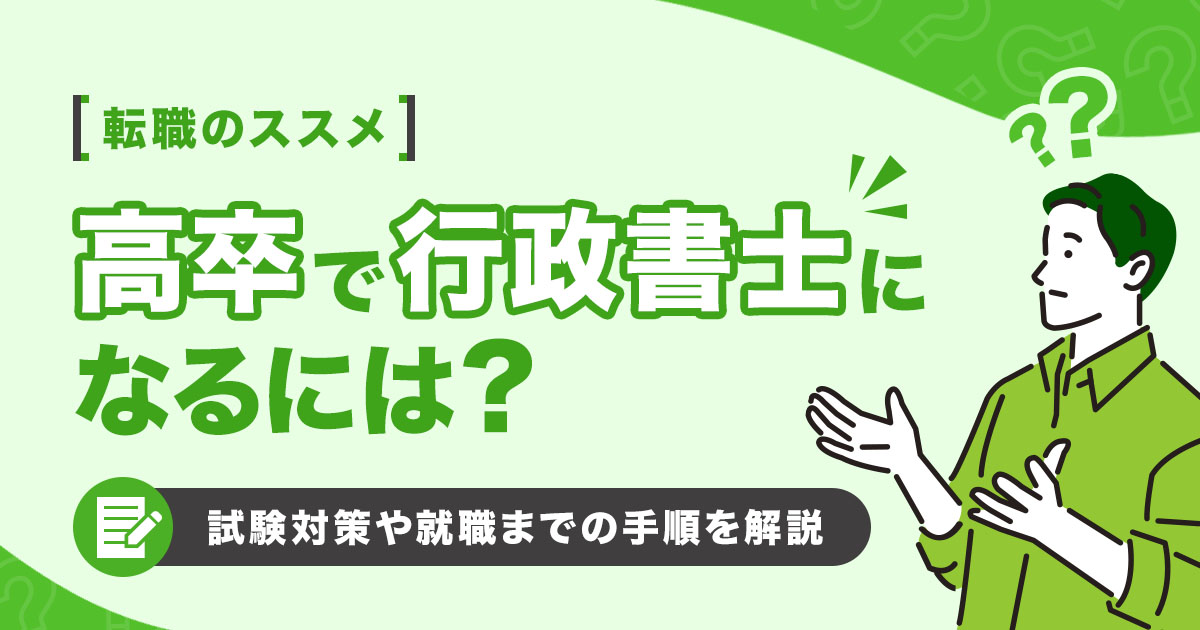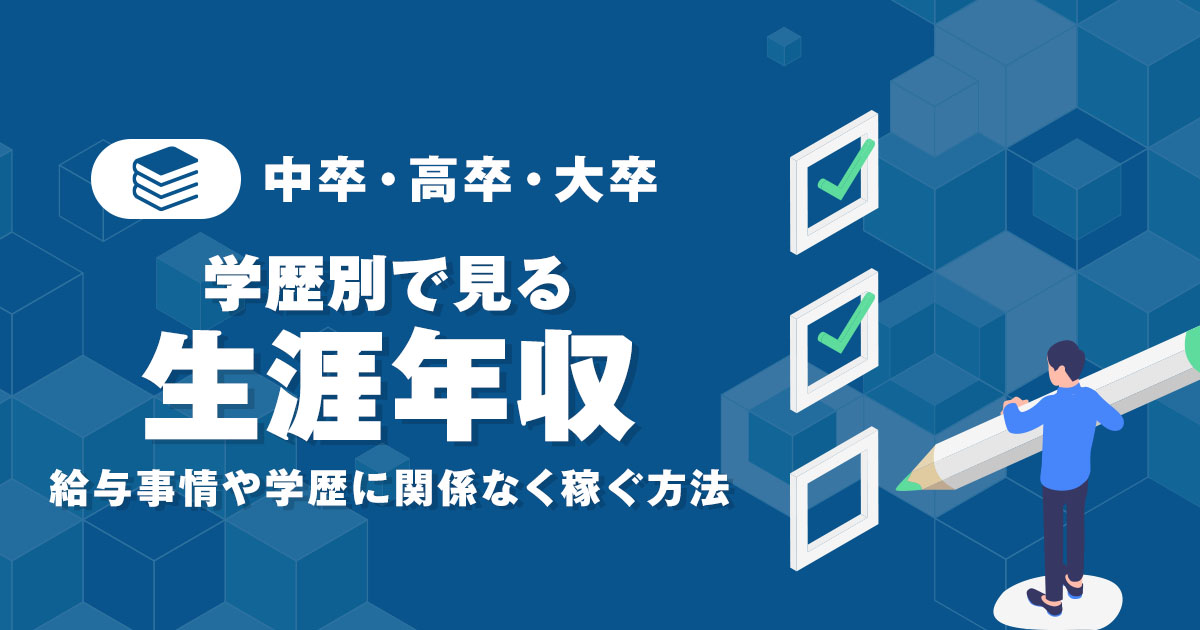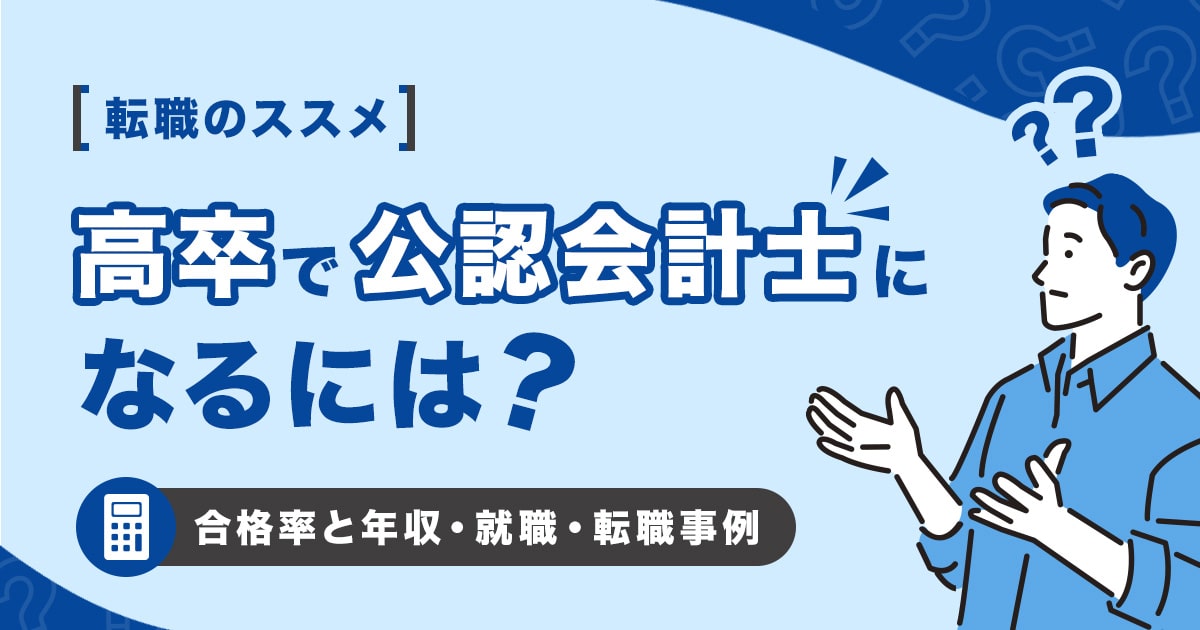-
高卒で行政書士になれる?
-
高卒が行政書士の資格に合格できる方法が知りたい
行政書士は学歴に関係なく、高卒も自分の努力次第でチャンスをつかめる職業です。実際に高卒で行政書士として活躍している人もいます。
この記事では、高卒で行政書士になるための条件や手順、効果的な試験対策法、合格後のキャリアパスなどをわかりやすく解説します。
手に職をつけて自分の力で未来を切り拓きたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
高卒で行政書士になれるが学歴以外の条件がある

高卒で行政書士になることは可能です。
高卒が行政書士になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 行政書士試験に合格する
- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持っている
- 公務員として行政事務に17年以上従事して「特認制度」を利用する
この中で、高卒の方にとって最も現実的なのは、1つ目の「行政書士試験に合格する」ルートです。
試験に合格して国家資格を取得する必要がありますが、その他の条件は、いずれもさらに難関の国家資格や公務員としての実務経験が求められるため、より多くの時間と労力がかかります。
もちろん、行政書士試験も決して簡単ではありませんが、しっかりと対策をすれば高卒も合格を目指せます。そのため最短かつ実現可能なルートとして多くの人に選ばれています。
行政書士の学歴内訳

行政書士試験は学歴不問で受験可能ですが、実際に合格している人たちの学歴が気になる方も多いのではないでしょうか。
行政書士の学歴内訳は以下の通りです。
| 学歴 | 割合 |
|---|---|
| 高卒未満 | 0.0 % |
| 高卒 | 5.6 % |
| 専門学校卒 | 3.7 % |
| 短大卒 | 1.9 % |
| 高専卒 | 0.0 % |
| 大卒 | 87.0 % |
| 修士課程卒(修士と同等の専門職学位を含む) | 0.0 % |
| 博士課程卒 | 0.0 % |
| わからない | 13.0 % |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「行政書士」(参照 2025-7-15)
※全てを足しても100%になるとは限りません
大卒者が圧倒的に多いものの、実際に高卒で合格している人はいるので、努力次第で合格できる可能性は十分にあります。
高卒で行政書士になる手順

先述の通り、高卒で行政書士になるには、主に下記の3つの方法があります。
- 行政書士試験に合格する
- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持っている
- 公務員として行政事務に17年以上従事して「特認制度」を利用する
ここでは、高卒で行政書士になる人が最も選んでいる「行政書士試験に合格する」ルートに絞り、合格を目指すための具体的な手順を解説していきます。
手順①行政書士試験に合格する
行政書士試験は年齢・学歴・国籍を問わず、誰でも受験することができます。
試験のスケジュールと概要は以下の通りです。
| 試験要項の発表日 | 7月初旬 |
| 受験の申込期間 | 7月下旬から8月下旬 |
| 試験日 | 11月の第2日曜日午後1時から午後4時までの3時間 |
| 合格発表日 | 翌年の1月下旬 |
| 試験形式 | 筆記試験(全60問)①マークシートによる択一式②記述式 |
| 試験会場 | 全国47都道府県(どの試験場でも受験可能) |
| 受験手数料 | 10,400円 |
行政書士試験は例年、上記のスケジュールで実施されています。
年に1回しか試験がなく、試験の難易度も高いので、計画的に対策をすることが合格への近道となります。
参考:一般財団法人 行政書士試験研究センター「試験の概要」(参照 2025-7-15)
手順②行政書士会に入会し名簿登録を受ける
行政書士試験に合格しただけでは、行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士として仕事を始めるには、各都道府県の行政書士会に入会し、日本行政書士会連合会の名簿に登録される必要があります。
登録の流れは以下の通りです。
- 行政書士会に申請書を提出する
- 独立開業する場合は、都道府県の行政書士会による現地調査を受ける
- 日本行政書士会連合会による審査を受ける
審査に通過すると、行政書士証票が交付されます。
これらの手続きを経て初めて行政書士としての資格が公的に認められ、正式に行政書士として活動を開始することが可能になります。
高卒で行政書士になるための試験対策

難関試験である行政書士試験に合格するには、出題形式に合わせた入念な対策が欠かせません。
ここでは、試験範囲を効率良く学習するための具体的な勉強法について解説します。
以下の各項目を参考に、着実に準備を進めていきましょう。
- 勉強のスケジュールを計画する
- 5肢択一式や選択式問題の学習を行う記述式問題の学習を行う
- 過去問を使って繰り返し知識を定着させる
- 模試を活用して本番演習を行う
対策①勉強のスケジュールを計画する
まずは、試験の出題内容や現在の自分の実力を把握し、学習スケジュールを立てましょう。
行政書士試験は以下の科目から出題され、問題数は全部で60問あります。
| 行政書士の業務に関し必要な法令等(全46問) | 憲法、行政法、民法、商法、基礎法学 |
| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(全14問) | 一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解 |
試験範囲が広いため、月単位・週単位で細かく目標を決め、自分にとって無理のない範囲で継続して勉強することが重要です。
また、全ての科目が同じ割合で出題されるわけではないので、最初は最も配点が高い「行政法」と「民法」から重点的に取り組むのがおすすめです。
行政法は暗記中心、民法は理解中心で基本的な知識を定着させてから、出題形式ごとの対策をしていきましょう。
対策②5肢択一式や選択式問題の学習を行う
科目ごとの基礎知識を学んだら、5肢択一式問題や多肢選択式問題の対策をしましょう。
特に、1問につき5つの選択肢の中から最も適切なものを選ぶ5肢択一式問題は、全体の得点に大きく影響するため、最初に重点的に取り組むのがおすすめです。
主に行政法や民法といった法律分野から出題され、正確な知識と判断力が求められるので、基礎から丁寧に理解を深めておくことが重要です。
また、多肢選択式問題は、複数の選択肢から正しいものをすべて選ぶ形式で、文章の読解力や正確な知識が求められます。出題は行政法と憲法に限られており、各分野で1問ずつ出題されます。
まずは基本知識をしっかり固めたうえで、問題文を丁寧に読み取る練習を行いましょう。
対策③記述式問題の学習を行う
記述式問題は、主に民法や行政法の条文・判例をもとに、論理的に答えを組み立てる力が求められます。
かなり配点が高い分野なので、しっかり対策をしておく必要があります。
記述式は、5肢択一式問題や多肢選択式問題などの択一式の学習範囲から出題されるため、択一式の勉強が一段落したタイミングで始めるのがおすすめです。
まずは参考書や過去問を確認しながら、頻出テーマや出題形式に慣れましょう。
また、短く簡潔に要点を押さえて記述する力を養うことが、記述式対策のカギです。模範解答と自分の文章と照らし合わせて改善していく練習を重ねましょう。
対策④過去問を使って繰り返し知識を定着させる
過去問を活用すると、試験の出題傾向や学んだ知識が定着しているかどうかを把握できます。
「参考書の内容が実際の試験でどのように出題されるのか」「各科目をどこまで勉強すれば良いのか」がわかるので、学習が一通り終わってから使うのではなく、基礎知識をインプットしながら解いていくのがおすすめです。
参考書で知識をインプットさせたら、過去問で都度アウトプットを行い、知識を定着させていきましょう。
また、間違えた問題は重点的に解説を読んだり、参考書や条文で該当部分の知識を再確認したりするといったインプットに戻り、しっかり定着するまで反復学習をするのが重要です。
対策⑤模試を活用して本番演習を行う
模試は、試験本番で実力を発揮するための演習として非常に有効です。
模試を受けることで、試験本番の雰囲気や現時点での自分の弱点が明確になります。問題を解く順番や各科目にかける時間を意識し、本番のシミュレーションをしてみましょう。
また、模試は学習の方向性を修正する指標としても役立ちます。模試の後は必ず復習を行い、間違えた問題の原因を分析したり、学習スケジュールを見直したりするのがおすすめです。
さらに、本番に近い環境で緊張感を持って取り組むと、心の準備にもつながります。何回か受験して試験に慣れておくと、合格へつながりやすくなるでしょう。
高卒で行政書士になったあとのキャリアプラン

行政書士は法務事務所・弁護士事務所といった士業事務所に就職して「使用人行政書士」として活躍する道もあれば、行政書士になる過程で得た知識やスキルを活かして一般企業で働く道、独立して行政書士事務所を開業する道もあります。
ここでは、高卒で行政書士としての資格を活かせる代表的なキャリアプランをご紹介します。
- 法務事務所で働く
- 行政書士事務所で働く
- 弁護士事務所で働く
- 一般企業の法務部や総務部で働く
- 独立して行政書士事務所を開く
①法務事務所で働く
法務事務所は、行政書士をはじめとした弁護士以外の法務関係者が開業する事務所の名称で、行政書士資格を活かせる就職先として、最も一般的です。
企業や個人の法律問題に対応し、契約書の作成・確認、各種登記手続き、法律相談の補助といった幅広い業務を行います。
行政書士として就職する場合、実務の中で法的文書の取り扱いや、さまざまな許認可申請などの行政書士としての経験を積むことができ、実践力を高めるに最適な環境です。
また、法律分野の幅広い業務に関わるため、法務事務所での経験が独立や他分野への展開にも役立ちやすいです。
幅広い案件に関わってスキルを磨きたいと考える新人行政書士にとっては、成長のチャンスが多くある職場と言えます。
②行政書士事務所で働く
行政書士事務所で実務経験を積むという選択肢もあります。
行政書士事務所では、官公署に提出する各種書類の作成や、書類作成に関する相談対応などの業務を担当します。
将来的に行政書士として独立開業を目指す人にとっては、行政書士事務所で得られる実務経験や人脈は大きな武器となるでしょう。
働き方や業務内容は所長の方針によって大きく異なるので、自分の希望に合う事務所を探すことが大切です。
とは言え、行政書士事務所は個人事務所が多い傾向にあり、採用活動をしているケースは稀です。行政書士業務の募集ではなく、事務のサポート作業の募集が大半なので、「使用人行政書士」として行政書士のスキルを積む機会はかなり限られるのが実情です。
③弁護士事務所で働く
弁護士事務所も、行政書士の就職先としてよく候補に挙がります。
弁護士事務所で働く場合は、弁護士の指示を受けて、法令・判例の調査、契約書・書証といった法律文書の作成や校閲といった法律事務業務を行います。法律知識を有している人材が重宝される弁護士事務所では、行政書士の知識を活かしやすいです。
ただし、弁護士事務所で働く場合は、パラリーガル(法律事務員)として働くことになるので、行政書士として活躍できるわけではありません。行書書士の知識を活かせるものの、行政書士の業務スキルや経験を身につけるのは難しい点に注意が必要です。
しかし、在留資格や入管問題といった行政書士が対応できる業務を取り扱っている事務所もあるため、事務所を選ぶ際は任せてもらえる業務をしっかり確認しましょう。
④一般企業の法務部や総務部で働く
行政書士の知識やスキルを活かして、一般企業で働くという選択肢もあります。
特に、建設業や不動産業の企業では行政の許認可が必要となることが多いので、行政書士の知識を活かせます。法務部や総務部といった法律に関わる業務が多い部署で、契約書の作成やチェック、許認可申請、コンプライアンス関連業務などで活躍できるでしょう。
ただし、行政書士連合会の会則により、一般企業に行政書士として雇用され、その企業内で行政書士業務を行うことはできません。
とは言え、「行政書士資格保有者歓迎」の求人や、「行政書士に対する資格手当」を設けている企業はあるので、行政書士の資格を活かして一般企業で活躍している人は多くいます。
⑤独立して行政書士事務所を開く
行政書士として一定の実務経験を積んだ後に、自身で行政書士事務所を開業するキャリアも選べます。
独立する場合は、行政書士としての業務に加えて、事務所経営の戦略立案、営業活動、顧客との折衝なども自ら行う必要があります。
業務の幅は広がりますが、裁量も大きくなり、自分の得意分野を活かして事業を展開することが可能です。
また、特定の分野に特化して専門性を高めれば、より多くの依頼を受けられるようになり、大幅な年収アップにもつながります。
働き方や収入が自分次第で決まるため、自分のペースで働きたいと考える人や、さらに稼ぎたい人におすすめのキャリアパスでしょう。
高卒で行政書士に向いている人

行政書士は法律に関する専門知識や正確な書類作成スキルが求められる職業です。
特に高卒で行政書士を目指す場合、自ら計画的に学習を進める力や、実務で信頼される人間性が大きな武器となります。
以下のような特徴を持つ人は、行政書士に向いていると言えます。
- 粘り強く几帳面な人
- 勉強熱心で自ら学習する人
- 行動力がある人
①粘り強く几帳面な人
行政書士の主な仕事は、法律に基づいた正確な書類の作成や申請・手続きです。記載ミスや抜け漏れが許されないため、細かい作業に丁寧に取り組める几帳面さが欠かせません。
加えて、作業の過程で法令の確認や見直しを繰り返すことも多いので、集中力と粘り強さも必要です。さらに、依頼者の要望をじっくりと聞き取り、形にしていく根気も求められます。
こうした資質を持つ人は、行政書士に非常に向いている可能性が高いです。
②勉強熱心で自ら学習する人
行政書士が取り扱う業務は幅広く、遺言書の作成から建設業許可の申請まで多岐にわたるので、さまざまな分野の知識を身に付ける必要があります。
また、法律は改正が頻繁に行われるため、常に最新の知識を学び続ける姿勢が大切です。実務に支障をきたさないように、自主的に学習を継続できることが欠かせません。
日々の情報収集や勉強を惜しまない勉強熱心な人は、行政書士として長く活躍できる資質を持っていると言えるでしょう。
③行動力がある人
行政書士として活躍していくには、積極的な行動が求められます。
行政書士の業務を進めるには、顧客だけでなく役所や同業者との密なコミュニケーションが求められます。意外にも人と関わる機会が多い仕事なので、自発的に動くことが苦にならない行動力のある人は、行政書士として活躍しやすいでしょう。
また、独立開業を目指す場合には、営業活動や人脈作りも重要で、積極的に仕事を得る行動も不可欠です。
高卒で行政書士に向いていない人

行政書士の仕事は専門性が高く、正確性や柔軟性、積極性などが求められます。
そのため、人によって向き・不向きが出やすい仕事でもあります。
ここでは、高卒で行政書士にあまり向いていない人の特徴をご紹介します。
- 細かい作業や確認が苦手な人
- IT技術に苦手意識がある人
- ルーティンワークの仕事をしたい人
①細かい作業や確認が苦手な人
行政書士は正確性と責任感が求められる職業です。
行政書士の業務では、契約書や申請書などの法的な書類を取り扱います。一つのミスがクライアントに大きな損害を与える可能性があるため、法律に照らし合わせての確認や誤字脱字のチェックといった、責任感をもって細かい作業を丁寧にこなすことが重要です。
ルールに則った書類の作成や確認作業に苦手意識がある人は、行政書士の仕事は向いていないと言えます。
②IT技術に苦手意識がある人
行政書士の仕事は、パソコンやオンラインシステムを使う場面も多いです。
最近は行政手続きの多くが電子申請に切り替わっており、専用のシステムを使いこなすことが必要です。書類の作成や提出もオンラインで行うケースが多く、IT技術に対する苦手意識があると業務が滞ってしまう恐れがあります。
今後もデジタル化が進み、行政書士の業務に使う知識やスキルが変わってくる可能性は高いです。そのため、新しい技術を学ぶことに消極的だと、行政書士としての活躍が難しいかもしれません。
③ルーティンワークの仕事をしたい人
行政書士の業務は、毎日同じ作業を繰り返すものではありません。
扱う書類は1万種類以上あるとも言われ、クライアントごとに相談内容や手続きの内容が異なります。法律や制度の改正も日々行われるため、最新の情報を把握しながら、都度最適な対応を考える必要があるのです。
変化に対応できる柔軟性や問題解決力が重視される仕事なので、毎日決まった作業をこなすルーティンワークを望む人には、行政書士の仕事は向いていないと言えるでしょう。
高卒で行政書士になるメリット

行政書士は学歴に関係なく資格取得が可能で、高卒にも大きなチャンスがある職業です。
実力次第で収入や働き方を自由に選べるため、キャリアを築きたい人には魅力的です。
ここでは、高卒で行政書士になることで得られる主なメリットをご紹介します。
- 年収が日本の平均以上
- 独立開業しやすい
- 年齢関係なく活躍できる
①年収が日本の平均以上
行政書士の平均年収はおよそ591万円とされ、日本の平均年収の460万円よりも130万円ほど高い水準です。また、独立開業して仕事が軌道に乗れば、年収1,000万円を超えることも十分にあり得ます。
行政書士として登録して働けるのは20歳からなので、高卒で早い時期から行政書士として経験を積めば、若いうちから安定した収入を得られる可能性があります。
学歴に関係なく、努力と実力によって収入が増える点は、行政書士の大きなメリットと言えるでしょう。
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「行政書士」(参照 2025-7-15)
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」(参照 2025-7-15)
②独立開業しやすい
行政書士は、実務未経験で独立開業しやすい点もメリットです。
行政書士は開業の条件として実務経験や特別な実務修習が義務づけられていないため、資格試験に合格して行政書士会に登録すれば、すぐに自分の事務所を開設できます。
早く事業を始めたい人にとっては、メリットを感じやすいでしょう。
さらに、行政書士は自宅での開業も可能なので、資金も最低限に抑えることができ、独立開業で抱えるリスクが少ない点も魅力です。
③年齢に関係なく活躍できる
行政書士は年齢制限や定年がないため、試験に合格して行政書士として登録さえすれば、生涯にわたって仕事を続けることができます。
行政書士の業務はデスクワークが中心で体力を求められる仕事ではないので、年齢を重ねても続けやすいです。実際、現役の行政書士は40代から50代が中心で、60代以降で活躍している人も多い職業と言われています。
年齢を理由に就職が不利になることが少なく、自分のペースで働ける環境を作りやすい職業なので、第二の人生として行政書士を目指す人も少なくありません。
高卒で行政書士になる注意点

行政書士は高卒も目指せる職業ですが、試験の難易度が高く、さらに会社員として行政書士の業務ができないといった制限や、同業者との競争が激しい現実があります。
ここでは、高卒で行政書士になる際に考えられる注意点を詳しくご紹介します。
- 試験難易度が高く取得までに時間がかかる
- 一般企業の会社員として行政書士の業務に携われない
- 競争が激しい
①試験難易度が高く取得までに時間がかかる
行政書士試験は、学歴や年齢に関係なく誰でも受験できますが、決して簡単な試験ではありません。
行政書士試験の直近5年間の合格率は以下の通りです。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 令和6年度 | 12.90% |
| 令和5年度 | 13.98% |
| 令和4年度 | 12.13% |
| 令和3年度 | 11.18% |
| 令和2年度 | 10.72% |
ここ数年の合格率は10~15%前後で推移しています。
出題科目が幅広く、単に知識を暗記するだけでなく、条文の解釈や実際の事例への応用力も養わなければいけないので、法律系の資格の中でも難関です。
合格までの勉強時間は500~800時間ほどと言われていますが、高卒が独学で一から法学に触れる場合、基礎理解にさらに時間がかかります。
このように、資格を取得するまでに膨大な時間がかかる点はデメリットと言えるでしょう。
②一般企業の会社員として行政書士の業務に携われない
行政書士の仕事をする場合は、独立開業をするか、法務事務所・行政書士事務所などに就職する必要があります。
一般企業の会社員が会社の名義で行政書士業務を行う行為は、行政書士連合会の会則によって禁止されています。
ただし、一般企業で働きながら兼業として行政書士の仕事をしたり、企業と業務委託契約を結んで会社の許認可申請を引き受けたりすることは可能です。
また、企業の法務部や総務部などで知識を活かして働くケースは問題がないので、資格そのものが役立つ場面は多くあります。
③競争が激しい
行政書士は人気の資格であり、資格を持つ人が年々増えているため、業界内での競争が激しくなっています。特に大都市を中心に、多くの行政書士事務所が競争をしている状態です。
単に資格を持っているだけでは安定して仕事を得るのが難しい可能性もあるので、自分ならではの強みを持つことが活躍できるカギになります。
たとえば、顧客を獲得するには、以下のような対策が有効です。
- ニッチな専門分野を持つ
- SNSやWebサイトなどで積極的に集客を行う
- 他の士業の専門家と連携してワンストップサービスを提供する
行政書士以外のおすすめの仕事

行政書士は大幅な収入アップのチャンスを得られる仕事ですが、資格取得の難易度が高く、合格までに時間がかかります。
そのため、今は行政書士を目指すのが難しいという場合は、高卒から目指せる行政書士に近い仕事を検討するのも手です。
ここでは、法律事務に関連した仕事を中心に、おすすめの職種を紹介します。
- 法務事務
- 海事代理士
- ナイト系スタッフ
①法務事務
法務事務とは、一般企業や法律事務所などで、契約書の作成や書類管理、法的手続きの補助を行う仕事です。法律に関わる業務を担当するため、行政書士の仕事内容に近いと言えます。
高卒からでもチャレンジしやすく、特別な資格がなくても就職できる点が魅力です。
また、実務を通して法的知識・書類作成のスキルが身についたり、実際の業務の流れやクライアント対応の経験を積んだりすることができるので、将来的に行政書士を目指す場合にも役立ちます。
②海事代理士
海事代理士は、船の登録や航行手続きなど、海に関する法律業務を代行する仕事です。行政書士と似た仕事が多く、「海の行政書士」と呼ばれることもあります。
従事するには国家資格の取得が必要ですが、試験の合格率は約50%と行政書士よりも高く、高卒も十分に目指せます。資格取得後は、港湾や造船会社などの幅広い分野で活躍可能です。
法律の知識を活かせるうえ、独立開業もできるため、将来的に自分の事務所を持ちたい人にもおすすめの職業です。
③ナイト系スタッフ
ナイト系スタッフは、接客や受付業務、キャストの管理といった店舗運営を中心に行う仕事です。
行政書士は合格までに数百時間以上の勉強が必要とされ、試験に合格して就職するまでの期間は収入が安定しにくい一方、ナイト系は比較的すぐに収入を得ることが可能です。
ナイト系は学歴や経歴、資格不問の求人が大半を占めている業界で、高卒で今すぐ稼ぎたいという人にも向いています。
また、実力主義の仕事なので、高卒で昇給・昇格し、年収1,000万円以上を達成している人も多くいます。学歴に関係なく高収入を狙うのにうってつけです。
高卒で行政書士になるためのおさらい

行政書士は高卒も十分に目指せる国家資格です。
試験に合格して行政書士会に登録することで、学歴に関係なく行政書士として活躍できます。また、資格取得後は事務所勤務や独立開業など、幅広い働き方が選べます。
学歴に左右されず、専門職として成功を目指す人にとって、魅力的な仕事と言えます。
ただし、資格試験の難易度が高く、長期間の学習が欠かせず、競争率が高い職業でもあります。
地道な努力が必要なので、資格試験のスケジュールや将来のキャリアプランを計画的に立てて目指しましょう。