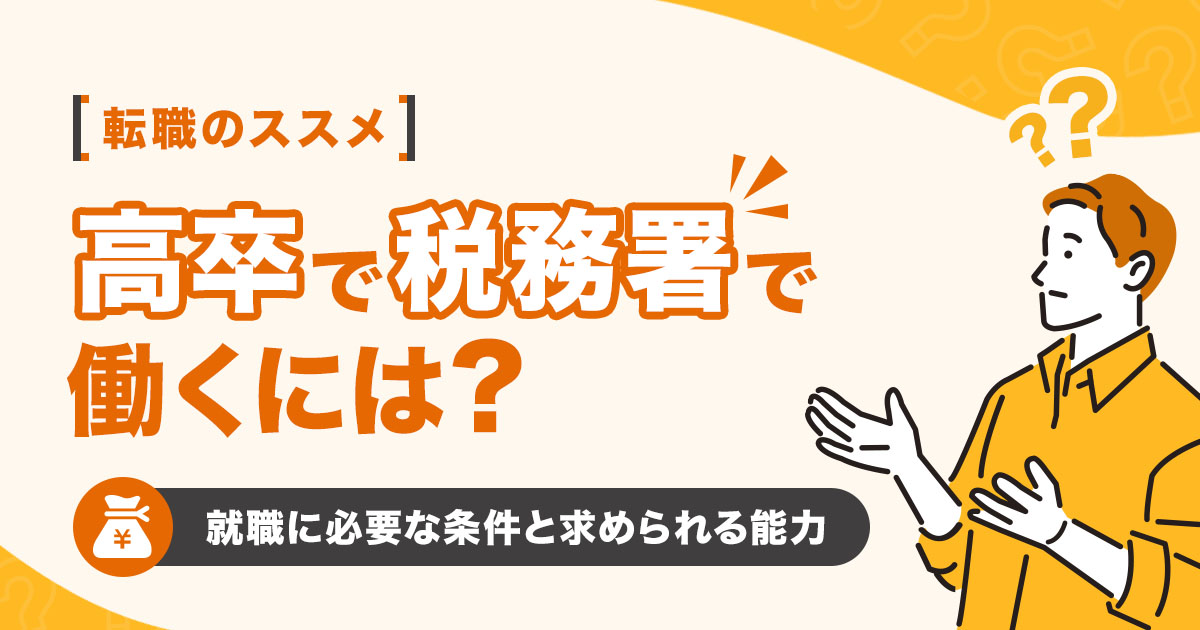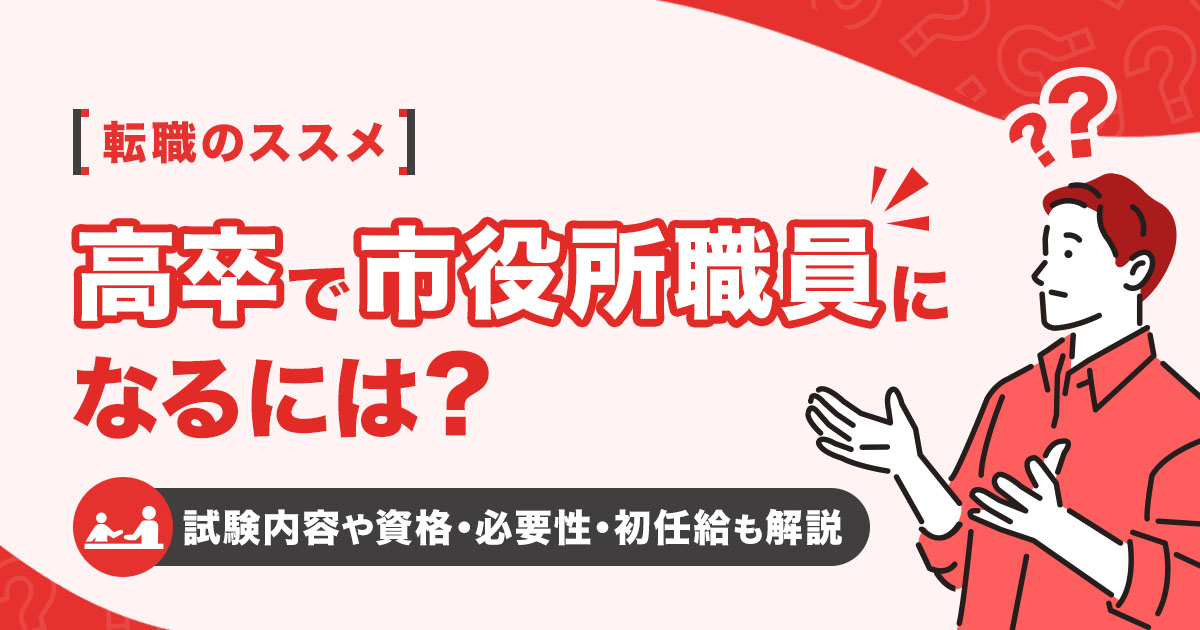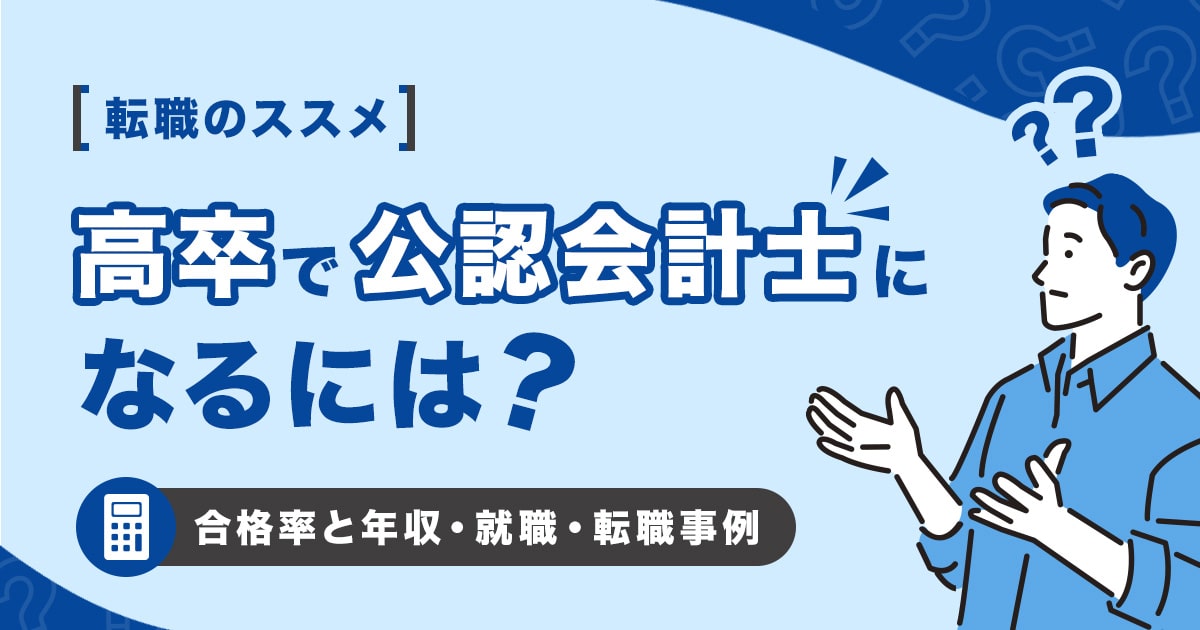-
高卒で税務署職員って目指せるの?
-
高卒で税務署職員になるにはどんな資格やスキルが必要?
税務署職員は国家公務員の一種ですが、「高卒・未経験でも目指せるのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
実はいくつかの条件を満たせば、税務署職員は高卒の方も十分に目指せます。
本記事では、高卒で税務署職員になるために必要な条件や手順、キャリアパス、平均年収などを詳しく解説します。
高卒で税務署職員になれるが学歴以外の条件がある

税務署職員は、高卒も目指せる職業です。
とはいえ、誰でもすぐになれるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
- 「税務職員採用試験」の受験資格を持っていること
- 「税務職員採用試験」に合格し、採用されること
「税務職員採用試験」の受験資格は、「高校または中学校を卒業してから3年以内(卒業見込みを含む)」であることが条件です。
この条件を満たしていれば、試験を受けることができます。
なお、試験に合格して採用された後は、税務大学校で研修を受け、正式に税務署職員としてのキャリアがスタートします。
税務署職員の学歴内訳

職業情報提供サイト「jobtag」を参考に、税務署職員として就労している人の学歴内訳をまとめました。
なお、学歴ごとの割合をすべて足した場合でも100%になるとは限りません。
| 学歴 | 割合 |
|---|---|
| 中卒 | 0.0% |
| 高卒 | 49.0% |
| 専門学校卒 | 11.8% |
| 短大卒 | 2.0% |
| 大卒 | 68.6% |
| 大学院卒 | 0% |
| 不明 | 9.8% |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「税務事務官」(参照 2025-07-22)
このデータからわかるとおり、高卒で働いている税務署職員は全体の約半数を占めています。大卒がもっとも多いものの、高卒も次に多く、学歴だけで道が閉ざされるわけではありません。
きちんと準備をすれば、高卒でも十分に目指せる職業といえるでしょう。
税務署職員の平均年収

職業情報提供サイト「jobtag」を参考に、税務署職員の平均年収を年齢別にまとめました。
| 年齢 | 年収 |
|---|---|
| ~19歳 | 257.08万円 |
| 20~24歳 | 338.02万円 |
| 25~29歳 | 432.79万円 |
| 30~34歳 | 487.16万円 |
| 35~39歳 | 535.18万円 |
| 40~44歳 | 557.13万円 |
| 45~49歳 | 562.06万円 |
| 50~54歳 | 579.71万円 |
| 55~59歳 | 572.06万円 |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「税務事務官」(参照 2025-07-22)
税務署職員の平均年収は509.3万円です。年齢別で見ると、年齢とともに右肩上がりとなり、50〜54歳で年収のピークを迎えます。
なお、税務署職員にはいくつかの役職があり、役職が上がれば上記よりも年収アップが見込めます。このように安定した収入を得られる点は、国家公務員として働く大きな魅力のひとつです。
高卒で税務署職員になる手順

高卒から税務署職員になる手順は、以下の6ステップです。
- 税務署職員採用試験の受験に申し込む
- 受験票を作成する
- 第1次試験に合格する
- 面接カードをダウンロードする
- 第2次試験に合格する
- 税務大学校で研修を受ける
税務署職員になる方法はいくつかあるものの、高卒から目指す場合はこの方法が最短かつ現実的です。
ここでは上記の手順に沿って流れとやるべきことを解説します。
手順①税務職員採用試験の受験に申し込む
まずは、税務職員採用試験に申し込むところからスタートです。受付期間が決まっているため、スケジュールを事前に確認しておくことが重要です。
税務職員採用試験の申し込みの流れは、以下のとおりです。
- 「事前登録」のためのデータ入力
- 「事前登録完了通知メール」受信
- 「申し込み」のためのデータ入力
- 「申し込み受付完了通知メール」受信
原則として、受験申し込みはパソコンを使ってWebで行います。
専用サイトにアクセスし、説明に従って入力を進めて手続きを済ませます。
- 注意点
- 申し込みは「事前登録」と「本申込み」の2段階に分かれており、事前登録だけでは完了になりません。忘れずに本申込みまで進めるようにしましょう。
手順②受験票を作成する
第1次試験のおよそ2週間前を目安に「受験票発行通知メール」が届くので、その案内に従って準備を進めましょう。
受験票の作成手順は、以下のとおりです。
- パーソナルレコードにログイン
- 受験票(PDFファイル)をダウンロード・印刷
- 受験票を作成
ログインには、申し込み時に設定したパスワードとユーザーIDが必要です。印刷はA4サイズのコピー用紙でOKです。本人写真は指定されたサイズ・形式に従って貼り付けましょう。
- 注意点
- ・受験票のダウンロードには期限があります。通知を受け取ったら、できるだけ早めに対応しましょう。
・第1次試験当日は、受験票を必ず持参してください。忘れると受験できない場合があります。
手順③第1次試験に合格する
第1次試験では、以下の3つの試験が実施されます。
- 基礎能力試験
- 適性試験
- 作文試験
第1次試験の合格者は「基礎能力試験」と「適性試験」の成績を総合して決定され、「作文試験」は第1次試験合格者を対象に評定したうえで、最終合格者決定に反映されます。
合格発表は人事院の専用ページにて行われます。その際に、第2次試験の案内も展開されるので、見逃さないようにしっかり確認しておきましょう。
なお、第1次試験の詳細や過去の試験問題は、以下から確認できます。
参考:人事院「税務職員採用試験受験案内」(参照 2025-07-30)
人事院「国家公務員試験採用情報NAVI」(参照 2025-07-30)
手順④面接カードをダウンロードする
第1次試験に合格したら、第2次試験に必要な面接カードをダウンロードします。
面接はこのカードに記入した内容をもとに質問がされるため、自分をアピールできる内容をしっかりと準備することが重要です。また、面接カードに記入した内容が深掘りされるので、答えの事前準備も入念に行いましょう。
面接カードの記入項目の例は、以下のとおりです。
- 最終学歴
- 職歴
- 受験の動機
- 印象に残っている体験
- 関心事項
- 趣味、特技など
- 好きな学科・得意な分野
- 自己PR
この面接カードはA4サイズのコピー用紙で3部印刷し、3部とも第2次試験当日に持参する必要があるため、忘れないようにしましょう。
手順⑤第2次試験に合格する
第2次試験では、以下の2つの試験が実施されます。
- 面接試験(人物試験)
- 身体検査
面接試験では、面接カードの内容に沿って質問されます。税務職員としての適性や人柄が評価される場でもあるため、自分の考えをわかりやすく伝える練習をしておきましょう。
「身体検査」は主に一般内科系検査で、呼吸器、循環器などの検査項目について、視診・問診・聴打診が行われます。
手順⑥税務大学校で研修を受ける
第2次試験に合格すると、税務大学校で約1年間の研修が始まります。
税務大学校は全寮制で、全国に12ヶ所あります。
税務大学校の研修は、新規採用者を国民から信頼される税務職員に育てることを目的に実施されるものです。研修を通じて、税務職員に必要な知識やスキルの取得を目指します。
ただし、学校といっても研修機関のため、卒業しても学歴が変わるわけではありません。
また、税務大学校在籍中も公務員にあたるので、給料が発生します。
研修を経て、全国の税務署に配属されると、税務職員としてのキャリアがスタートします。
高卒で税務署職員になるための試験対策

ここからは、高卒で税務署職員になるために必要な税務署職員採用試験のうち、以下の4つの試験について対策方法を解説します。
- 基礎能力試験(第1次試験)
- 作文試験(第1次試験)
- 適性試験(第1次試験)
- 人物試験(第2次試験)
各試験のポイントを押さえて、税務職員採用試験の合格を目指しましょう。
①基礎能力試験(第1次試験)
基礎能力試験では、公務員として必要な一般教養や基礎学力を問う問題が出題されます。内容は「一般知能」と「一般知識」に分かれており、出題範囲が広いのが特徴です。
そのためまずは過去問を使った、出題傾向の把握が重要です。特に最新年度の過去問を優先的に取り組むことで、直近の傾向を効率よくつかめます。
また、出題頻度の高い分野を中心に学習を進めるのがおすすめです。中でも、数的推理や判断推理など、理解に時間がかかる分野は早めに対策しておきましょう。
一通り勉強したら、模擬試験は予備校で開催されている模擬試験を受けて本番の雰囲気や時間配分に慣れておくことも重要です。
なお、税務職員採用試験の過去問は、人事院のホームページに掲載されています。勉強する際は、以下を活用してみてください。
参考:人事院「国家公務員試験採用情報NAVI」(参照 2025-07-30)
②作文試験(第1次試験)
作文試験は、自分の考えや主張を論理的かつ分かりやすく文章にまとめる力を評価する試験です。テーマはいくつかパターンがあり、テーマに沿って自分の考えを記述することとなります。
試験内容はシンプルながら、最終合格者決定に反映される重要な試験です。思うような文章が書けず不合格とならないよう対策をしましょう。
また、基礎能力試験とは異なり、習熟度がわかりづらいのも注意すべきポイントです。そのため、予備校の講師や学校の先生などに添削してもらい、フィードバックを受けるのがおすすめです。
人事院のホームページに掲載されている過去問を活用し、実際の試験時間と同じ制限時間50分で書き上げる練習法もおすすめです。
③適性試験(第1次試験)
適性試験は、事務処理能力があるかを測る試験です。
試験内容は簡単な計算や図形や数字の組み合わせから答えを導き出す問題などが出題されます。
出題範囲は計算、照合、置換、分類の4分野になり、このなかから複合問題を含めて3分野が出題されます。
試験時間は15分で120問出題されるので、短時間でどれだけ多くの問題を正確に解けるかが問われます。
特別な専門知識は不要なものの制限時間も短いため、スピードを意識して練習しておくことがおすすめです。
人事院のホームページに掲載されている過去問を活用して、出題傾向を把握しておきましょう。
④人物試験(第2次試験)
人物試験は、いわゆる面接試験です。
税務職員採用試験の人物試験は、面接カードの内容に基づいた質問が中心です。そのため、質問の答えをあらかじめ答えを準備しておくことが大切です。
また、就職面接でよくある定番の質問内容も確認しておくほか、税務職員採用試験の面接ならではの質問も想定しておくと安心です。
たとえば、「税といってもいろいろありますが、知っている税をいくつか教えてください」といった面接カードにない質問をされるケースもあります。
面接試験の質問の傾向を把握して、模範解答を考えておくことがポイントです。
実践力を鍛えるために、模擬面接を受けるのも効果的でしょう。本番同様の緊張感を体験できるだけでなく、第三者から客観的なアドバイスをもらえるといったメリットもあります。
高卒で税務署職員になったあとのキャリアプラン

税務署職員は実務経験や実績を積むことで、キャリアプランが広がります。ここでは、高卒で税務署職員になったあとのキャリアプランをご紹介します。
- 上級職を目指す
- 税理士を目指す
- 独立して開業する
紹介するキャリアプランを参考に、自分の理想を明確にしてみましょう。
①上級職を目指す
まずは初級職として採用され、経験を積んで上級職への昇進を目指すキャリアプランです。
税務署職員のキャリアパスには以下のようなものがあり、勤務年数に応じて昇進の機会が設けられています。
- 1~3年目:国税庁係員・税務署調査員
- 4~6年目:係長・留学
- 7年目~:課長補佐・税務署長
上級職を目指すには、昇進試験や選考に合格する必要があります。実務経験を積みながら、積極的に学習に取り組んで専門知識を習得していくと、昇給のチャンスを掴みやすくなるでしょう。
②税理士を目指す
経験を積んで税理士を目指すというのも選択肢のひとつです。税務署職員は、勤続年数に応じて税理士試験の科目が免除される制度があります。
免除になる条件は、以下のとおりです。
- 税務署職員として10~15年間勤務すると税法の試験が免除される
- 税務署職員として23年間勤務して指定研修を修了すると会計学を含む全科目が免除される
税理士試験は難易度が非常に高く、税理士になるのは簡単ではありません。しかし、税務署職員として働き続けることで試験の科目が免除されるケースもあるため、退職後に税理士として活躍する道もあります。
③独立して開業する
前述した内容のとおり、税務署職員として実務経験を積むと税理士を目指しやすくなります。
現職の公務員は税理士法により税理士登録ができないものの、免除申請や試験の受験はできます。
退職翌日から税理士登録を申請できる状態を整えておけば、スムーズに税理士事務所や税務コンサルタントとして独立・開業が可能です。
独立・開業は仕事が軌道に乗らないと収入が不安定ですが、結果を出せば年収アップが期待できるのは大きなメリットです。
独立・開業のメリットやデメリットを比較・検討しながら、キャリアパスの選択肢として慎重に判断するといいでしょう。
高卒で税務署職員に向いている人

税務署職員は専門的な知識が求められる職業で、人によって向き・不向きがあります。
高卒で税務署職員に向いている人の特徴は、以下の3つです。
- 日々勉強して知識を蓄えられる人
- コミュニケーション能力が高い人
- 細かく地道な作業が苦にならない人
上記3つの特徴について、詳しく解説します。
①日々勉強して知識を蓄えられる人
税務署職員は専門的かつ幅広い知識が必要です。くわえて、税法や関連する法律などの最新情報を取得して知識をアップデートすることが求められます。
とくに税制改正は毎年国会で審議され、社会情勢によって大小の改正が入るため、4月の施行に合わせて覚え直しが必要です。
税務署職員になったからといって勉強は終わりではありません。経験を重ねてもなお知識の蓄積を継続してできる人や、日々の勉強が苦でない人に向いている職業といえます。
②コミュニケーション能力が高い人
税務署職員は、業務上多くの人と関わります。
とくに、税務調査では個人事業主や会社経営者など、さまざまな職業・年齢の人と会話をする必要があります。
また、地域の人々に対して税金に関する啓蒙活動や税務相談を行う業務もあり、丁寧な説明を求められる場面も多いです。
よって、コミュニケーション能力に自信があり、相手にわかりやすく物事を伝えられる人に向いている職業といえるでしょう。
③細かく地道な作業が苦にならない人
税務署職員は、税務調査や税金の徴収といった業務を行うため、細かい数字を確認したり慎重に作業を進めたりする場面が多々あります。税金に関わる仕事ゆえ、ミスや見落としは許されません。
また、国税徴収官が滞納処分で差し押さえを執行する際は、帳簿の作成や各種登記の確認などを担当します。
細心の注意を払いながら集中力を保って最後まで取り組む必要があるため、細かく地道な作業が苦にならない人に向いているでしょう。
高卒で税務署職員に向いていない人

税務署職員は税金を扱う国家公務員ゆえに働き方にも特徴があるため、合わないと感じる人もいます。
高卒で税務署職員に向いていない人の特徴は、以下の3つです。
- ストレス耐性が低い人
- 転勤に抵抗がある人
- 自由に副業したい人
それぞれ詳しく解説します。
①ストレス耐性が低い人
税務署職員は仕事の性質上、税務調査対象者や税金滞納者への対応が仕事の大半を占めます。
また、国税徴収官が執行する滞納処分の補佐も業務に含まれます。執行内容は差し押さえをはじめとした強制徴収も含まれるので、嫌われ役になりやすい仕事です。
そういった場面で不満や苦情などの心ない言葉を投げかけられて、強いストレスを覚える人もいます。
こういった理由から、ストレス耐性の低い人には向いていない仕事といえます。
②転勤に抵抗がある人
税務署職員は納税者との癒着防止策のために約3〜4年ごとに転勤があります。
基本的に採用局管内での転勤で、転居が必要になるケースは稀ですが、同じ場所で働けないことがデメリットになる人もいるでしょう。
家庭を持っている場合、転勤が多い税務署職員として働くには家族の理解も必要です。家族の理解を得られない人や転勤に抵抗がある人には不向きの職業といえます。
③自由に副業したい人
国家公務員は副業が厳しく制限されており、原則として副業は禁止されています。
国家公務員が副業可能な場合の条件は、以下のとおりです。
- 兼業先が非営利団体である
- 報酬が社会通念上相当と認められる程度を超えない金額である
- 勤務時間と兼業に従事する時間が重複しない
また、副業をするのであれば、副業開始までに兼業許可申請書を各省に提出して許可を得る必要があります。このように、税務署職員は副業の自由度が低いため、副業にチャレンジしたい方には不向きといえるでしょう。
高卒で税務署職員になるメリット

税務署職員は国家公務員なので、就職するとさまざまなメリットを得られます。
高卒で税務署職員になるメリットは、以下の3つです。
- 収入が高水準で安定している
- 福利厚生が充実している
- 仕事を失う可能性が低い
上記のメリットについて、詳しく解説します。
①収入が高水準で安定している
国家公務員の給料は法律によって決められているため、景気に左右されにくく安定しているのが特徴です。
毎年昇給の機会や年2回のボーナスの支給もあり、勤務年数が増えるごとに年収が上がっていきます。
年収のピークは50〜54歳と遅めですが、見方を変えれば長期的に右肩上がりで年収が増えるともいえます。
また、一般的な給与所得者の平均給与よりも高水準で、稼ぎやすい点は大きなメリットといえるでしょう。
②福利厚生が充実している
税務署職員は国家公務員なので、福利厚生が手厚いのも魅力です。
通勤手当や住居手当などの各種手当のほか、各種休暇も用意されています。
また、国家公務員はメンタルヘルスに関する福利厚生が手厚いのも特徴です。心の不調の予防、不調の早期対応、円滑な職場復帰の三段階でケアしてくれます。
そのほか、退職金もあり、長く働いていける待遇・生活面のサポート・福利厚生が充実しているのは大きなメリットです。
③仕事を失う可能性が低い
税務署職員は国税に関わる仕事をしており、納税の公平性を維持する重要な職業なので、将来的に仕事がなくなる可能性は非常に低いです。
さらに、公務員は特殊な理由がない限りリストラされる可能性もなく、いきなり仕事がなくなるといったリスクも抑えられます。
AIのような技術が発展しても、日本の税法に対してはまだまだ課題が残っています。結局は人によるチェックが必要となるため、AIに取って代わられる可能性も低く、長く働きやすい職業です。
高卒で税務署職員になる注意点

高卒で税務署職員になると、大卒と比べて収入面や採用面、生活面などで差が生まれやすいという特徴もあります。
高卒で税務署職員になる注意点は、以下の3つです。
- 税務職員採用試験を受けられる期間が短い
- 大卒と年収に差がある
- 約1年間の寮生活がある
上記3つの注意点について、詳しく解説します。
①税務職員採用試験を受けられる期間が短い
高卒で税務署職員になるには、税務職員採用試験を受けて、合格する必要があります。しかし、受験資格を得られるのは高校卒業から3年未満の人のみです。
受験資格に限りがあるため、税務署職員を目指すかどうかは早めに決断しなければなりません。
税務署職員として働いた結果、合わないと感じたら転職も可能ですが、そもそも税務署職員を目指すかどうかを考える時間が限られる点はデメリットといえるでしょう。
②大卒と年収に差がある
高卒で税務署職員になると、大卒と年収に差が生まれる点はよく理解しておきましょう。
そもそも高卒と大卒では、税務署職員になるための試験の種類も異なります。大卒の場合は「国税専門官採用試験」を受験する必要があり、合格すると国税専門官として採用されます。
初任給も高卒より大卒のほうが高く設定されており、年齢を重ねるごとにその差は開いていく傾向が強いです。毎年昇給の機会はあるものの、大卒の年収を超えるのは難しいのが実情といえます。
③約1年間の寮生活がある
高卒が税務職員採用試験に合格・採用されたあと、全寮制の税務大学校で約1年間の研修を受ける必要があります。大卒は研修期間が3ヶ月なので、4倍ほど時間がかかります。
寮の部屋は個室ですが、共有スペースや同期・先輩職員との懇親会などもあるため、他人と一緒に生活することが苦痛な人にとってはデメリットといえるでしょう。
また、門限や寮の敷地内での飲酒・喫煙禁止といった規則も設けられており、寮では規則正しい生活が求められます。
税務署職員以外のおすすめの仕事

ここまで税務署職員になる手順や条件などを解説してきましたが、就職・転職するのは難しいと感じている方もいるでしょう。
そこで、税務署職員以外のおすすめの仕事を3つご紹介します。
- 地方公務員の一般行政職
- 公認会計士
- 一般企業の経理・財務
税務署職員を目指すか迷っている方は、仕事選びの参考にしてみてください。
①地方公務員の一般行政職
地方公務員の一般行政職は、地域住民の生活や地域に密着した業務を行います。さまざまな部署があり、部署異動を繰り返して幅広い分野の業務に携われるのが特徴です。
なお、地方公務員試験は高卒で受験が可能ですが、年齢制限が設けられています。
自治体によって違いはあるものの、ほとんどの自治体では受験可能な年齢を18〜21歳としているので、受験できる期間が短い点には注意してください。
②公認会計士
公認会計士は、税務署職員と同じくお金の流れをチェックする職業で、監査・会計分野のスペシャリストです。主に、企業が作成した会計帳簿の正確性を確認する業務を担当します。
公認会計士になるには取得難易度の高い国家資格が必須ですが、学歴や年齢不問で受験できるため、実際に高卒で公認会計士になっている人も数多くいます。
税務署職員からキャリアチェンジする人が多い税理士と同様に、年齢を重ねてからでも挑戦でき、将来的に独立も可能な職業です。
③一般企業の経理・財務
一般企業の経理・財務は、社内お金の処理や資産管理などを行うのが主な仕事内容です。お金を扱うため、責任感や会計に関する知識が求められる仕事で、税務署職員を目指す人にもおすすめです。
企業によっては高卒向けの求人が出ている場合もあるので、高卒からでも目指せます。経理・財務になるのに必須の資格はありませんが、日商簿記やビジネス会計検定などの資格を取得しておくと有利に働きやすくなります。
高卒で税務署職員になるためのおさらい

税務署職員は、実は高卒も目指しやすい職業です。
税務職員採用試験に合格し、国家公務員として採用されれば、高卒から税務署職員になることができます。
また、税務署職員になったあとは、「上級職を目指す」「税理士を目指す」「独立して開業する」といったキャリアパスが豊富にあります。
ただし、税務職員採用試験を受験できるのは、高校卒業から3年未満のみという制限がある点には注意が必要です。そのため、税務署職員を目指すかどうかは早急な決断が求められます。
税務署職員を目指すと決めたら、今日から勉強をスタートしましょう。