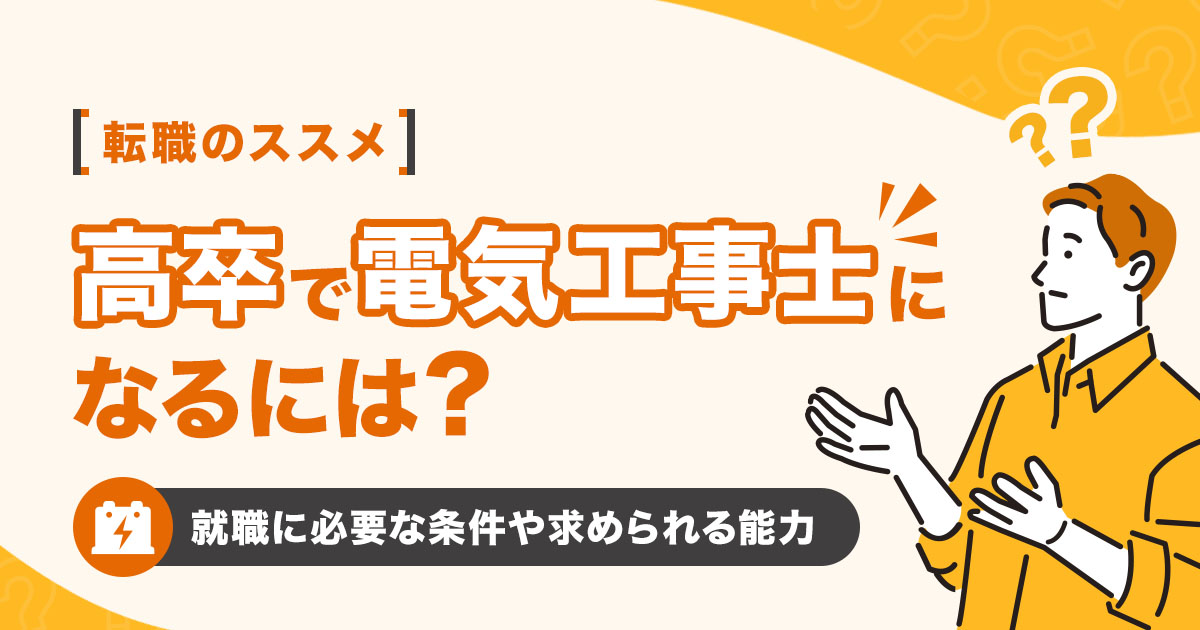-
電気工事士って高卒未経験でもなれる?
-
高卒で電気工事士になったときの年収ってどのくらい?
電気工事士は専門性の高い職業ですが、実は高卒の方も無資格・未経験からでもなることができます。
本記事では、電気工事士になりたい高卒に向けて、ねらい目の求人や平均年収などを紹介します。
また、電気工事士になったあとのキャリアパスや向いている人・向いていない人の特徴、目指すメリットや注意点についても詳しく紹介しています。
高卒で電気工事士になりたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
高卒の仕事探しなら電気工事士がオススメ!

電気工事士は学歴や資格・スキルの有無に関係なく、未経験から目指せる職業です。
近年は電気工事に携わる人材が不足しており、無資格・未経験者を積極的に採用する企業が増えているので、高卒未経験も就職しやすくなっています。
ただし、電気工事の仕事の中には資格がないと担当できない作業も多いため、最初は「見習い」として軽微な工事や作業補助から始めるのが一般的です。
- 【軽微な工事とは】
- 電気工事法において電気工事の対象外となる工事のことです。主に「電圧が600V以下の修理や交換」や「電気工事士の作業補助」を行います。
| 軽微な工事の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 接続工事 | 差込み・ねじ込み接続器、ソケット、スイッチなどに電線を接続する工事 |
| ねじ止め工事 | 電気機器の端子にコードやキャブタイヤケーブルをねじ止めする工事 |
| 取付・取り外し工事 | 電力量計、電流制限器又はヒューズの取り付け、または取り外す工事 |
| 二次側の配線工事 | 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球といった小型変圧器(二次電圧が36V以下)の二次側の配線を行う工事 |
| 工作物の設置・変更工事 | 電線を支持する柱、腕木、地中電線用の暗渠(あんきょ)または管の設置・変更を行う工事 |
このような作業を通じて、現場経験を積みながら資格取得を目指すのが、未経験者の一般的なキャリアステップです。
電気工事士の学歴内訳
職業情報提供サイト「jobtag」を参考に、実際に電気工事士として働いている人の学歴内訳を紹介します。
| 学歴 | 割合 |
|---|---|
| 中卒 | 9.8% |
| 高卒 | 56.1% |
| 専門学校卒 | 12.2% |
| 短大卒 | 0.0% |
| 高専卒 | 2.4% |
| 大卒 | 17.1% |
| 大学院卒 | 2.4% |
| 不明 | 7.3% |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「電気工事士」(参照 2025-07-02)
※すべての数字を合計しても100%になるとは限りません。
最も多いのは「高卒」で、全体の半数以上(56.1%)を占めています。
これは、工業高校在学中に電気工事士の資格を取得し、そのまま就職する人が多いためと考えられます。
また、電気工事士は人材不足の影響から、学歴を問わず幅広く人材を受け入れる企業が多いのも特徴です。こうした背景から、高校卒業後すぐに働きたい方や、実務経験を重ねながら成長していきたい方にも目指しやすい職業といえるでしょう。
高卒で電気工事士になるうえでねらい目の求人

高卒で電気工事士の仕事に就きたい場合、次のような特徴を持つ求人がねらい目です。
- 学歴や資格・未経験OKの求人
- 2~3月掲載の求人
- 8~9月掲載の求人
高卒で電気工事士を目指す場合、学歴や資格不問で、未経験OKの求人へ応募しましょう。また、求人数が増える時期を狙って探すのもおすすめです。
それぞれのポイントについて詳しく紹介します。
①学歴や資格・未経験OKの求人
高卒から電気工事士を目指す場合、学歴や資格の有無を問わない未経験OKの求人に応募するのがおすすめです。
近年、電気工事士の業界は人手不足なので、未経験者の採用に積極的な企業がたくさんあります。
実際に、未経験OKの企業は専門知識を習得できる研修があったり、「第二種電気工事士」をはじめとした資格取得支援制度を設けていたりと、人材育成に力を入れているケースが多いです。
学歴・資格不問かつ未経験OKの企業なら、高卒未経験でも電気工事士としてステップアップしていけるでしょう。
②2~3月掲載の求人
電気工事士も含めたほとんどの業界では、2〜3月の年度末に退職者が多く、人手不足になりやすいので、求人を探す際のねらい目の時期です。
また、電気工事士の場合、2〜3月は冬の寒さが原因で電気設備の故障が増えることから、人手が必要な時期でもあります。
さらに、入社時期が新卒者と重なるため、研修内容や教育体制が充実している可能性が高いです。新年度へ向けてとくに採用活動が活発化する時期であれば、さまざまな求人の中から自分に合った求人を見つけられるでしょう。
③8~9月掲載の求人
電気工事士の求人は、8〜9月も増加しやすく、ねらい目の時期といえます。
というのも、8〜9月は夏の暑さによってエアコンの設置・メンテナンスの需要が高まり、人手が必要とされるタイミングだからです。近年は、とくに猛暑日が続いていることから、今後もこの時期の現場の対応数が増えていくでしょう。
また、夏季休暇明けの時期は入社希望者が少なく、企業側の人員が不足しやすい状況です。加えて、下半期の業務に備えて採用活動を強化する企業も多いため、求人が増える傾向があります。
電気工事士の平均年収

職業情報提供サイト「jobtag」を参考に、電気工事士として就労している人の平均年収を年齢別に紹介します。
| 年齢 | 年収 |
|---|---|
| ~19歳 | 310万円程度 |
| 20~24歳 | 410万円程度 |
| 25~29歳 | 480万円程度 |
| 30~34歳 | 540万円程度 |
| 35~39歳 | 580万円程度 |
| 40~44歳 | 580万円程度 |
| 45~49歳 | 650万円程度 |
| 50~54歳 | 640万円程度 |
| 55~59歳 | 590万円程度 |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「電気工事士」(参照 2025-07-07)
電気工事士の平均年収は547.6万円となり、45歳〜49歳頃で年収のピークを迎えます。電気工事士は、資格の取得や経験の積み重ねが重要な職業なので、見習いの割合が大きい20代前半は年収が低い傾向にあります。
見習い期間を終える人が多い25〜29歳頃になると平均年収は480万円程度になり、日本の平均年収である460万円を超えるため、電気工事士の年収は高い水準といえるでしょう。
参考:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」(参照 2025-07-07)
高卒で電気工事士になったあとのキャリアプラン

高卒で電気工事士になったあとは、次のようなキャリアプランが考えられます。
- 現場の上級職を目指す
- 経験を積んで電気工事のスペシャリストになる
- 独立して開業する
電気工事士のキャリアプランは、現場で上級職を目指す道や、電気工事士の技術を磨いてスキルアップを図る道、そして将来的に独立して事業を立ち上げる道など、多岐にわたります。
以下ではこれら3つのキャリアパスについて、詳しく解説しています。
①現場の上級職を目指す
高卒未経験で電気工事士になった場合、見習いからスタートします。その後は「技能者」になり現場での経験を積み、「職長」「上級職長」へのキャリアアップを目指します。
それぞれの役職に就くために必須の特別な資格はありません。しかし、技能者になるためには「第一種・第二種電気工事士」の資格取得を求められることが多く、職長になるためには「職長教育」を受ける必要があります。
役職ごとの主な仕事内容は以下のとおりです。
| 役職 | 仕事内容 |
|---|---|
| 見習い | 電気工事士の補助業務が中心。仕事の流れや施工図の読み方を覚えていき、必要な資格の取得を目指す。 |
| 技能者 | 電気工事士の資格を取得していて、ひととおりの業務ができる状態。職長の指示に従いながら、現場で電気工事の仕事に携わる。 |
| 職長 | 現場で技能者をまとめ、管理をするリーダー的な役割。スタッフの配置決めや安全対策など、作業が円滑に進むように計画する。 |
| 上級職長 | 現場全体の施工計画の立案や部下への技術指導など、主にマネジメント業務を担当。工事を効率的に進めるための提案力や管理力が求められる役職。 |
②経験を積んで電気工事のスペシャリストになる
電気工事士になったあと、経験を積んで技術に特化した現場のスペシャリストになるのもキャリアステップの1つです。
とくに「ものづくりの現場にずっと携わっていたい」「出世にはこだわらないが、技術力を高めたい」と考える人にとっては、電気工事のスペシャリストを目指す道が適しています。
業務に役立つ資格を取得してさまざまな現場で経験を積むことで、大規模な設備工事や複雑な配線作業にも対応できるようになり、業務の幅が広がります。専門性が高まるほど、社内での評価も上がりやすく、実力次第では収入アップも期待できるでしょう。
電気工事士のスペシャリストとして技術を磨き続けることで、主任技師などの専門職の上位ポジションを目指せます。
③独立して開業する
電気工事士は在籍している企業でキャリアアップするだけではなく、独立して開業するという道もあります。
ただし、すぐに独立開業できるわけではなく、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 第一種または第二種電気工事士の資格を保有していること
- 3年以上の実務経験があること(第二種電気工事士の場合は免状取得から3年以上)
- 登録電気工事業者等の登録をしていること
独立開業は、仕事をすればするほど収入が増えますが、仕事をしなければその分収入が減ってしまうという不安定な一面もあります。
そのため、電気工事の技術だけではなく、顧客を獲得する営業力や事業を運営していくためのマーケティング力も必要です。
しかし、事業が軌道に乗れば、電気工事士の平均年収を超える「年収1,000万円」も夢ではありません。
電気工事士への就職やキャリアアップに役立つ資格

ここでは、電気工事士への就職やキャリアアップを目指す方に向けて、役立つ資格や合格率などをわかりやすく紹介します。
▼電気工事士への就職やキャリアアップに役立つ資格
| 資格名 | 内容 |
|---|---|
| 第一種・第二種電気工事士 | 電気設備の配線や設置工事を行うために必要な資格 |
| 1級・2級電気工事施工管理技士 | 電気工事の現場における施工管理能力を認定する資格 |
| 消防設備士第4類(甲種・乙種) | 火災報知設備を扱えるようになる資格 |
| 第一種~第三種電気主任技術者(電験) | 事業用電気工作物の保安・監督業務を行うために必要な資格 |
以下の項目からは、資格内容や取得難易度についてさらに詳しく紹介しているので、高卒から電気工事士を目指している方はチェックしておきましょう。
①第一種・第二種電気工事士
高卒未経験で電気工事士として就職した場合、まずは第二種電気工事士の資格取得を目指すのが一般的です。
第二種電気工事士の資格取得後は、実務経験を積んだうえで第一種電気工事士の資格取得を目指します。
種別ごとにできる業務の違いは以下のとおりです。
- 第二種電気工事士
- 一般住宅や小規模な店舗・事務所の電気工事を行う。
電圧600Vの低圧電気設備の工事、コンセントや照明、エアコンなどの電気工事ができる。
- 第一種電気工事
- 大規模な施設や工場などの電気工事も含む広範囲の工事が可能になる。
第二種電気工事士で扱える低圧設備に加えて、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事ができる。また、高圧電線の工事にも携われる。
第二種電気工事士は、就職後最初に取得を目指す資格なので、持っておくと就職時に有利になります。
第一種・第二種電気工事士の合格率は以下のとおりです。
| 年度 | 試験種別 | 合格率(第二種) | 合格率(第一種) |
| 2024年度 | 学科 | 58.1% | 56.7% |
| 技能 | 70.3% | 59.9% |
参考:生涯学習のユーキャン「第一種・第二種電気工事士の資格試験の難易度|合格率と出題科目から難易度を解説」(参照2025-07-07)
最初に目指す第二種電気工事士の合格率は、学科試験が約60%、技能試験が約70%です。業務に関わる国家資格の中では比較的取得しやすく、高卒を含め誰でも十分合格を狙えます。
問題の出題例や、試験の日程を確認したい方は、電気技術者試験センターの公式ホームページをチェックしてください。
②1級・2級電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、電気工事の現場において、工事の進行や安全管理などの施工管理能力を認定する資格です。
現場を統括するだけでなく、スケジュール調整などの管理業務に携われるようになるので、年収もアップする傾向にあります。
電気工事施工管理技士を取得するとできることは以下のとおりです。
- 2級電気工事施工管理技師
- 一般建設業の営業所ごとに配置が求められている「専任技術者」や、工事現場で進行管理や安全管理を行う「主任技術者」になれる。
- 1級電気工事施工管理技師
- 2級の範囲に加えて、特定建設業の「専任技術者」や、外注総額4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の大規模な現場を管理できる「監理技術者」になれる。
続いて、電気工事施工管理技士の合格率を見ていきましょう。
| 年度 | 検定種別 | 合格率(2級電気工事施工管理技師) | 合格率(1級電気工事施工管理技師) |
| 2024年 | 一次検定 | 47.5% | 36.7% |
| 二次検定 | 51.4% | 49.6% |
参考:一般財団法人建設業振興基金 試験研修本部「過去の受検状況・検定問題・合格基準」(参照 2025-07-07)
二次検定の合格率は、2級で約51%、1級で約50%と、先ほど紹介した電気工事士と比較すると、少し難易度の高い資格です。
試験の日程や受験料、受験資格などは、施工管理技術検定の公式ホームページで確認してみてください。
③消防設備士第4類(甲種・乙種)
消防設備士第4類(甲種・乙種)は、自動火災報知設備などの点検や整備を行うための資格です。
消防設備士は複数の種類に分かれていますが、火災報知設備を扱うことができる「第4類」が電気工事と関連性が高いです。
乙種は点検や整備のみ行えますが、甲種は工事などのすべての業務に従事できるようになります。
消防用設備工事を手がけている電気工事会社も多いため、取得していると社内で高い評価を得られ、昇給・昇進に繋がります。
消防設備士第4類(甲種・乙種)の合格率は以下のとおりです。
| 年度 | 種別 | 合格率 |
| 2024年 | 甲種 | 31.7% |
| 乙種 | 31.2% |
参考:一般財団法人消防試験研究センター「試験実施状況(令和6年4月~令和7年3月)」(参照2025-07-07)
甲種・乙種の合格率を平均すると約31%となり、比較的取得するのが難しい資格といえます。
試験の日程や過去問はこちらの消防試験研究センターの公式ホームページから確認しましょう。
④第一種~第三種電気主任技術者(電験)
第一種〜第三種電気主任技術者を取得すると、ビルや工場、発電所、変電所などの電気設備の保安監督業務ができるようになります。
種類によって扱える電気工作物の電圧数は異なりますが、第三種さえ取得できれば大半の設備に対応できるため、キャリアアップをしていく際の武器になります。
種別ごとの合格率は以下のとおりです。
| 年度 | 種別 | 試験 | 合格率 |
| 2024年 | 一種 | 一次試験 | 29.8% |
| 二次試験 | 15.5% | ||
| 二種 | 一次試験 | 28.8% | |
| 二次試験 | 18.9% | ||
| 三種 | – | 16.4% |
参考:一般財団法人 電気技術者試験センター「第一種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(参照2025-07-07)
一般財団法人 電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(参照2025-07-07)
一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の試験結果と推移」(参照2025-07-07)
入門資格である第三種でも合格率が10%台と、非常に取得が難しい国家資格であることがわかります。
取得が難しい国家資格ですが、電気工事士を監督する立場を任せてもらえるようになるので、年収アップやキャリアアップが期待できるでしょう。
電気主任技術者の試験日程などは、電気技術者試験センターの公式ホームページからチェックしてみてください。
高卒で電気工事士に向いている人

高卒で電気工事士に向いている人は、以下のとおりです。
- 細かい作業が得意な人
- 日々の学習が苦にならない人
- 体力に自信がある人
なぜ上記のような人が電気工事士に向いているのか、詳しく解説します。これから電気工事士を目指そうと考えている方は、自分に当てはまるかどうかチェックしてみてください。
①細かい作業が得意な人
電気工事士の仕事では、配線の接続や機器の取り付けなど、細かい作業が多く発生します。
こういった配線の接続工事の場合、少しのミスが火災や感電事故などを引き起こす可能性があるのです。
図面どおりに仕上げる正確さと丁寧さが必要不可欠であることから、細かい作業ができる人は電気工事士としての適性が高いといえます。
作業の正確性は、経験を積んで向上させることもできますが、もともと細かい作業が得意な人は作業に対するストレスが少ないため、就職後も効率的に業務を進められるでしょう。
②日々の学習が苦にならない人
電気工事士の資格を取得してキャリアアップするには、現場で使う専門用語や電気技術の知識をしっかり身につける必要があります。
そのため、毎日コツコツと計画的に学習を続けられる人に向いています。
さらに、技術の進歩や法規制の改正があることから、経験を積んだ後も常に最新の情報をキャッチできるようにアンテナを張り、自己学習を怠らない姿勢が重要です。
こうした学習の積み重ねができる人は、電気工事士として着実にキャリアアップしていけるでしょう。
③体力のある人
電気工事士は、手先の器用さだけではなく、体力が求められるシーンも少なくありません。
電気工事士が作業する場所は一般住宅やオフィス、施設など屋内外を問わず多岐にわたります。
作業の性質上、長時間立ちっぱなしだったり、重い機材を運搬したりすることもあるため、一定以上の体力が必要とされます。
そのため、体力に自信のある人は、長く続けやすい仕事といえるでしょう。
高卒で電気工事士に向いていない人

高卒で電気工事士に向いていない人は以下のとおりです。
- 注意力に欠ける人
- ルールに沿った行動が苦手な人
- チーム連携が得意でない人
なぜ上記のような人が電気工事士に向いていないのか、詳しく解説します。自分が本当に電気工事士として働いていけるのかを判断する材料にしてください。
①注意力に欠ける人
電気工事士の仕事は、危険を伴う作業が多く、わずかなミスでも感電や火災など重大な事故につながる可能性があります。
そのため、作業中は細部まで注意を払い、高い集中力と正確さを維持することが不可欠です。
万が一注意力が足りず集中力が続かない状態で作業を行うと、配線ミスや安全確認不足による設備不良を引き起こす恐れがあります。
このような理由から、注意力に欠ける人には不向きな職業といえるでしょう。
②ルールに沿った行動が苦手な人
電気工事の現場では、作業者の安全確保や、適切な電気設備の提供を行うために、法規制や安全基準に則って守らなければならないルールがたくさんあります。
「面倒だから」「こっちの方がやりやすいから」という理由でルールを勝手に変えたり省略したりしてしまうと、後々重大な事故につながりかねません。
そのため、ルールを守ることを面倒に感じたり、自分の判断で作業を簡略化したりする人には難しい職業です。
③チーム連携が得意でない人
電気工事士の仕事は一人で完結できるものが少なく、チームで協力しながら進める必要があります。
現場では他の電気工事士に加え、建築業者や設備業者など、さまざまな人とコミュニケーションをとらなければなりません。
チームワークやコミュニケーションが苦手だと、現場の状況に応じて行動しなければいけないプレッシャーやストレスから、仕事に支障をきたすおそれがあります。
そのため電気工事士は、協調性に自信がない人や、一人で黙々と作業するのが好きな人には不向きかもしれません。
高卒で電気工事士になるメリット

高卒で電気工事士になる場合、3つのメリットがあります。
高卒で電気工事士になるメリット
- 未経験でもキャリアアップを目指せる
- 就職・転職しやすい
- 仕事がなくなる可能性が低い
電気工事士は、高卒未経験からでも目指せる職業であること以外にも、いくつかメリットがあるので詳しく解説します。
①未経験でもキャリアアップを目指せる
電気工事士は、高卒未経験からでもキャリアアップを目指せる職業です。
資格取得支援をはじめ教育環境を整えている企業が多く、業界未経験に対して充実したバックアップ体制が出来上がっている傾向にあります。そのため、仕事をしながら電気工事士に必要な資格を取り、高度な知識やスキルを習得できるのが魅力です。
もちろん自分の時間を使って学習することも必要ですが、仕事をしながらでも資格を取り、手に職を付けていけるのはメリットといえるでしょう。
②就職・転職しやすい
第一種・第二種電気工事士など電気工事士に関連する資格を取得すれば、同業種へ転職する際に役立ちます。
とくに、取得難易度が高い第一種電気工事士の資格を持っていれば、住宅以外の工事を扱う会社にも応募ができるようになり、さらに転職先の選択肢が広がります。
電気工事士の資格は、電気関係に限らず、インフラ系や情報通信系など幅広い業界で需要があるので、職に困りにくい資格といってもいいでしょう。
③仕事がなくなる可能性が低い
電気は暮らしに欠かせないインフラであり、その工事全般を支える電気工事士の需要は今後も高まると予想されます。
近年はAI技術の進歩によって、仕事そのものがなくなる可能性のある職業も存在します。しかし、専門的な知識・スキルを必要とし、現場での作業も担う電気工事士は、AIによる代替は難しいでしょう。
さらに、第一種・第二種電気工事士ともに有資格者が不足しており、今後も必要とされるため、仕事がなくなる心配が少ない職業といえます。
高卒で電気工事士になる注意点

高卒で電気工事士になる注意点は3つあります。
- 危険を伴う仕事がある
- 力仕事や立ち仕事が多い
- 経験を積まないと低年収の傾向がある
高卒で電気工事士になる注意点を知らずに就職してしまうと、早期離職に繋がる可能性が高いので、事前に確認しておきましょう。
①危険を伴う仕事がある
電気工事士の作業には、危険を伴う仕事が多くあります。
とくに高電圧を扱う現場では、一瞬の油断が感電や熱傷など大きな事故につながりかねません。また、高所での配線作業では、転落の危険性もはらんでいます。
そのため、どんなに過酷な環境下でも常に高い集中力や注意力を保つ必要があり、精神的にも強くないといけません。
電気工事士は高卒未経験からキャリアを築きやすい職業ではあるものの、現場によって危険と隣り合わせの作業になる可能性があることを知っておきましょう。
②力仕事や立ち仕事が多い
「電気工事士に向いている人」でも解説したとおり、この仕事は体力が求められます。
電気工事士は、力仕事や立ち仕事が多く、とくに屋外の作業では夏の暑さや冬の寒さに耐える必要があるため、身体への負担も大きいです。
また、電線や配電盤など重い機材を取り扱うケースもあります。作業時に機材を持ち上げたり移動させたりするのも珍しくないため、筋力も必要です。
加えて高所での作業も発生することから、電気工事士は想像以上に疲労を感じる仕事といえます。
③経験を積まないと低年収の傾向がある
電気工事士は高卒未経験でもなれる職業ですが、就職したばかりの見習い期間は低収入の傾向があります。
また、電気工事士の資格を取得してから就職した場合でも、実務経験が浅いため任される業務が限られており、その分給与も低めです。
とはいえ、電気工事士の資格を取得して一人前になれれば、年収は着実に上がっていきます。電気工事士の平均年収は547.6万円で、日本の平均年収を超えているともいわれているので、スキルを磨けば磨くほど大幅な収入アップが狙いやすい仕事です。
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「電気工事士」(参照 2025-07-07)
電気工事士以外で高卒におすすめの職業

ここまで読んでみて「電気工事士に就職・転職するのは難しそう…」と感じた方は、電気工事士に似た仕事を検討してみるのもひとつの手です。
高卒で電気工事士以外の道を考えている方におすすめの職業は3つあります。
- 消防設備士
- 建設業者
- ナイト系スタッフ
それぞれの職業の仕事内容やおすすめ理由について解説します。
①消防設備士
電気工事士に興味のある方には、消防設備士という職業もおすすめです。
扱う設備こそ異なりますが、設置・保守・点検など、業務内容に共通点が多くあります。
消防設備士は、第二種電気工事士の資格だけでは従事できませんが、消防設備士の甲種第4類を実務経験なしで受験可能です。
消防設備士の仕事は電気工事士に比べて体力的な負担が少ない傾向があり、長期的に安定して働きやすいというメリットもあります。
さらに、未経験歓迎の求人が多く、高卒の方も比較的チャレンジしやすい職業です。
②建設業者
仕事内容こそ異なりますが、建設業者も電気工事士と同じインフラ分野で、安定性のある職業のひとつです。
複数の取引先から受注をしてもらう電気工事士とは違い、主に自社の案件を担当することが多く、仕事量も安定している傾向があります。
また、建設業界は深刻な人手不足と高齢化が進んでいるため、未経験者や若手人材の需要が非常に高まっています。
体力を必要とする作業が多いことから、高卒未経験の方も採用されやすく、転職の成功率も比較的高めです。
とくに工業高校卒の方は基礎知識を評価され、選考で有利になる可能性が高いです。
③ナイト系スタッフ
ナイト系のスタッフ職は、高卒・未経験からでも挑戦しやすく、スタート時点から比較的高収入を狙える職業です。
電気工事士のように資格を取らなくても給料が高めに設定されている点は大きな魅力といえます。
また、年齢や経験を問わず、実力次第でスピード出世が可能なため、若いうちから責任あるポジションを目指すこともできます。
さらに、独立支援制度を用意している企業もあり、実力次第で将来的に自分の店舗を持つというキャリアも築けるでしょう。
店舗運営だけでなく、Webサイト運営・送迎ドライバー・撮影スタッフなど職種は多岐にわたり、興味のある分野でスキルを磨くことができます。
高卒で電気工事士になるためのおさらい

電気工事士は、高卒未経験も含めて誰でも目指せる職業です。
最初は、見習いからのスタートになるので年収がやや低くなりますが、資格を取得したりスキルを磨いたりしながら経験を積んでいくことで、日本の平均年収より高い収入を得られる可能性があります。
また、電気は暮らしに欠かせないインフラの一つであり、今後も電気工事士の需要は高まっていくと予想されているため、将来性のある職業なのも魅力です。
もちろん向き・不向きやメリット・注意点はあります。これらをすべて把握したうえで、それでも電気工事士になりたいと思った方は、さっそく転職活動をスタートしてみましょう。