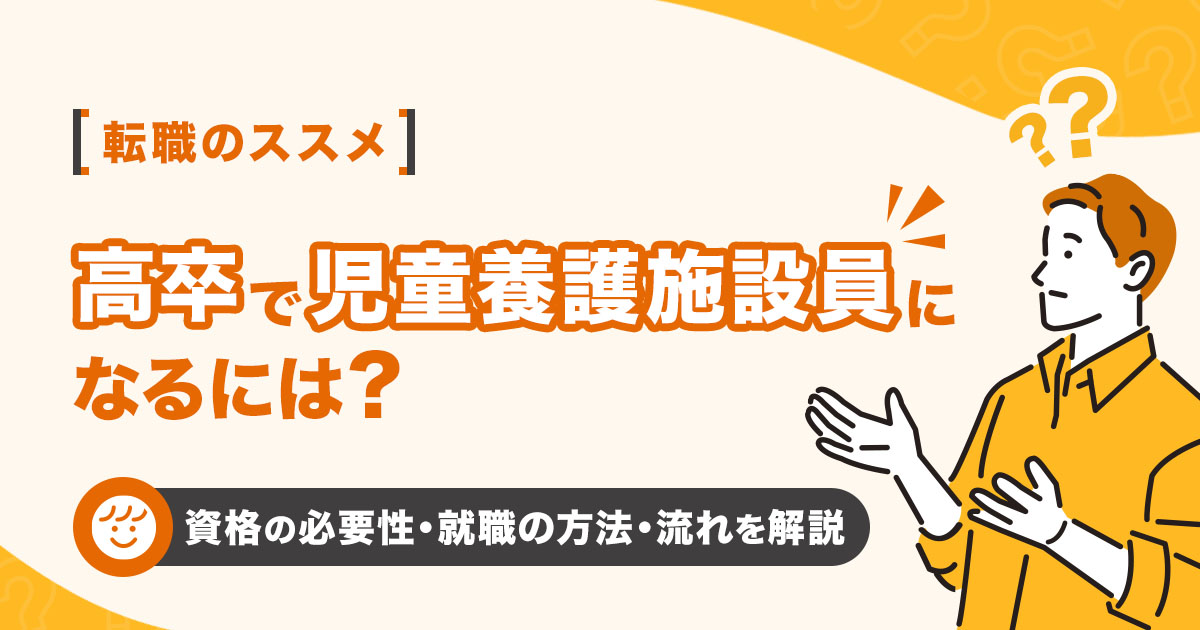-
児童養護施設で働きたいけれど、高卒では難しいの?
-
高卒で児童養護施設で働くのに必要な資格はあるの?
今回は児童養護施設で働きたいと考えている高卒に向けて、職員になる際におすすめの資格や目指す手順を紹介します。
また、児童養護施設職員になったあとのキャリアパスや向いている人・向いていない人の特徴、目指すメリット・デメリットについても詳しくご紹介します。
児童養護施設で働きたいと考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。
高卒が児童養護施設で働くには資格があったほうがいい

大前提として、高卒も資格なしで児童養護施設で働けます。
ただし、無資格でも応募可能な求人のほとんどは非正規の募集で、その数も決して多くありません。
もし正社員雇用を目指すなら、仕事に役立つ資格を取得するのがおすすめです。
児童養護施設で暮らす子どもは、複雑な家庭環境の影響でさまざまな悩みや不安を抱えています。子どもの気持ちに配慮しつつ、生活援助・指導を行う必要があるため、専門的な知識やスキルがあると証明できる資格を取得しておいたほうが就職活動に有利です。
本記事では、正社員を目指すことを想定して、児童養護施設職員になる基本条件や手順を紹介します。
児童養護施設職員になる基本条件
高卒で児童養護施設職員を目指すなら、まずは「児童養護施設職員」とはどのような仕事かを理解しておくことが大切です。
児童養護施設では、さまざまな専門職が協力して子どもたちの生活や成長を支えています。「児童養護施設職員」には、具体的に以下のような職種が挙げられます。
- 児童指導員
- 保育士
- 家庭支援専門相談員
- 里親支援専門相談員
- 看護師
- 医師・嘱託医
- 栄養士
この中でも、「児童指導員」は子どもたちの生活指導や学習支援を行う中心的な存在であり、高卒からでも比較的目指しやすい職種です。
児童指導員になるには「児童指導員任用資格」の取得が必要ですが、他の国家資格と比べて取得のハードルが低いのが特徴です。
高卒で児童養護施設の正社員を目指す上で、現実的かつ有力な選択肢と言えます。
児童指導員任用資格とは
先述した通り、児童指導員任用資格は、児童指導員として働く時に取得が義務付けられている資格です。
- 【児童指導員とは】
- 主に保護者と一緒に暮らすのが難しい子どもや障害を持つ子どもが入所する施設で、子ども達の生活支援及び健全な成長を促すための指導を行います。
児童養護施設の場合、原則2歳〜18歳未満の子どもを対象に、一人ひとりに合った支援計画を立ててサポートするのが主な役割です。
児童指導員任用資格を取得するためには、以下の5つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
出典: 職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「児童指導員」(参照 2025-04-26)1.4年制大学や通信制大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学部、学科を卒業していること
2.社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得していること
3.高校若しくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事していること
4.3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること
5.幼稚園教諭、小中学校、高等学校の教員免許を所有しており、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること
高卒の場合、児童福祉事業に2年以上従事するルートが、最短で児童指導員任用資格を取る方法になります。
児童養護施設職員の学歴内訳
児童指導員の学歴内訳は、以下の通りです。
| 学歴 | 割合 |
|---|---|
| 高卒 | 8.6% |
| 専門学校卒 | 13.8% |
| 短大卒 | 20.7% |
| 大卒 | 51.7% |
| 修士課程卒 | 1.7% |
| 博士課程卒 | 0% |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「児童指導員」(参照 2025-04-26)
※すべてを足しても100%になるとは限りません
学歴内訳を見るかぎり、児童指導員の約7割が短大卒もしくは大卒以上です。これは、短大や大学で所定の課程を修了して児童指導員任用資格を取った人が、卒業後に児童指導員として働いていることが要因として考えられます。
高卒で児童指導員になった人の割合は全体の8.6%になります。
決して高い数字ではないものの、高卒で児童指導員として働いている人は存在するので、努力次第で目指すことは可能です。
高卒で児童養護施設職員になる手順

ここからは、高卒で児童指導員として正社員の児童養護施設職員になる手順を紹介します。
- 児童養護施設でアルバイトやパートとして実務経験を2年以上積む
- 児童指導員任用資格を取得する
- 正社員登用を目指すor正社員の求人に応募する
高卒で児童養護施設で働きたい人は、ぜひチェックしてみてください。
児童養護施設でアルバイトやパートとして実務経験を2年以上積む
まずは、児童指導員任用資格の取得条件をクリアするために、児童福祉事業で2年以上の実務経験を積む必要があります。
2年以上の実務経験とは、実務年数が2年以上かつ360日以上従事することを指します。これは、週4日程度勤務すればクリアできる計算です。
実務経験を積める児童福祉事業は、児童福祉法で「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」に定められている以下の施設が当てはまります。
- 児童養護施設
- 福祉型障害児入所施設(指定管理施設)
- 障害者支援施設(指定管理施設)
- 障害福祉サービス事業(指定管理事業)
児童指導員を目指すなら、最初から児童養護施設の求人に応募するのが得策です。
ただし、実務経験として認められるのは、上記の施設で「障害児等への直接支援または相談業務」に従事している場合に限ります。児童養護施設で働いているからといって、すべての業務が実務経験に該当するわけではないので、事前に仕事内容を確認しておきましょう。
なお、先述した通り、無資格で応募できる児童養護施設のほとんどは非正規雇用です。そのため、最低でも2年間はアルバイトやパートとして働くことになります。
児童指導員任用資格を取得する
児童養護施設で2年以上の実務経験を積めば、児童指導員任用資格を取得できます。別途試験を受けたり免許証を申請したりする必要はありません。
ただし、児童指導員として働けることを証明するためには、勤め先の児童養護施設で「実務経験証明書」を発行してもらう必要があります。
発行期間は施設によって異なるものの、2週間〜1カ月程度かかります。正社員の児童指導員に応募する際に「任用資格の取得を証明できない」という事態に陥らないように、早めに手続きを済ませておきましょう。
また、自治体によっては実務経験証明書のフォーマットが決まっている場合があります。自分が住んでいる自治体で実務経験証明書に関する規定があるかどうか、事前に確認しておくのが重要です。
社員登用を目指すor正社員の求人に応募する
児童指導員任用資格を取得したあと、以下の方法で正社員を目指します。
- 在職中の児童養護施設で社員登用制度を利用する
- 正社員を募集する別の児童養護施設に就職する
勤め先の児童養護施設に社員登用制度がある場合、職場環境に不満がなければこの制度を利用するのがおすすめです。
社員登用制度を利用できる条件は施設によって異なるものの、日頃から業務に対して真摯に取り組み、正社員になりたいとしっかりアピールすれば前向きに検討してもらえる可能性があります。
在職中の児童養護施設での社員登用が難しい場合、正社員を募集する施設の求人に応募しましょう。児童養護施設の正社員求人を探す時は、ハローワークや転職サイトを活用するのがおすすめです。
児童養護施設の採用試験は、面接とは別にグループディスカッションを取り入れるケースもあります。
どの形式の試験でも対応できるように対策しておくことが、児童養護施設の採用試験を突破するコツです。
高卒で児童養護施設職員になったあとのキャリアパス

高卒で児童指導員になったあと、次のようなキャリアパスが築ける可能性があります。
- 施設長に昇進する
- 児童発達支援管理責任者を目指す
主に施設長として児童養護施設の運営に携わるルートと、児童発達支援管理責任者に転身するルートがあります。
それぞれどんなキャリアパスが築けるのか詳しく解説していくので、児童福祉業界で長く活躍したい人はぜひ参考にしてください。
施設長に昇進する
児童指導員は、施設職員としての経験を活かして、施設長に昇進するキャリアパスがあります。
- 【施設長とは】
- 施設の運営や職員の管理、運営方針などを決める役割を担う責任者を指します。
高卒の場合、「勤務する施設と同じ種別の施設で3年以上の勤務経験がある人」もしくは「自治体から同等以上の能力があると認められ、所定の講習を修了した人」であれば、施設長になる要件を満たせます。
児童養護施設の施設長になるためには、以下のようなスキルが求められます。
- マネジメントスキル
- 指導力
- 観察力
- 問題解決力
施設長は、「親を頼れない子どもの成長と自立を支援する」という児童養護施設の役割を十分理解したうえで、施設運営や職員の管理を行う必要があります。
児童発達支援管理責任者を目指す
児童指導員としての知識やスキルを活かして、児童発達支援管理責任者を目指すルートもあります。
- 【児童発達支援責任者とは】
- 主に児童発達支援施設や放課後等デイサービスなどの障害のある子どもを支援する施設で、子どもとその家族、職員への支援・指導・助言を行うリーダーの役割を担います。
児童発達支援施設には、必ず児童発達支援管理責任者を1名以上配置することが定められています。
児童発達支援管理責任者の主な仕事内容は、「個別支援計画書の作成」「子どもへの支援・療育の進捗管理」です。児童指導員の経験を活かしてキャリアチェンジを図りたい人に適しています。
児童指導員が児童発達支援管理責任者になるためには、児童養護施設で児童相談業務に5年以上従事したあと、2種類の研修を修了することが求められます。
高卒で児童養護施設職員に向いている人・向いていない人

ここでは、高卒で児童指導員に向いている人と向いていない人の特徴をそれぞれ解説します。
児童指導員は、子どもの成長を直接サポートする役割を担うことから、人によって向き不向きが出やすい職業です。
自分に児童指導員が適しているかどうかの判断材料としてお役立てください。
| 児童指導員に向いている人 | 児童指導員に向いていない人 |
|---|---|
| 子どもの成長に興味関心がある | リスク管理能力に長けていない |
| コミュニケーションが得意 | 忍耐力がない |
| 体力がある | 向上意欲がない |
向いている人の特徴①子どもの成長に興味関心がある
児童指導員は、複雑な家庭事情を抱える子どもとしっかり向き合い、深い愛情を注ぐことが求められます。そのため、子どもの成長に興味関心がある人に向いている職業です。
子どもを成長させるうえで、一人ひとりの性格や特性を把握し、時には親代わりとして接することが欠かせません。たとえ反抗されたとしても、子どもの健全な成長のために根気強く接する必要があります。
これらの業務は、子どもへの興味関心がないと難しいと言えるでしょう。
向いている人の特徴②コミュニケーションが得意
児童指導員は、子どもとのコミュニケーション能力が求められる職業です。
児童養護施設に入所する子どもの中には、過去のトラウマで大人と接することを極端に嫌う子や、心を開くことに恐怖心を抱いている子も存在します。
コミュニケーションを取るのが難しい子どもとも良好な関係を築く必要があるので、コミュニケーション能力に長けた人は児童指導員に向いている可能性が高いです。
向いている人の特徴③体力がある
児童指導員は、大半の勤務時間を子どもと一緒に過ごすため、体力に自信がある人に向いている職業です。
子どもの中には、力加減ができない子や常に動き回る子もいます。そういった子どもを児童指導員が一人で面倒を見るケースも珍しくないことから、体力が求められる仕事と言っていいでしょう。
また、児童指導員は夜勤が発生する場合が多いです。不規則な勤務にも耐えられる体力がある人は、長く活躍できる可能性があります。
不向きな人の特徴①リスク管理能力に長けていない
児童指導員は、施設内で起こりうるさまざまなリスクを想定して行動しなければいけません。そのため、リスク管理能力が低い人は向いていないでしょう。
児童養護施設には、たくさんの子どもが入所しており、職員はその子どもたちの健康や命を守る役割を担います。万が一子どもが事件に巻き込まれたり、災害が発生したりした時も適切な対応ができるように意識しておくのが重要です。
また、子どもの些細な行動が思わぬ事故につながるかもしれないことを念頭に置いてリスクヘッジできる人は、児童指導員として活躍できる人材と言えます。
不向きな人の特徴②忍耐力がない
忍耐力がない人も、児童指導員として働くのは難しいです。
児童養護施設で生活する子どもの多くは、心に深い傷を負っているケースが多く、その反動で反抗的な態度を取ってしまう場合も珍しくありません。
たとえ暴言を吐かれたとしても、「子どもの健全な成長を支援する」という強い意思を持って根気強く接することが求められます。
子どもの成長を長い目で見守れる忍耐力がない人は、子どもと良好な関係を築くのが難しく、途中で挫折する可能性があります。
不向きな人の特徴③向上意欲がない
児童指導員は、施設の子どもに対して適切な支援をするために、常に学び続けることが求められます。そのため、児童養護に関する知識やスキルを高める意欲がない人には厳しい職業です。
子どもは、成長するにつれて考え方が変わっていきます。児童指導員は、変化する子どもの考えに合わせて適切な支援を考えなければいけないので、知識やスキルの習得は必要不可欠です。
児童養護に関する知識やスキルを習得する方法は、主に施設内で実施される研修や講義、外部セミナーの参加があります。
高卒で児童養護施設職員になるメリット・デメリット

ここでは、高卒で児童指導員になるメリット・デメリットを解説します。
メリット・デメリットを理解しておけば、本当に自分に合う職業かどうか見極めやすくなります。
児童指導員を目指すべきかどうか悩んでいる人は、ぜひご覧ください。
| 高卒で児童指導員になるメリット | 高卒で児童指導員になるデメリット |
|---|---|
| 子どもが成長していく姿を見られる | 夜勤などがあり大変な場合も |
| 密に子どもとコミュニケーションを取れる | 子どもとの接し方が難しい場合も |
| 他業界へのキャリアチェンジがしやすい | 子どもを支援する責任が大きい |
メリット①子どもが成長していく姿を見られる
児童指導員は、子ども一人ひとりに適した生活支援や指導をしていく役割を担っています。
自分が支援する子どもが成長していく姿を間近で見られるのは、児童指導員ならではのメリットでしょう。
入所当初はコミュニケーションもままならなかった子どもが、職員による支援や指導を通して徐々に意思疎通が取れるようになり、自立していきます。立派に成長した子どもが自分に明るく接してくれる姿を見て、達成感ややりがいを得やすいです。
メリット②密に子どもとコミュニケーションを取れる
子どもと密なコミュニケーションを取れる点も、児童指導員になる長所の一つです。
児童指導員は、子どもとほぼ同じ時間を過ごします。そのため、特に子ども好きな人や幅広い年代の子どもと接したい人は有意義に働ける職業と言えます。
子どもは職員のことを保護者に近い存在として認識している場合が多いです。血のつながりがなくても、まるで親子や兄弟のような関係を築きやすいのは、児童指導員になる大きな利点になるでしょう。
メリット③他業界へのキャリアチェンジがしやすい
児童指導員は、業務を通じてさまざまな業界で求められるスキルを磨けるので、他業界へのキャリアチェンジに成功しやすいメリットもあります。
児童養護施設で働けば、主に以下のスキルが身に付きます。
- コミュニケーションスキル
- リスク管理能力
- 忍耐力
- 業務に関する学習スキル
これらのスキルは、福祉以外の業界においても役立つ場面が多いです。そのため、今後未経験の職種に転職したとしても、児童指導員で培った経験が活かせる可能性があります。
デメリット①夜勤などがあり大変な場合も
児童指導員は、子どもたちを24時間体制で支援する必要があるため、基本的に夜勤が発生します。また、土日祝日の勤務がある施設も少なくありません。
このように、勤務時間や休日が不規則であるがゆえに、プライベートの時間を確保しにくいデメリットがあります。
ただでさえ体力が求められる業務が多いのにくわえて、ワークライフバランスも取りにくいことから、人によっては体調を崩すリスクを考慮しなければいけないでしょう。
デメリット②子どもとの接し方が難しい場合も
児童指導員は、すべての子どもに対して、施設に入所することになった経緯や現在抱えている問題などを理解したうえで接する必要があります。高度なコミュニケーションスキルが求められる点は、働く際に課題になりうると言えるでしょう。
ある子どもにとっては適切な対応だったとしても、別の子どもに同じ対応をすると不本意に傷つけてしまうケースも珍しくありません。
時には子どもから反抗的な態度を取られる場合もあるので、子どもとの接し方に悩んでしまう可能性があります。
デメリット③子どもを支援する責任が大きい
児童指導員は、子どもにとって保護者のような存在です。子どもの生活支援や指導を行い、健全な成長を促す役割を担います。
子どもの人格形成に強く影響するため、一つひとつの業務を責任を持って行う必要があります。
児童養護施設で暮らす子どもの心はとても繊細です。自分の言動がその子どもの人生を左右するきっかけになることもありえます。
大きなやりがいを感じられる仕事であるメリットがある一方で、重い責任を背負わなければいけないデメリットもあるので、人によっては大きなプレッシャーにつながるリスクも考えられます。
高卒で児童養護施設職員になるためのおさらい

高卒でも児童養護施設で働くことは可能です。
多くの場合、最初は非正規雇用からのスタートとなりますが、正社員を目指すことも十分にできます。
中でも「児童指導員」は、高卒から目指しやすい職種のひとつです。
子どもたちの生活や学習を支える中心的な役割を担い、「児童指導員任用資格」があれば働くことができます。
この資格は、他の福祉系職種に必要な国家資格と比べて取得しやすいのが特徴です。
この職種は、子どもの成長を間近で感じられるやりがいのある一方、夜勤やシフト勤務があり、生活リズムの管理が難しい一面もあります。
また、正社員になれば、施設長や児童発達支援管理責任者など、将来のキャリアも広がります。
このようなメリットとデメリットを理解したうえで、今日から準備を始めましょう!