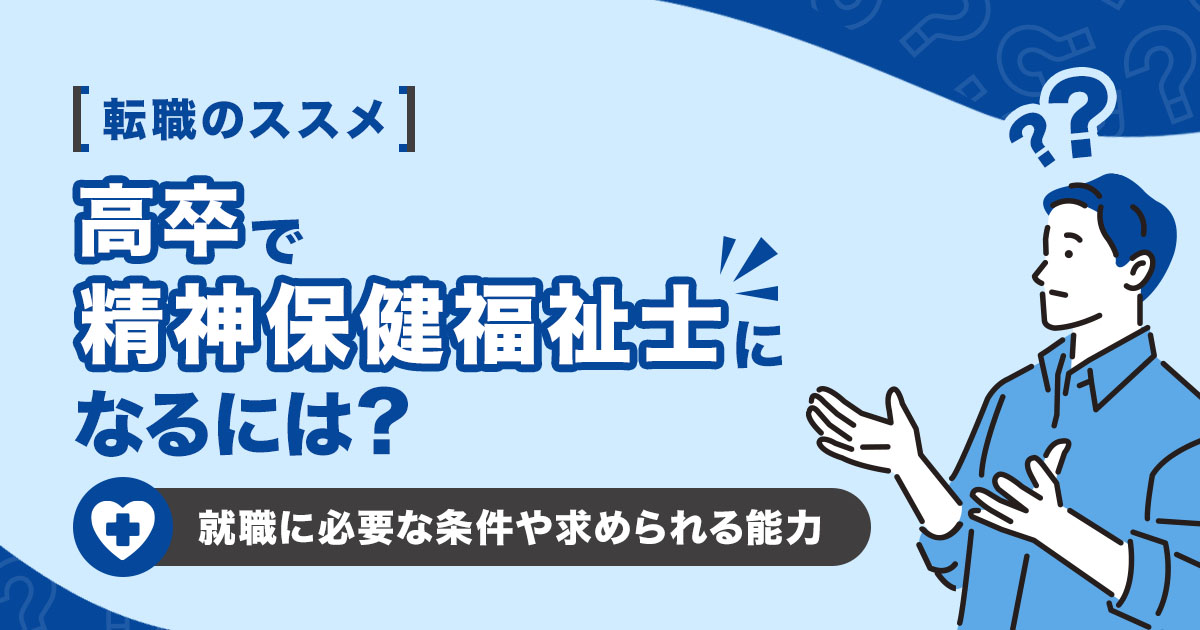-
精神保健福祉士は高卒で目指せるの?
-
高卒で精神保健福祉士になるにはどうすれば良い?
精神保健福祉士は「福祉系の大学や専門学校を卒業しないとなれない」と思われがちですが、実は高卒から目指せる仕事です。
ただし、仕事内容は専門性が高く相応の知識が求められるので、精神保健福祉士になるまでに十分な学習が必要です。
本記事では、高卒で精神保健福祉士になるための条件や手順、向いている人と向いていない人の特徴、就職後のキャリアプランなどを詳しく解説します。
高卒で精神保健福祉士になれるが学歴以外の条件がある

精神保健福祉士は、高卒が目指せる職業です。
高卒のまま精神保健福祉士になるには、以下の条件を満たし、精神保健福祉士国家試験に合格する必要があります。
- 厚生労働大臣が定める施設で相談援助の実務経験を4年積む
- 厚生労働大臣が指定する一般養成施設等で1年以上学ぶ
精神保健福祉士として働き始めるまでには、最短ルートでも資格取得に合計5年はかかります。
「今すぐに精神保健福祉士になれるわけではない」という点は念頭に置きましょう。
精神保健福祉士国家試験の合格内訳

2025年2月に実施された第27回精神保健福祉士国家試験の合格結果をもとに、合格内訳をご紹介します。
精神保健福祉士国家試験の受験条件を満たす方法は複数あります。以下の表では、国家試験の受験ルートごとの合格率をまとめました。
高卒は「④一般養成施設等(1年以上)ルート」に該当します。
| 受験ルート | 合格率 |
|---|---|
| ①保健福祉系大学等(4年制)ルート | 69.8% |
| ②保健福祉系大学等卒+実務経験ルート | 37.4% |
| ③短期養成施設等(6ヶ月以上)ルート | 78.4% |
| ④一般養成施設等(1年以上)ルート | 63.4% |
参考:厚生労働省「第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(参照2025-07-03)
高卒を含む④のルートは、大卒の割合を大きく占める①③のルートと合格率に大きな差はありません。
④のルートのうち高卒の割合は不明ですが、合格率が6割を超えていることから、しっかり試験対策すれば高卒も合格を十分狙えるといえます。
高卒で精神保健福祉士になる手順

高卒で精神保健福祉士になる方法と手順は以下のとおりです。
- 厚生労働大臣が定める施設で相談援助の実務経験を4年積む
- 指定の一般養成施設(1年以上)に入学する
- 必要な科目と実習を履修する
- 精神保健福祉士国家試験に合格する
- 精神保健福祉士として登録する
ここからは、高卒で精神保健福祉士を目指す最短ルートの手順を解説します。
相談援助の実務経験を積める施設や一般養成施設の学費、精神保健福祉士国家試験の概要、免許登録の方法などご紹介するので、精神保健福祉士に興味がある方はぜひご覧ください。
手順①厚生労働大臣が定める施設で相談援助の実務経験を4年積む
まずは厚生労働大臣が定める施設で相談援助の実務経験を4年積むことから始めましょう。
実務経験が積める施設の代表例は以下のとおりです。
- 精神科病院
- 児童相談所
- 保健所
- 精神病床を有する診療所
- 更生施設
など
たとえば病院の精神科ソーシャルワーカーや保健所の精神保健福祉相談員として働くことで、相談援助の実務経験として認められます。
また、施設の相談員以外の職種でも「認定範囲の業務に携わっている」と認められれば、実務経験としてカウントされます。
参考:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験 受験資格」(参照2025-07-15)
手順②指定の一般養成施設(1年以上)に入学する
相談援助の実務経験を積んで一般養成施設の入学資格を得たら、一般養成施設にて1年以上カリキュラムを履修します。
一般養成施設は、精神保健福祉士や社会福祉士を目指す人が、より高度な専門知識とスキルを習得するために通う施設です。
ここでカリキュラムを履修することで、精神保健福祉士国家試験の受験資格が得られます。
一般養成施設で学ぶには、入学金に加えて授業料などで130万円ほどかかるのが相場です。
ただし、精神保健福祉士の資格取得にあたって、勤務している施設長や医院長から推薦を受けられれば、学費や入学金が減免されることもあります。
また、条件を満たせば個人で教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)や携教育ローンの利用も可能です。
ご自身がどんな制度を活用できるのかは、あらかじめ調べておきましょう。
手順③必要な科目と実習を履修する
一般養成施設では、合計1200時間の学習時間が設定されており、以下のカリキュラムを履修します。
- 全科目合計990時間の座学カリキュラム
- 210時間の実習
一般養成施設のカリキュラムを全て履修すると、国家試験の受験資格が得られます。
ただし、実務経験があれば一般養成施設の学長判断で実習が免除される場合があります。
- ポイント
- 【実習の免除について】
厚生労働省が指定する施設で、1年以上相談援助の業務に従事してから入学した方は精神保健福祉援助実習の履修を免除できます。
参考:厚生労働省「Ⅳ-⑥実務経験に対する実習免除の取り扱い」(参照2025-07-15)
手順④精神保健福祉士国家試験に合格する
一般養成施設等で必要なカリキュラムを履修したら、いよいよ精神保健福祉士国家試験を受験します。
精神保健福祉士国家試験の概要は以下のとおりです。
| 試験日 | 毎年2月頃 |
| 試験地 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |
| 試験科目 | 社会福祉士・精神保健福祉士共通科目、専門科目 |
| 試験形式 | 五肢択一方式を基本に、五肢択二、四肢択一の問題あり |
| 受験料 | 24,140円 |
| 合格率 | 70.7%(2025年度) |
| 合格条件 | 総得点の正答率が60%程度ある(問題によって難易度補正あり) 試験科目9科目群、全てにおいて得点がある |
受験に関する手引きは毎年8月上旬頃にセンター公式サイトから請求できるので、詳細はそちらを参考にしましょう。
手順⑤精神保健福祉士として登録する
精神保健福祉士国家試験に合格したら、精神保健福祉士の資格登録手続きが必要です。精神保健福祉士の登録には19,050円(登録免許税15,000円+登録料4,050円)ほどかかります。
合格通知に同封される登録の手引きに従って「税金と登録料の支払い」にくわえ、「戸籍に関する書類の取得」「登録申請書類の記入」を済ませましょう。
登録の準備が整ったら、必要書類を書留で返送してください。1ヶ月ほど審査期間があり、登録されると精神保健福祉士登録証が届きます。
登録証が手元に届けば、精神保健福祉士と名乗ることができ、「精神保健福祉士の資格必須」の求人にも応募可能です。
高卒で精神保健福祉士になるための試験対策

高卒で精神保健福祉士になるための試験対策方法を3つ解説します。
- 合格ラインを把握する
- 模試を受けて自分の弱点を洗い出す
- 3年分の過去問題を繰り返し解く
2025年度の精神保健福祉士国家試験の合格率は70.7%で、資格取得の難易度は比較的高いものではないとされています。
しかし、出題範囲が広く、専門知識がなければ解けない問題も多いため、事前にしっかり対策しておくことが大切です。
これから解説する試験対策を参考に、効率的に勉強を進めましょう。
①合格ラインを把握する
まずは、試験合格に必要な最低ラインを把握しておくことが大切です。
【精神保健福祉士国家試験の合格ライン】
- 全体の正答率60%程度(問題によって難易度補正あり)
- 試験科目9科目群、全てにおいて得点がある
つまり、得意科目を伸ばしつつ、各試験科目で0点回避を目指す勉強法が必要です。
精神保健福祉士国家試験は全132問と問題数が多く、出題範囲も広いです。
初めから高得点は目指すのではなく、60%程度の合格ラインを確実に達成できるよう対策を立てましょう。
専門性を深く追求するよりも全科目を網羅的に勉強することが試験合格の近道です。
②模試を受けて自分の弱点を洗い出す
効果的な勉強法として、精神保健福祉士国家試験の模擬試験を受けて、自分の弱点や苦手科目を洗い出す方法がおすすめです。
模試は、いくつかの団体が定期的に実施しています。
本試験では1科目でも0点があると不合格なので、まずは模試で自分の弱点を正確に把握し、克服を目指しましょう。
なお、模試の受験スタイルは「Web受験」と「会場受験」の2つあります。
- ポイント
- 【Web受験のメリット】
1年を通して好きなタイミング、好きな場所から受験できる。自分の学力を把握したいときに適している。
【会場受験のメリット】
模試会場へ出向いて本試験に近い環境で受験できる。国家試験前の予行練習に向いている。
模試は年に何度でも受験可能なので、うまく活用して効率的な勉強や本試験の緊張緩和につなげてください。
③3年分の過去問題を繰り返し解く
精神保健福祉士国家試験に合格するためには、3年以内の過去問題を繰り返し解くことがおすすめです。
過去問題を繰り返し解くことで、試験全体の出題傾向が掴めます。また、得意分野と苦手分野の把握にも効果的です。
まずは去年の過去問題から3年前まで、さかのぼるように過去問題を解いていきましょう。
古い過去問題だと社会制度や医療制度の改訂が反映されていない可能性があるため、3年以内の過去問題を繰り返し解いたほうが、効率よく学習できるかもしれません。
大規模な法改正でも準備期間は2〜3年なので、基本的には3年以内と覚えておきましょう。
過去問題の反復でどれだけ知識が身についたかは、模試で確認するといいですよ。
高卒で精神保健福祉士になったあとのキャリアプラン

精神保健福祉士の資格を取得すると、医療、福祉、司法など幅広い領域で活躍できます。
高卒で精神保健福祉士になったあとの代表的なキャリアの選択肢は、以下の3つです。
- 精神科ソーシャルワーカーになる
- 社会復帰調整官を目指す
- 地域包括支援センターのスタッフとして働く
それぞれ解説しますので、自分のキャリアプランを立てる際の参考にしてください。
①精神科ソーシャルワーカーになる
精神保健福祉士の資格があれば、精神科病院や心療内科クリニックの精神科ソーシャルワーカーとして働けます。
- 参考
- 【精神科ソーシャルワーカーの仕事】
精神と心の病気を抱えている患者さんやその家族のサポートが主な仕事です。
入退院や通院の手続き、福祉サービスの紹介、ときには社会復帰支援や就労支援も行います。
精神科医療の現場では、入院患者数が減少している一方で、外来患者数は増加傾向です。
そのため、医師と同じくらい精神科ソーシャルワーカーのニーズが高まると予想されています。
精神保健福祉士の資格を活かして、総合病院のような規模の大きい医療機関に転職すると、キャリアアップや年収アップも目指せます。
②社会復帰調整官を目指す
精神保健福祉士の資格は、社会復帰調整官をはじめとした司法の場でも活かせます。
- 参考
- 【社会復帰調整官の仕事】
心神喪失や心神耗弱などの状態で重大な他害行為をした人の社会復帰を支援する仕事です。
生活環境の監督や通院・服薬状況の観察といった業務を行います。
多岐に渡るサポートを通して、対象者が社会復帰する姿を見守ります。
ただし、高卒で社会復帰調整官を目指す場合、精神保健福祉士の業務経験を9年以上求められます。
また、募集先によって応募条件が異なるケースも少なくありません。募集要項はよく読んで必要なら電話で確認を取りましょう。
社会復帰調整官になると、勤務成績に応じて以下のような役職へ昇任できる可能性もあり、精神保健福祉士の資格を活かして大きくキャリアアップしたい人にも適しています。
- 統括社会復帰調整官
- 首席社会復帰調整官
- 保護観察所長
参考:法務省「令和7年度 社会復帰調整官の採用案内」(参照2025-07-15)
③地域包括支援センターのスタッフとして働く
地域包括支援センターとは、高齢者の健康・生活全般の相談に対応し、さまざまな面から支援する地域拠点です。
- 参考
- 【地域包括支援センタースタッフの仕事】
地域の高齢者やその家族の相談窓口になり、サポートの提案を行う仕事です。
精神保健福祉士の資格があれば、認知症やアルコール依存症に対して、より専門的な提案を行うスペシャリストとして働けます。
地域包括支援センターにおいて、精神障がいや認知症の高齢者は増加傾向にあり、精神保健福祉士のニーズが高まっています。
事実、北海道旭川市では認知症総合支援事業を立ち上げ、精神保健福祉士の有資格者が活躍中です。
全国にこの動きが広がれば、将来的に役職者や上級現場スタッフとしての道が開き、ステップアップも目指せるでしょう。
参考:永山地域包括支援センター「地域包括支援センター、精神保健福祉士の業務」(参照2025-07-15)
高卒で精神保健福祉士に向いている人

精神保健福祉士に向いている人の主な特徴は、以下の3つです。
- 人と話すことが好きで共感力のある人
- 忍耐力があって切り替えが上手い人
- 継続的に学習ができる人
精神保健福祉士は専門性が高く、向き不向きがはっきりしている仕事です。
自分に適性があるかの判断材料になるので、向いている人の特徴を把握して、精神保健福祉士を目指すかどうかを考えましょう。
①人と話すことが好きで共感力のある人
人と話すことが好きな人は、精神保健福祉士に向いています。
なぜかというと、精神保健福祉士の仕事は根本部分にコミュニケーションがあるからです。
純粋に人と話すこと自体が好きな人は、その共感力の高さから相手の本音を引き出しやすいとされています。
話し上手や聞き上手だからこそ、問題の本質に触れやすいのは大きなアドバンテージです。
精神保健福祉士の仕事においては、サポートに必要な情報を会話から得やすいでしょう。
②忍耐力があって切り替えが上手い人
ストレスやトラブルに直面した際に、上手に気持ちを切り替えられる人は精神保健福祉士に向いています。
精神保健福祉士は業務上、辛い現実や問題に突き当たったり、相手から心ない言葉をぶつけられたりする場合があります。
また、サポートが計画通りに進まないケースもあるので、時間をかけて問題に向き合える忍耐力も重要です。
精神保健福祉士のこういった仕事の特性上、気持ちを切り替えて自分をケアできるという特徴は大きな武器になります。
③継続的に学習ができる人
自分から継続的に学習ができる人は精神保健福祉士に向いています。
精神保健福祉士は、医療制度や社会制度、法律が変わるたびに知識をアップデートをしなければなりません。
また、「精神的な不調」へのサポートを提案するといっても、その実情はさまざまです。うつ病や統合失調症、認知症、アルコール依存症など症状ごとに適したサポートがあります。
サポートの提案には十分な知識が必要なため、高い学習意欲を保てるのは精神保険福祉士に適した特徴です。
高卒で精神保健福祉士に向いていない人

精神保健福祉士に向いていない人の主な特徴は、以下の3つです。
- 我が強すぎる人
- スケジュール管理ができない人
- 協調性に欠ける人
高卒で精神保健福祉士を目指すなら、4年の実務経験や一般養成施設で1年以上のカリキュラム履修など時間も労力もかかります。
取得へ向けて動き始める前に向き不向きはよく確認しておきましょう。
①我が強すぎる人
精神保健福祉士は、相談者の選択肢を増やしたり患者さんの希望に基づいて支援したりするのが仕事です。つまり、我が強すぎる人には向いていません。
業務では、相手の気持ちに配慮しながら現状や問題を整理し、1つずつ丁寧に対応する必要があります。
他人に譲歩するのが苦手だと、相手と良好な関係が築けず、適切な対応が難しくなってしまいます。
自分の提案を押し付けるような態度を取ってしまう人も、相手から信頼されにくいため、精神保健福祉士には向かない傾向です。
②スケジュール管理ができない人
精神保健福祉士の業務は相談対応以外にも、他スタッフとの会議、行政機関とのやり取り、外部機関との折衝などスケジュールが詰まりがちです。
つまり、スケジュール管理が苦手だと各所への影響が大きく、精神保健福祉士として働くのが難しくなります。
時間に遅れたり予定を無断でキャンセルしたりすれば、相手からの信頼を損ね、仕事に大きな支障をきたします。
円滑な業務には、時間管理能力やスケジュール進行力が必要不可欠で、タイムマネジメントができない人には難しい仕事です。
③協調性に欠ける人
精神保健福祉士の仕事は個人で完結しないため、協調性に欠ける人にも不向きです。
業務をスムーズに進めるには、医師や行政関係者、民間のサポートなどとの連携が欠かせません。
精神保健福祉士は各関係者の意見をまとめ、最適な支援プランを立てる役割を任せられることも多く、協調性が重視されます。
協調性がなければ、関係各所で意見の相違やトラブルが発生した場合に問題を長引かせてしまい、適切な支援の提供も難しくなります。
高卒で精神保健福祉士になるメリット

高卒で精神保健福祉士になるメリットは、以下の3つです。
- 取得さえできれば就職・転職にとても有利な資格
- 行政機関や司法関係など幅広いキャリアを築ける
- 正規職員として働きやすい資格
精神保健福祉士はニーズの高い資格ですから、取得できれば望んだキャリアを実現させやすいのがメリットです。ここでは、各メリットについて詳しく解説します。
①取得さえできれば就職・転職にとても有利な資格
高卒で精神保健福祉士国家試験に合格するのは努力が必要ですが、一度資格を取得してしまえばその後の就職・転職で非常に有利です。
精神保健福祉士の国家資格は、自身が持つ技能や知識を国が認定したことを示すものです。そのため、医療機関や介護施設からの信頼が厚く、さまざまな場で活躍できます。
また精神保健福祉士は、認知症やアルコール依存症を患う人へ提案とサポートができる資格です。
その専門性を活かせば、行政機関や地域の福祉施設でスペシャリストとしてのキャリア形成も可能です。
②行政機関や司法関係など幅広いキャリアを築ける
精神保健福祉士の資格があれば、行政機関や司法関係のキャリアも築けます。
精神保健福祉士は精神に不調を抱える人を助けるエキスパートです。その特性から近年は特に司法分野でのニーズが高まっています。
この他にも、教育機関や企業などでカウンセラーとして働く道もあり、多様な職場でスキルを生かせるのは大きなメリットです。
このように精神保健福祉士の資格を取得すれば就職の選択肢が一気に広がります。
③正規職員として働きやすい資格
精神保健福祉士は、正規職員として働く人が多い資格です。厚生労働省の資料によると、正規職員として勤務する精神保健福祉士の割合は約80%にも上っています。
また、昨今は認知症へのサポートが求められており、高齢者が多く福祉の届きにくい地方でのニーズが高いのも特徴です。
都市部と地方を問わず正規職員として働きやすいです。
精神保健福祉士の資格は、安定を求める人にとってもおすすめの資格といえます。
参考:厚生労働省「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の「就労状況調査」(速報版)について」(参照2025-07-15)
高卒で精神保健福祉士になる注意点

高卒で精神保健福祉士になる注意点は以下の3つです。
- 取得までかなりの時間がかかる
- 資格取得後も継続的な学習が求められる
- 業務によっては精神的に疲弊しやすい
精神保健福祉士は資格取得までに時間と労力がかかるだけでなく、資格取得後も努力が求められます。
資格取得を検討する際は、注意点までしっかり把握することが大切です。
①取得までかなりの時間がかかる
高卒で精神保健福祉士の資格を取得するには、最速でも5年かかります。
相談援助の実務経験を4年積むのに加え、一般養成施設等で1年以上学習する必要があり、決して短い時間ではありません。
また、一般養成施設で学ぶには入学金や授業料が必要なので、学習スケジュールだけでなく資金計画もきちんと立てておかなくてはいけません。
精神保健福祉士の取得を目指すなら、金銭的にも苦しくならないよう、働きながら実務経験を積む4年の間にお金を貯めておくのがおすすめです。
②資格取得後も継続的な学習が求められる
精神保健福祉士の国家資格は「取得したら勉強終了」ではなく、働く限り継続的な学習が求められます。
精神保健福祉士の資格には更新制度がなく、たとえ勉強をしなくても資格の剥奪や失効はありません。
しかし、社会制度や法律などの知識をこまめに更新しないと患者さんを適切にサポートできず、人材として求められなくなってしまいます。
制度・法律が変わるたびに再学習を要する点をよく理解してからの挑戦をおすすめします。
③業務によっては精神的に疲弊しやすい
精神保健福祉士の業務は精神的に疲弊しやすく、メンタル面の不調を理由に離職する人もいます。
精神保健福祉士は、精神的な不調を抱える本人やその家族のサポートをすることが多い一方で、常に全員を良い方向にサポートできるとは限りません。
力を尽くしても患者さんの症状が悪化するケースもあり、責任感が強い人ほど自責の念や後悔を抱きやすいです。
また、職場や業務によっては利用者から心ない言葉をぶつけられる場合があり、強いストレスを感じるときがあります。
精神保健福祉士以外のおすすめの仕事

精神保健福祉士以外にも福祉で人の役に立つ仕事は存在します。
ここからは、精神保健福祉士に近い特徴や共通点を持つおすすめの仕事を2つ紹介します。
- 介護施設での生活相談員
- 見守りスタッフ
精神保健福祉士は取得までに最短でも5年かかり、取得後も継続的な学習が求められる仕事です。
自分の適性や特徴を考えて、別の選択肢も考えたい方はぜひ参考にしてください。
①介護施設での生活相談員
民間の介護施設であれば、精神保健福祉士の資格がなくても生活相談員としてサポート業務ができます。
生活相談員は、入退所手続き、施設利用者とその家族の相談援助、外部機関との調整などが主な業務内容です。
施設利用者との距離が近いからこそサポートできているという実感を得やすく、精神保健福祉士と同じくらい充足感を感じるでしょう。
生活相談員の求人を探す際は、介護職に特化した転職サービスを使うと、自分に合った職場が見つかりやすくなります。
②見守りスタッフ
見守りスタッフとは訪問介護の一種で、要介護度の低いお年寄りを見守る仕事です。
利用者が自分でできることは尊重しつつ、行動や様子を観察して、事故を未然に防いだり必要に応じて声かけをしたりします。
見守りスタッフは、単発や短期のアルバイトとして募集されるケースもあり、比較的気軽に挑戦しやすいのも利点です。
精神保健福祉士に向いているかを判断する基準として「介護業界の実情をちゃんと把握したい」と考える人にもおすすめです。ぜひ一度求人を探してみてください。
高卒で精神保健福祉士になるためのおさらい

高卒で精神保健福祉士になるには、国家試験を受験して資格を取得しなければなりません。
受験資格を得るには「相談援助の実務経験を4年」と「一般養成施設等で1年以上のカリキュラムの履修」が必要です。
資格を取得すれば、医療福祉だけでなく行政や司法分野も目指せるなど、就職の選択肢が大きく広がります。
ただし、高卒で精神保健福祉士になるには最短でも5年かかるうえ、就職してからも継続的な学習を求められます。
メリットとデメリットを把握したうえで、それでも精神保健福祉士になりたいと考えるなら、資格取得に向けて行動を開始しましょう。