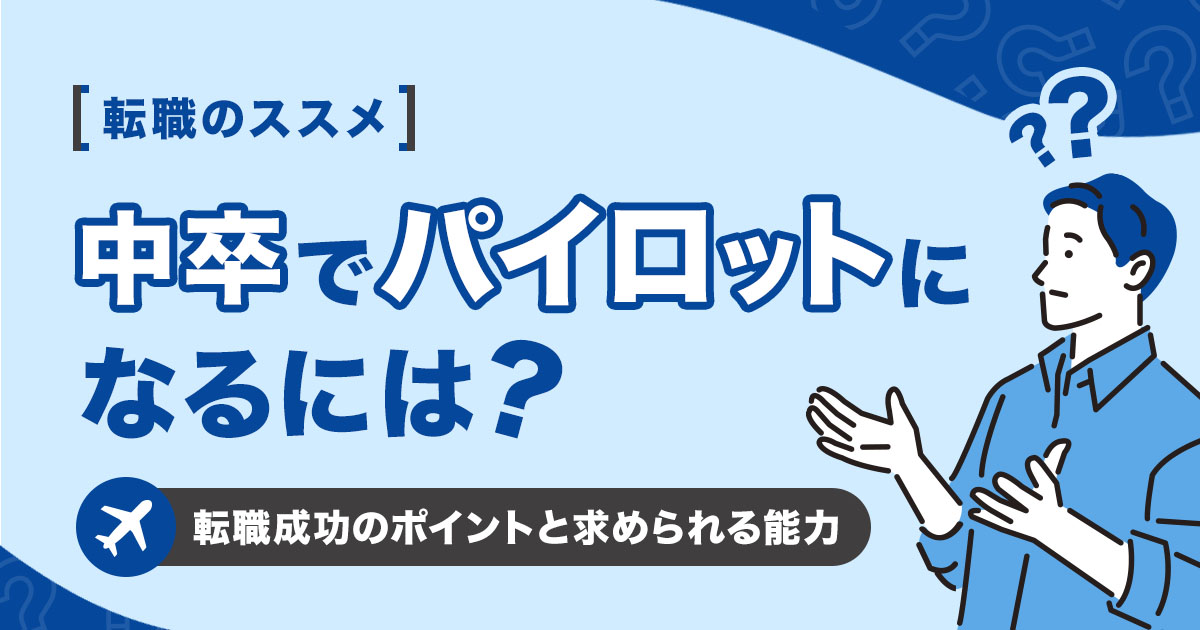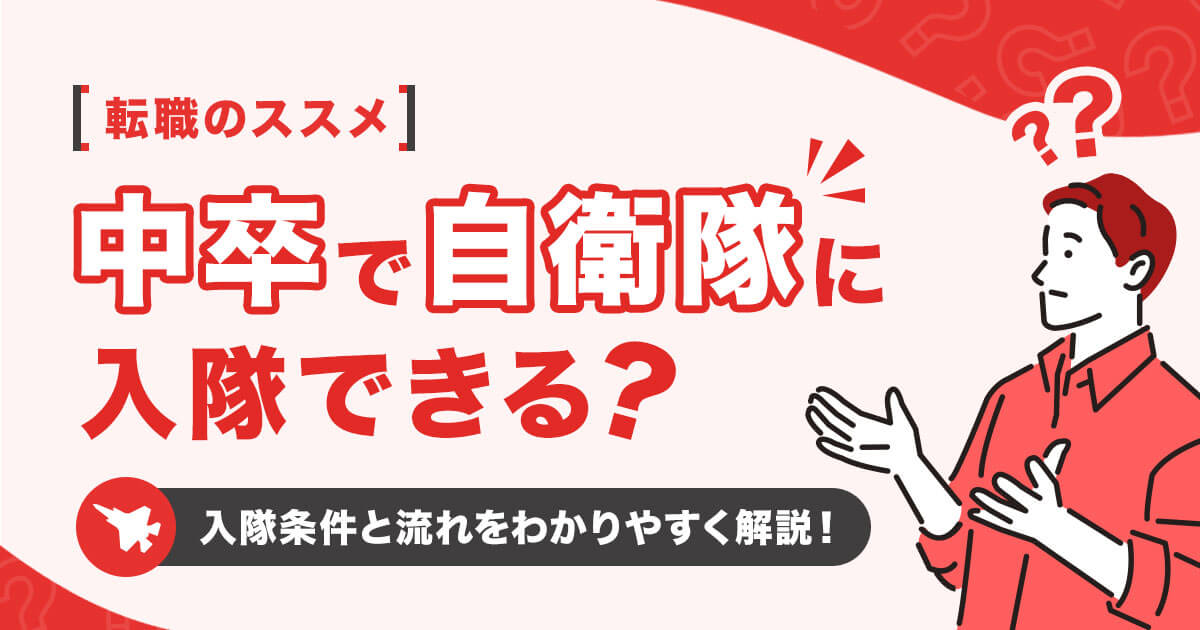パイロットとは、飛行機やヘリコプターの操縦者を指します。
多くの人が憧れる職業の一つとして知られていることから、「どうやってパイロットになるんだろう?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
パイロットになる方法自体はいくつかありますが、今回は中卒者がパイロットを目指す現実的な方法を解説します。
パイロットに向いている人の特徴や、中卒でパイロットになる手順、試験の特徴も紹介するので、ぜひご一読ください。
中卒でパイロットになることはできる

パイロットは、中卒のままでは目指すのが難しい職業です。
パイロットになる主なルートとして、以下の5つが挙げられます。
- 航空大学校へ進学する
- パイロット養成コースのある専門学校や私立大学へ進学する
- 防衛大学校の幹部候補生となる
- 大手航空会社に就職して自社養成パイロットになる
- 航空学生として自衛隊に入隊する
ただし、ご紹介したルートは高卒や大卒でないと目指せなかったり、学歴による制限がない場合にも競争率の高さから、中卒の入社が極めて難しいのが実情です。
それでもパイロットになりたい場合、中卒者から目指す最短ルートは「航空学生として自衛隊に入隊する」です。
高卒認定を取得して航空学生の採用試験に合格後、訓練を受けながら免許を取得すれば、戦闘機・輸送機・救難機などのパイロットになれます。
- 注意点
- 航空学生として入隊後、パイロットとして部隊に配属されるまでには最短で6年ほどかかります。
中卒者は高卒認定試験や航空学生の採用試験に合格するための勉強期間を含めると、最短でも中卒者の場合、少なくとも7~8年はかかるでしょう。
このように、ここでご紹介した5つのルートは、いずれも最初に高卒認定試験を取ることが求められます。そのため、中卒のままパイロットになるのは厳しいと言えるでしょう。
パイロットになる基本条件
パイロットになるためには、国土交通大臣の航空従事者技能証明(ライセンス)の取得が必要です。
以下3つの資格のいずれかを取ることで、パイロットとして航空機を操縦できるようになります。
| ライセンス | 業務範囲 |
|---|---|
| 自家用操縦士 | 無報酬での航空機操縦が許可されるパイロットとしての仕事は行えない |
| 事業用操縦士 | 有報酬での航空機操縦が許可される自衛隊や民間企業でパイロットとして働ける |
| 定期運送用操縦士 | 旅客機の機長に求められるライセンス航空会社の航空機操縦に必要 |
中卒者が取得できるライセンスは、「自家用操縦士」と「事業用操縦士」です。
「自家用操縦士」の資格は、16歳以上かつ所定の飛行経験さえあれば取得できるものの、パイロットとして報酬を受け取ることはできません。そのため、パイロットを仕事にしたいのであれば、「事業用操縦士」の資格取得を目指しましょう。
- ポイント
- 中卒からパイロットを目指す最短ルートの「自衛隊の航空学生になる方法」の場合、手順を踏んだうえで試験に合格できれば「事業用操縦士」の資格が取得できます。
自衛隊のパイロットになれば、ヘリコプターや戦闘機、輸送機といった自衛隊で使われる航空機の操縦士として勤務可能です。
なお、「定期運送用操縦士」は航空会社に入社後、訓練を受けながら副操縦士として約7~8年勤務すれば、試験の受験要件を満たせます。かなりの時間を要するのはもちろん、未経験の中卒者が航空会社のパイロット候補として入社するのはかなり難しいため、取得するのは事実上不可能に近いでしょう。
中卒でパイロットを目指す手順

ここでは、中卒からパイロットになるための手順を解説します。
- 高卒認定試験に合格
- 航空学生として自衛隊に入隊
- 航空訓練と国家資格の取得
民間航空会社のパイロットは、希望者が殺到する傾向にあり、基本的に大卒者以外が採用されるのは難しいです。中卒の場合、高卒認定試験に合格後、航空学生として自衛隊に入隊し、海上・航空自衛隊のパイロットになるのが最も確実なルートと言えます。
手順ごとの詳細を解説するので、中卒でパイロットになりたい方はご参考にしてください。
①高卒認定試験に合格
中卒でパイロットになる最初のステップは、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)に合格することです。
中卒で自衛隊のパイロットを目指すためには、自衛隊の採用試験に合格して航空学生にならなければいけません。航空学生の採用試験の受験条件として、「高校を卒業した人と同等以上の学力があることの証明」が挙げられます。
そのため、中卒者の場合、高卒認定試験の合格は必要不可欠です。
高卒認定試験には必修科目と選択科目の2つがあり、計8科目に合格すると高卒認定が得られます。
各科目の最低合格ラインはおおよそ40点前後なので、確実に合格したい場合は各科目100点満点中50点以上を目指すと良いでしょう。
試験は8月と11月の年2回実施されます。合格した科目は次回試験で免除されるため、計画的に学習を進めれば合格率を高めやすくなります。
ちなみに、令和5年8月に行われた高卒認定試験の合格率は46.7%でした。
受験自体は16歳以上から受けられますが、合格の効力が働くのは18歳以上という点に要注意です。
参考:文部科学省「令和5年度第1回高等学校卒業程度認定試験実施結果について」(参照 2025-02-02)
②航空学生として自衛隊に入隊
高卒資格を取得したあと、自衛隊の航空学生の採用試験に合格して自衛隊への入隊を目指します。航空学生の採用試験における応募資格と試験科目は以下の通りです。
| 応募資格 | 海上自衛隊:18歳以上23歳未満 航空自衛隊:18歳以上24歳未満 |
| 試験科目 | 【1次試験】 ・筆記試験 ・適性検査 【2次試験】 ・航空身体検査 ・口述試験 ・適性検査 【3次試験】 ・航空身体検査(海) ・操縦適性検査及び医学適性検査(空) |
採用試験自体は高卒認定試験に合格すれば受験できますが、上記のように年齢制限があります。また、令和5年度航空学生の採用試験の合格率は9.4%とかなり低めです。
何歳からでも航空学生になれるわけではないことから、本腰を入れて航空学生の採用試験の対策に取り組む必要があります。
参考:
自衛官募集「航空学生とは」(参照 2025-02-25)
令和6年度版防衛白書「資料68 自衛官などの応募と採用状況」(参照 2025-02-25)
中卒で自衛隊のパイロットになる手順③航空訓練と国家資格の取得
自衛隊の航空学生の採用試験に合格したあとは、約4年間かけて飛行要員になるための知識と体力を習得し、パイロットの国家資格を取得します。
航空学生の場合、航空自衛隊と海上自衛隊に分類されますが、どちらも最初の2年間は航空学生課程を修了する必要があります。
航空学生課程の主な学習内容は以下の通りです。
| 航空学生課程 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 1年目 | ・一般教養(数学、物理、電磁気学、応用解析学、法学、政治学、哲学など) ・自衛官としての基礎(敬礼、規律、心構えなど) ・体育(筋力トレーニング、持久走、遠泳、サッカーなど) |
| 2年目 | ・操縦教育(電子工学、航空工学、電子機器、航空原動機、航空力学、航空気象、航空英語など) ・体育(器械体操、競泳など) |
1年目は自衛隊員に必要な考え方と一般教養を学び、2年目は操縦訓練に向けた専門的な知識の習得が求められます。また、勉学と平行して、パイロットになるための体力づくりの場が設けられているのも特徴です。
なお、全科目に定期試験があり、進級はその結果に基づいた厳正な判定のうえで決定されます。
航空学生課程を修了したあとは、航空自衛隊と海上自衛隊で国家資格を取得するまでの流れが異なります。
| 航空自衛隊 | 海上自衛隊 |
|---|---|
| 【飛行準備課程(約5~8.5カ月)】 ・英語、航空法規、航空気象、空中航法 ・落下傘降下準備訓練、遠心力発生装置を使った耐G訓練、低圧力環境での航空生理訓練など(計10日間) | 【操縦士基礎課程(約8~6.2カ月)】 ・操縦士基礎(共通)課程(約16週) ※「固定翼要員」「回転翼要員」のどちらかを選択 ・操縦士基礎(固定翼)課程(約17週) ・操縦士基礎(回転翼)課程(約11週) |
| 【初級操縦課程(約6カ月)】 ・飛行訓練(基礎的な操縦法、単独飛行、編隊飛行) | 【計器飛行課程】 ・固定翼:約25週(約5.7カ月) ・回転翼:約16週(約3.6カ月) |
| 【基本操縦課程】 ・T-4(戦闘機):約54週(約12.4カ月) ・T-400(輸送機、救護機):約47週(10.8カ月) ※初級操縦課程を修了後、本人の適性や希望を踏まえてどちらか選択 | 【操縦士回転翼基礎課程】 約17週(約3.9カ月) ※回転翼要員のみ |
| 国家資格の取得 | 国家資格の取得 |
航空自衛隊は、約6カ月間で飛行に必要な知識を習得したあと、単独飛行や編隊飛行ができることを目標に飛行訓練を行います。そして、初級操縦課程の検定試験に合格後、担当する航空機の操縦方法について学び、国家資格を取得する流れです。
海上自衛隊は、飛行訓練が始まった最初の16週でどのタイプの航空機の操縦要員になるのかが決まります。残りの期間は、決められた航空機の操縦技術を磨いていき、国家資格を取得します。
ちなみに、自衛隊のパイロットが取得できるのは「事業用操縦士」の資格のみです。
また、事業用操縦士の資格を取得したあとも、各航空機の操縦課程や部隊実習、幹部候補生学校への入学・卒業などを経る必要があります。そのため、航空学生として入隊後、パイロットとして部隊に配属されるまでに最短でも約6年かかります。
中卒でパイロットを目指す難易度

中卒者にとって最も現実的なルートである「航空学生として自衛隊に入隊する」方法でパイロットを目指す場合、以下の理由でハードルがかなり高めです。
- 高卒認定を取得する必要があるから
- 航空学生の採用試験に合格する必要があるから
- 事業用操縦士試験に合格する必要があるから
- 中卒からパイロットとして働けるまで最短でも7~8年ほどかかるから
中卒者の場合、パイロットになるためには「高卒認定試験」「航空学生の採用試験」「事業操縦士試験」に合格するという関門を突破しなければいけません。
ここでは、高卒認定試験と航空学生の採用試験の合格率をまとめました。
| 試験名 | 合格率 |
|---|---|
| 高卒認定試験 | 46.7%(令和5年第2回) |
| 航空学生の採用試験 | 約9.4%(令和5年度) |
参考:
文部科学省「令和5年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について」(参照 2025-04-07)
令和6年度版防衛白書「資料68 自衛官などの応募と採用状況」(参照 2025-04-07)
なお、事業用操縦士試験の正式な合格率は非公開ですが、約50%程度と言われています。
どの試験も合格率が50%を切っていることから、パイロットになる資格を得るまでに相当の努力が必要です。
また、先述した通り、中卒者が上記の方法でパイロットとして働けるようになるまでには、最短でも7~8年を要します。すぐにパイロットになれない点を踏まえると、中卒でパイロットを目指す難易度は高いでしょう。
中卒からパイロットを目指すための資格試験の対策方法

ここでは、中卒者がパイロットになるために必要な資格の試験対策方法を解説します。
中卒者がパイロットになる場合、高卒認定を取得して自衛隊の航空学生を目指すのが現実的なルートです。自衛隊のパイロットには、事業用操縦士の資格が必須なので、事業用操縦士の試験合格に向けて、どんな対策をするべきなのか理解しておきましょう。
事業用操縦士の試験対策
「事業用操縦士」の資格を取得するためには、学科試験と実地試験にそれぞれ合格する必要があります。
自衛隊のパイロットになる際の必須資格なので、どんな内容が出題されるのが理解しておきましょう。
事業用操縦士の学科試験
事業用操縦士の学科試験は、以下の5科目を受験します。
- 航空工学
- 航空気象
- 空中航法
- 航空通信
- 航空法規
すべてマークシート方式で、各科目で100点満点中70点以上で合格となります。
航空学生の場合、すでに航空機の基本的な操縦が理解できている段階で受験するので、飛行訓練以外は学科試験の対策に注力できるかどうかが重要です。
受験する時期によって異なるものの、航空自衛隊は基本操縦課程、海上自衛隊は「操縦士回転翼基礎課程」もしくは「計器飛行(固定翼)課程」を修了する前から受験対策を始めます。約2カ月程度は学科試験に向けた勉強が行われるのが一般的です。
学科試験の効果的な対策は、ひたすら過去問を解くことです。基本的に過去問をベースに出題されるため、過去問を丸暗記する勢いで解き続ければ、合格に限りなく近づくでしょう。
なお、事業用操縦士の過去問は、国土交通省の公式ホームページに掲載されています。実際に問題を解きながら、出題傾向を掴みましょう。
事業用操縦士の実地試験
事業用操縦士の実地試験では、以下の3つが段階的に行われます。
- 書類審査
- オーラル試験
- 実技試験
書類審査では、実地試験を受験するために必要な書類の確認を行います。所定の専門医がいる病院で検査を受けたことを証明できる「第1種航空身体検査証明」や、飛行経歴をまとめた「ログブック」などが求められます。
自衛隊の飛行要員として受ける場合、事業用操縦士を受験する時点で書類を提出できる条件を満たしているので、そこまで気にする必要はありません。
オーラル試験とは、学科試験で行う内容を技能審査員から直接問われる「口頭試験」です。審査員からの質問に対して口頭で説明しなければならないため、冷静な対応力と分かりやすく説明するプレゼンテーション力が欠かせません。
また、審査員からの質問に回答したあと、さらに深掘りされる場合が多いです。そのため、なんとなく模範解答を暗記するだけではなく、その問題や答えの本質を理解しておかなければ、回答に行き詰まる可能性がある点に注意しましょう。
オーラル試験を終えると、いよいよ実際に航空機でフライトを行う実技試験に移ります。
実技試験は2日間実施され、1日目はハイワーク、2日目は航法・野外飛行の技術力が審査されます。
- ハイワーク:基本飛行や急旋回など航空機を制御する術を上空で行うこと。
- 航法・野外飛行:航空機が母基地以外の目的地まで正しく飛行すること。
2日目の航法・生地飛行の場合、フライト前に正確な野外飛行計画を30分以内に作成し、その場で審査員に確認してもらう必要があります。
完成した野外飛行計画は、以下の5点を重点的にチェックされます。
- 正確な野外飛行計画を30分以内に作成できているかどうか
- 気象情報、航空情報を正確に把握できているかどうか
- 航法諸元を正確に算出できているかどうか
- 飛行経路周辺の障害物、不時着場、制限区域など配慮された飛行計画が作成されているかどうか
- 審査員からの質問に正しく答えられるかどうか
飛行計画の内容は当日に発表されるので、時間内に正確に作成できるように練習しておくことが大切です。
パイロットになったあとのキャリアパス

先述した通り、中卒でパイロットを目指せる現実的な方法は、「高卒認定試験に合格後、自衛隊の航空学生になってパイロットの資格を取ること」です。
自衛隊のパイロットになったあと、以下のようなキャリアパスを築ける可能性があります。
- 自衛官として高い階級を目指す
- パイロットとして民間企業に転職する
パイロットとしてどんな道に進めるのか理解し、自分の将来像を描いていきましょう。
自衛官として高い階級を目指す
自衛隊でパイロットになった場合、自衛官としてさらに高い階級を目指すのが一般的です。
自衛官の階級は、以下のように定められています。
- 参考
- ・将官
・左官
・尉官
・曹
・士
※階級が高い順に記載
ほとんどの隊員は、順調に進めばパイロットの資格を取得した時点で「1等空曹」「2等海曹」あたりになっています。
資格を取得したあと、さらに飛行要員として必要な課程を修了し、幹部候補生学校も卒業すれば、「3等空尉」「3等海尉」あたりに昇任している可能性が高いです。「3等空尉」「3等海尉」からは幹部扱いとなり、隊のなかで指揮官や指揮官補佐である幕僚として活躍できます。
ここからさらに上の階級を目指すためには、勤続年数を伸ばしつつ、階級によっては厳しい昇任試験を突破しなければなりません。
- 昇任試験
- 学科試験、体力測定、実技試験が実施されます。
特に、数人の隊員に行動を指示する「部隊指揮の実技試験」は難関です。
25メートル四方で待機する部隊の行動を指揮する減点方式の試験なので、指揮能力を日々磨いてリーダーシップを向上させる必要があります。
自衛官として上位の階級を目指すためには、今の自分に何を求められているのか理解したうえで日頃から努力を怠らないことが大切です。
パイロットとして民間企業に転職する
自衛隊で取得したパイロットの資格を活かして、民間企業に転職する方法もあります。
自衛隊で取得できる「事業用操縦士」の資格は、「2人で操縦する航空機もしくは運送事業の機長」以外であれば従事できます。そのため、エアラインの副操縦士やレジャー関連の航空機パイロット、ドクターヘリなど転職先の選択肢が広いです。
ただし、自衛隊のパイロットから民間のパイロットに転職するのはかなり難しいです。その理由は、後ほど転職する方法と一緒に解説します。
方法①自衛隊操縦士の割愛制度を利用する
「自衛隊操縦士の割愛」とは、一定の年齢に達した操縦士を対象に航空会社をはじめとした民間企業への転職をサポートする制度を指します。パイロットとして十分な経験を積んでいることが認められれば、民間のパイロットへの転職が可能です。
ただし、割愛制度を利用して転職できた操縦士は、年に数人いるかいないかです。毎年多くのベテラン操縦士が希望を出す傾向にあるため、この方法で転職できる人はごく一部である点に注意しましょう。
方法②自衛隊を退職してから民間企業に就職する
民間のパイロットに転職するもう一つの方法として、「自衛隊を辞めて2年後にパイロットを募集する民間企業に就職する」が挙げられます。
実は、自衛隊法の規則のなかに、「離職後2年間は在職時の職務に関する行為をしてはいけない」というルールがあります。パイロットの場合、退職してから2年間はパイロットとしての転職ができません。
自衛隊を退職してから再就職するまでブランクが空いてしまうことや、民間企業への転職活動において中卒という学歴がネックになる可能性が高いことから、かなり難易度が高い方法と言えます。
このように、自衛隊のパイロットから民間のパイロットへの転職に厳しい制限を設けるのは、「せっかく多額の税金を使って育成した操縦士を簡単に手放したくない」「最前線で活躍する若手の操縦士が民間企業へ流出するのを避けたい」という背景があります。
そのため、最初から民間企業への転職を視野に入れたキャリアプランを持っている方は、本当に自衛隊のパイロットを目指していいのかどうか検討してから行動しましょう。
中卒でパイロットに向いている人・向いていない人

パイロットは、職務を通して大きなやりがいが得られる一方で、日頃から自己管理や鍛練を欠かさず行う必要がある職業でもあります。
他の職業とは特性が異なる部分が多いからこそ、自分がパイロットを目指していいのかどうか知っておくことが大切です。
パイロットに向いている人・向いていない人の特徴を3つずつ解説するので、チェックしてみてください。
| パイロットに向いている人 | パイロットに向いていない人 |
|---|---|
| 冷静な判断力と責任感がある人 | 継続した学習ができない人 |
| 健康管理を続けられる人 | ストレスに耐えられない人 |
| 勉強熱心な人 | 健康管理ができない人 |
中卒でパイロットになるのに向いている人の特徴
パイロットに向いている人の特徴は以下の3つです。
- 冷静な判断力と責任感がある人
- 健康管理を続けられる人
- 勉強熱心な人
自衛隊のパイロットは、緊急時でも人命を最優先するための冷静な判断力と、どんな状況でも安全飛行を続ける強い責任感が必須です。
また、冷静な判断力が鈍ることなく操縦を行うためには、心身を健康に保つことも欠かせません。パイロットは半年に1回「航空身体検査」を受ける必要があります。検査項目は、眼科検査や内科系検査、心電図検査など多数あり、1つでも不合格を受けたパイロットは乗務停止処分となります。
万が一身体的な問題が発生した場合、パイロットの仕事を続けられなくなる可能性もあるため、日々の健康管理を意識できるかどうかが重要です。
また、パイロットは勉強熱心な人に向いている職業です。パイロットは、管制官とやりとりするうえで航空英語を覚える必要があります。航空英語は、TOEIC700点以上の英語力が求められるという声もあるほど、かなり難易度が高めです。
自衛隊の場合、航空学生から年数をかけてパイロットに必要な英語力を習得するカリキュラムが組まれているものの、海外派遣になるとフライトでも英語力が問われる場面が出てくるため、常に英語の勉強を続けなければいけません。
パイロットになる前もなったあとも高度な知識や技術を習得することに重きを置ける人は、パイロットとして活躍できるでしょう。
中卒でパイロットになるのに向いていない人の特徴
パイロットに向いていない人の特徴は以下の3つです。
- 継続して学習できない人
- ストレスに耐えられない人
- 健康管理ができない人
パイロットになれば、常に試験勉強や学習に追われる日々を送ります。また、どのパイロットにおいても、スキルアップを怠るのが許されない環境下で働くことになるため、学習を継続する意思が弱い人は向いていないでしょう。
また、パイロットなるまでには、さまざまな困難を乗り越える必要があります。パイロットになったあとも、常にプレッシャーを抱えながら働かなければいけないので、ストレスに耐えられない人も難しい職業と言えます。
そして、パイロットの仕事を長く続けていく際、健康に人一倍気を遣わなければいけません。先述した通り、パイロットは半年に1回実施される「航空身体検査」をクリアできなければ操縦業務から外されてしまうほど、高い健康意識と厳しい自己管理が求められる職業です。
そのため、乱れた食生活や睡眠不足の常態化など体調を崩す原因になりかねない生活を送りがちな人は、パイロットの仕事が続けられなくなる可能性があります。
中卒でパイロットになるメリット・デメリット
中卒でパイロットになると、さまざまなメリット・デメリットがあります。どんな長所と短所があるのか知ることで、パイロットという職業に対する理解度が深まります。
中卒でパイロットになるメリット・デメリットを紹介するので、自分が思い描くキャリアプランに合っているかどうかの判断材料としてお役立てください。
| 中卒でパイロットになるメリット | 中卒でパイロットになるデメリット |
|---|---|
| 大きなやりがいを感じられる | 資格取得だけでも大変な努力が必要 |
| 世界中を飛び回る機会がある | 資格取得後も厳しい訓練と勉強が必要 |
| 特別な景色と空の感動に出会える | 不規則な生活への対応が求められる |
中卒でパイロットになるメリットは3つ

中卒でパイロットになるメリットとして以下の3つが挙げられます。
- 大きなやりがいを感じられる
- 世界中を飛び回る機会がある
- 特別な景色と空の感動に出会える
パイロットは、厳しい訓練と試験を乗り越えてこそなれる職業です。自分で航空機を操縦し、安全に飛行することが求められるからこそ、フライトを無事に終えた時の達成感は格別でしょう。
また、海外へ飛行する機会もあり、異なる国の文化や生活に触れる機会が得られるので、仕事を通して充実した毎日を過ごしやすくなります。
さらに、航空機の操縦席からは雲海の上に広がる夕陽や、街の灯りが輝く幻想的な夜景など、地上では見られない景色が楽しめるのもメリットです。
空を飛ぶたびに新しい感動があり、刺激的な体験ができるのがパイロットの醍醐味と言えます。
中卒でパイロットになるデメリットは3つ
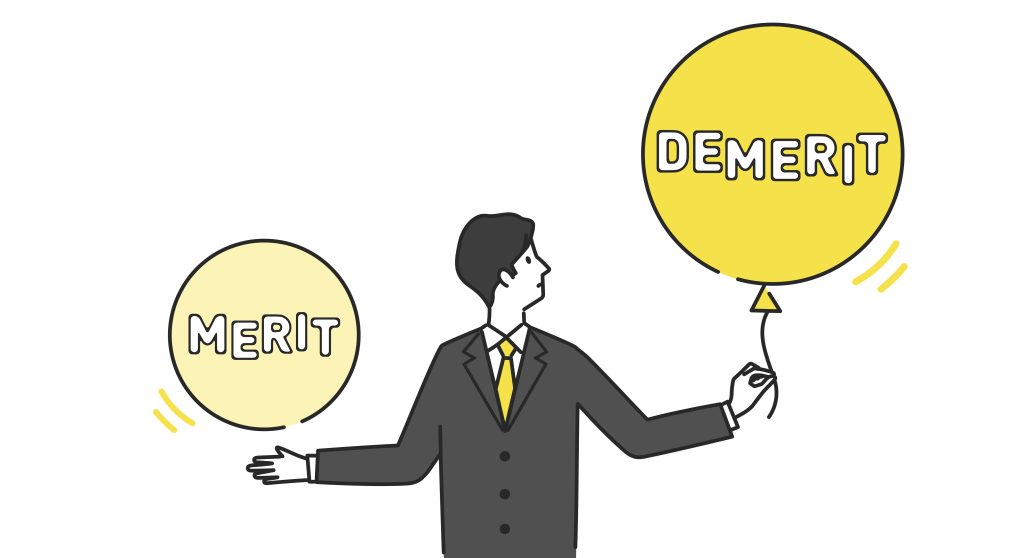
中卒でパイロットになるデメリットとして以下の3つが挙げられます。
- 資格取得だけでも大変な努力が必要
- 資格取得後も厳しい訓練と勉強が必要
- 不規則な生活への対応が求められる
パイロットを目指すためには、高度な専門知識や技術を習得し、数々の定期試験や資格試験に合格する必要があります。特に中卒の場合、パイロットになれる現実的な方法や期間が限られているため、血のにじむような努力をして少ないチャンスを掴まなければいけません。
また、パイロットの資格を取得したあとも、厳しい訓練や審査が続きます。それぞれをクリアするために常に勉強し続ける必要がある点も、パイロットならではのデメリットと言えます。
さらに、パイロットは早朝や深夜のフライトも珍しくなく、生活が不規則になりやすいです。そんな労働環境のなかでも、体調不良にならないように強い健康意識と高い自己管理を心がけることが求められます。
健康第一の職業とは言え、決して体調管理をしやすい勤務体制ではない点もデメリットの一つです。
中卒でパイロットを目指すためのおさらい

中卒者がパイロットを目指すには、高卒認定を取ることが前提になるため、中卒のままパイロットを目指すのはほぼ不可能です。
また、高卒認定を取得したあとは、「航空学生として自衛隊に入隊する」が最も現実的なルートと言えます。
- 高卒認定試験に合格
- 航空学生として自衛隊に入隊
- 航空訓練と国家資格の取得
高卒認定試験に合格したあと、まずは自衛隊の航空学生の採用試験を受験します。合格率はわずか9.4%とかなり低く、応募できる年齢が限られていることから、中卒でパイロットを目指すなら早めの行動と対策が必要不可欠です。
その後、約4年以上にわたる教育課程を経て事業用操縦士の試験に合格すれば、晴れてパイロットの資格を取得できます。
ご覧の通り、中卒からパイロットを目指すのはかなり大変で、本気で努力してもなれない可能性がある職業です。だからといって、絶対になれないというわけでもありません。
真剣にパイロットになりたい中卒者は、さっそく今日から準備を始めていきましょう。