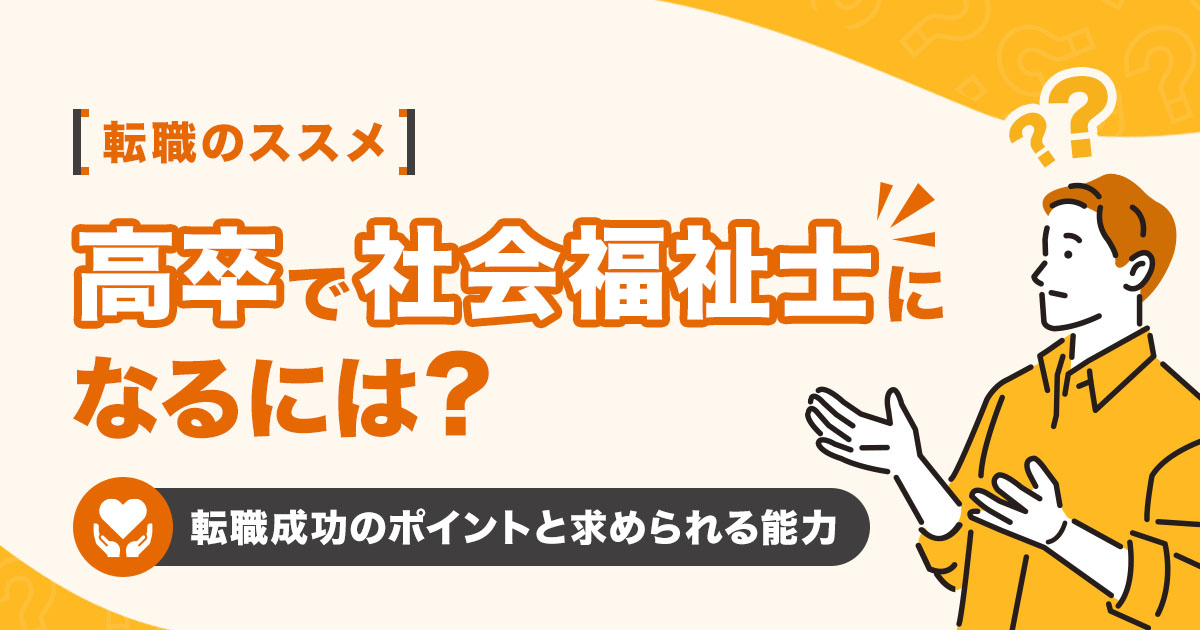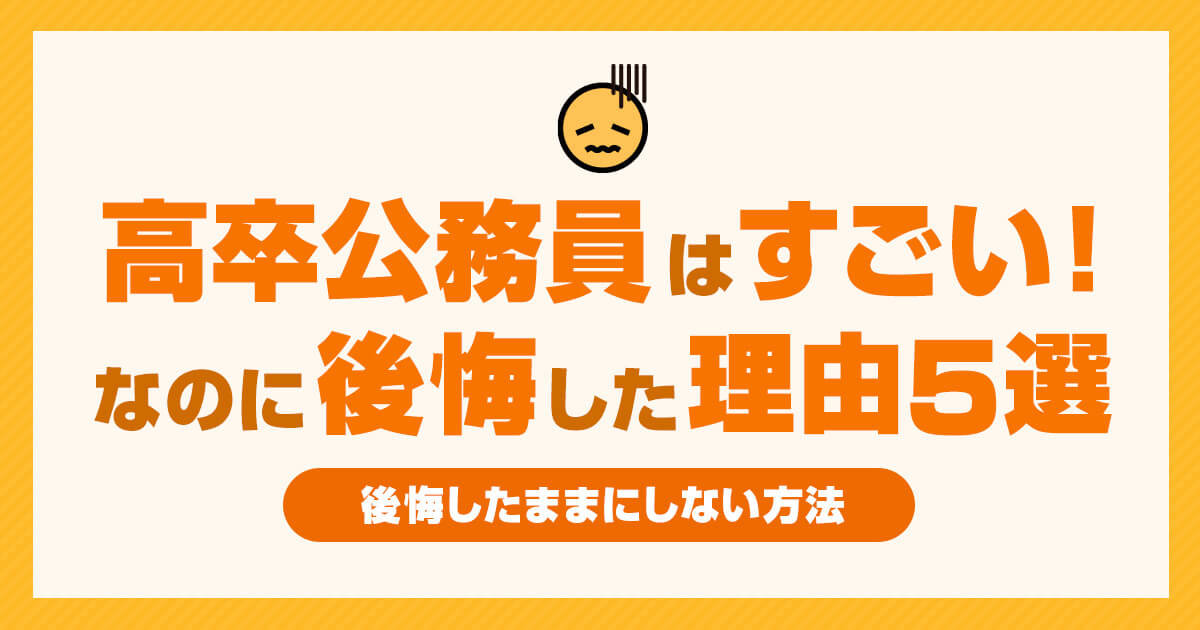社会福祉士とは、高齢者や心身に障害を抱える人など、日常生活に困難が生じている人の相談を受け、解決に向けてサポートを行う福祉の専門家です。
本記事では、高卒から社会福祉士になるための条件や方法、なったあとのキャリアパス、目指す上でのメリット・デメリットなどを解説します。
社会福祉士を目指したい高卒の方や、資格を取得するか迷っている方はぜひ参考にしてください。
高卒で社会福祉士になることはできる

社会福祉士は高卒も目指すことが可能です。
社会福祉士になるには国家資格の取得が必要ですが、一定の条件を満たせば、高卒の場合でも受験資格を得ることができます。
近年、高齢化が進む中で社会福祉士の需要は年々高まっており、活躍の場も幅広くあります。資格を取得すれば、学歴や経験を問わない求人も多いため、高卒の方にとってもチャレンジしやすい仕事と言えるでしょう。
なお、社会福祉士の資格は、以下のような職場で活かすことができます。
- 地方公共団体
- 地域包括支援センター
- 病院
- 学校
- 介護施設
- 特別養護老人ホーム
- デイサービス
- 児童福祉施設
社会福祉士の仕事では、学歴よりも「資格を持っていること」や「現場での経験」が重視される傾向があります。興味がある方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。
社会福祉士になる基本条件
社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験に合格後、社会福祉士として登録申請をすることが必須条件です。
社会福祉士国家試験を受験するためには、まず受験資格を得る必要があります。
最終学歴が高卒の場合、「指定されている職場・業務での実務経験を4年以上積み、一般養成施設で1年以上学ぶ」というルートが最短かつ最も現実的です。
受験資格を得る方法自体は12ルートありますが、その他の方法は専門学校や福祉系大学を卒業したり、社会福祉士以外の資格を取得したりする必要があります。
また、どのルートを選んだ場合でも、実務未経験の高卒が資格試験の受験資格を満たすには数年かかります。そのため、「今からすぐに社会福祉士になれるわけではない」という点には注意が必要です。
【注意点】社会福祉士を名乗るには資格の取得が必須
社会福祉士の資格は「名称独占資格」です。
社会福祉士の資格を取得しなくても社会福祉に関する相談業務には携われるものの、資格を持っていないと、「社会福祉士」という名称を名乗って働くことはできません。
社会福祉士は生活相談員の総称である「ソーシャルワーカー」に分類される職業ですが、ソーシャルワーカーには、資格なしで類似した業務内容を行える職業も存在します。
まずは特定の資格が必要ない仕事で実務経験を積みながら、社会福祉士の資格取得を目指していきましょう。
社会福祉士の学歴内訳
ここでは、社会福祉士国家試験合格者の合格率から社会福祉士の学歴内訳をご紹介します。
以下の表は、各受験ルートの新卒者と既卒者の合格率を比較したもので、()内は受験者数のうちの合格者数です。
学歴別の合格率は公表されていませんが、高卒は「③短期養成施設等(6ヶ月以上)ルート」か「④一般養成施設等(1年以上)ルート」のいずれかに含まれます。
| 受験ルート | 新卒者 | 既卒者 |
|---|---|---|
| ①福祉系大学等(4年制)ルート | 75.2% | 35.8% |
| ②福祉系大学等卒+実務経験ルート | - | 36.1% |
| ③短期養成施設等(6ヶ月以上)ルート | 67.9% | 36.6% |
| ④一般養成施設等(1年以上)ルート | 80.1% | 39.3% |
参考:厚生労働省「第37回社会福祉士国家試験合格発表」(参照 2025-4-17)
短期養成施設や一般養成施設の新卒者は、①や②の大卒向けルートとさほど合格率に違いはありません。
特に高卒の最短ルートである一般養成施設の卒業者はもっとも合格率が高いため、しっかり勉強すれば新卒者・既卒者を問わず高卒も合格を目指せると言えるでしょう。
高卒で社会福祉士になる方法と手順

高卒で社会福祉士になる方法と手順について解説します。
高卒で社会福祉士になる最短ルートは以下の通りです。
- 相談援助補助の実務経験を4年間積む
- 一般養成施設で1年以上学習する
- 社会福祉士国家試験に合格する
高卒かつ現時点で実務経験がない場合は、まず社会福祉士国家試験の受験資格を得る必要があります。
指定された施設で相談援助の実務経験を4年以上積み、その後、一般養成施設に1年以上通いましょう。
受験資格を取得後に国家資格試験に合格すれば、晴れて社会福祉士を名乗れるようになります。
手順①相談援助の実務経験を4年間積む
厚生労働省が定めた施設・職種で「相談援助」の実務経験を4年以上積むと、資格試験の受験条件である実務経験をクリアできます。
相談援助の実務とは、生活支援が必要な人の相談を受け、アドバイスや指導、支援サービスを提供する機関との連携・調整などの援助を行う仕事です。
無資格の高卒が相談援助の実務経験を積める施設と職種の例は以下です。
| 施設種類 | 実務経験として認められる職種の例 |
|---|---|
| 児童分野 | 児童相談所の受付相談員、電話相談員母子生活支援施設の母子支援員 |
| 高齢者分野 | 指定介護老人福祉施設の生活相談員養護老人ホームの生活相談員 |
| 障害者分野 | 身体障害者更生相談所のケースワーカー |
| その他の分野 | 生活保護救護施設の生活指導員日常生活支援住居施設の生活支援員 |
参考:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験|受験資格」(参照 2025-4-17)
ただし、対象の施設・職種で働いても、相談援助業務を担当していないと実務経験とは認められません。
希望する就職先・職種が受験資格の対象になるかは必ず確認しておきましょう。
手順②一般養成施設で1年以上学習する
一般養成施設とは、都道府県ごとに定められている、社会福祉士になるための訓練を行う養成所を指します。
相談援助の実務経験を4年以上積んでいる場合は、最終学歴に関係なく入学でき、1年以上修業すれば社会福祉士国家試験の受験資格を得られます。
夜間・通信課程が用意されている施設もあるので、働きながらの修業も可能です。ただし、ある程度のスクーリング(対面での授業)も必須のため、全てのカリキュラムを通信で終えることはできません。
一般養成施設で学ぶ内容は23科目1,200時間に及びます。テキストを使った座学だけでなくレポート提出や実習なども求められますが、相談援助の実務経験が1年以上ある場合は、実習科目が免除されます。
参考:厚生労働省「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」(参照 2025-4-14)
手順③社会福祉士国家試験に合格する
社会福祉士国家試験の受験資格を得たら、いよいよ資格試験の合格を目指しましょう。
社会福祉士国家試験は年1回で、毎年2月頃に実施されます。
試験科目は全19科目あり、内容は医療分野だけでなく社会制度、行財政など多岐にわたります。試験範囲が広く難易度も高いので、しっかり勉強して試験に臨むことが重要です。
合格率は毎年バラつきがあり、直近5年間では29.3~58.1%の間で推移しています。
ちなみに、社会福祉士国家試験に合格しても、登録証がないと社会福祉士を名乗ることはできません。
資格試験の合格通知と一緒に申請書類が届くので、必要書類をそろえて資格登録の申請も行いましょう。
参考:厚生労働省「社会福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」(参照 2025-4-14)
高卒で社会福祉士になるための資格試験の対策方法

社会福祉士は国家資格の中でも取得難易度が高めと言われています。何も対策をせずに受験すると不合格になる恐れがあります。
合格するには、以下の4つの対策方法を講じるのが有効です。
- 試験の全体像を把握する
- 苦手分野の対策をする
- 模擬試験を受けてみる
- 一度試験に落ちても諦めない
それぞれの対策方法について詳しく解説していきます。
①試験の全体像を把握する
試験の全体像を把握していると、学習スケジュールが立てやすくなり、勉強を効率的に進められます。
社会福祉士国家試験は240分の間に全19科目・129問の問題を解く必要があります。出題形式は、五肢択一または多肢選択式のマークシート方式です。
| 共通科目 | 専門科目 |
|---|---|
| ・医学概論 ・心理学と心理的支援 ・社会学と社会システム ・社会福祉の原理と政策 ・社会保障 ・権利擁護を支える法制度 ・地域福祉と包括的支援体制 ・障害者福祉 ・刑事司法と福祉 ・ソーシャルワークの基盤と専門職 ・ソーシャルワークの理論と方法 ・社会福祉調査の基礎 | ・高齢者福祉 ・児童・家庭福祉 ・貧困に対する支援 ・保健医療と福祉 ・ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) ・ソーシャルワークの理論と方法(専門) ・福祉サービスの組織と経営 |
参考:社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験 4 試験科目(第37回)」(参照 2025-4-17)
合格基準点は「得点率60%以上」を軸にして難易度による補正がかけられる仕組みです。
1科目でも0点があると、その時点で不合格になってしまうので、専門性よりも網羅性が求められる試験と言えるでしょう。
②苦手分野の対策をする
筆記試験は19科目すべてで最低でも1点を取らなければならないので、苦手科目の対策は必要不可欠です。
まずは数年分の過去問題を解いて、自分の得意分野と苦手分野を洗い出すことが大切です。
得意分野と苦手分野を把握できたら、苦手分野を重点的に学習します。テキストの内容をしっかり暗記し、過去問題を繰り返し解いていくと、知識が定着します。これを繰り返し、どの科目もまんべんなく問題を解けるように対策しましょう。
苦手分野の対策が完了したら、全体の底上げをしていくイメージで復習を繰り返すのが効果的です。解けなかった問題に都度チェックを入れたり、ふせんを貼ったりしておけば、苦手な問題の把握や復習がしやすくなります。
③模擬試験を受けてみる
試験本番の雰囲気に慣れるために模擬試験を受けてみるのもおすすめです。
模擬試験を受けると、時間配分や今の自分の実力を確認できるというメリットもあります。模擬試験の結果を踏まえて、点数が取れなかった分野を集中的に勉強する方法も有効です。
以下のように、いくつかの団体が定期的に模擬試験を開催しているので、活用してみましょう。
| 模擬試験 | 詳細 |
|---|---|
| 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟(ソ教連)模試 | 時期:10月~11月上旬頃 費用:6,600~9,900円 |
| 中央法規全国模擬試験 | 時期:7月頃 費用:6,600円 |
| 社会福祉士会全国統一模擬試験 | 時期:9月~11月頃 費用:6,000円前後 |
| 東京アカデミー全国公開模試 | 時期:9月頃 費用:3,300~3,800円 |
模擬試験によって実施時期や開催方法、受験料などは異なるため、詳細は各団体のホームページをご確認ください。
④一度試験に落ちても諦めない
一度試験に落ちたとしても受験資格はなくならないので、諦めずに再度勉強して次年度に改めてチャレンジしてみましょう。
ただし、社会福祉士国家試験は既卒者を含めると合格率が低いです。令和7年の一般養成施設等ルートにおける既卒者の合格率は39.3%でした。
既卒者の合格率が低い理由は、以下が考えられます。
- 試験内容が都度アップデートされるから
- 19科目中1科目でも0点があると不合格になってしまうから
既卒者の場合は、前年度の試験内容をそのまま勉強すれば良いわけではありません。医療の進歩や制度変更があると試験内容も変わるため、変更点を把握して各科目の対策を見直すようにしましょう。
高卒で社会福祉士になったあとのキャリアパス

社会福祉士はさまざまな分野で活躍できる職業なので、一度資格を取得すれば就職先には困らないでしょう。
社会福祉士の資格を取得したあとの代表的なキャリアパスは、以下の4つです。
- 福祉施設での相談員・指導員
- 行政機関や公的機関の職員
- 医療ソーシャルワーカー
- スクールソーシャルワーカー
それぞれ詳しく解説するので、将来自分がどうなりたいかを考えて転職活動に踏み切ってみましょう。
キャリアパス①福祉施設の相談員・指導員
福祉施設とは、高齢者や児童、障害者、生活困窮者といった人の日常生活のサポートを行い、社会福祉の増進を図ることを目的とした施設を指します。
福祉施設の支援相談員・生活指導員は、福祉サービスを必要とする人やその家族に対してのケアや相談・指導などを行うのが主な仕事内容です。
就職先は公営・民間ともに豊富で、「児童分野」「高齢者分野」「障害者分野」などが主です。児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、母子生活支援施設、特別養護老人ホーム、保育所などが該当します。
経験を積めば、将来的には管理職や施設長へのステップアップも目指せます。
キャリアパス②行政機関や公的機関の職員
社会福祉士の資格があれば、公務員試験を受けて行政機関や公的機関で働く道もあります。
行政機関・公的機関の福祉相談窓口で地域住民や施設者からの相談に応じたり、関係機関の参加・協力のもとで「福祉のまちづくり」の実現を目指す業務に携わったりするのが主な仕事です。
就職先は、地方自治体の福祉事務所、市役所・区役所、地域包括センター、社会福祉協議会、公共職業安定所(ハローワーク)、児童相談所、保護観察所などが当てはまります。
地方公務員になれば、収入面や福利厚生が安定しやすくなります。また、将来的には管理職やリーダー、各施設が設けるキャリアレベルに応じた高ランク職員としてステップアップを目指せるでしょう。
キャリアパス③医療ソーシャルワーカー
社会福祉士は「医療ソーシャルワーカー(メディカルソーシャルワーカー)」として、医療分野でも働けます。
病院やクリニックをはじめとした医療機関・施設で患者やその家族の相談に応じ、医療機関や関係機関との連携・調整を行います。具体的には、受診・受療に関する援助、入退院・転院の援助、社会復帰の支援、受けられる支援の案内などが主な業務です。
また、患者のニーズに応じたサービスの提供ができるように、関係機関と連携して地域の保健医療福祉システムづくりに貢献するといった活動を行うことも可能です。
将来的にはリーダーや組織運営に携わるような管理職も目指せます。
キャリアパス④スクールソーシャルワーカー
スクールソーシャルワーカーとは、小中学校や高等学校、特別支援学校、教育委員会、教育事務所などの教育分野で活躍する社会福祉士を指します。
不登校やいじめ、虐待、心身の健康に関する問題といった、教育現場に関わる幅広い問題についての支援と解決を図るのが主な仕事内容です。ほかにも、関係機関とのネットワークの構築や連携、保護者や教職員に対する支援や相談の対応、教職員への研修活動など多岐にわたります。
将来的にはスクールソーシャルワーカーを続けながら、後見人活動や企業のサポートなど活躍の幅を広げることも可能です。
高卒で社会福祉士に向いている人・向いていない人

社会福祉士は学歴不問で活躍できる職業ですが、人によって向き・不向きがあります。
ここでは、社会福祉士として求められる人物像や能力について解説します。
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 学び続ける意欲があり、勉強が好きな人 | 相談相手の話に感情移入しすぎる人 |
| 聞き上手で根本的な問題を把握できる人 | 忍耐力がない人 |
| 思いやりと共感性のある人 | マルチタスクが苦手な人 |
社会福祉士に向いている人の特徴3つ
社会福祉士に向いている人の主な特徴は以下の3つです。
- 学び続ける意欲があり、勉強が好きな人
- 聞き上手で根本的な問題を把握できる人
- 思いやりと共感性のある人
社会福祉士に関係する法律や制度は時代に伴って変化していきます。必要な知識が常にアップデートされるため、資格取得後も継続して自主的に学び続ける姿勢があると、大きな武器になるでしょう。
また、社会福祉士は日常生活で困難を感じている人と接し、問題解決に向けて必要なサポートを行う職業です。相手に寄り添いながら、相手が何に悩み、何を求めているのかを理解する必要があります。
そのため、聞き上手で根本的な問題を把握できる人や、思いやりと共感性のある人は、社会福祉士の適性が高いです。相手との信頼関係も築きやすく、社会福祉士としてさまざまな場所で活躍できるでしょう。
社会福祉士に向いていない人の特徴3つ
社会福祉士に向いていない人の主な特徴は以下の3つです。
- 相談相手の話に感情移入しすぎる人
- 忍耐力がない人
- マルチタスクが苦手な人
社会福祉士は相談相手に寄り添う姿勢が大切ですが、相手に感情移入しすぎると、客観的な判断ができなくなります。また、相手の悩みを自分ごとのように受け止めすぎると、精神的な負担が大きくなることもあるため、感受性が強い方は注意が必要です。
心に深い悩みや傷を抱えた方と向き合うことも多く、中には話の内容がまとまっていなかったり、会話がスムーズに成り立たなかったりする場面もあります。
そのような状況でも冷静さを保ち、情報を整理しながら対応を進める力が求められるため、忍耐力に自信がない方や、同時に複数のことをこなすのが苦手な方には、少し大変に感じるかもしれません。
高卒で社会福祉士になるメリット・デメリット
高卒で社会福祉士になるメリット・デメリットは、それぞれ以下の3つです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 専門性が高いので就職・転職しやすい | 資格取得までの道のりが長く、取得後も継続した学習を求められる |
| 収入アップや昇進につながりやすい | 近しい業務内容で資格不要の仕事もある |
| 幅広い業界でキャリアを築ける | 業務内容により精神的に疲弊しやすい |
社会福祉士を目指すか悩んでいる方は、これから解説するメリット・デメリットを理解したうえで決断するようにしてください。
高卒で社会福祉士になるメリットは3つ

高卒で社会福祉士になるメリットは以下の3つです。
- 専門性が高いので就職・転職しやすい
- 収入アップや昇進につながりやすい
- 幅広い業界でキャリアを築ける
高度な知識や技術を証明できる国家資格を持つ社会福祉士は、社会的信用が高く、転職・就職の際に有利に働きます。高齢化社会に伴って社会福祉士の需要は高まっているため、仕事に困る可能性は少ないでしょう。
また、社会福祉士の資格を取得していれば資格手当がつく職場も多いです。重要なポジションを任せてもらいやすくもなり、高卒の一般的なソーシャルワーカーより昇進できるチャンスも増えます。
その上、社会福祉士の資格があれば、精神保健福祉士や認定社会福祉士、認定上級社会福祉士といった資格も取得しやすくなり、より幅広い業界でキャリアを築けます。
高卒で社会福祉士になるデメリットは3つ
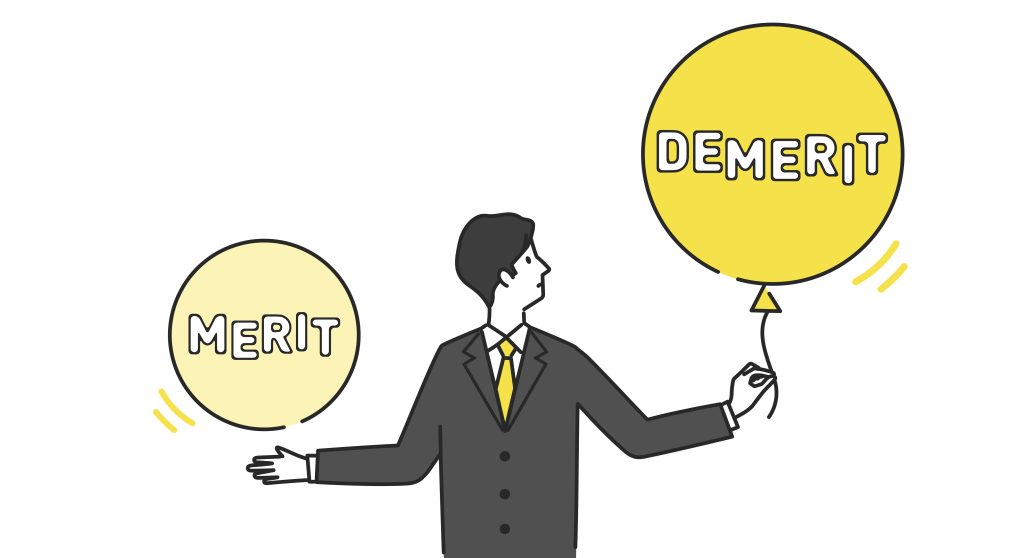
高卒で社会福祉士になるデメリットは、以下の3つです。
- 資格取得までの道のりが長く、取得後も継続した学習を求められる
- 近しい業務内容で資格不要の仕事もある
- 業務内容により精神的に疲弊しやすい
社会福祉士の資格は取得までの道のりが非常に長いです。また、社会福祉士になったあとも常に知識のアップデートが求められる職業なので、継続した学習は欠かせません。
社会福祉士は業務独占の資格ではないため、特に介護や福祉の現場では、資格がなくても近しい業務内容で働けるケースがあります。希望業務や働き方によっては資格がなくても働ける場合があるため、むやみに資格取得にこだわらないことも大切です。
そして、社会福祉士は支援が必要な相手をサポートする仕事なので、ストレス負荷がかかりやすく、精神的に負担を感じやすい職業であることにも留意しましょう。
高卒で社会福祉士になるためのおさらい

社会福祉士になるためのポイントをまとめました。
- ポイント
- 【高卒から社会福祉士になる方法】
・相談援助の実務経験を4年間積む
・一般養成施設で1年以上学習する
・社会福祉士国家試験に合格する
【社会福祉士になるメリット】
・専門性が高いので就職・転職しやすい
・収入アップや昇進につながりやすい
・幅広い業界でキャリアを築ける
社会福祉士を名乗るには資格取得が必須ですが、学歴不問・未経験歓迎の求人も多いので、高卒から社会福祉士を目指すことは可能です。
ただし、資格取得までには時間がかかり、精神的な負担も大きい仕事です。
それでも社会福祉士を目指したいと思えた方は、さっそく今日から準備を進めていきましょう!