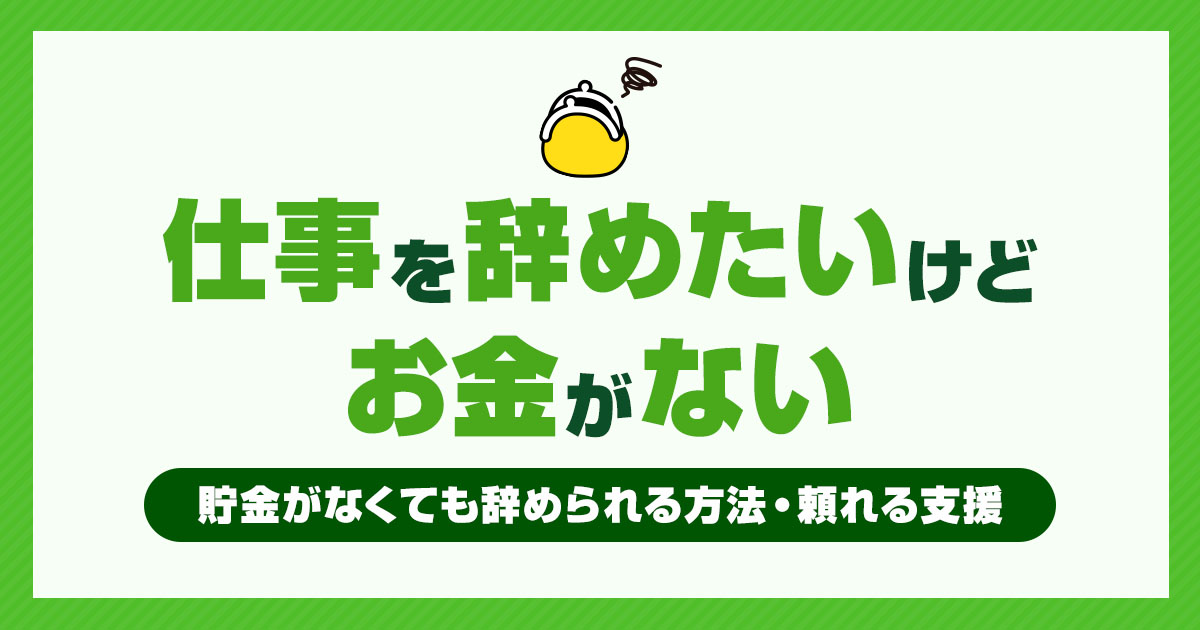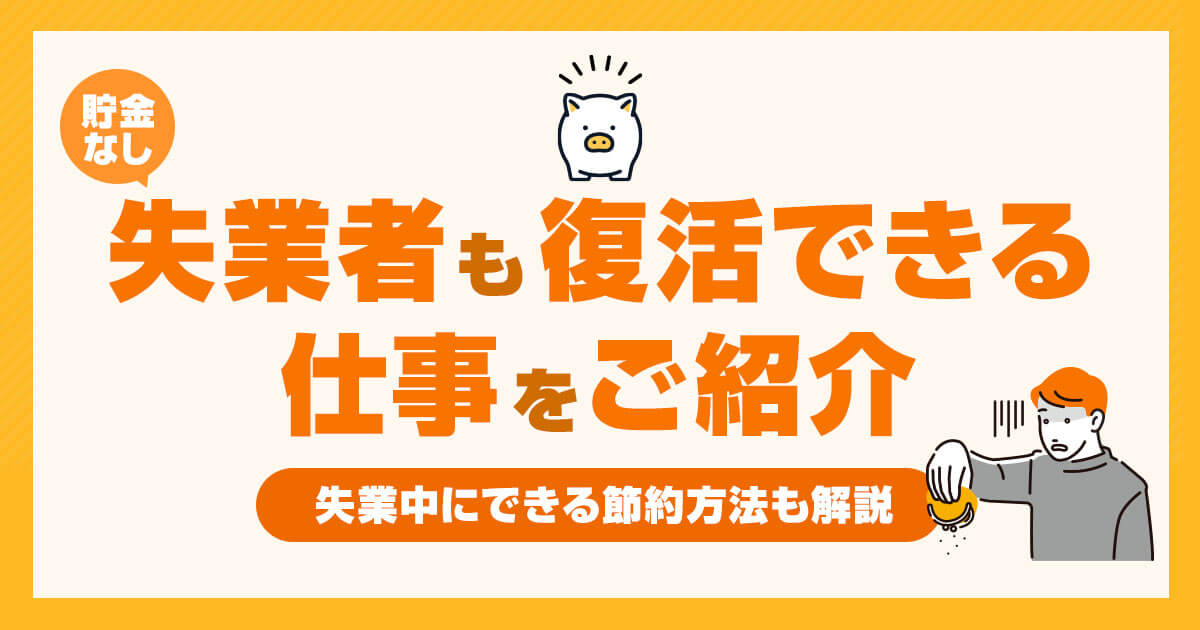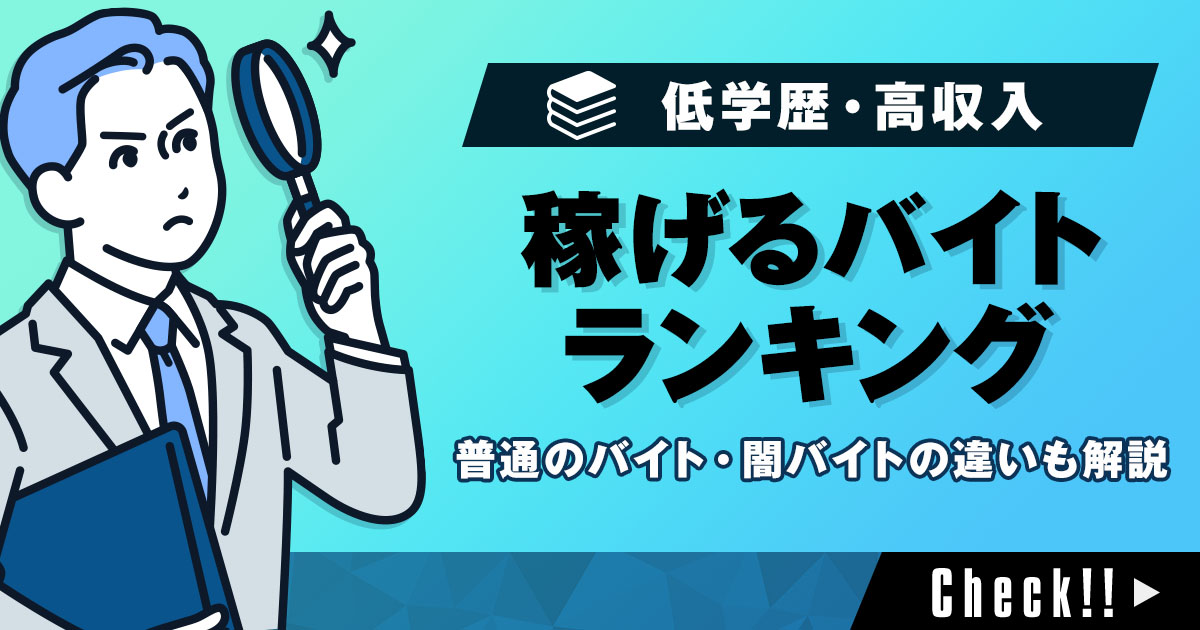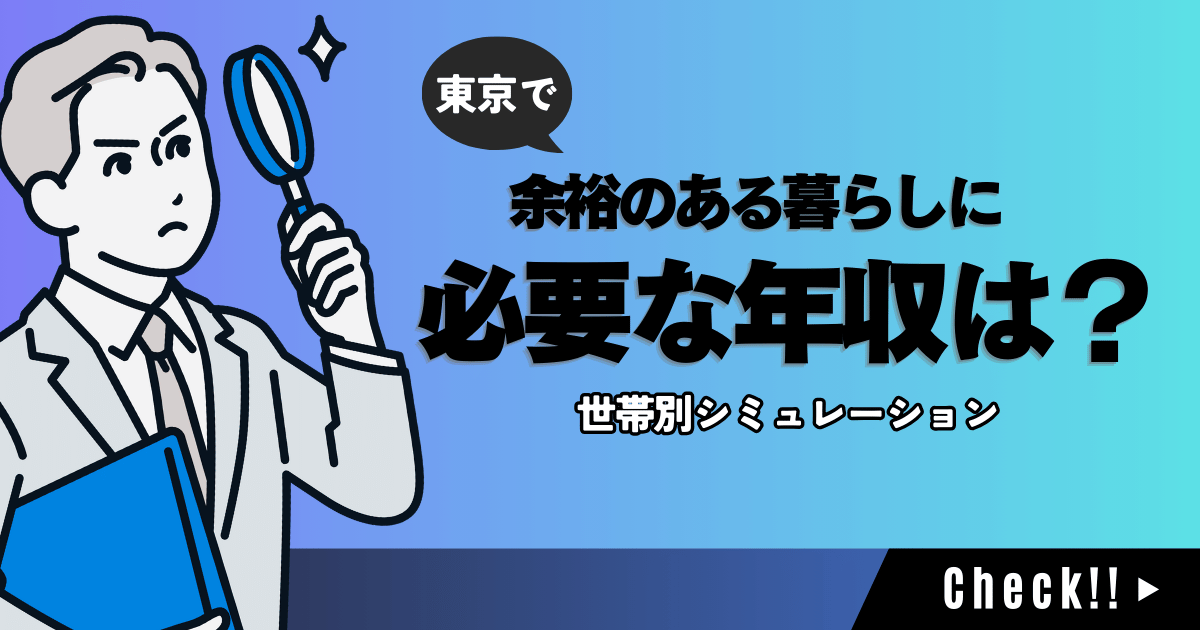「仕事を辞めたいけど、お金がないから辞められない」と悩んでいませんか?
労働環境や人間関係、将来の生活への不安などから今の仕事をすぐに辞めたいと思っても、貯金が少ないとなかなか一歩を踏み出せないものです。
でも、安心してください。たとえ貯金が少なくても、仕事を辞めて新しい道に進むことは可能です。
本記事では、退職後にかかるお金、利用できる支援制度、仕事を辞める前に準備しておきたいこと、さらには新たな働き方の選択肢まで詳しく解説します。
お金の不安で諦めないためのヒントを、一緒に見つけていきましょう。
お金がなくても仕事を辞めることは可能

結論から言えば、貯金が少なくても仕事を辞めることはできます。
「収入がなくなったら生活できないし、税金も払えないから絶対に辞められない…」
そう思い込んでいる人も多いでしょう。
とは言え、転職サイトの「リクナビNEXT」によると、退職後に転職活動をした人の実際の貯金額は「10万円未満が最多」になり、意外と貯金がない状態で辞めている人が多いことがわかります。
それに、これから紹介する国の支援制度や、辞める前にできる準備、新しい働き方を知っておけば、限られた貯金でも仕事を辞めて十分に生活することはできます。
参考:リクナビNEXT「転職時に貯金はいくら必要?転職にまつわるお金の話」(参照2025-08-01)
仕事を辞めたいけどお金がない…辞められないと感じる背景
「仕事を辞めたいのにお金がなくて辞められない」と感じてしまう背景には、次のような要因があります。
- 次の仕事が決まるまで生活できるか心配
- 貯金がないのに仕事を辞めたら、周囲から甘えと思われそうで不安
- 周囲に相談できる人がおらず、自分の決断に自信が持てない
経済的な不安だけでなく、漠然と心理的にプレッシャーを感じてしまい、踏み出せずにいる人もたくさんいます。
しかし、打開策はあるので、我慢して今の仕事を続けないといけないということは決してありません。
まずは、お金がない中で退職をした際にどんな手段を取ればいいのか把握していきましょう。
退職後にかかるお金の種類と目安

仕事を辞めたら、どんなお金がどれくらい必要になるのか、事前に知っておくことが大切です。
主な出費は次の4つです。
- 生活費
- 国民健康保険料・国民年金保険料
- 住民税・所得税
- 転職活動費
それぞれの費用の目安を具体的に解説するので、「仕事を辞めた後に、何にどれくらいお金が必要なのかわからない」と不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。
生活費
生活費は住む地域や物件の条件、ライフスタイルなどによって大きく異なります。
現在の自分の生活を振り返り、毎月どのぐらいの生活費がかかっているのかをシミュレーションしてみましょう。
ちなみに、総務省のデータによると、一人暮らしの1ヶ月の平均生活費は、おおよそ18.8万円です。
| 支出項目 | 平均 |
|---|---|
| 住居費(家賃) | 53,135円 |
| 食費 | 42,015円 |
| 水道・光熱費 | 11,619円 |
| 生活用品費(家具・家事用品) | 4,218円 |
| 交通・通信費 | 20,170円 |
| 保健医療費 | 7,751円 |
| 被服費 | 5,221円 |
| 娯楽費 | 20,114円 |
| その他(交際費など) | 23,373円 |
| 教育 | 13円 |
| 合計 | 187,628円 |
※小数点以下第2位を四捨五入
参考:総務省統計局「家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表」(2024年)(参照2025-08-01)
このデータはあくまで全国平均です。
特に交際費や娯楽費は、工夫次第でぐっと抑えられます。節約できるところはしっかり見直してみましょう。
詳しい節約方法は以下の記事で解説しています。
国民健康保険料・国民年金保険料
仕事を辞めても、健康保険と年金の支払いは必須です。
健康保険は、次の3つの選択肢から選べます。
| 選択肢 | 加入先・内容 | 保険料の目安 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 前職の健康保険を最長2年間継続 | 在職中の約2倍 ※会社負担分も自己負担 | 最長2年まで利用可能 |
| 国民健康保険 | お住まいの自治体で加入 | 月額1〜2万円程度※自治体により異なる | 所得や世帯構成によって金額が変動 |
| 家族の扶養 | 家族の健康保険に加入 | 自己負担なし | 扶養に入れる条件あり |
また、20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が義務です。
令和7年度の月額は17,510円ですが、収入が少ない場合は全額もしくは一部免除の制度があり、退職を理由にした特例免除も利用可能です。
ちなみに、免除を受けた期間分は、10年以内であれば後から納付(追納)することもできます。
参考:全国健康保険協会「退職後の健康保険について」(参照2025-08-01)
日本年金機構「国民年金保険料」(参照2025-08-01)
住民税・所得税
退職後も、住民税や所得税の支払いは続きます。
特に住民税は、前年の所得をもとに6月から翌年5月分までを支払う仕組みのため、退職した翌年に「こんなに払うの?」と驚くことがあります。
住民税の支払い方法は、退職する月によって変わります。
| 退職時期 | 住民税の支払い方法 |
|---|---|
| 1月〜5月退職 | 最終給与や退職金から一括徴収される |
| 6月〜12月退職 | 自治体から届く納付書を使用して、一括または4分割で納付する |
このように、住民税は退職後にまとまった金額を支払うケースもあります。
支払いが遅れると、延滞金が加算されることもあるので、もし支払いが厳しそうなら、早めに役所に相談しましょう。
所得税は、年内に再就職すれば転職先で年末調整されるため、手続きは不要です。
一方、年内に再就職しない場合は、翌年に確定申告が必要となります。対処の仕方に迷ったときは自治体や税務署へ早めに確認しましょう。
転職活動費
転職活動には、意外とお金がかかります。
- 面接会場までの交通費
- スーツや靴などの身だしなみ代
- 履歴書や職務経歴書の印刷代
最小で数千円ほど、スーツの用意からとなると数万円程度、必要になることもあります。
また、職種によっては資格試験の受験料や講座の受講料、教材費などが発生するケースもあるでしょう。
そのため、なるべく短期のうちに効率良く転職活動が終わるように費用を準備しておいたり、志望職種に就く際に必要な条件を必ず確認しておくと安心です。
なお、ハローワークや一部の転職エージェント、キャリア相談サービスは無料で利用できます。
お金がなくても仕事を辞める方法

ここでは、お金がない中でも、経済的なリスクを抑えて退職へ向かうための具体的な方法を紹介します。
- 働きながら転職活動を進める
- ボーナスをもらってから退職する
- 実家に戻って生活コストを下げる
- 副業で収入源をつくる
- アルバイト・派遣で一時的に生活を支える
在職中の今からできるだけの準備をして辞めるという選択肢もあります。今すぐに辞めるのは不安という場合は、できるだけ準備をしておくと心理的な不安も抑えられるでしょう。
働きながら転職活動を進める
お金に余裕がないなら、今の仕事を続けながら転職活動をするのが一番安心で確実な方法です。
次の仕事が決まってから退職すれば、生活費や転職活動費の不安を最小限に抑えられます。
さらに、在職中であれば、焦らず落ち着いて転職先を選べる点も大きなメリットです。経済的な余裕があると、じっくり企業を判断する時間を設けられるので、社風や業務内容のミスマッチを避けながら、転職先を選びやすくなります。
具体的な方法としては、転職サイトの登録やスカウト機能の活用、ハローワークの求人検索、転職エージェントへの相談などがあります。無料で利用できるサービスも多いため、情報収集から始めてみましょう。
ボーナスをもらってから退職する
ボーナスをもらってから退職すると、退職後の資金に余裕を持たせられます。支給額は企業によって異なりますが、数十万円以上になることもあり、大きな助けになる可能性は高いです。
ただし、事前に支給日や在籍条件などの確認は必ずしておきましょう。
たとえば、支給基準日に在籍していないとボーナスを受け取れないケースがあるため、退職日を決める際には注意が必要です。
また、退職の意向を伝える時期によっては、ボーナスが減額されてしまう恐れもあるので、職場に退職の旨を伝えるタイミングも重要と言えます。
実家に戻って生活コストを下げる
退職してから次の仕事が決まるまでの家賃や光熱費、食費などの固定費を抑える方法として、実家に戻るという選択肢があります。
一人暮らしに比べて生活コストを大幅に下げられるので、金銭的な不安を軽減できます。加えて、家族のそばで過ごすことで精神的にも安心感を得られるケースも多いです。
もちろん、家族との距離感や生活スタイルの違いが気になる方もいるでしょう。実家に戻る際は、家族と事前に期限や条件などを話し合い、無理のない形で同居できると安心です。また、必要に応じて生活費を一部負担するなどの配慮も大切です。
副業で収入源をつくる
副業で収入源をつくっておくのも、退職前後の金銭的不安を軽減する有効な手段です。
スキマ時間にできる副業は、Webライティングやデータ入力、フードデリバリー、動画編集、スキル販売などがあります。副業は未経験から始めやすいものも多く、最近は在宅で完結できる仕事も増えています。
最初は小さな収入でも、実績を積めば将来的にフリーランスとして独立を目指すことも可能です。副業は、収入確保だけでなく、自分の強みや興味を見直す機会にもなるので、まずは小さい規模から始め、無理なく継続できる副業を見つけてみましょう。
アルバイト・派遣で一時的に生活を支える
転職までに時間がかかりそうな場合は、正社員だけにこだわらず、短期のアルバイトで一時的に生活費を補うのも手です。
シフト制・短時間勤務のアルバイトや高時給の単発アルバイト、派遣といった働き方なら、転職活動との両立もしやすいです。
また、短期間でも収入が得られれば、収入がゼロの状態よりも気持ちに余裕が生まれやすくなります。前向きに次の仕事を探すためにも、一時的に非正規雇用で働くのもありでしょう。
高時給のバイト探しをする際は、こちらの記事も参考にしてみてください。
お金がなくても仕事を辞めるべき判断のポイント

退職後の生活資金に関する不安は大きな問題ですが、下記のようにそれ以上に深刻な状態を抱えている場合は、辞めることを真剣に考える必要があります。
- 心身に不調をきたしている
- ハラスメントなどブラックな労働環境
- 会社の業績悪化など将来性に不安がある
ここでは、退職を検討すべき具体的なケースを紹介します。まずは、自分の状況がこれらに当てはまっていないか見つめ直してみましょう。
心身に不調をきたしている
すでに体調やメンタルに不調を感じている場合は、退職も視野に入れましょう。
健康は何よりも重要です。自分の心身を守ることを第一に考え、決して無理をしない選択をするのが重要です。
たとえば、不眠や食欲不振、出社時の吐き気や動悸、休日も仕事のことが頭から離れないといった症状がある際は、早めの対処が必要でしょう。
本格的に体調が悪化すると、回復までに長期の治療期間と膨大な費用が必要になり、さらに深刻な状態に発展するリスクもあります。
必要に応じて医師や産業医にも相談して診断書を作成してもらい、傷病手当金の利用や休職も検討しましょう。
ハラスメントなどブラックな労働環境
パワハラやセクハラ、長時間労働、残業代が支払われないといった問題がある職場の場合も、すぐに退職を考えた方が良いケースが多いです。
つらい環境で大きなストレスを感じ続けていると、心身に大きな負担がかかり、将来的に健康問題に発展する恐れもあります。
会社都合の退職であれば失業保険を早く受け取れる可能性があるので、できる限り証拠となるメールや録音、日記などを用意して、労働基準監督署をはじめとした相談窓口に相談するのも手です。
また、上司に退職の意向を言い出せない場合や、強く引き止められて辞められないときは、退職代行サービスを利用する方法もあります。
会社の業績悪化など将来性に不安がある
会社の業績が悪化していると、突然の給与支払いの遅延や未払い、福利厚生・ボーナスのカット、社員サポートの低下、人員整理などのリスクが高まります。
特に経営状態が著しく悪い場合は、退職金すら支払われずに解雇や倒産となってしまうケースもあり、お金がない中で自分の意思で退職をするよりも状況が悪くなる可能性も出てくるでしょう。
経費削減の強化、役職者の退職、事業縮小などは、経営状態の判断材料になります。会社の状況を客観的に判断し、自分の生活や将来を第一に考える行動をとることが大切です。
お金がない状態で仕事を辞める際に頼れる公的支援制度

「お金がないままに退職したら生活が立ち行かないのでは…」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、実は頼れる公的支援制度がいくつかあります。
- 失業保険
- 傷病手当金
- 税金・社会保険料の減免
上記は条件を満たせば利用できる制度です。いざというときのために、確認しておきましょう。
失業保険
失業保険は、仕事を辞めて再就職したい人が、条件を満たせばもらえる給付金です。
もらえる金額は、だいたい辞める前の6ヶ月間の月収の45〜80%が目安です。
自己都合で辞めた場合でも、辞める前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に入っていれば、受給できます。
ただし、申請から実際に受け取れるまでには、1ヶ月半くらいかかります。
ハローワークでの手続きと定期的な求職活動の報告が必要になるので、退職を考え始めたら早めに調べておきましょう。
参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(参照2025-08-01)
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、給与の代わりに支給される制度です。支給額は月給のおおよそ3分の2で、最長1年6ヶ月まで受け取れます。
在職中に医師の診断を受けており、出勤できない状態が継続しているなどの一定の条件を満たせば、退職後も引き続き受給が可能です。
うつ病などのメンタル不調で出勤が困難な場合も、退職前に診断書をもらっておくことで傷病手当の対象となる可能性があります。
会社の健康保険に加入していた人が対象になるので、退職を考える前に条件に当てはまるか確認しておきましょう。
参考:全国健康保険協会「11)傷病手当金」(参照2025-08-01)
税金・社会保険料の減免
収入が減った際に、税金や保険料の支払いを軽減できる制度もあります。
対象となる費目と申請先の例は以下です。
- 国民健康保険料:自治体の保険年金課
- 国民年金保険料:年金事務所・自治体の国民年金窓口
- 住民税:自治体の税務課
- 所得税:所轄の税務署
これらはすべて申請が必要で、収入減や失業などの状況を証明する書類の提出も求められます。また、減免には期限が設けられているケースも多いです。
窓口で相談すれば手続きの流れを案内してもらえるので、気になる人は早めの相談・確認が大切です。
参考:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」(参照2025-08-01)
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(参照2025-08-01)
国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」(参照2025-08-01)
お金がないまま仕事を辞めて後悔しないためのアドバイス

「貯金が少ないけど、仕事を続けるのはもう限界」と退職したものの、準備不足のために必要以上に不安を抱えてしまったり、後悔してしまったりする人もいます。
しかし、あらかじめ以下のポイントを押さえておけば、前向きに次のステージに向かいやすくなります。
- 転職活動期間の目安を把握する
- 自分の選択に自信を持つ
- 高収入を目指せる「新しい働き方」も選択肢に入れる
ここでは、勢いだけで辞めてしまう前に知っておきたい大切な視点をご紹介します。
転職活動期間の目安を把握する
転職活動は一般的に3〜6ヶ月ほどかかると言われています。
求人探し、履歴書や職務経歴書の準備、応募、面接、内定後のすり合わせ、入社と工程が多く、未経験の職種や人気職種への転職の場合はさらに長引くケースもあります。
退職後に転職活動をする際は収入が途絶える可能性があるため、失業保険の受給や貯金の切り崩し、公的支援の活用など、生活費の計画を立てておくことが大切です。
特に一人暮らしの方や扶養家族がいる方は、固定費を見直す、実家への一時帰省を検討するなど、無収入期間を乗り切る工夫も必要です。
退職後に焦らずに活動できるよう、退職後の生活をイメージしてできる限り準備しておきましょう。
自分の選択に自信を持つ
「退職は、今後の人生を第一に考えた結果だ」とポジティブに考えることが、前向きな一歩につながります。
退職の決断をするには勇気がいりますが、SNSや周囲の人の声に惑わされず、「このまま働き続けたらどうなるか」を想像し、自分の心や体の声に耳を傾けましょう。
じっくり考えて自分が納得して選んだ道なら、それが正解です。人の評価や意見よりも、自分の気持ちを大切にしましょう。
また、つらい職場で得た経験であっても、今後の働き方や職場選びのヒントになります。過去の出来事を振り返りつつ、「次はどう働きたいか」を考える時間を持つことで、自分の今後のキャリアビジョンにとってプラスにつなげられます。
高収入を目指せる「新しい働き方」も選択肢に入れる
退職後の収入の不安を乗り越える手段として、これまでとは違った働き方を取り入れるのも選択肢です。
たとえば、ナイト系を視野に入れるのもありでしょう。ナイト系は学歴や職歴ではなく、やる気やコミュニケーションスキルが何よりも重視される業界のため、未経験でも挑戦しやすいのが特徴です。
短時間勤務でも高収入を得られる可能性があり、効率良く生活資金を確保したい方にも向いています。
また、人脈を広げたり、自分の新たな強みを発見できたりといったチャンスにもつながるでしょう。特定の働き方にとらわれず、多様な働き方を知っておくと、自分の可能性を広げられるかもしれません。
お金がなくても選択肢はゼロではない!

お金がなくても仕事を辞めることは可能です。
また、事前に準備をしておけば、状況は大きく変わってきます。たとえば、失業保険や傷病手当金などの公的制度を活用する道もあれば、未経験からでも高収入を狙える新しい働き方に踏み出すという選択肢もあります。
「辞めたい」と思ったときに備えて、あらかじめ情報を集めておくことが重要です。お金がなくても仕事を辞める方法があると知っておけば、無理をして仕事を続けずに、自分らしい道を選びやすくなります。
お金がなくても、未来を変える方法は必ずあります。自分の気持ちを重視して、前向きに自分が納得できる選択をしていきましょう。