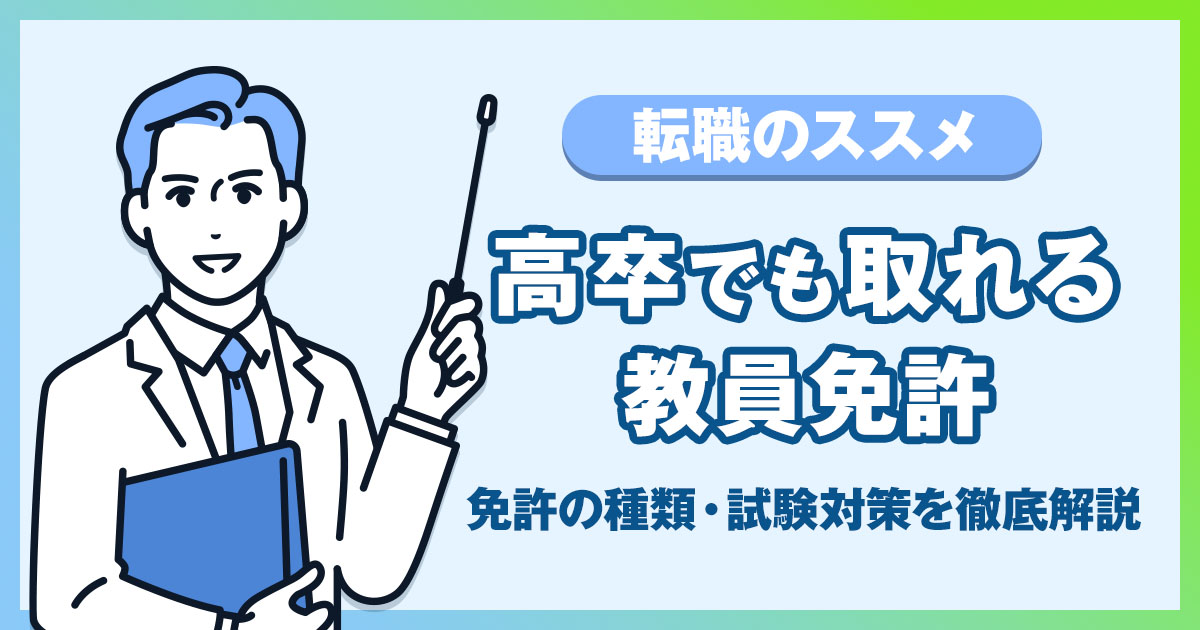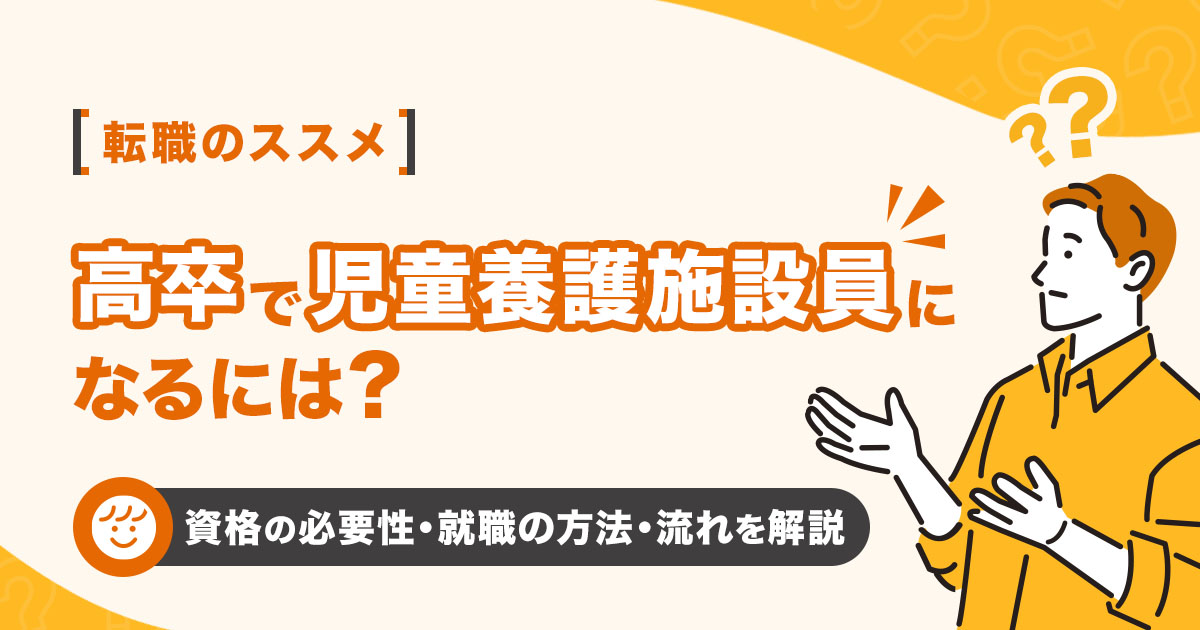-
高卒でも教員免許って取得できる?
-
高卒で教員免許を取得する方法を知りたい
教員免許は、高卒の人も取得できます。
その中でも、最短で取れるのが「小学校教員免許(小学校教諭二種免許状)」です。
本記事では、高卒で小学校教員免許を取得する手順や免許の種類、試験対策などを解説します。
教員免許取得後のキャリアパスや取得するメリット・デメリットもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
高卒でも教員免許を取得できるが学歴以外の条件がある

高卒でも教員免許を取得することは可能です。
いくつか種類はありますが、高卒の人が一番早く取れるのは「小学校教員免許」です。
ただし、免許を取るには「教員資格認定試験」に合格する必要があります
高校を卒業していて20歳以上であれば、誰でも受けられるので、受験すること自体は難しくありません。
とはいえ、この試験は難関なため、しっかり試験対策を行うことが大切です。
教員免許を取得した学歴内訳

下の表は、小学校の教員免許を持っている人の学歴をまとめたものです。
| 学歴 | 割合 |
|---|---|
| 高卒 | 2.0% |
| 短大卒 | 6.1% |
| 高専卒 | 2.0% |
| 大卒 | 95.9% |
| 修士課程卒 | 16.3% |
| 博士課程卒 | 4.1% |
参考:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag「小学校教員」(参照 2025-07-30)
このデータから、ほとんどの人が大学を出てから教員免許を取っていることがわかります。高卒の割合は2.0%と少ないですが、「ゼロ」ではありません。
「自分にもできるかな…」と不安に思うかもしれませんが、高卒でも努力すれば目指せる資格です。
最短で高卒で教員免許を取得する手順

高卒で教員免許を取得するためには、教員資格認定試験を受ける必要があります。
教員資格認定試験の種類は以下の3つです。
- 小学校教員資格認定試験 小学校教諭二種免許状
- 幼稚園教員資格認定試験 幼稚園教諭二種免許状
- 高等学校(情報)教員資格認定試験 高等学校教諭(情報)一種免許状
上記3つのうち、高卒が最短で受験・取得できるのは「小学校教員資格認定試験」です。
ここでは高卒が小学校教諭二種免許状を取得する手順を6つのステップに分けて解説します。
手順①小学校教員資格認定試験の受験願書等を入手する
まずは、試験を受けるための願書を手に入れることから始まります。
願書の請求期間は毎年決まっていて、期間を過ぎると一切もらえなくなってしまうので注意が必要です。
令和7年度の場合:令和7年1月24日~2月28日
最新の情報をしっかりチェックして、請求期間内に忘れずに手続きをしましょう。
なお、請求された受験願書等は随時発送され、おおむね2~3日程度で届きます。受験願書等が届いたら、案内に従って送付手数料415円を支払います。
参考:文部科学省「教員資格認定試験」(参照 2025-08-27)
手順②教員資格認定試験の願書を提出する
願書に必要事項を書き込み、必要な書類をすべてそろえて、決められた期間内に「教員資格認定試験受付事務局」まで郵送します。
受験願書の請求期間と同じく、期間を過ぎると受理されないので注意が必要です。
令和7年度の場合:令和7年2月10日~3月7日(当日消印有効)
必要書類は、受験願書以外にも「戸籍謄本もしくは住民票の写し」「高等学校の卒業証明書」などさまざまです。
また、受験手数料として25,000円を支払ったあと、振替支払受付証明書の原本も提出する必要があります。
手順③受験票が交付されたら準備をする
願書が受理されると、受験票が送られてきます。
令和7年度の場合:令和7年4月中旬頃
万が一期日までに受験票が到着しない場合は、受験案内に記載されている指定の日時までに教職員支援機構へ連絡してください。
受験票に、試験会場や時間、持ち物などが書かれています。また、試験当日は受験票を提示しないと受験できないため、必ず持参するようにしましょう。
なお、教員資格認定試験の受験地は東京・大阪の2ヶ所のみです。年によって試験会場が変わる場合があるので、試験開始の時間に間に合うように交通手段をチェックしておきましょう。
手順④第1次試験に合格する
小学校教員資格認定試験は第1次試験と第2次試験に分かれており、まずは第1次試験の合格を目指します。第1次試験は筆記試験です。
令和7年度の場合
試験実施日:令和7年5月11日(合否の発送は7月23日)
| 試験科目 | 内容 | 方法 |
|---|---|---|
| 教科及び教職に関する科目(Ⅰ) | 教職専門科目に関する内容 | マークシート方式 |
| 教科及び教職に関する科目(Ⅱ) | 小学校の各教科の具体的な授業場面を想定した指導法及びこれに付随する基礎的な教科内容 | マークシート方式 |
| 教科及び教職に関する科目(Ⅲ) | 小学校の各教科の具体的な授業場面を想定した指導法及びこれに付随する基礎的な教科内容 | 論述式 |
| 教科及び教職に関する科目(Ⅳ) | 教職への理解及び意欲、児童理解、実践的指導力等、小学校教員として必要な能力等の全般に関する事項 | 論述式 |
第1次試験の合格基準は、各科目満点の6割以上です。
手順⑤第2次試験に合格する
小学校教員資格認定試験の第1次試験に合格したら、第2次試験を受験します。
第2次試験は、教職の適性があるかどうかを重視した内容で、主に受験者のコミュニケーション能力や実践的指導力の有無を判定します。
令和7年度の場合
試験実施日:令和7年9月6日(合否の発送は10月15日)
| 内容 | 方法 |
|---|---|
| 教職への理解及び意欲、小学校教員として必要な実践的指導力に関する事項 | 学習指導案作成、模擬授業、口頭試問(個別面談)等 |
第2次試験では、複数課題をそれぞれA・Bの2段階で評価され、Aが合格です。
手順⑥文部科学省に合格証明書の発行申請をする
小学校教員資格認定試験に合格すると、合格通知が郵送されます。
自治体によっては、教員免許を申請する際に「合格通知」ではなく「合格証明書」の提出が必要になるケースもあります。その場合は、同封されている「合格証明書の申請案内」に則って申請しましょう。オンラインフォームからの申請も可能です。
なお、合格証明書は教員免許ではないので注意が必要です。
教員資格認定試験はあくまで「この人は教職へ就くに足る能力と資質を持っている」と証明するものなので、合格証明書が発行されたら必ず教員免許の発行も行いましょう。
手順⑦各都道府県で教員免許を発行する
合格証明書が届いたら、各都道府県の教育委員会へ教員免許(小学校教諭二種免許状)の発行申請を行います。基本的に在住地もしくは転居予定地の教育委員会以外では申請できないので注意が必要です。
必要書類は、各都道府県の教育委員会が指定するものを揃えるようにしてください。申請書類を提出後、書類に不備がないかといった審査が行われます。
審査通過後、発行手数料を支払います。発行手数料は都道府県によって異なり、東京都の場合は免許状1枚につき3,300円です。
手数料の納付確認後に申請が受理されれば、教員免許(小学校教諭二種免許状)が発行されます。なお、発行までに30日~60日程度の時間を要します。
高卒で教員免許を取得するための試験対策

高卒で教員免許を取得するためには、教員資格認定試験に合格しなければなりません。令和6年度小学校教員資格認定試験の合格率は24%で、難易度は高めといえます。
教員資格認定試験に合格するためには、以下のような試験対策を重点的に行うことが重要です。
- 過去問を解きながら「学習指導要領」を熟読する
- いち早く自分の得意科目を把握する
- 対策講座を受講する
ここでは、上記3つの試験対策について解説していきます。
①過去問を解きながら「学習指導要領」を熟読する
第1次試験「教科及び教職に関する科目(Ⅰ)」は、20問の択一形式で出題され、以下の教職教養を問われます。
| 教育原理 | 教育に関する根本的な考え方、原理など |
| 教育史 | 東西の教育における歴史 |
| 教育法規 | 教育に関する法律、近年の政策など |
| 教育心理 | 教育における心理的な側面、関係性構築など |
暗記問題が多く覚える範囲も広いので、以下の流れで時間をかけて勉強しましょう。
- NITS(独立行政法人教職員支援機構)の公式サイトに掲載されている過去問を繰り返し解く
- 小学校教員資格認定試験の参考書や文部科学省が定める「学習指導要領」を熟読する
「学習指導要領」とは、全国の学校で一定の基準を保てるように、文部科学省が定めている教育課程の基準を指します。
過去問を繰り返し解いて参考書や学習指導要領を熟読することで、知識の定着をはかりやすくなります。
②いち早く自分の得意科目を把握する
第1次試験「教科及び教職に関する科目(Ⅱ)」は以下の10科目から6科目、「教科及び教職に関する科目(Ⅲ)」は同じく以下の10科目から1科目を選択して問題を解きます。
- 国語、社会、算数、理科、生活、家庭、外国語(英語)、音楽、図画工作、体育
「教科及び教職に関する科目(Ⅱ)」の科目を選択する際は、6科目のうち「音楽、図画工作、体育」の中から2つ以上を必ず含めなければいけません。
受験科目を決めて重点的に学習するためにも、いち早く自分の得意科目を把握する必要があります。過去問を繰り返し解くことで、高い得点が取れる科目が明確になっていきます。
選択科目を決めたあとは、「学習指導要領」を読んで学習を進めていきましょう。
③対策講座を受講する
第2次試験の「学習指導案作成」「模擬授業」「口頭試問(個別面接)」は、公式サイトに過去問が掲載されておらず、関連の参考書も少ないので、独学で対策をするのは難しいです。
第2次試験の合格率を上げたいのであれば、対策講座を受講しましょう。
また、自治体によっては公式サイトに「学習指導案」をまとめている場合もあります。書き方が分からない人はチェックしてみてください。
なお、令和7年度に実施された小学校教員資格認定試験の場合、第1次試験の合格発表から第2次試験までは約1ヶ月強しかありませんでした。余裕を持って取り組むためにも、第1次試験を受験後すぐに試験対策を始めるのがおすすめです。
高卒で教員免許を取得したあとのキャリアプラン

高卒で教員免許を取得すると、キャリアプランの選択肢が広がります。ここでは、高卒で教員免許を取得したあとのキャリアプランを3つご紹介します。
- 小学校の教員になる
- 保育士として働く
- 学童保育所や児童養護施設の職員として働く
理想のキャリアプランを見つけるためにも、どんな選択肢があるのか詳しく見ていきましょう。
①小学校の教員になる
1つめのキャリアプランは、「小学校の教員になる」です。小学校教諭二種免許状を取得すれば、公立・私立小学校の教員になれます。
小学校の教員になる手順を公立・私立に分類して表にまとめました。
| 公立(地方公務員) | 各自治体の教育委員会が主催する教員採用試験を受験し、合格する |
| 私立(運営団体職員) | 学校が独自で実施する採用試験を受験し、合格する |
小学校の教員になったあと、勤務年数を積むことで学年主任や教務主任になれる可能性があります。ただし、小学校教諭一種免許状の取得者のみを昇進の対象とする学校も存在するので、赴任先によっては一種免許状を取る必要が出てくるかもしれません。
②保育士として働く
2つめのキャリアプランは、「保育士として働く」です。小学校教諭二種免許状を取得すれば、保育士として働ける場合があります。
本来であれば、保育園で働くには保育士免許の取得が必要です。しかし、保育士の深刻な人手不足に伴い、2016年4月に「保育所等における保育士配置に係る特例」が執行されました。
- 「保育所等における保育士配置に係る特例」とは
- 仕事内容や教育の対象年齢が近いとされる「幼稚園教諭」「小学校教諭」「養護教諭」の資格保有者を保育士の代理として雇用できる特例制度を指します。
この特例制度の実施の有無は、自治体や事業所の判断に委ねられます。保育士不足の地域であれば、小学校教員免許を取得したあとに許可保育所で保育士として採用される可能性があります。
ただし、あくまで一時的な救済措置として実施されているだけなので、今後保育士としてキャリアアップを目指すのであれば保育士資格を取得するのがおすすめです。
③学童保育所や児童養護施設の職員として働く
3つめのキャリアプランは、「学童保育所や児童養護施設の職員として働く」です。
- 学童保育所とは
- 小学校の子どもたちを平日の放課後や土曜日、夏休みなどの長期休暇中に預かる施設を指します。
- 児童養護施設とは
- 親がいない、または家庭での養育が困難な子どもたちを支援・養育するための施設のことです。
学童保育所は「放課後児童支援員」、児童養護施設は「児童指導員」の任用資格を取得することでキャリアアップを目指せます。いずれも小学校教員免許を取得すれば実務経験なしで要件を満たせるため、キャリアプランの選択肢の一つとして視野に入れてみるのもおすすめです。
高卒で教員免許の取得に向いている人

高卒で小学校教員免許を取得するには、難易度の高い小学校教員資格認定試験に合格しなければなりません。教員免許の取得に向いている人の特徴は、以下の3つです。
- 自主的に勉強計画を立てられる人
- 十分な学習時間を取れる人
- 子どもの教育について考えられる人
教員免許の取得を目指している方は、自分が上記に当てはまっているかぜひチェックしてみてください。
①自主的に勉強計画を立てられる人
小学校教員資格認定試験の出題範囲は広く、多くの専門知識の習得も求められます。また、第2次試験は独学での対策が難しく、対策講座の受講も視野に入れることになります。
難易度が高い小学校教員資格認定試験に合格するためには、あらかじめ長期的な勉強計画を立てなければなりません。よって、自主的な勉強計画を立てられる人は、教員免許の取得に向いているといえるでしょう。
②十分な学習時間を取れる人
小学校教員資格認定試験に合格するために必要な勉強時間は、1,000~1,500時間程度といわれています。
第1次試験の一部は得意な科目の選択制ではあるものの、それでも学習範囲が広いです。また、学習指導案の作成をはじめ、教職ならではのスキル習得も必須となります。
毎日コツコツと学習を続ける時間が確保できる人は、アドバンテージが大きいでしょう。試験に向けて十分な学習時間を取れる人は、教員免許の取得に向いています。
③子どもの教育について考えられる人
小学校教員免許は、子どもの教育について考えられる人が取得しやすい傾向です。
小学校教員資格認定試験では、「生徒に教える際、どうすれば興味を持ってくれるか」「どうすれば分かりやすく、間違いなく伝わるか」など、教育において自分の考えを具体的な解答を求められる問題もあります。
ただ子どもが好きというだけではなく、児童教育について理解する意欲がある人は、資格を活かして働ける可能性が高いでしょう。
高卒で教員免許の取得に向いていない人

小学校教員資格認定試験は難易度が高く、さまざまな知識が必要となるため、教員免許の取得に不向きな人もいます。高卒で教員免許の取得に向いていない人の特徴は、以下の3つです。
- 勉強する科目の優先順位を立てられない人
- 人と話すことが苦手な人
- 継続的に勉強する時間がない人
自分に適性があるかを判断するためにも、上記に当てはまらないかぜひチェックしてみてください。
①勉強する科目の優先順位を立てられない人
第1次試験「教科及び教職に関する科目(Ⅰ)~(Ⅲ)」は、6割以上正解しないと不合格になります。
なかでも「教科及び教職に関する科目(Ⅱ)」は選択した6教科のうち1教科でも最低基準(4割)に満たない場合は不合格になるので、難易度は高めといえるでしょう。
試験に合格するために必要な点数を稼ぐことを考えて、勉強する科目の優先順位を立てられるかどうかが重要です。
勉強する範囲が広く、暗記する量も多いという点を踏まえても、勉強する科目の優先順位を立てられない人は教員免許の取得に向いていないかもしれません。
②人と話すことが苦手な人
人と話すことが苦手な人の場合、教員免許の取得は難しい傾向にあります。
小学校教員資格認定試験は、個別面接だけでなく模擬授業も含まれており、模擬授業では円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
また、小学校教員免許を活かせる仕事のほとんどが児童や保護者、他の先生などとコミュニケ―ションを取る機会が多いです。そのため、人と話すことが苦手な人は、免許取得や就職後のキャリアアップがしにくくなる可能性があります。
③継続的に勉強する時間がない人
仕事や家庭の事情で勉強に十分な時間を割く余裕のない人は、教員免許の取得の難易度が高いかもしれません。
第1次試験では、最低でも6科目の教科を網羅する必要があるのにくわえて、教職に就くための基礎的な知識を覚えなくてはなりません。
学習範囲がかなり広いので、継続的に勉強する時間を確保しないと試験合格は厳しいといえます。仕事柄まとまった学習時間が作りにくい人は、出勤前や通勤中、退勤後など、スキマ時間に解消できそうな学習内容を事前に決めておくのがおすすめです。
高卒で教員免許を取得するメリット

小学校教員免許を取得するのは簡単ではありませんが、取得するとさまざまなメリットを得られます。高卒で教員免許を取得するメリットは、以下の3つです。
- 通信制大学や短大に通うより費用を抑えられる
- キャリアパスが広がる
- 働きながら教員免許を取得できる
小学校教員免許を取得すべきかお悩みの方は、判断材料の一つにしてみてください。
①通信制大学や短大に通うより費用を抑えられる
小学校の教員免許を取得する際、通信制大学や短大へ通う方法が一般的です。独学より免許取得に必要な知識が習得しやすいメリットがある一方で、最低でも100万円以上の学費が必要になるデメリットもあります。
大学に通わずに小学校教員資格認定試験を受験する場合、主な費用は以下の通りです。
- 受験料25,000円
- 願書の送付手数料415円
- 受験場所までの交通費
- 教員免許の発行手数料(東京都は免許状1枚につき3,300円)
よって、通信制大学や短大に通うより受験費用がかからないのは大きな利点といえるでしょう。
②キャリアパスが広がる
小学校教員免許を取得すると、教育分野においてキャリアの選択肢が広がるメリットがあります。教職免許は教育に関する高い知識やスキルを証明できるので、教育業界に就職する際に有利に働きやすいです。
また、小学校教員免許の取得を通じて、コミュニケーション能力や問題解決力といったスキルも身につけられるため、以下のように他業界でも活躍できる可能性があります。
- 人事
- 営業職
- 事務職
- 医療職、福祉職
業界を問わず多くの企業が求めるスキルを習得しやすい点は、小学校教員免許を取得する強みの一つといえます。
③働きながら教員免許を取得できる
小学校教員資格認定試験の受験資格は、「高卒以上」「20歳以上」の2つのみです。通信制大学や短大に通わなくても受験できるので、仕事とプライベートを両立しながら試験対策を進めやすいメリットがあります。
とはいえ、小学校教員資格認定試験の難易度はかなり高いです。試験合格を目指して通信講座の受講を検討する人も少なくないでしょう。
ほとんどの通信講座は仕事と両立できるようにカリキュラムが組まれている場合が多いので、働きながら小学校教員免許を取得することは可能です。
高卒で教員免許を取得する際の注意点

高卒で教員免許を取得するメリットが多い一方で、注意しなければならない点もいくつかあります。高卒で教員免許を取得する際の注意点は、以下の3つです。
- 取得難易度が高い
- 勉強するモチベーションを維持するのが難しい
- 目指すキャリアによっては今後一種免許状へ変更する必要がある
教員免許の取得を目指している高卒者は、上記3つの注意点を踏まえたうえで検討しましょう。
①取得難易度が高い
先述した通り、小学校教員資格認定試験は合格率が20%台で推移しており、取得難易度が高いです。
令和6年度の実施結果は、受験者数807人のうち合格者数は194人で合格率は24%でした。
取得難易度が高い理由として、「試験対策の範囲が広すぎて独学ですべて網羅するのが難しい」という点が挙げられます。
小学校教員資格認定試験に合格するためには、綿密に立てた学習スケジュール通りに勉強を続けていくことが求められます。
参考:独立行政法人教職員支援機構「教員資格認定試験過去の実施結果(令和6年)」(参照 2025-08-01)
②勉強するモチベーションを維持するのが難しい
高難易度の小学校教員資格認定試験に合格するには、遅くとも1年ほど前から試験対策を始める必要があります。
独学の場合、長期戦になるせいか勉強するモチベーションを保つのが難しくなり、知識を身につけるスピードが遅くなってしまうケースが起こり得ます。
一人で勉強し続ける状況に不安がある人は、対策講座やセミナーを受講して同じ受験者と情報交換をしたり、講師からアドバイスを受けたりするのが有効です。
第三者と関わりながら勉強に取り組むことで、さまざまな角度から良い刺激を受け、モチベーションの向上につながります。
③目指すキャリアによっては今後一種免許状へ変更する必要がある
先述した通り、小学校教員資格認定試験で取得できるのは、二種免許状のみです。
小学校の場合、教頭や副校長、校長のような管理職になるうえで一種免許状へ切り替える「努力義務」を定める学校も存在します。小学校の教員としてキャリアアップを目指すのであれば、今後一種免許状へ変更しなければならない可能性があります。
二種免許状から一種免許状に切り替えるには、小学校の教員として働きながら通信制大学や短大に通い、一種免許状へ切り替える際に不足する単位数を取得するのが一般的です。
教員免許がなくても働けるおすすめの仕事

小学校教員免許を取得するためには、膨大な学習時間を確保したうえで、教職に求められる専門的な知識を効率よく習得していく必要があります。
合格率も20%前後と決して高くないことから、教員免許取得へのハードルが高いと感じる方も少なくないでしょう。
ここでは、教員免許がなくても働けるおすすめの仕事を3つご紹介します。
- 塾講師
- 家庭教師
- 教育サービスの企画・運営
特に教育分野に携わりたい方は、ぜひご覧ください。
①塾講師
塾講師は、生徒に勉強を教えるという点で教師と似ている職業です。塾講師になるのに特別な資格は必要ないので、教員免許がなくても働ける可能性があります。
なお、以下のような資格を取得しておくと塾講師として採用されやすくなります。
- TOEIC600点以上
- 実用英語技能検定2級以上
- 実用数学技能検定2級以上
- 日本漢字能力検定2級以上
- 学習塾講師検定
生徒の成績を伸ばせる優秀な講師になれば、大幅な収入アップも狙えます。
②家庭教師
家庭教師は、1対1で教えることに特化しており、塾講師と同じく生徒に勉強を教えるという点で教師と似ています。生徒との関わりがより深くなるため、きめ細かな対応が求められます。
家庭教師は正社員よりもアルバイトでの採用が多く、副業を検討する社会人を採用する企業も珍しくありません。
また、スキルを磨き「プロ家庭教師」として活動するキャリアプランもあります。案件の受注方法はさまざまですが、仲介会社に登録して仕事を紹介してもらったり、SNSで自分の教育論を積極的に発信して集客したりする方法が基本です。
③教育サービスの企画・運営
教育サービスを提供する企業に就職し、教育教材や出版物の企画、教育サービスの運営などを行う仕事もあります。
提供する教育サービスの主な種類は、以下の通りです。
- 通信教育
- 教育系の出版
- プログラミング、科学、そろばん、作文といった能力開発型の教育サービス
なお、企業によっては企画・運営業務の経験者を求める傾向にあります。教育分野の知識を持っていても採用されない可能性もあるため、事前に応募条件をよく確認しましょう。
高卒で教員免許を取得するためのおさらい

高卒が最短で教員免許を取得できるのは、「小学校教員免許(小学校教諭二種免許状)」です。
高卒のまま小学校教員免許を取得するには、小学校教員資格認定試験に合格する必要があります。合格率は20%前後とかなり低いので、過去問や「学習指導要領」を活用しながら効率よく勉強を進めていくことが重要です。
教員免許を取得すれば、小学校の教員や保育士、学童保育所や児童養護施設の職員として働ける可能性があります。また、コミュニケーション能力や問題解決力といった社会人スキルも身につきやすいため、教育以外の業界でも活躍できるでしょう。
高卒で教員免許を取得するメリットに魅力を感じた方は、ぜひ挑戦してみてください!