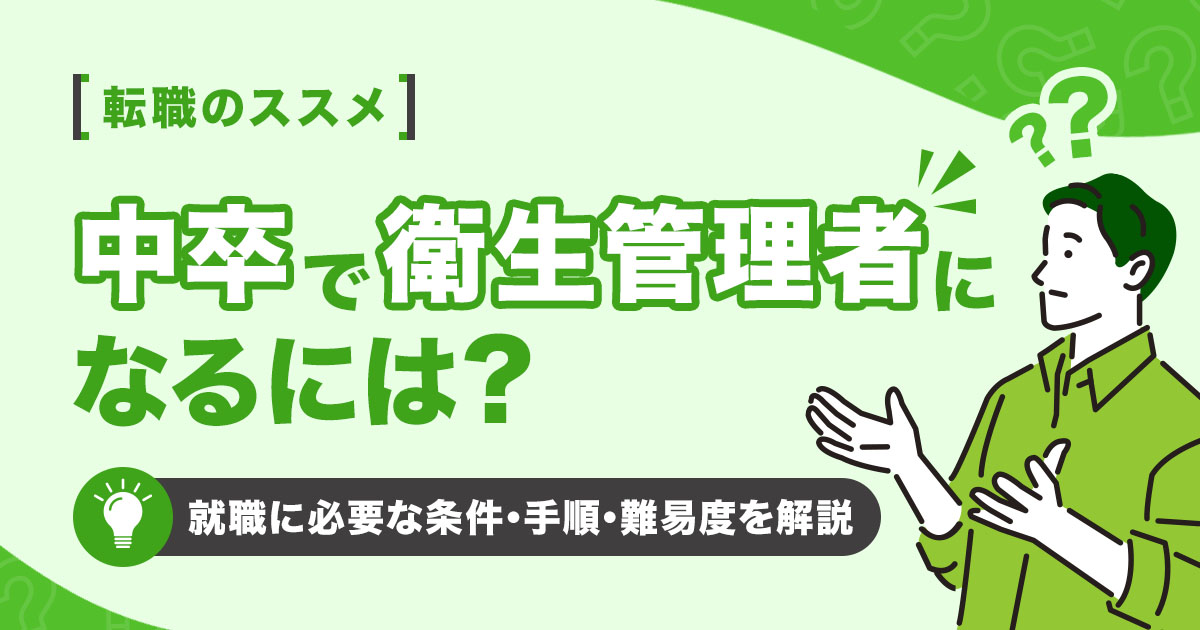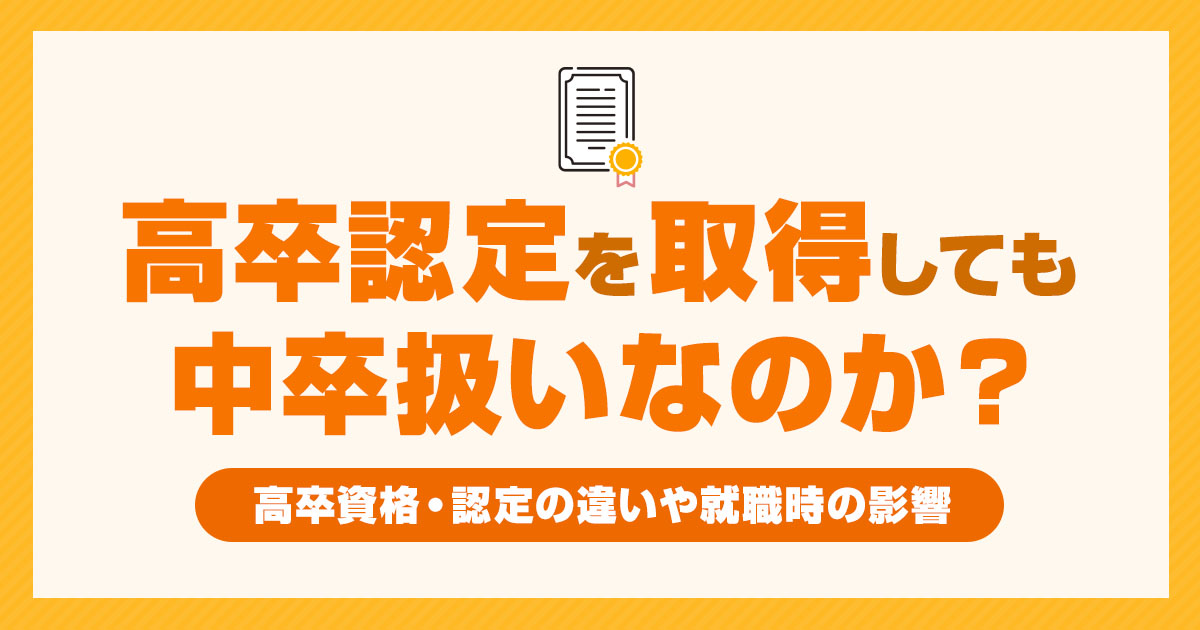-
中卒で衛生管理者になれるの?
-
衛生管理者になるために学歴以外に必要な条件を知りたい
衛生管理者は、労働安全衛生法で定められた国家資格で、職場の労働環境を衛生的に保ち、病気やケガを防ぐための管理を行う職業です。
受験資格を満たせば中卒から試験への挑戦と資格の取得が可能です。
この記事では、中卒から衛生管理者になるまでの手順や試験の受験条件、効果的な試験対策、取得後のキャリアプラン、向き不向きやメリット・注意点などを詳しく解説します。
中卒で衛生管理者になれるが学歴以外の条件がある

中卒から衛生管理者になることは可能です。ただし、衛生管理者試験を受けるには次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 中卒:労働衛生の実務経験が10年以上ある
- 高卒認定試験合格者:労働衛生の実務経験が3年以上ある
受験資格を得るための実務経験とは「労働衛生の実務に従事した経験」を指し、13種類の業務が該当します。
実務経験に当てはまる業務内容の詳細は次項で説明するので、そちらをご確認ください。
なお、中卒の場合は10年以上の実務経験が必要ですが、試験そのものは年齢や学歴に制限がなく、誰でも挑戦可能です。
自分の経験が条件に当てはまるかどうかは、安全衛生技術試験協会のホームページにある「受験資格アシスト」を使って調べられます。
受験資格アシストを活用すれば、実務経験年数と卒業した学校の種別を選ぶだけで、受験資格の有無だけでなく、必要な添付書類についてもアナウンスしてくれます。
参考:公益財団法人 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者の紹介・2.受験資格」 (参照 2025-09-01)
中卒で衛生管理者になる方法

中卒から衛生管理者を目指すには、以下の2つのルートがあります。
- 方法① 実務経験を10年以上積んで衛生管理者試験に合格
- 方法② 高卒認定を取得後、実務経験を3年以上積んで衛生管理者試験に合格
どちらの方法にもメリット・デメリットがあり、自分の学歴やキャリアに合わせた選択が大切です。
また、衛生管理者の資格には 「第一種」と「第二種」 の2種類があります。
- 第一種:すべての業種で対応可能
- 第二種:情報通信業、金融業、保険業など有害業務の少ない業種限定
第一種と第二種では必要な学習時間も異なるため、「どちらを目指すのか」を早めに決めておくと計画が立てやすくなります。
次の章では、それぞれのルートについて詳しく解説します。
方法① 実務経験を10年以上積んで衛生管理者試験に合格
中卒から衛生管理者を目指す最も基本的な方法は、実務経験を積んだうえで衛生管理者試験に合格するルートです。
免許取得までの手順は以下のとおりです。
- 労働衛生の実務に10年以上従事する
- 衛生管理者試験に合格する
- 東京労働局免許証発行センターに免許を申請する
実務経験は勤務先が変わっても合算でき、派遣やアルバイトでの経験も対象です。そのため転職をしていても、労働衛生に関連する業務に携わっていれば実務経験としてカウントされます。
ただし、単純な清掃や備品交換といった作業は実務経験に含まれない点に注意が必要です。
- 注意点
- ※①の「労働衛生の実務」は、以下の業務が含まれます。
1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5.衛生教育の企画、実施等に関する業務
6.労働衛生統計の作成に関する業務
7.看護師又は准看護師の業務
8.労働衛生関係の作業主任者(※②に記載する職務に限る。)としての職務
9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11.保健衛生に関する業務
12.保健所職員のうち、試験、研究に従事する者等の業務
13.建築物環境衛生管理技術者の業務
※②の労働衛生関係の作業主任者は、次の職務に限られます。
・高圧室内作業主任者
・エックス線作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・四アルキル鉛等作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者
・有機溶剤作業主任者
・石綿作業主任者
参考:公益財団法人 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者の紹介|事業所証明書」(参照 2025-09-01)
方法② 高卒認定を取得後、実務経験を3年以上積んで衛生管理者試験に合格
中卒で衛生管理者になるには、最低でも10年の実務経験が必要です。
「できるだけ早く資格を取りたい」という方には、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)を受けるルートがおすすめです。
合格すれば、必要な実務経験が3年以上に短縮され、より早く衛生管理者試験に挑戦できます。
2026年度(令和8年度)の高卒認定試験からは、新科目「情報」が必修に追加され、合格に必要な科目数は9~10科目(必修科目7科目+選択科目2~3科目)に変更される予定です。
- メモ
- 【2026年度(令和8年度)から必要な科目数】
国語、地理、歴史、公共、数学、英語
理科「科学と人間生活+理科の基礎科目どれか1つ」または「理科の基礎科目どれか3つ」
情報(追加された新科目)
※理科の基礎科目:物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎
過去の履修状況や保有資格によって免除される科目もあるので、実際の受験科目数は人によって異なります。
受験料は科目数に応じて次のように定められています。
| 受験科目数 | 受験料 |
|---|---|
| 3科目以下 | 4,500円 |
| 4~6科目 | 6,500円 |
| 7科目以上 | 8,500円 |
なお、高卒認定に合格しても最終学歴は「高卒」とならない点も理解しておきましょう。
参考:文部科学省|高等学校卒業程度認定試験規則・告示等「高等学校卒業程度認定試験における試験科目の変更等について(令和8年度から)」(参照2025-09-03)
中卒で衛生管理者になるための試験対策

中卒から衛生管理者を目指す場合、試験合格に向けて「どう勉強するか」が重要です。働きながら勉強する方も多いので、教材や講習をうまく使いながら効率よく知識を積み上げていきましょう。
- 学習のステップ
- ①合格までのスケジュールを立てる
②参考書を熟読する
③問題集・過去問で学習する
④講習に参加する
大事なのは、自分の生活リズムに合わせて無理なく続けられる学習スタイルを作ることです。
①合格までのスケジュールを立てる
まずは試験の合格基準をしっかり把握しておきましょう。
衛生管理者試験は科目ごとに40%以上、かつ全体で60%以上の得点が必要です。出題範囲は「労働衛生」「関係法令」「労働生理」の3分野で、試験時間は3時間のマークシート方式です。
| 第一種 | 有害業務を含む全業種が対象 | 44問・400点満点 |
| 第二種 | 有害業務を除く業種が対象 | 30問・300点満点 |
一般的な勉強時間は第一種で約100時間、第二種で約60時間とされ、働きながら挑戦する場合は4~6か月ほどかけて準備するのが目安だといわれています。
衛生管理者試験の合格を目指して、受験日から逆算して計画を立て、無理のないスケジュールを組むことが合格のポイントになります。
②参考書を熟読する
衛生管理者試験に合格するには、参考書をはじめとした教材を活用することが欠かせません。
衛生管理者は第一種と第二種によって試験範囲が異なり、受験する試験に応じた参考書を選びましょう。
| 第一種衛生管理者 | 科目 |
| 第一種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものも含む) |
| 関係法令(有害業務に係るものも含む) | |
| 労働生理 | |
| 第二種衛生管理者 | 労働衛生(有害業務に係るものを除く) |
| 関係法令(有害業務に係るものを除く) | |
| 労働生理 |
第一種・第二種ともに出題範囲は幅広く、一度読んだだけで覚えるのは難しいです。そこで同じテキストを何度も繰り返し読むことで、少しずつ理解を深めていきましょう。
また、参考書には「初学者向け」と「経験者向け」があります。どちらも「わかりやすい」と書かれていても、対象レベルが違うので注意が必要です。本屋で実際に手に取って比べ、自分に合った1冊を見つけましょう。
参考書を何冊も揃えなくても、自分に合った1冊を繰り返し活用できれば、試験合格に必要な知識が身につきます。基礎が定着すれば、自然と応用問題にも対応できるようになります。
③問題集・過去問で学習する
参考書で学んだ内容を定着させるには、問題集や過去問を繰り返し解く勉強法が効果的です。
問題集は「学んだ内容が理解できているか」を確認するために使いましょう。間違えた箇所は参考書に戻って復習し、再度解き直すことで知識がしっかり定着します。
また、過去問を解くことで出題傾向がつかめるだけでなく、本番を想定した時間配分の練習にもなります。自分がどの分野でつまずきやすいのかを把握できれば、重点的に対策できるようになります。
さらに最近はスマホアプリで過去問を解けるものもあるので、通勤や休憩のスキマ時間を使って効率よく勉強することも可能です。時間に追われがちな社会人に特におすすめな勉強方法です。
④講習に参加する
独学での勉強が苦手な方には、講習を受ける方法もおすすめです。
受講料はかかりますが、講師から直接指導を受ければ理解が深まり、不明点もその場で質問できるのが大きなメリットです。さらに、同じ目標を持つ仲間と出会えることで、試験勉強のモチベーションも維持しやすくなります。
会場まで通うのが難しい場合や時間が限られている場合には、オンライン講座やDVD講座など自宅で学ぶ方法もあります。2~3日程度で修了する短期集中型の講習もあるため、効率的に学びたいときにも適しているでしょう。
自分に合った講習を選べば、効率よく知識を吸収でき、合格に大きく近づけます。
申し込みの際は、自分が受験する区分が第一種向けか第二種向けかを必ず確認して、受講するカリキュラムを間違えないように注意しましょう。
中卒で衛生管理者になったあとのキャリアプラン

衛生管理者として経験を積んだあとは、さらなる専門資格を取得すればキャリアを広げられます。
- 労働衛生コンサルタントを目指す
- 社会保険労務士の資格を取る
将来的にキャリアアップを考えている方は、衛生管理者を足がかりに資格取得や専門職への挑戦を視野に入れると良いでしょう。
①労働衛生コンサルタントを目指す
労働衛生コンサルタントは、労働者の衛生水準を高めるために、事業場の状況を診断し、改善に向けた指導を行う専門家です。
衛生管理者が実施している対策が正しく行われているかを確認・評価する役割を担っており、衛生管理者の上位に位置づけられます。
衛生管理者は自社の従業員から選任されるのに対し、労働衛生コンサルタントは企業から依頼を受けて外部の専門家として携わる場合が多いです。
客観的かつ高度な専門知識が求められるものの、独立開業を目指しやすい職業なので、自ら事務所を構えて活動する道も開ける可能性があります。
中卒から労働衛生コンサルタントを目指す場合は、国家試験に合格して資格を取得することが必要です。
常時50人以上の労働者を抱える事業場で衛生管理者として選任され、10年以上の実務経験を積めば受験資格を得られます。
②社会保険労務士の資格を取る
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険の手続きを代行し、労務管理に関する相談や指導を行う国家資格の専門家です。
中卒から社労士を目指す場合は、労働衛生コンサルタントの取得や社労士事務所での補助業務など、関連する実務経験を3年以上積むことで国家試験の受験資格を得られます。
衛生管理者試験と社会保険労務士試験では、出題範囲が重複する部分があります。
重要度の高い労働基準法や労働安全衛生法も重複する範囲です。衛生管理者試験での学びを活かせば、効率的に対策できるでしょう。
衛生管理者と社会保険労務士は、どちらも職場の衛生管理や従業員の健康管理に関わる仕事です。
両方の資格を有していれば、安全対策が特に求められる職場で役立ちますし、企業からも評価されやすくなります。
そのため、人事・労務分野でのキャリアアップに大きく役立つ資格の組み合わせです。
中卒で衛生管理者に向いている人

衛生管理者は、労働者の健康と職場環境を守る大切な役割を担います。特に次のような特徴を持つ人に向いている仕事です。
- 責任感が強い人
- 周囲の状況変化に気づける人
- 人の役に立ちたい人
これらの資質を持つ人は、現場で信頼されやすく、衛生管理者として長く活躍できるでしょう。
①責任感が強い人
労働者の安全や健康を守る役割を担う衛生管理者は、強い責任感を持って行動できる人に向いています。
労災につながる可能性のある問題を発見した場合、会社へ報告するだけでなく、未然に防ぐ方法を考え行動する姿勢が求められます。
自分や仲間の安全を守る環境をつくり出す意識を持ち、困難な状況でも主体的に取り組める人こそ、衛生管理者として活躍できるでしょう。
②周囲の状況変化に気づける人
衛生管理者には、仕事を進めながら労働者の様子や職場環境の変化を素早く察知する力が必要です。
察知した変化の整理と分析をすれば、問題解決の糸口を見つけやすいでしょう。
また、小さな異変や不調に早く気づければ、事故やトラブルを未然に防げます。
変化の察知能力は、業務のなかで日々磨かれるものではあるものの、得意もしくは意識できる人であれば、より活躍できる可能性があります。
周囲を丁寧に観察し、広い視野で状況を判断できる人に向いている職種といえるでしょう。
③人の役に立ちたい人
衛生管理者は、労働者の安全や健康を守るために、職場の衛生環境を整えたり必要に応じて指導を行ったりする、大変重要な役割を担っています。
よって、人の役に立ちたいという思いを持っている人に向いている仕事です。
衛生管理者の取り組みは、従業員一人ひとりの安心や健康を支えるだけでなく、その家族や地域社会全体の安全にもつながっていきます。
人のために尽くすことを誇りに感じながら働ける、やりがいのある職業なのです。
中卒で衛生管理者に向いていない人

衛生管理者は、労働者の安全と健康を守るために積極的な姿勢や柔軟な対応力が求められます。
つまり、次のような特徴を持つ人にはあまり向いていない仕事です。
- 受け身な人
- コミュニケーションが苦手な人
- マルチタスクが苦手な人
これらに当てはまる人は、業務を円滑に進めにくく、問題の早期発見と改善指導が難しくなる可能性があります。
①受け身な人
衛生管理者は労災を未然に防ぐため、危険を察知した際に自ら行動し、積極的に対策を講じる姿勢が求められます。
ときには、現場の問題点を会社に提言したり、改善策を提案したりするといった重要な役割を担う機会も多いです。
そのため、常に指示を待つ受け身な姿勢では、職場の安全を守るという職務に影響が出る可能性があります。
また、受け身な人が「自分から動かなきゃ!」と気負ってしまうと、メンタル面への負担が大きいです。
メンタル面を考慮しても、衛生管理者として活躍するのは難しいかもしれません。
②コミュニケーションが苦手な人
衛生管理者は、労働者と会社の橋渡し役として安全衛生に関する提案や調整を行う重要な存在です。
業務を行うには、周囲と積極的にコミュニケーションを取る力が欠かせません。
労働者の声を吸い上げて会社に伝えたり、産業医と連携して健康管理体制を整えたりするなど、多方面とのやり取りが求められます。
特に相談や報告が滞ると、職場全体の安全管理にも影響が及びかねません。
そのため、コミュニケーションが苦手な方には、不向きといえるでしょう。
③マルチタスクが苦手な人
衛生管理者は、さまざまな業務を同時並行に行う場合が多いです。
衛生管理者としての業務も幅広く、健康診断の実施や職場環境の改善、安全衛生教育など多岐にわたります。
その特性から、同時に複数の業務をこなすマルチタスク能力が欠かせません。
万が一問題が発生すれば責任を問われる立場でもあるので、マルチタスクが苦手な人に向かない部分がある仕事です。
中卒で衛生管理者になるメリット

衛生管理者の資格を取得すると、就職や転職の場面で評価されやすくなり、キャリアの幅を広げやすくなります。
さらに、資格手当や昇給といった待遇面での優遇を受けられる会社もあります。
- 就職・転職で有利になる
- キャリアアップにつながる
- 会社によっては資格手当や昇給がある
これらのメリットを活かせば、長期的に安定したキャリア形成につなげられるでしょう。
①就職・転職で有利になる
衛生管理者は、常時50名以上の労働者がいる事業場では50名ごとに1人の配置が義務付けられており、需要が非常に高い職業です。
衛生管理者の資格は保有者が少ないことから、有資格者というだけで即戦力として評価されやすいのも大きな魅力です。
また、性別や年齢を問わず活かせる資格であり、定年後の再雇用を目指す人からも注目されています。
就職・転職の選択肢を広げ、長期的に安定したキャリアを築くうえで大きな武器になるでしょう。
②キャリアアップにつながる
衛生管理者は、総務部や人事部などへの配属が多く、企業によっては管理職昇進の条件として資格取得を設けるケースもあります。
資格の取得で業務の幅が広がり、労務管理や職場環境の改善に積極的に取り組めるようになるので、社内での評価アップにもつながるでしょう。
特に総務・人事でキャリアアップを目指す人にとっては、有資格者であることが大きな強みとなり、昇進や昇給のチャンスを広げられるメリットがあります。
③会社によっては資格手当や昇給がある
衛生管理者は、労働者50名以上の事業場に配置が義務付けられる需要の高い職業なので、多くの企業で資格手当の対象になる場合が多いです。
資格を持っていると収入アップにつながりやすく、さらに管理職へ昇進できれば、より大きな収入増も期待できます。
衛生管理者の資格取得には受験料や教材費など一定の費用がかかりますが、更新不要で一生使える資格です。長期的に見れば、収入面において大きなプラスとなるでしょう。
中卒で衛生管理者になる注意点

中卒から衛生管理者を目指す場合、資格を取得するまでに乗り越えなければいけないハードルがあります。
受験資格を得るまでの期間や学習時間の確保など、あらかじめ理解しておくことが大切です。
- なるまでに時間がかかる
- 勉強時間の確保が難しい
これらの注意点を踏まえて計画的に取り組めば、資格取得への道を着実に進められるでしょう。
①なるまでに時間がかかる
中卒から衛生管理者を目指す場合、受験資格を得るまでに以下のように長い時間が必要です。
- 10年以上の労働衛生の実務経験を積む
- 高等学校卒業程度認定試験(高認)に合格し、その後3年以上の労働衛生の実務経験を積む
さらに、令和6年度の衛生管理者試験の合格率は第一種で約46.3%、第二種で約49.8%と半数程度にとどまっています。
決して高い合格率とはいえないので、事前に計画を立てて試験勉強を進めないとさらに時間がかかる可能性があります。
参考:公益財団法人安全衛生技術試験協会「統計」(参照 2025-09-17)
②勉強時間の確保が難しい
衛生管理者を目指すには、仕事と並行して試験勉強を進める必要があります。
出題範囲の最も広い第一種の場合、合格に必要な勉強時間は一般的に約100時間とされています。出題範囲が狭まる第二種でも約60時間です。
休日や帰宅後の時間に勉強し、通勤時間に過去問アプリを活用するなどして、毎日少しずつでも勉強する姿勢が求められます。
仕事、プライベート、勉強のバランスを取りつつ、いかに計画的に勉強を進められるかが重要です。
衛生管理者以外のおすすめの仕事

衛生管理者の業務と共通点が多い、安全や人事に関わる仕事、また人のキャリア支援を行う専門職なども、安定して働ける選択肢です。
- 安全管理者
- 人事
- キャリアコンサルタント
自分の興味や強みを踏まえて転職先の選択肢を広げることで、より充実したキャリア形成につなげられるでしょう。
①安全管理者
安全管理者は、職場の設備や作業方法に危険がある場合に応急処置や防止策を講じ、安全装置や保護具の点検を行う専門職です。
建設業や製造業など特定の業種で、労働者が50人以上いる事業場では選任が義務付けられています。
従業員の安全を守る重要な役割を担い、業務内容が衛生管理者と近いため、似たような役割を担う職種に就きたい方におすすめです。
中卒から目指す場合は、産業安全に関する実務経験を7年以上積み、安全管理者選任時研修を受講すればなれます。
②人事
人事部は、採用や労務管理、就業規則の整備などを通じて、会社と従業員の働きやすい環境づくりを支える部署です。
加えて、職場環境や人間関係といった相談窓口を担うケースも多く、労働者の声を直接受け止める重要な役割を果たします。
衛生管理者と同じく従業員の安全や健康に関わる業務をサポートできるので、近い経験を積める点も魅力です。
人事として経験を重ねていけば、ゆくゆくは以下のようなポジションに就ける可能性もあります。
- 人事部門のスペシャリスト:採用に特化したリクルーターのような専門職
- 最高人事責任者(CHRO):経営層から人事戦略を担当する業務
- 管理部門のゼネラリスト:人事・経理・法務などバックオフィス業務全体の管理職
③キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントは、中卒からでも取得可能な国家資格で、個人のキャリア支援や就労相談を行う専門職です。
相談者一人ひとりの適性や状況に合わせ、アドバイスやカウンセリングを通じて職業選択やキャリア形成を支援します。
衛生管理者と同じく、人の生活や働き方を支える点で共通しており、人の役に立ちたいという思いを持つ方に向いています。
今後ますます多様な働き方が広がるなかで、需要も高まっている注目の職業です。
中卒で衛生管理者になるためのおさらい

中卒から衛生管理者になれますが、受験資格を得るまでに長い時間と実務経験が必要です。要点を整理すると以下のとおりです。
- 常時50人以上の事業場で10年以上の実務経験を積む
- または、高卒認定に合格し、3年以上の実務経験を積む
- 第一種・第二種いずれかの衛生管理者試験に合格する
- 試験合格率は約50%前後で、学習には最大100時間程度が必要
このように、中卒から衛生管理者を目指す難易度は高く、長期的な計画と努力が欠かせません。
ただし、一度資格を取得すれば一生使えるので、就職・転職やキャリアアップにも大きく役立ちます。
まずは高卒認定の取得や参考書の確認など、今日からできる準備を始めていきましょう。