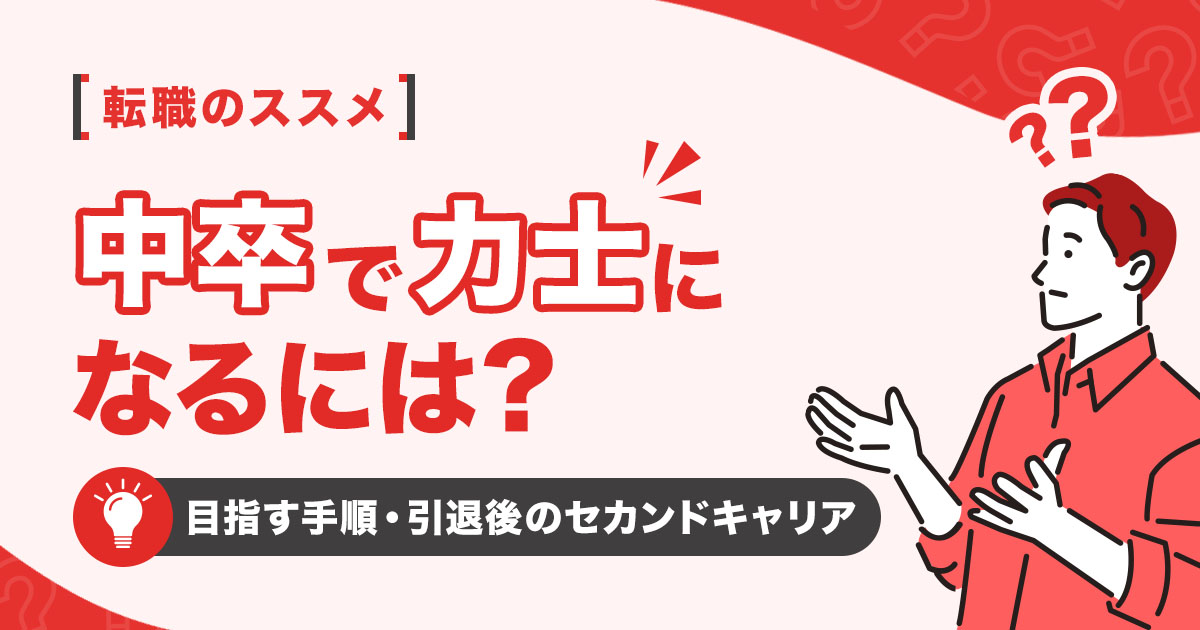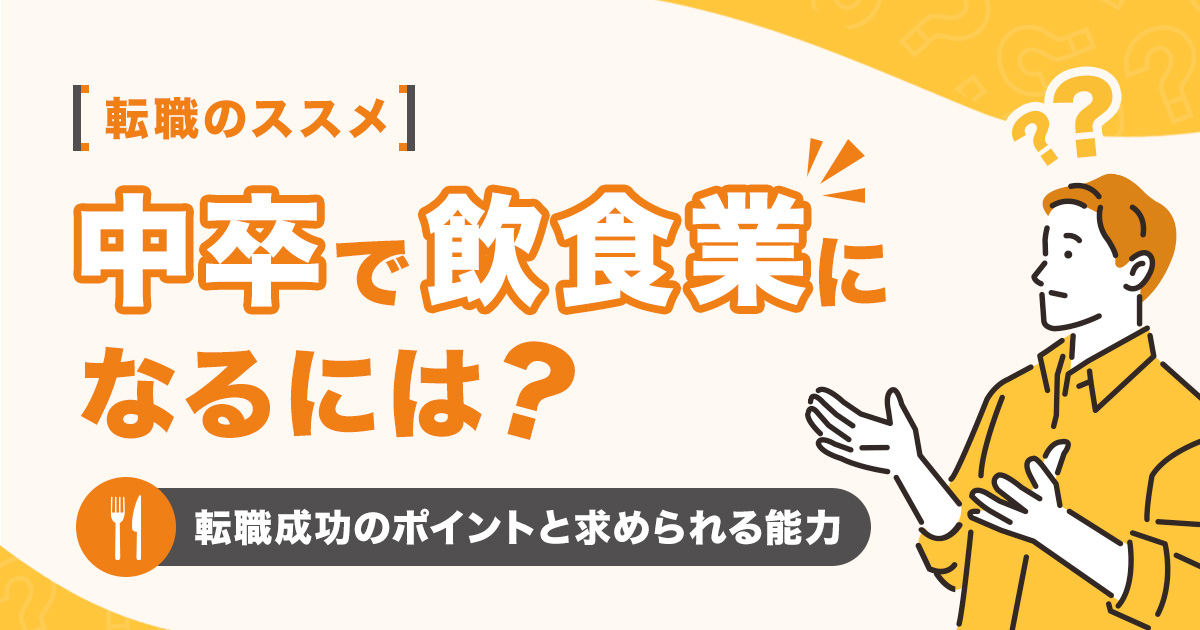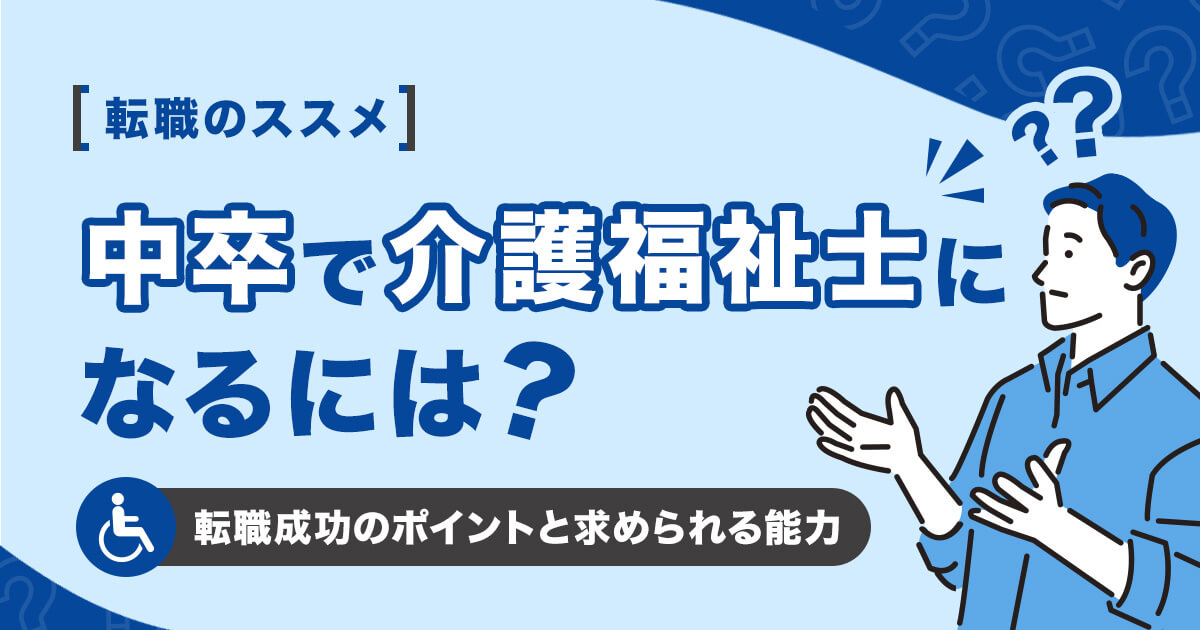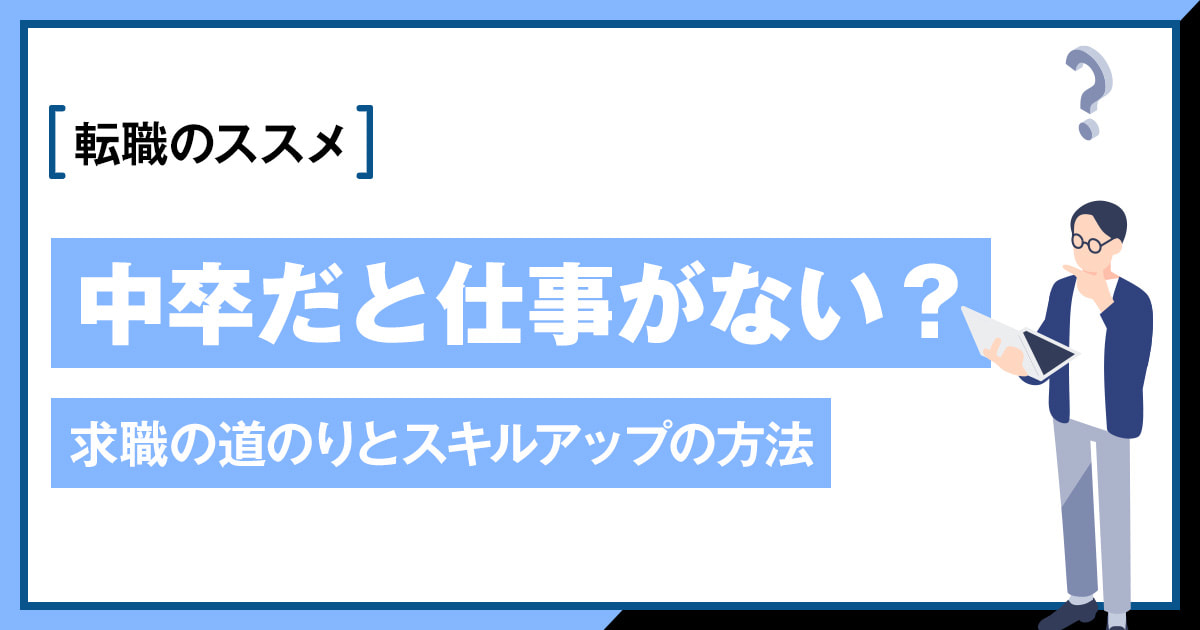-
中卒で力士って目指せるのかな?
-
力士になるには何が必要なのか知りたい
日本の国技として知られる相撲の力士は、実は中卒から目指せる職業です。
本記事では、中卒で力士になる手順や検査対策、力士になった後のセカンドキャリアなどを解説します。
力士に向いている人や向いていない人の特徴、目指す場合の注意点もご紹介しているので、「自分でも目指せるかな?」と迷っている方もぜひ参考にしてみてください。
中卒で力士になれるが学歴以外の条件がある

力士は学歴に関係なく、中卒からでも目指せる職業です。
ただし、力士になるには日本相撲協会が実施する「新弟子検査」に合格する必要があります。
受検資格は次のとおりです。
- 中卒以上(義務教育を修了している)
- 検査受検日時点の満年齢が23歳未満
- 身長167cm以上
- 体重67kg以上
これらの条件を満たしている健康な男性であれば、中学卒業後すぐに新弟子検査を受け、力士になることができます。
また、一定の条件をクリアすれば、基準を満たしていなくても例外的に受検が認められるケースもあります。
【例外】年齢や体格の基準を満たしていなくても受検できる場合もある
年齢や体格の基準に届かなくても、下記の条件に当てはまる場合は受検が可能です。
たとえば、年齢が23歳以上であっても、25歳未満であれば以下の条件を満たすことで新弟子検査を受検できるようになります。
- 日本相撲協会が指定しているアマチュア大会で一定の成績を残している
- 新弟子運動能力検査に合格している
また、身長や体重の基準を満たしてない場合も、25歳未満なら新弟子二次検査の運動能力検査に合格すると、力士になれる可能性があります。
中卒で力士になる手順

ここからは、中卒で力士を目指すための具体的な流れを紹介します。
力士になるまでのステップは次の5つです。
- 入門する部屋を決める
- 師匠を通じて力士検査届を提出する
- 新弟子検査に合格する
- 前相撲を取る
- 相撲教習所に通う
このうち、3つ目の「新弟子検査に合格する」を突破すれば正式に力士として認められます。
ただし、それ以降の「前相撲を取る」と「相撲教習所に通う」という過程も、力士として活躍していくうえで欠かせない大切なステップです。
中卒から力士を目指すなら、この流れを押さえて準備を進めましょう。
手順①入門する部屋を決める
まずは、自分が入門したい相撲部屋を決めましょう。
相撲部屋は全部で45部屋あります。
以下のサイトから、各部屋の年寄(親方)や所属力士の人数、実績などを確認できます。
入門後はその部屋で共同生活をしながら稽古をすることになるため、部屋選びはとても重要です。
多くの部屋では「見学」や「体験入門」ができるので、実際の雰囲気を体感してから決めるのがおすすめです。
入門したい部屋を決めたら、保護者同伴で面談を行い、その後に入門手続きへと進みます。
手順②師匠を通じて力士検査届を提出する
入門が決まったら、次は相撲部屋の師匠(年寄・親方)を通じて日本相撲協会に「新弟子検査」を申し込みます。
このとき、「力士検査届」とあわせて、以下の書類を提出する必要があります。
- 親権者の承諾書
- 本人の意思確認書
- 戸籍謄本、または戸籍抄本
- 医師が発行した健康診断書
書類はすべて日本相撲協会の規定に沿って準備する必要があります。
保護者と相談しながら、漏れのないように慎重に進めましょう。
そして、書類内容に問題がなければ新弟子検査へと進むことができます。
手順③新弟子検査に合格する
新弟子検査は年に6回、各本場所初日の数日前に実施されます。
ちなみに、受検資格を満たしていれば、何度でも受検が可能です。
検査の内容は下記の2種類に分けられます。
- 体格検査
- 内臓検査
体格検査では、身長167cm以上・体重67kg以上が基本条件です。
ただし、三月場所の新弟子検査に限り、身長165cm以上、体重65kg以上の中学校卒業見込みの中学生も受検可能です。
また、体格基準を満たしていなくても、新弟子運動能力検査に合格すれば問題はありません。
内臓検査の検査項目は健康診断、心電図、エコー検査の3つで、健康面に異常がないかを確認します。
新弟子検査に合格すると、力士として登録され、晴れて力士の仲間入りとなります。
手順④前相撲を取る
新弟子検査に合格したあとは、「前相撲(まえずもう)」を取ります。
- 前相撲とは?
- まだ番付に載っていない力士が取る相撲。
新弟子にとってのいわゆるデビュー戦(初土俵)です。
前相撲は本場所の3日目(3月場所の場合は2日目)から始まり、勝ち抜き方式で行われます。3勝した力士から勝ち抜けていき、対戦者がいなくなるまで連日取り組みが続きます。
成績に関わらず、前相撲を取った力士は次の場所から「序ノ口力士」として番付に名前が載り、四股名を授与されます。
ここまでくれば、名実ともに力士としての第一歩を踏み出したことになります。
手順⑤相撲教習所に通う
前相撲を終えると、次は「相撲教習所」で半年間の研修を受けます。
相撲教習所は日本相撲協会が運営する教育機関で、相撲に必要な知識や教養を学ぶ場所です。
この期間は、相撲部屋での厳しい稽古と並行しながら、精神面・体力面の基礎を固めていきます。
カリキュラムは実技と座学の2本立てで、次のような内容が含まれます。
- 四股やてっぽうなどの基本動作
- 相撲の歴史や礼儀作法
- 一般常識や書道
- 運動医学やケガ予防の知識
座学は曜日ごとにテーマが変わり、力士としての総合的な人間力を養う場でもあります。
なお、外国出身の力士の場合は1年間通い、日本語や日本文化、生活マナーなどを重点的に学ぶ必要があります。
こうして全課程を修了すれば、力士としてスタートラインに立つことができます。
中卒で力士になるための検査対策

力士志望者の最初の関門となるのが新弟子検査です。ここでは、新弟子検査に合格するための対策方法を3つご紹介します。
- 身長を伸ばす努力を行う
- 体重を増やす努力を行う
- 運動神経を向上させる
今のうちからしっかり対策を行っておきましょう。
①身長を伸ばす努力を行う
新弟子検査の体格検査のうち身長の合格基準は、167cm以上(中学校卒業見込みの場合は165cm以上)です。
基準に届かない場合は、できる限り身長を伸ばすための生活習慣を整えましょう。
身長を伸ばすには、「栄養バランスの整った食事」や「良質な睡眠」「適度な運動」が欠かせません。
特に食事面では、次のポイントを意識すると効果的です。
- 1日3食しっかり食べる
- 肉や魚などの動物性たんぱく質と、大豆製品などの植物性たんぱく質をバランス良く摂る
- 牛乳やヨーグルト、小魚、海藻類などからカルシウムを摂る
- 赤身の肉やレバー、貝類などから鉄分を摂る
- 魚やキノコ類からビタミンDを摂る
- 夕食後は3時間以上空けてから就寝する
さらに、正しい姿勢を意識したり、ストレスを溜めない生活習慣を心がけたりすることも、体の成長において重要なポイントです。
参考:池尻大橋せらクリニック「身長を伸ばすための「食べ方」とは?」(参照 2025-10-14)
②体重を増やす努力を行う
新弟子検査の体格検査のうち体重の合格基準は、67kg以上(中学校卒業見込みの場合は65kg以上)です。
もし体重が足りない場合は、健康的に体を大きくするための食事とトレーニングを意識しましょう。
体重を増やすには、1日の総摂取カロリーを増やした食事や、運動や筋トレによる筋肉量アップが欠かせません。
体重を増やすポイントは次のとおりです。
- 1回あたりの食事量を少しずつ増やす
- 高カロリーで栄養価の高い食材を取り入れる
- 揚げ物やいため物など油を使った調理法を活用する
- たんぱく質・糖質・脂質をバランス良く摂取する
効率良く体重を増やすには、「摂取カロリー > 消費カロリー」にすることが重要です。
1日の摂取カロリーを消費量よりも300〜500kcalほど多くすることで、無理なく体重を増やせます。
参考:天神駅前まめクリニックコラム「ガリガリ体型を卒業!健康的に太る方法【食事・筋トレ・生活習慣】」(参照 2025-10-14)
③運動神経を向上させる
身長や体重の基準に届かなくても、「運動能力検査」に合格すれば新弟子検査を受けることができます。
運動能力検査に合格するためには、日頃から運動神経を鍛えておくことが重要です。
運動能力検査は以下の7種目で構成されています。
- 握力
- 背筋力
- 反復横跳び
- ハンドボール投げ
- 立ち幅跳び
- 上体起こし
- 50m走
これらの種目に対応できるように、筋トレやストレッチ、反射神経を鍛えるトレーニングなどをバランス良く取り入れましょう。
自分だけで練習メニューを組むのが難しい場合は、スポーツジムでプロの指導を受けるのも効果的です。
中卒で力士になった後のキャリアプラン

力士としてキャリアを積んで収入を上げるためには、「勝ち続けて上位の階級へ昇進すること」が重要です。
また、力士の階級と報酬の違いは以下の通りです。
| 階級 | 年額給与 |
|---|---|
| 横綱 | 3,600万円 |
| 大関 | 3,000万円 |
| 関脇・小結 | 2,160万円 |
| 前頭 | 1,680万円 |
| 十両 | 1,320万円 |
| 幕下 | 99万円 |
| 三段目 | 66万円 |
| 序二段 | 52.8万円 |
| 序ノ口 | 46.2万円 |
幕下より上の階級は「幕内」と呼ばれ、6段階に細分化されます。
上記の年額給与にくわえて、賞与や手当、成績に応じてもらえる力士褒賞金なども支給されるため、実際の総額はさらに高くなります。
2025年8月現在、全力士は合計615人いますが、十両以上は70人のみで、非常に狭き門です。一方、もっとも多い階級は212人いる序二段です。
上位の階級を目指すためには、日々の稽古を積み重ねて力や技術を磨き続けなければいけません。
中卒で力士になった後のセカンドキャリア

中卒で力士になった後は、主に次のようなセカンドキャリアがあります。
- 年寄(親方になる)
- 若者頭(わかいものがしら)になる
- 世話人(せわにん)になる
- マネージャー・コーチになる
- 飲食店で働く
- 介護職として働く
- 整体師として働く
力士の経験や知識を活かして、さまざまな場所で活躍できます。
これからご紹介するセカンドキャリアを念頭に置いたうえで将来のキャリア設計をしていきましょう。
①年寄(親方)になる
現役を引退した後は、年寄(親方)として、後進を育てる道に進む人もいます。
年寄(親方)は、日本相撲協会の構成員として、力士の指導や監督、相撲部屋の運営を行う重要な役職です。
親方になるためには日本国籍を有していることに加え、以下のような条件を満たす必要があります。
- 幕内力士として通算20場所以上の出場
- 十両以上として通算30場所以上の出場
すでに存在している相撲部屋の継承者として協会に承認されれば、基準は上記よりも少しゆるくなります。
一方、部屋を自分で開く場合は条件がさらに厳しくなるため、年寄(親方)を目指すハードルは高めといえるでしょう。
②若者頭(わかいものがしら)になる
引退後の選択肢として、「若者頭(わかいものがしら)」になる道もあります。
若者頭は、幕下以下の若手力士を指導・育成し、取組の進行を補助する立場です。
本場所では花道付近で進行を見守り、土俵まわりのトラブルに即対応できるよう待機するなど、裏方として非常に重要な役割を担っています。
若者頭になれるのは、現役を引退して年寄名跡を取得できなかった十両・幕下力士が対象です。
ただし定員はわずか8名と決まっており、空きが出ない限り新たに就任することはできません。
そのため、非常に狭き門で、タイミングと実力に恵まれなければなれない職業です。
③世話人(せわにん)になる
引退後の選択肢として、「世話人(せわにん)」になる道もあります。
世話人は、相撲競技用具の運搬や管理、観客の案内、会場運営の補助などを行う、縁の下の力持ちのような存在です。
派手さはありませんが、相撲界を支えるうえで欠かせない重要な職務です。
世話人になれるのは若者頭と同じく、現役を引退して年寄名跡を取得できなかった十両・幕下力士が対象です。定員はわずか13名で、空きが出ない限り就任はできず、非常に狭き門です。
ただし、タイミングによっては就任のチャンスが巡ってくる可能性もあります。
④マネージャー・コーチになる
年寄(親方)になるのはハードルが高く、若者頭や世話人は定員が少ないため、いずれも非常に狭き門です。他の職業で相撲業界に携わり続けたい場合は、マネージャーやコーチとして働く道もあります。
仕事内容は若者頭と似ており、力士の育成や技術指導、メンタルケアなどが主です。多くの場合、各相撲部屋が直接雇用する形で働くことになります。
力士が最高のパフォーマンスを発揮できるように支える重要な役割を担うポジションであり、やりがいを感じられる仕事といえるでしょう。
⑤飲食店で働く
力士のセカンドキャリアとして人気が高いのが飲食業です。
相撲部屋では、主に幕下以下の力士が当番制で料理を作ります。この担当を「ちゃんこ番」と呼び、力士が日常的に食べる料理を総称して「ちゃんこ」と呼びます。
現役時代に身につけた調理技術を活かし、引退後にちゃんこ料理店を開業したり、飲食店で働いたりする元力士は少なくありません。
特に相撲の聖地である東京の両国駅周辺には、元力士が経営するちゃんこ料理店が軒を連ねています。
このように、飲食業は現役時代の経験をそのまま仕事に活かせるため、力士にとって挑戦しやすいセカンドキャリアといえるでしょう。
⑥介護職として働く
引退後に介護職に就く元力士も少なくありません。
力士は現役時代、上位力士の付き人として身の回りのお世話をしたり、幅広い年齢層の力士や年寄(親方)たちと共同生活を送ったりするため、自然と気遣いやコミュニケーション能力が磨かれます。
こうした経験は、介護職で高齢者と接する際に大いに活かせる強みとなります。
実際、元力士が経営しているデイサービスも存在し、相撲が好きな利用者から喜ばれることも多く、介護中も話題に困らず、スムーズな関係を築きやすい点もメリットです。
また、力士ならではの知識を活かし、運動プログラムに相撲の動きを取り入れているところもあるようです。このように、介護職は現役時代の経験を直接活かせるセカンドキャリアとして有力でしょう。
⑦整体師として働く
力士のセカンドキャリアとして、整体師を目指す人もいます。
現役時代に激しい稽古や取り組みでケガや慢性的な痛みに悩んだ経験から「同じように悩む人を助けたい」という思いを持つ人が多いのです。実際に自分がケアを受けた経験は、施術を行う際の大きな強みとなります。
整体師になるには、引退後に専門学校に通い、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格を取得するのが一般的な流れです。
現役時代に通っていた整体の良い点や効果があった施術方法などを取り入れてみると、現役時代の経験を効果的に活かせるかもしれません。
中卒で力士に向いている人

中卒で力士を目指す場合、次のような特徴がある人は力士に向いているといえます。
- 相撲が好きな人
- 継続的に努力ができる人
- 運動神経が良い人
ここでは上記3つの特徴について、詳しく解説します。自分に適性があるかを判断するための参考にしてみてください。
①相撲が好きな人
力士を目指すうえでまず何よりも重要なのは、相撲が好きであることです。
力士は日々厳しい稽古をする必要がありますが、あまりの厳しさから途中で逃げ出してしまう力士も少なくありません。そのため、相撲への情熱がなければ続けるのは難しいでしょう。
また、力士として上位の階級を目指すには、強い覚悟が必要です。勝ち続けなければ昇進できず、挫折を味わうことも多い世界です。
よって、相撲が好きで「強くなりたい」「上を目指したい」という強い気持ちを持続できる人は、力士に向いています。
②継続的に努力ができる人
力士が階級を上げるには、真剣に稽古に取り組み続けなければいけません。
厳しい稽古は横綱になっても続き、体力維持や技術向上のために努力し続けることが必要です。特にきついといわれる稽古の「ぶつかり稽古」は、全身を使った激しいぶつかり合いにより、心身ともに大きな負荷がかかります。
また、力士は体を大きくすることも重要で、日々体づくりに向き合う覚悟が求められます。
稽古も食事も努力を惜しまず、毎日コツコツと継続できる人は力士に向いているでしょう。
③運動神経が良い人
力士はアスリートなので、高い運動神経が求められます。
たとえ新弟子検査の体格基準を満たしていなくても、運動能力検査に合格すれば力士になれるのは、運動神経の重要性が理由といえるでしょう。
力士が土俵で勝ち抜くには、単に力が強いだけでなく、俊敏さや体感などを兼ね備えていることが不可欠です。実際、力士たちは巨体でありながら、持ち前の運動神経のおかげで素早く動ける人が多いです。
そのため、運動神経が良い人は、力士として活躍できる素質が高いです。
中卒で力士に向いていない人

力士は日々の稽古をこなすだけでなく、相撲部屋での共同生活を送る必要があるので、以下のような人は向いていない可能性が高いです。
- 集団生活が苦手な人
- 上下関係が嫌いな人
- 制限のある生活が苦手な人
ミスマッチを防ぐためにも、しっかり確認しておきましょう。
①集団生活が苦手な人
力士になると、相撲部屋での共同生活が始まります。
幕下以下の力士には個室がなく、他の力士と同じ大部屋で過ごすことになります。稽古や取り組みの間だけでなく、日常生活においても他の力士や相撲部屋関係者と暮らす必要があるため、気遣いや協調性が必要です。
また、一般的な社会人と比べて一人になれる時間も限られており、プライベートな空間を十分に確保するのは難しいといえます。そのため、集団生活が苦手な人や自分の時間を大切にしたい人には不向きでしょう。
②上下関係が嫌いな人
力士の世界では、番付によって上下関係が厳格に決まっており、上の階級の力士に対する身の回りのお世話も仕事の1つです。
特に幕下以下の力士は、お風呂で関取力士の背中を流したり、関取力士よりも起床時間や稽古時間が早かったりというように、階級ごとに役割や待遇が大きく異なります。
こうした厳しい上下関係に抵抗がある人や、自由な環境で働きたい人には不向きといえるでしょう。
③制限のある生活が苦手な人
力士は毎日決められたスケジュールに沿って行動します。夜には自由時間もあり外出もできますが、門限を守る必要があります。
また、休日であっても、稽古がある日と同様に料理当番や掃除などの役割を果たさなければならず、完全に自由に過ごすことは難しいのが現実です。
厳しい規律や制限の多い生活を送る必要があるので、縛られる生活が苦手な人には続けることが難しいといえます。
中卒で力士になるメリット
力士として活躍できるようになるまでには努力と長い道のりが必要ですが、以下のような力士ならではのメリットもあります。
- 早くから相撲漬けの生活を送れる
- 長期的にキャリアを積める
- 早期からプロに指導をしてもらえる
- 学歴による給料の差がない
ここでは、上記4つの中卒で力士になるメリットについて解説します。
①早くから相撲漬けの生活を送れる
中学卒業後、すぐに力士になれれば、早くから相撲漬けの生活を送れるメリットがあります。
高卒や大卒の人が学校に通っている期間も相撲に全力で打ち込むことができるため、相撲に集中できる時間的が長いというアドバンテージは見逃せません。
歴代の横綱は最終学歴が中卒の方が多い点からも、早くから力士として相撲漬けの生活を送れるのは、メリットといえるでしょう。
②長期的にキャリアを積める
早くから力士になることで、長期的にキャリアを積める可能性が高い点もメリットです。
大相撲を引退する年齢はおおむね30歳前後といわれており、他のスポーツと比べても若いうちに引退する傾向があります。
そのため、中卒で入門した方が高卒や大卒よりも現役期間が長くなり、順調に勝ち進めば早い段階で上位階級に昇進でき、長期的に力士としてのキャリアを積めるチャンスがあるといえます。
③早期からプロに指導をしてもらえる
中卒で入門すれば、早くからプロの指導を受けられるメリットがあります。
プロから指導を受けると、相撲の基礎からしっかり学べて技術や知識を正しく身につけられるため、自己流のクセがつきにくいです。
また、プロの指導は、力士本人の個性や特性などを生かした稽古、指導などを行ってくれます。
後から自分のクセを直すのは大変なので、早期から年寄(親方)に指導してもらうことによって、力士としての能力を効率的に伸ばせます。
④学歴による給料の差がない
一般的な企業で働く会社員は、学歴による給料の差が大きく、高卒や大卒に比べて中卒は給料が低い傾向にあります。
一方、力士の世界は完全に実力社会であり、自身の階級や成績によって報酬が決まります。
十両以上の階級になれば、学歴に関係なく年額1,000万円を超えることも夢ではありません。実力次第で高収入を得られる可能性があるのは、中卒で力士になる大きなメリットといえるでしょう。
中卒で力士になる注意点
中卒で力士になると早くからプロの指導を受けられ、長くキャリアを積めるというメリットがあります。
しかし、中卒で力士になる場合には、以下のような注意点があることも把握しておきましょう。
- 力士として成功できる可能性が低い
- セカンドキャリアのハードルが高い
それぞれの注意点について詳しく解説します。
①力士として成功できる可能性が低い
中卒で力士になれたとしても、必ずしも成功できるとは限りません。
2025年8月現在で、全力士615人のうち十両以上は70人と限られており、思ったように昇進できないまま相撲界を去る力士もたくさんいます。
報酬面は、十両以上と幕下以下で大きな開きがあります。十両以上になれば学歴に関係なく年収1,000万円以上も可能ですが、現実的には非常に狭き門です。
力士になるための間口は広いですが、実際に力士として成功できる可能性は低い点に注意しましょう。
②セカンドキャリアのハードルが高い
先述したように、力士の平均引退年齢は30歳前後といわれているため、引退後のセカンドキャリアをしっかり考える必要があります。
中には、ケガや成績不振によって30歳よりも早い段階で引退する力士もいます。選手生命が短いという点は力士になるデメリットといえるでしょう。
特に中卒で力士になった場合、引退後は相撲以外の経験やスキルがない状態で転職活動を始めることになります。
一般企業への就職を目指す際は、中卒だとキャリアの幅が狭まりやすく、不利になりやすい点には注意が必要です。
力士のセカンドキャリアを推進・支援する協会や会社もありますが、スムーズに転職するには自身の努力が重要になるため、力士として成功するための努力と平行して、引退後の将来も見据えることも重要です。
力士以外のおすすめの仕事

力士に興味はあるものの、さまざまな理由で目指すのは難しいと感じてしまっている方もいるでしょう。
力士以外で相撲界に関わる他の仕事にも目を向けたいと考えている場合は、次のような仕事がおすすめです。
- 床山(とこやま)
- 行司(ぎょうじ)
- 呼出(よびだし)
なお、上記3つの仕事は相撲界の裏方として働けますが、公募はなく、基本的に相撲部屋に所属して親方の許可を得る必要があります。
それぞれの仕事について、詳しく解説します。
①床山(とこやま)
床山は力士の髷(まげ)を結う専門職です。
日本相撲協会が採用を行っており、義務教育を修了した満19歳までの男性であれば応募できます。
定員は50名で、自主退職しない限り定年65歳までの終身雇用になる安定性のある職業です。
また、床山は勤続年数や成績に応じて「特等」から「五等」まで6つの等級があり、階級ごとに給料が異なります。特等の床山に昇進すれば、月給36万円~40万円程度が支給されます。
②行司(ぎょうじ)
行司は大相撲の進行管理と勝負の判定を担当する職業です。
そのほか、番付の作成や場内アナウンスなども行い、仕事内容は多岐にわたります。
行司も日本相撲協会によって採用され、応募条件は義務教育を修了した満15歳以上満19歳以下の男性です。
定員は45名で、自主退職しない限り定年65歳までの終身雇用となります。
行司には、「序ノ口格」から「立行司格式式守伊之助/立行司格式木村庄之助」まで8つの階級があり、階級によって服装や給料が異なります。
判定や勤務態度、声量などが昇進に影響し、力士の土俵を公正に支える責任ある職業です。
③呼出(よびだし)
呼出は、大相撲の取組で力士の呼び上げや土俵の整備、太鼓打ちなどを担当する職業です。
競技の進行を円滑にする重要な役割を担っています。
定員は45名で、義務教育を修了した満19歳未満までの男性であれば応募可能です。
日本相撲協会によって採用され、定年65歳の終身雇用となります。
呼出にも「序ノ口呼出」から「立呼出」まで9つの階級があり、勤続年数や実績に応じて給料が変動します。
中卒で力士になるためのおさらい

力士は新弟子検査に合格すれば学歴を問わずなれるため、中卒から夢を追うことは十分可能です。中卒で入門すると、早期からプロの指導を受けながら必要な技術や知識を効率良く身につけられるのも大きなメリットでしょう。
努力を重ねて地道に勝ち進めば、学歴に関係なく高収入を得るチャンスも広がります。
とはいえ、厳しい稽古に耐え、成功できる人は一握りです。また、力士は30歳前後で引退するケースが多く、中卒の場合はセカンドキャリアの選択肢が限られる点も覚悟しておく必要があります。
力士を目指したいと考えている方は、本記事の内容を参考にしながら、力士になる準備を始めてみましょう。