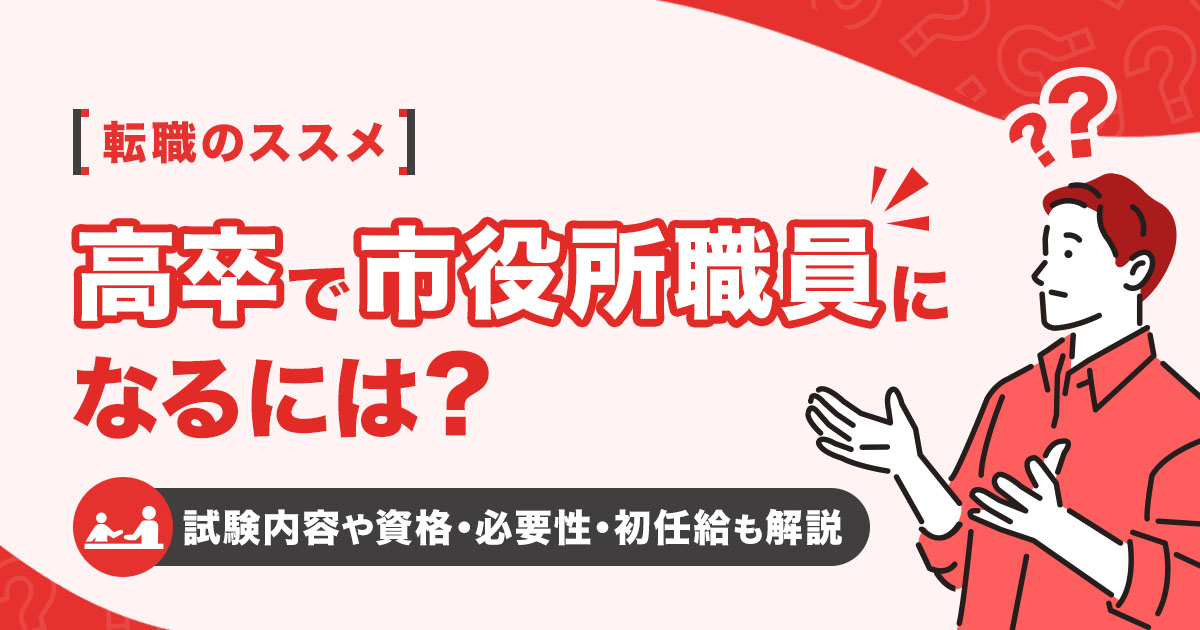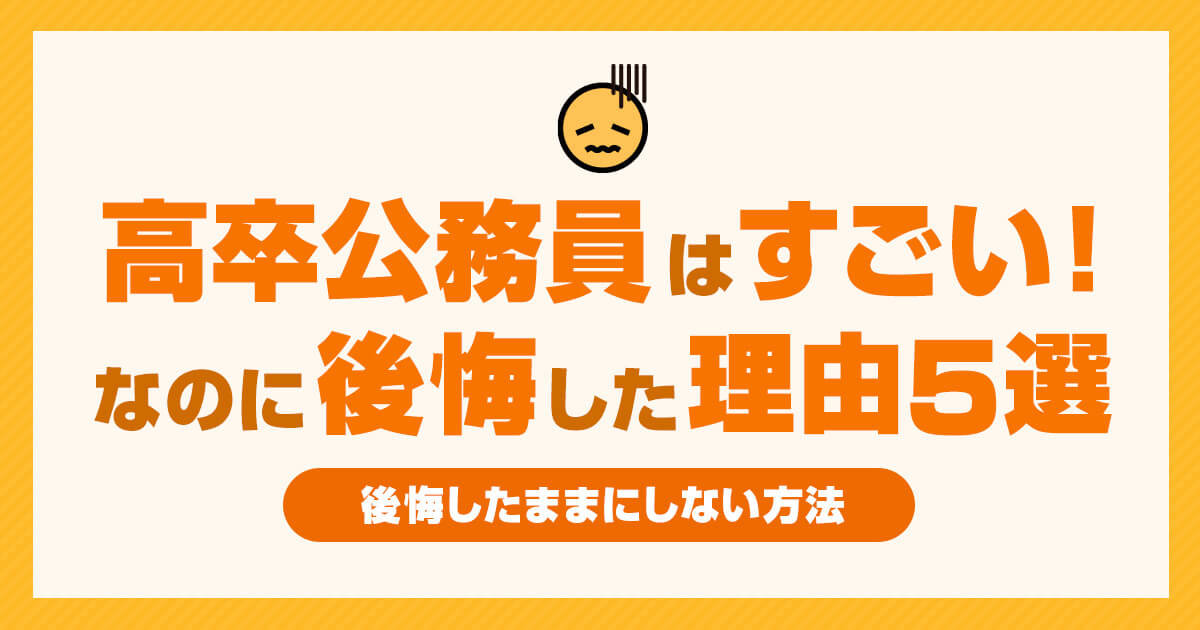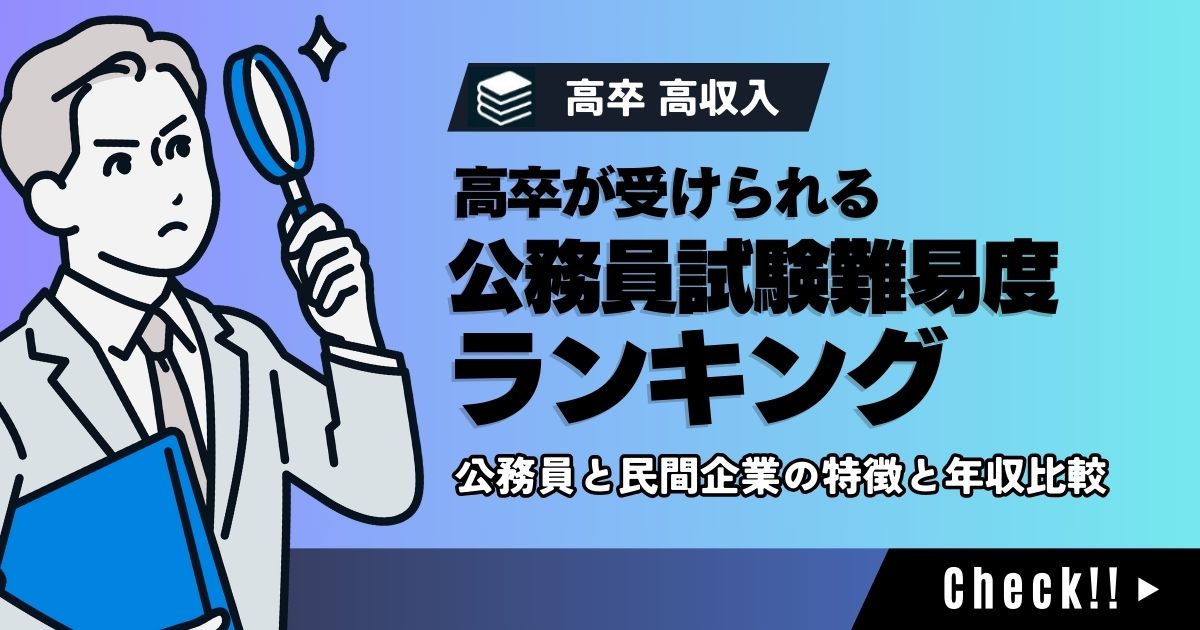-
高卒で市役所職員になるにはどうすればいい?
-
高卒者が市役所で働くメリットやデメリットを知りたい
高卒が市役所で働くには具体的に何をすればいいのかと、気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、高卒で市役所職員になる手順や公務員試験の対策方法、市役所で働くのに向いている人・向いていない人の特徴などを解説します。
高卒で市役所職員になって安定した雇用や収入を得たいと考えている方は必見です!
高卒で市役所職員になるには公務員試験に合格する必要がある

市役所職員は、地方公務員試験を受験して合格すれば、高卒もなれる職業です。
自治体によって詳細や名称は異なるものの、地方公務員試験の多くは「初級」「中級」「上級」といった区分があります。
それぞれ求められる学力レベルが異なり、初級は高卒程度、中級は短大卒程度、上級は大卒程度です。高卒は「地方初級公務員試験」を受験するのが一般的です。
なお、市役所職員の仕事は大きく分けて「技術職」「事務職」があり、職種によって試験の科目や受験資格が異なります。技術職は前職での経験や大卒以上の学歴を求められるケースが多いので、高卒者が目指しやすいのは事務職です。
そのため、本記事では事務職として市役所で働くことを前提にしています。
市役所職員になる基本条件
高卒が市役所職員になるには、地方公務員試験の合格が必須です。
高卒の場合は、高卒程度の学力があれば合格可能な「地方初級公務員試験」を受ける人が大半ですが、大卒程度の学力を身に付ければ「地方上級公務員試験」を受験することもできます。
地方初級公務員試験には、応募要件として年齢制限が設けられている点に注意が必要です。多くの自治体では、18~21歳が受験できる年齢となっています。
とはいえ、近年は年齢制限を緩和する動きもあり、年齢上限が高い自治体も増えてきました。21歳以上でも応募可能としている自治体もあるので、まずは志望する市役所の採用試験概要をチェックしてみましょう。
欠格事由に該当すると受験できない点に注意
地方公務員法では、犯罪歴や懲戒処分、特定の政党・団体への加入歴がある人は地方公務員になれないという欠格事由がいくつか定められています。
具体的には、以下の欠格事由に該当している人は、公務員試験を受験できないので注意しましょう。
- 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
市役所職員の学歴内訳
ここでは、神奈川県川崎市が公表したデータから、市役所職員の学歴内訳をご紹介します。
令和5年の神奈川県川崎市の市役所職員における学歴内訳は以下の通りです。
| 学歴 | 人数 |
|---|---|
| 中卒 | 88名 |
| 高卒 | 1,892名 |
| 短大卒 | 2,255名 |
| 大卒 | 14,414名 |
参考:川崎市公式ウェブサイト「令和5年川崎市職員の人事に関する統計報告」(参照 2025-05-07)
最も多い最終学歴は大卒であり、全体の約80%を占めています。そこから短大卒、高卒、中卒という順に職員の人数も減少しているので、高卒で市役所職員を目指すのは狭き門であることがうかがえます。
一方で、学歴が求められる他の職業では、大卒や専門学校卒の従業員のみで構成され、高卒・中卒は0名というケースも珍しくありません。
それを踏まえると、市役所職員は学歴重視の傾向が低く、高卒も活躍しやすい職業だと言えます。
高卒で市役所職員になる手順

地方公務員試験は、実施日が4つに分けられています。日程の早い順からA日程、B日程、C日程、D日程と呼び、日程によって試験の出題分野や難易度が変わる仕組みです。
そして、高卒区分にあたる地方初級公務員試験は、全国的に最も多くの市が9月下旬の「C日程」で実施しています。
そのため、ここではC日程の試験を前提に、高卒で市役所職員になる下記の手順を詳しく解説します。
- 希望する自治体に出願する
- 地方初級(C日程)の第一次試験に合格する
- 地方初級(C日程)の第二次試験に合格する
①希望する自治体に出願する
地方初級公務員試験を受験するには、事前に出願を行う必要があります。ほとんどの自治体でインターネット受付となっており、パソコン・スマートフォンから申し込めます。
たとえばC日程の場合、5~8月頃に各自治体のホームページで受験案内が公表され、7~8月頃から受験申し込みの受付開始となるケースが多いです。
なお、出願と同時にエントリーシートの提出を必須としている自治体が一般的なので、出願時期を迎える前から準備をしておきましょう。フォーマットは自治体によって異なりますが、主に志望動機や自己PRなどを記載します。
②地方初級(C日程)の第一次試験に合格する
地方初級公務員試験の第一次試験の内容は筆記試験で、主に「教養試験」と「作文試験」です。また、自治体によっては論文問題が出題される場合もあります。
教養試験の出題科目は、時事、社会、人文、自然に関する知識を問う「一般知識」と、数的処理、文章理解に関する能力を問う「一般知能」、そして「時事問題」があり、試験範囲は以下の通りです。
| 科目 | 範囲 |
|---|---|
| 社会 | 国際、経済、政治、社会、法律 |
| 人文 | 歴史(日本史・世界史)、地理、文学、芸術、思想 |
| 自然 | 化学、物理、生物、地学、数学 |
| 数的処理 | 図形を含む判断推理、数的推理、資料解釈 |
| 文章理解 | 現代文読解、英文読解 |
教養試験の回答時間は120分で、一般知識と一般知能から各20題ずつ、合計40題出題されます。回答形式は、5つの選択肢の中から正解を選ぶ五肢択一式です。
また、自治体によっては「適性検査」が行われる場合もあるので、志望する自治体の受験案内を確認しておきましょう。
③地方初級(C日程)の第二次試験に合格する
第二次試験は、主に人柄や対人能力などが見られる「人物試験」が行われます。
内容は各自治体によって異なりますが、多くの自治体で実施されているのが個別面接です。個別面接では、応募者の人物像から、公務員としての適性があるかを判断されます。
また、面接に加えて集団討論、適性検査などが行われるケースも多いです。
ちなみに、第二次試験に合格したからといって、すぐに市役所職員になれるわけではないので注意しましょう。
合格後は、最終合格者を対象に個別面談が実施され、意思確認が行われます。この最終の個別面談は「採用面接」とも呼ばれ、ここで意思表示して正式な内定者となれば市役所職員として働けるのです。
高卒で市役所職員になるための試験対策

高卒区分である地方初級公務員試験は、大卒区分の試験に比べると難易度が低いと言われていますが、採用者数は大卒区分の試験よりも少なく設定されています。
つまり、試験の難易度は大卒区分より低くても競争倍率は高くなりやすいため、高卒で市役所職員になるには、徹底した試験対策を行わなくてはいけません。
ここでは、C日程の試験を受験する想定で、地方初級公務員試験の対策方法を解説します。
対策①志望動機、自己PR、ガクチカを重点的に対策する
試験対策は、出願する前から始めておくのがおすすめです。受験案内がまだ公表されていない時期であっても、志望動機、自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の3つは、重点的に対策しておきましょう。
上記3つの項目は、出願時に提出するエントリーシートでよく質問されます。早い段階から対策しておけば、受験案内公表後に慌てずに済み、完成度の高いエントリーシートを提出できます。
出願時にエントリーシートの提出が不要な自治体もありますが、志望動機、自己PR、ガクチカは第二次試験の個別面接で聞かれる可能性が高いです。
自己分析をしてこれらの答えを洗い出しておくと、仮にエントリーシートがなかったとしても面接対策として役に立つでしょう。
対策②第一次試験と第二次試験の採点比率をチェックする
志望する自治体が第一次試験と第二次試験のどちらを重視しているのかについても、前もって確認しておきましょう。
どちらの結果をより重視するかは自治体によって異なるため、試験対策方法を考える際は志望している自治体の試験傾向に合わせる必要があります。
自治体の試験傾向は、各試験の倍率を他の自治体と比較するとわかりやすいです。例として、A市とB市を比較すると下記のようになります。
| 受験者数 | 第一次試験合格者数 | 第二次試験合格者数 (=最終合格者数) | |
|---|---|---|---|
| A市 | 1,000 | 100 | 50 |
| B市 | 1,000 | 500 | 50 |
A市は、第一次試験の倍率が10倍、第二次試験の倍率が2倍で、筆記試験を重視する傾向が強いと考えられます。対するB市は、第一次試験の倍率が2倍、第二次試験の倍率が10倍になっており、人物試験を重視していると言えるでしょう。
効率よく試験対策するためにも、志望している自治体の試験の比重は必ずチェックしておくことをおすすめします。
対策③出題数が多い科目から勉強を始める
第一次試験は科目数や出題範囲が膨大なので、対策に時間がかかる出題数が多い科目から優先して勉強を始めましょう。
「数的処理」「文章理解」「時事問題」は、筆記試験の中で出題割合が大きい傾向にあります。
特に数的処理は、他の公務員試験と比べて問題の難易度が低めな傾向にあるので、確実に点数につなげられるようしっかり対策しましょう。また、時事問題は日頃からこまめにニュースをチェックしておく必要があります。
全科目を完璧に仕上げようとすると、時間が足りず他の対策が疎かになってしまう可能性が高いです。合格ラインである7割以上の得点を意識して、効率的な学習計画を立てるのがポイントと言えます。
対策④自治体の課題にアンテナを張る
第一次試験では、作文・論文試験も課されるのが一般的です。これらの試験では、人口減少やインフラの老朽化、環境問題など、各自治体が抱える課題がよくテーマに取り上げられます。
作文・論文試験の難易度は教養試験に比べると低いと言われていますが、自治体の課題を把握していないと答えるのが難しいテーマが多いです。
日常的に自治体の課題にアンテナを張り、情報収集しましょう。課題をリサーチするには、こまめに自治体のホームページを確認するのがおすすめです。
また、見本の答案例や自治体の総合計画などで用いられている表現を参考にして、文章の書き方を学ぶのも有効な対策方法です。自分の論文を他人に読んでもらい、添削を受けるという手もあります。
対策⑤面接対策を徹底する
第二次試験の面接対策は、特に力を入れて行いましょう。C日程で試験を実施している自治体は募集人数が少ないケースも珍しくないので、面接でどれだけ好印象を残せるかが重要です。
対策方法は、模擬面接を繰り返し受けることが効果的です。
面接では論理的かつ簡潔に答える必要がありますが、この力は普段の日常会話だけではなかなか身につきません。模擬面接ではその場で自分の受け答えのフィードバックをもらえるので「わかりやすく答える力」を習得しやすいです。
なお、面接でよく聞かれる質問例は以下の通りです。
- 志望動機
- 自己PR
- 公務員として大切だと思うこと
よくある質問を確実に押さえ、良い印象を与えられる回答ができるようにしっかり準備しておきましょう。
高卒で市役所職員になったあとの流れ

市役所職員のキャリアは、勤務年数の長さに応じて段階的に上がっていくのが一般的です。公務員試験に合格して市役所で働き始めると、「主事」と呼ばれる一般職員のポジションからキャリアが始まります。
役署名や昇進スピードは自治体によって異なりますが、その後のキャリアの基本的な流れは、以下の通りです。
- 主事
- 主任(5年目前後)
- 係長(10年目前後)
- 課長補佐(15年目前後)
- 課長(20年目以降)
また、昇進の基準も各自治体で定められており、上司の推薦を受けて昇進する自治体もあれば、昇進試験に合格してキャリアアップする自治体もあります。
なお、課長補佐以上を管理職として扱う自治体が多く、管理職への昇進は実務経験に加えて人事評価の結果も重視される傾向が強いです。
高卒で市役所職員になるのに向いている人・向いていない人

市役所職員をはじめとする地方公務員は、業務の特性や働き方が民間企業とは大きく異なるため、人によって向き・不向きが出やすいです。
ここでは、高卒で市役所職員になるのに向いている人・向いていない人の特徴を解説します。
| 市役所職員に向いている人 | 市役所職員に向いていない人 |
|---|---|
| 自治体に貢献したいと考えている | 若いうちから稼ぎたいと考えている |
| コミュニケーション力がある | 民間企業への転職を視野に入れている |
| 学習意欲が高い | 将来は独立しようとしている |
向いている人の特徴①自治体に貢献したいと考えている
他人のために行動することが苦にならず、自分の仕事によって自治体や地域住民に貢献したいと考えている人は、市役所職員に向いています。
市役所職員は地域住民の視点で物事を考え、行動できる人が求められるからです。
また、市役所の仕事は民間企業とは異なり、利益追求をすることなく誰にでも平等にサービスを提供できる点が特徴です。社会への貢献意欲が高い人にとっては、役に立てる相手が多岐に渡るので、やりがいを感じながら働けるでしょう。
向いている人の特徴②コミュニケーション力がある
市役所職員は、地域住民はもちろん、同部署・他部署の職員、委託先である民間企業のスタッフなど、さまざまな人と多くのやりとりをします。
あらゆる年齢、立場、経歴、価値観の人と向き合わなくてはいけないので、柔軟な対応力や状況判断力をもとに、物事をわかりやすく伝える力は必須スキルです。
誰とでも円滑にコミュニケーションをとれる人は、市役所職員の適性があると言えるでしょう。
向いている人の特徴③学習意欲が高い
市役所職員に限らず、地方公務員は2~4年のペースで異動があり、定年までずっと同じ部署や勤務地で働き続けることはありません。
定期的な異動によって業務内容がガラリと変わっても、新たな知識を習得して職場に順応しなくてはいけないため、学習意欲が高い人でなければストレスを抱えてしまう可能性があります。
また、頻繁に変わる条例・法律によって業務内容が変更されるので、常に最新の知識や情報を学び続ける姿勢も求められます。
向いていない人の特徴①若いうちから稼ぎたいと考えている
「20代からガンガン稼ぎたい」「早く出世して高収入を得たい」と考えている人には、市役所職員は向いていません。
市役所職員の給料は年功序列で徐々に上がっていきます。出世に関しても勤務年数に応じて段階的に行われる仕組みのため、若いうちからスピード昇進して同世代の平均よりはるかに高い収入を得るといった展望は現実的ではありません。
年齢や勤続年数に関わらず実力を評価してもらえる環境で稼ぎたい場合は、民間企業に就職するのがおすすめです。
向いていない人の特徴②民間企業への転職を視野に入れている
早いうちから民間企業への転職を考えている人も、市役所職員に向かない可能性が高いです。
市役所職員の仕事は、職員による対応の違いが出ないよう、厳格なマニュアルが用意されています。必然的に業務が定型的になり、短期間での異動が多いこともあいまって特定のスキルが身につきにくい状態に陥りやすいです。
民間企業へ転職しづらい傾向にあるので、転職を視野に入れている人は、最初から民間企業に就職したほうが良いでしょう。
向いていない人の特徴③将来は独立しようとしている
将来的に独立しようとしている人は、市役所職員になるよりも民間企業でスキルを磨くほうが、効率的に夢を実現できる可能性が高いです。
市役所職員のスキルは、事務職であれば活かせるものの、プログラミングやWeb系、クリエイティブ職といった分野で開業をしたい場合は、活かしづらい傾向があります。
また、市役所は利益を求める職場ではないので、自ら売上を作る必要がある独立開業に必要な経験やスキルを積みにくいのも注意点です。
高卒で市役所職員になるメリット・デメリット

ここでは、高卒で市役所職員になるメリット・デメリットを解説します。
市役所職員を目指す上でのメリット・デメリットを総合的に把握して「本当に自分に合っているか」を考える参考にしてみてください。
| 高卒で市役所職員になるメリット | 高卒で市役所職員になるデメリット |
|---|---|
| 大卒公務員より早く社会経験を得られる | 大卒より給与が低い傾向にある |
| 試験難易度が大卒程度に比べて低め | 民間企業で通用するスキルが身につきづらい |
| 解雇のリスクが低い | 大卒に比べて昇進しづらい |
メリット①大卒公務員より早く社会経験を得られる
高卒ですぐに市役所職員になれば、大卒の職員よりも数年早く社会経験を積めます。
高卒は18〜21歳から市役所職員として業務に携われるのに対し、大卒が市役所職員になれるのは早くても22歳です。早くから社会に出ることで、業務スキルはもちろん、社会人としてのマナーや振る舞い、責任感などもいち早く習得しやすいです。
たった数年ではあるものの、新人時代の数年の差は大きく、経験値や知識量で一歩リードできるでしょう。
メリット②試験難易度が大卒程度に比べて低め
高卒程度の区分である地方初級公務員試験の難易度は、大卒程度の地方上級公務員試験に比べると低めです。
初級試験の第一次試験は教養試験のみのケースが多いですが、上級はさらに専門試験を受けなくてはいけないケースが大半で、試験範囲も広がります。
また、各試験の受験条件に学歴の制限はないものの、「高卒程度」「大卒程度」と明確に区分されていることから、初級試験は大卒の受験者が少ない点も、試験難易度が低い理由の一つです。
メリット③解雇のリスクが低い
市役所職員は解雇されるリスクが限りなく低く、安定性のある職業と言われています。
民間企業の場合、会社の利益が減少すれば倒産したり解雇されたりする可能性があります。一方で、市役所職員をはじめとする公務員はそもそも営利性がない組織に属しているため、組織の利益によって雇用を左右される心配がありません。
ルールに従って仕事をしている限り職を失うリスクが低いので、将来を不安視することなく働き続けられます。
デメリット①大卒より給与が低い傾向にある
市役所職員は、高卒・大卒ともに従事する業務内容は同じです。しかし、大卒職員よりも高卒職員のほうが給与は低くなる傾向にあります。
たとえば札幌市の職員の初任給は、高卒が154,000円なのに対し大卒は185,200円です。2年目においても高卒163,200円、大卒195,800円で、1年目・2年目ともに大卒のほうが3万円以上高いです。
高卒のほうが早くから働いているので、生涯賃金は大卒と大きくは変わりませんが、同じ仕事をこなしても給料が低いことに不満に感じる人は少なくないでしょう。
参考:札幌市公式ホームページ「札幌市人事行政の運営等の状況」(参照 2025-05-07)
デメリット②民間企業で通用するスキルが身につきづらい
市役所職員は基本的にマニュアルに沿って定型的な仕事をするため、業務によって得るスキルは市役所内でしか通用しないケースが多いです。また、定期的な異動によって取り扱う業務が頻繁に変わるので、特定の分野での専門性を深めるのが難しい点もデメリットです。
高卒で市役所職員になると、場合によっては民間企業で必要とされるスキルや専門性が身につきにくく、転職しようとしたときに苦労してしまうケースもあります。
デメリット③大卒に比べて昇進しづらい
市役所職員は、大卒程度の上級試験を受けて入職した人のほうが、昇進しやすい傾向にあります。
「上級試験に合格して入職した人」を昇進の条件にする自治体も多いため、初級試験を受けて職員になっていた場合、一定以上の役職の昇進を断念せざるを得ないこともあるのです。
しかし、市役所職員になった後から、改めて上級試験を受け直すという方法もあります。合格できれば、昇進スピードや役職の上限は大卒と同じになるので、役職に就きたい場合は一つの選択肢になるでしょう。
高卒で市役所職員になるためのおさらい

最後に、高卒で市役所職員になるためのポイントを振り返ります。
- ポイント
- 【高卒で市役所職員になる手順】
・希望する自治体に出願する
・地方初級(C日程)の第一次試験に合格する
・地方初級(C日程)の第二次試験に合格する
【高卒で市役所職員になるための資格試験の対策方法】
・志望動機、自己PR、ガクチカを重点的に対策する
・筆記試験と人物試験の採点比率をチェックする
・出題数が多い科目から勉強を始める
・自治体の課題にアンテナを張る
・面接対策を徹底する
市役所職員は、年齢制限さえクリアしていれば高卒でも目指せる職業です。高卒が就ける職業の中でも特に安定性が高く、解雇されるリスクがほとんどないのもメリットです。
市役所職員の仕事に興味がある方は、地方公務員試験合格を目指して対策を始めましょう。