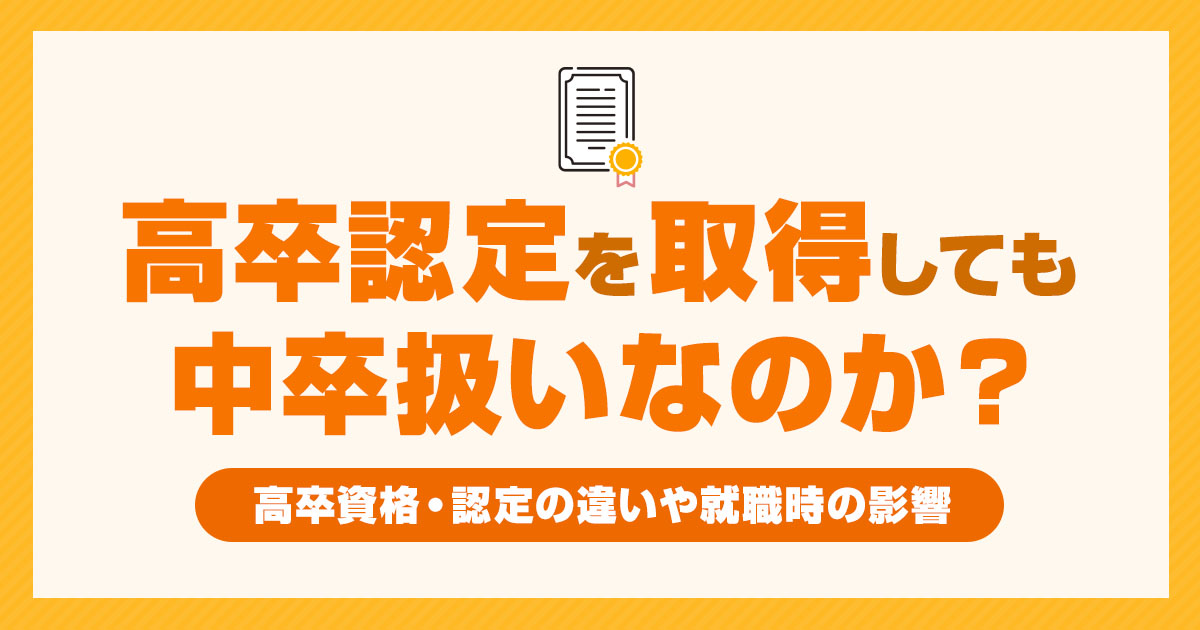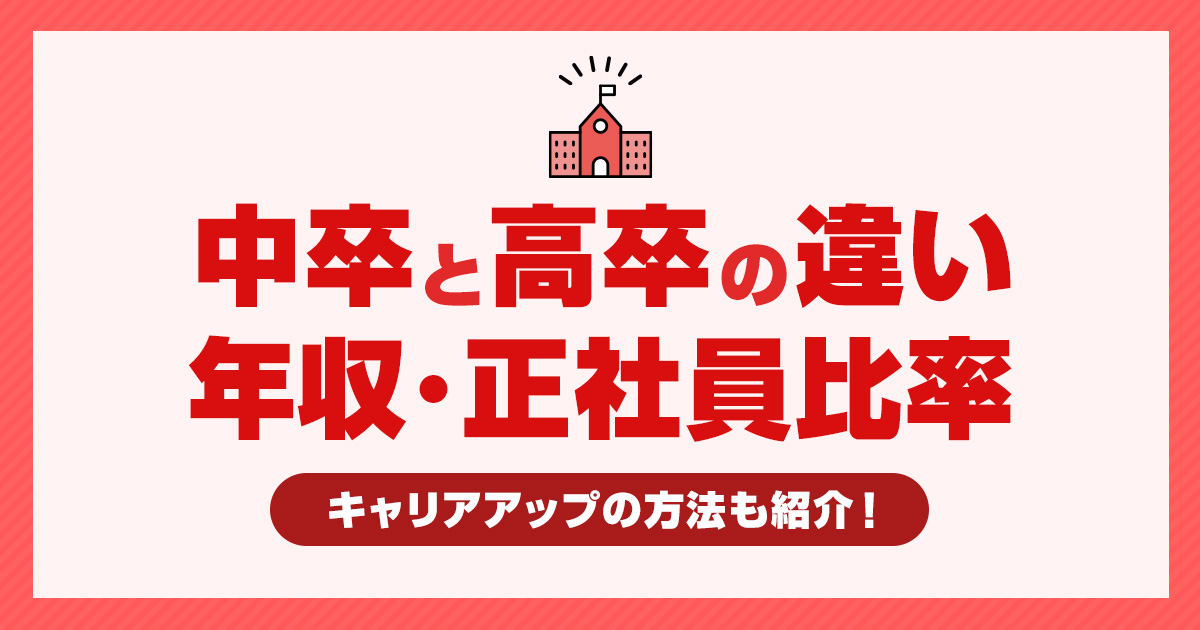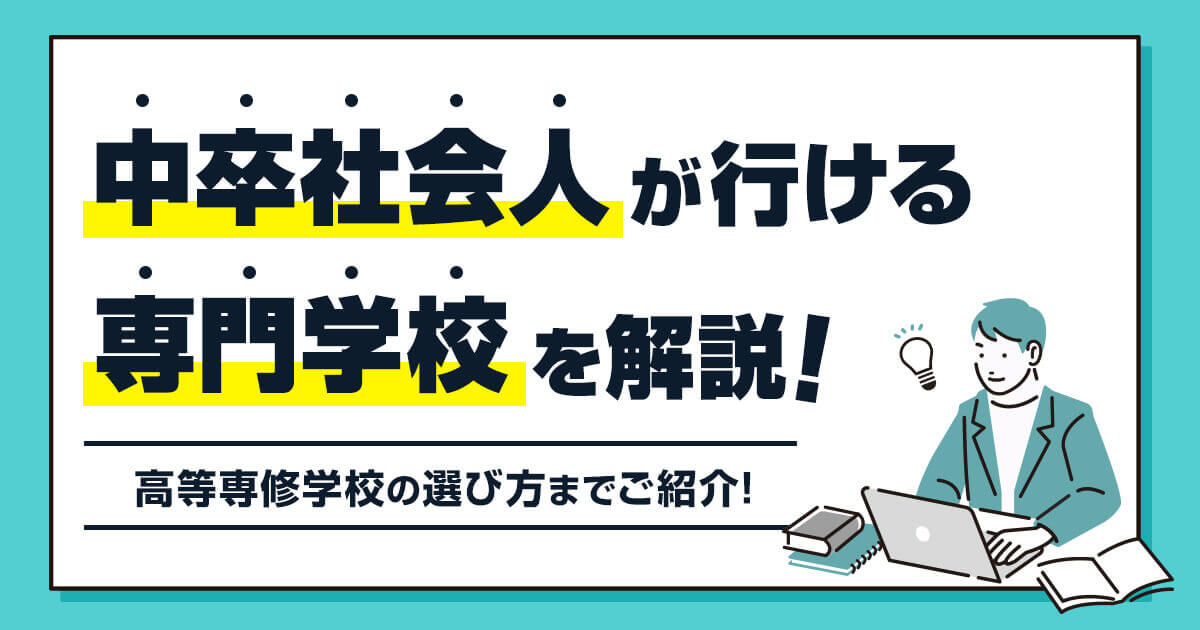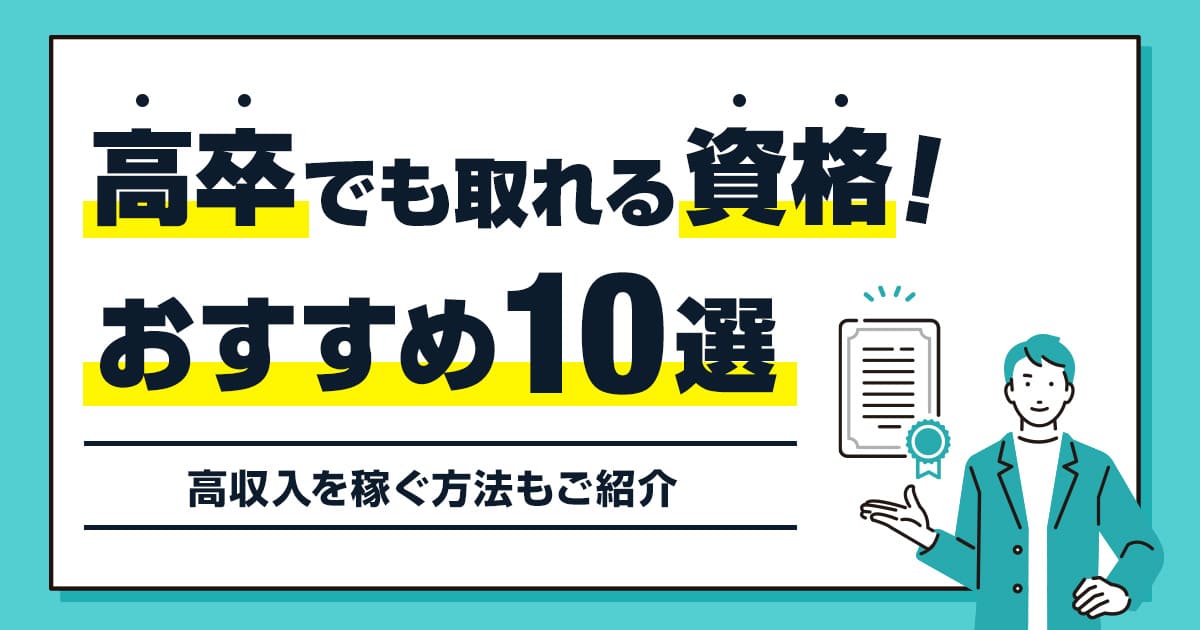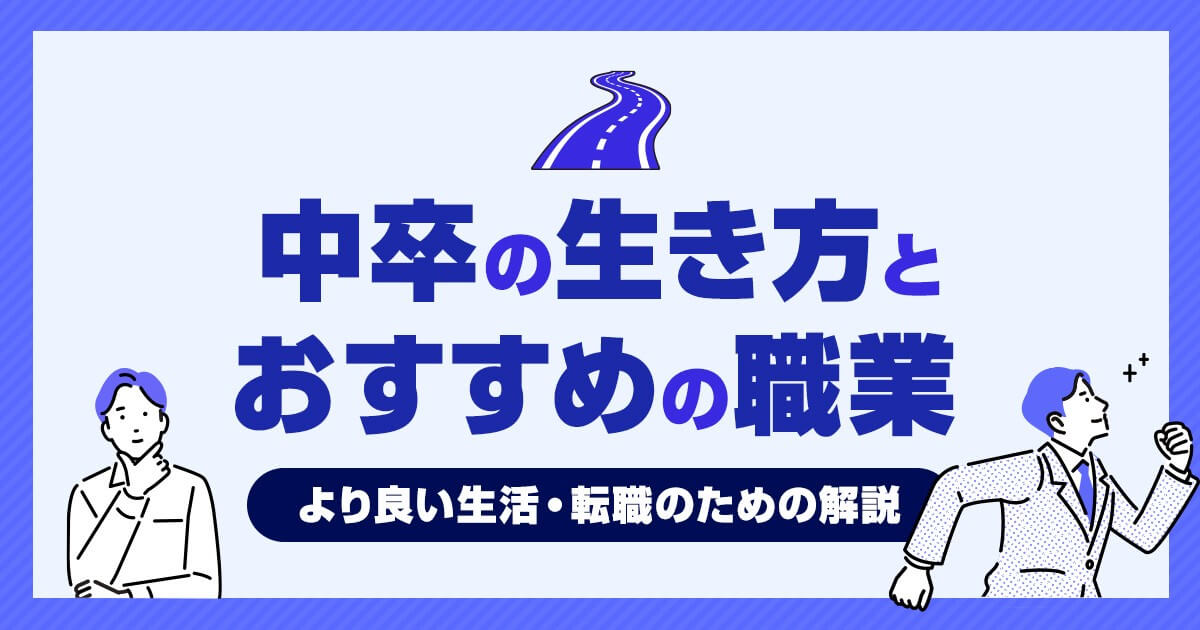「高卒認定を取っても学歴が中卒扱いなら意味がない」と、取得するか迷っている人は多いのではないでしょうか。
確かに高卒認定を取得しても学歴は中卒のままですが、進学や就職、資格取得の道を広げる大きなメリットがあります。「意味がない」と諦める前に、正しい情報を知っておいて損はありません。
この記事では、高卒認定と高卒資格の違いや高卒認定取得のメリット・デメリット、試験の概要などを詳しく解説していきます。
【結論】高卒認定を取っても学歴は中卒扱いになる

高卒認定を取得しても、学歴が高卒になるわけではありません。
高卒認定はあくまで「高卒と同等の学力がある」と国に認定してもらう制度であり、学歴は中卒扱いのままです。
しかし、高卒認定を取得すれば、高校に通学しなくても大学や専門学校への進学が可能となるほか、受験できる資格試験の幅も広がります。結果的に進路や就職の選択肢を増やす大きな一歩になるのは間違いありません。
高卒認定の意味を理解したうえで、自分の将来のために取得するべきかどうかを見極めましょう。
高卒認定と高卒資格の違い
高卒認定と似た言葉に「高卒資格」があります。
高卒資格とは、全日制、定時制、通信制のいずれかの高校を卒業することで得られる資格で、取得すると学歴が「高卒」になります。
一方、高卒認定は「高卒と同等の学力がある」と認められるものの、学歴は「中卒のまま」です。
また、両者には取得までの期間や費用にも大きな違いがあるので、目的や状況に応じて自分に合った方法を選びましょう。
| 高卒資格 | 高卒認定 | |
|---|---|---|
| 取得にかかる期間 | 3年以上 | 最短1回の試験で取得可能 |
| 取得にかかる費用 | 全日制・定時制:約150〜320万円 通信制:約2〜90万円 | 7〜9科目:8,500円 4〜6科目:6,500円 1〜3科目:4,500円 |
| 取得後の学歴 | 高卒 | 中卒 |
高卒認定試験の概要

高卒認定を取得するには、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)に合格する必要があります。
高卒認定試験は高校を卒業していない人が「高卒と同等の学力を有する」と国から認定を受けられる国家試験です。
ここでは、高卒認定試験の成り立ちや合格率、受験資格・日程、試験科目の内容について解説します。
高卒認定試験と大検との違い
高卒認定試験は、「大学入学資格検定(大検)」の後継とも言える試験で、平成17年度に現在の名称へと変更されました。
この変更により、下記のように受験資格や試験科目にもいくつかの見直しが行われています。
- 受験資格が拡大:受験する年度の終わりまでに満16歳以上になる人なら、誰でも受験可能に変更。
- 高校在籍中でも受験可能へ:全日制高校の在籍生も受験可能に変更。また、学長の判断により、高卒認定で合格した科目は在籍高校の卒業単位として認められるようになりました。
- 試験科目の見直し:「家庭科」「簿記」「保健」の3科目が廃止され「英語」が必修科目に変更。
高卒認定試験の合格率は約48%
令和6年度第2回の高卒認定試験における合格率は約48%でした。
合格者のうち約52.2%は中学校卒業または高校中退者なので、現在高校に在学していなくても合格できる可能性は十分にあると言えるでしょう。
公式に合格基準点は公表されていませんが、一般的には各科目で100点満点中50点程度が目安とされています。
なお、1回の試験ですべての科目に合格する必要はなく、一度でも合格した科目は次回以降の試験で免除されます。
継続的に学習を重ねることで合格への道は着実に開けるので、焦らず計画的に学習を進めましょう。
参考:文部科学省「令和6年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」(参照 2025-6-10)
高卒認定試験の受験資格・日程
高卒認定試験は、受験する年の3月末までに満16歳以上になる人であれば、誰でも受験可能です。現在高校に在籍している人や、高校を中退した人も対象となるため、幅広い年齢・背景の受験者がいます。
試験は毎年2回(8月と11月)実施され、2日間にわたって行われます。
会場は全国47都道府県に一か所ずつ設置されており、加えて少年院や刑務所などの矯正施設(令和5年度は延べ170か所)でも受験が可能です。
日程や試験会場の場所を早めに確認し、自分に合ったペースで学習を進めていきましょう。
高卒認定試験の試験科目・出題範囲
高卒認定試験では、下記の表のように教科ごとに定められた8~9科目に合格しなければいけません。
| 教科 | 試験科目 | 合格要件 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 必修 |
| 地理歴史 | 地理1、歴史1 | 必修 |
| 公民 | 公共 | 必修 |
| 数学 | 数学 | 必修 |
| 理科 | 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎 | 以下①または②のいずれかを満たすこと ①「科学と人間生活」を含む2科目 ②「科学と人間生活」以外の3科目 |
| 外国語 | 英語 | 必修 |
合格に必要な科目数は、在籍高校での修得単位や、前年度までの高卒認定試験での合格科目によって異なる場合があるため、個別に確認が必要です。
出題範囲は公式には明示されていませんが、原則として中学1年生から高校1年生修了レベルの学力を想定した問題が中心です。
さらに、令和8年度第1回の試験から試験科目に「情報」が追加され、合格に必要な科目数は9~10科目に増えます。
高卒認定を取るメリット

高卒認定を取得しても学歴は中卒扱いですが、進学や就職、資格取得の可能性を広げるうえで大きな意義があります。
採用の際に「高卒と同等」とみなす企業や教育機関もあるので、人生の選択肢を増やすための有効な手段とも言えます。
ここでは、具体的なメリットをさらに詳しく解説します。
大学・短大・専門学校などへ進学できるようになる
高卒認定を取得すると、大学・短大・専門学校などの入学試験の受験資格を得られます。
進学を考えている人にとっては、高卒認定の取得はほぼ必須と言っても過言ではありません。
ちなみに、最終学校卒業から1年間の間に正社員として就職している人の割合を見てみると、中卒は11.5%、高卒は64.8%、専門卒は78.9%、大卒は86.7%で、学歴によってその後の就職状況にも影響を受けることがわかります。
つまり、高卒認定を取得して進学をすると、就職の選択肢を広げられるというメリットも得られるのです。
ただし、特に大学入試では高卒認定試験よりも高度な学力が求められるため、合格後も継続して学習に取り組む必要があります。
参考:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」(参照 2025-6-10)
就職先の選択肢が広がる可能性がある
高卒認定を取得すると、求人で「高卒以上」の応募条件を設けている企業に応募できる可能性が出てきます。
履歴書上の学歴は中卒のままでも、企業によっては高卒と同等に扱う場合もあることから、就職先の選択肢が広がるのです。
また、高卒認定の取得により、一部の国家公務員採用試験も受験可能となります。
企業や自治体の扱いについては、後ほど詳しく解説しますが、就職を視野に入れたときに高卒認定の取得は有利に働く場面があると言えるでしょう。
【高卒認定を取得すると受験できる公務員試験】
- 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)
- 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)(護衛官の区分に限る)
- 入国警備官採用試験(警備官の区分に限る)
- 税務職員採用試験
- 航空保安大学校学生採用試験
- 海上保安大学校学生採用試験
- 海上保安学校学生採用試験
- 気象大学校学生採用試験
- 防衛大学校学生採用試験
- 防衛医科大学校医学科学生採用試験
- 防衛医科大学校看護学科学生採用試験
- 航空学生採用試験
- 衆議院事務局職員採用衛視試験
- 参議院事務局職員採用専門職(衛視)試験
- 裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、高卒者区分)
取得可能な国家資格が増える
下記のように、高卒認定を取得することで、受験資格を得られる国家資格もあります。
【高卒認定を取得すると受験できる国家資格】
- 1級(2級)土木施工管理技士
- 1級(2級)電気工事施工管理技士
- 幼稚園教員資格認定試験
- 小学校教員資格認定試験
- 保育士試験
- 第一種衛生管理者免許試験
- 1級土木施工管理技術検定試験
- 水産業普及指導員資格試験
- 土地区画整理士技術検定
- 食品衛生管理者
- 安全管理者
これらの資格は将来の就職や独立開業に直結するほか、現在就いている仕事に関連する資格を取得すれば、業務の幅が広がったり資格手当を得られたりするといったメリットもあります。
昇給・昇格や、より待遇の良い同業他社へ転職する際にも役立つ可能性が高いです。
高卒認定を取るデメリット
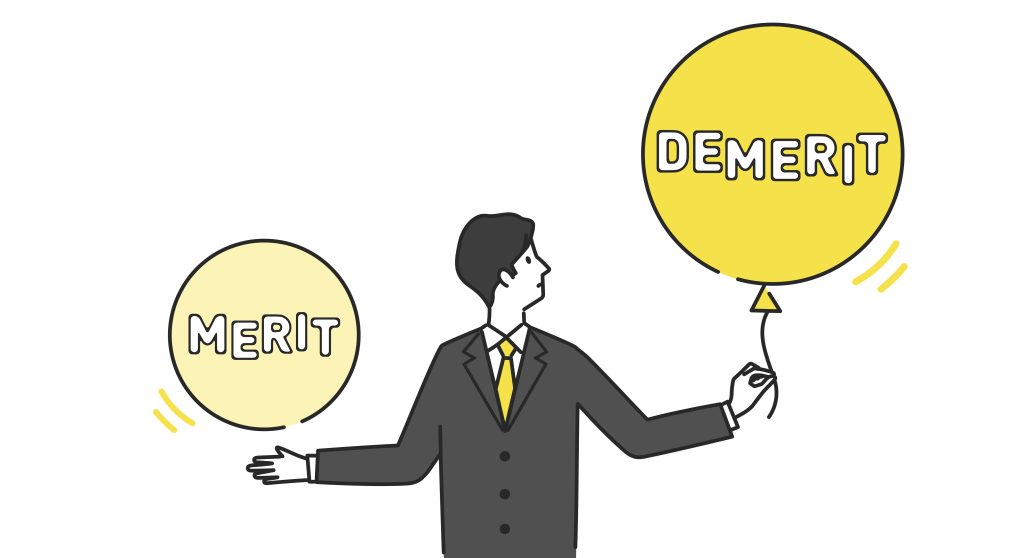
高卒認定は進学や就職の可能性を広げられますが、一方で注意すべき点もあります。
見落としがちなデメリットについても確認しておきましょう。
履歴書上は中卒のまま
高卒認定を取得しても、高校や大学、専門学校を卒業しない限り最終学歴は「中卒」のままとなるため、履歴書の学歴欄に「高卒」と記載することはできません。
たとえば、高校を中退している場合は、「〇〇高等学校 中途退学」と記載し、その下に「高等学校卒業程度認定試験 合格」と記入します。
また、就職活動では面接官から「なぜ高卒認定を取ったのか」「中退の理由は何か」「高校中退後はどのように過ごしていたか」といった質問をされる可能性があります。こうした質問に対しては、事前に回答を準備しておくと安心です。
「進学のために必要だった」「中退後も目標を持って学び続けた」といったように、自分の努力と意欲を前向きに伝えるようにしましょう。
自主学習を続けることが難しい
高卒認定試験の勉強は、基本的に独学で進める人も多く、合格までに強い意思を持ち続ける必要があります。
周囲に同じ目標を持つ仲間がいない場合、モチベーションを保てずに途中で挫折してしまうケースも少なくありません。
独学は周囲に比較対象になる人がおらず、勉強をサボっていても何か言われることがないので、日々の学習習慣と計画性が欠かせません。いかに自分のペースで集中力を維持できるかが、結果を左右します。
この記事でも、後ほど高卒認定試験に合格するための具体的な勉強法について紹介しますので、独学での勉強に自信がない方はぜひ参考にしてみてください。
高卒認定は意味ない?就職活動時の影響

高卒認定を取得しても学歴は中卒のままであるため、「取得する意味があるのか」と疑問に感じる人は少なくありません。
しかし、高卒認定の取得者を評価し、採用活動で高卒と同等に扱う企業や自治体も一定数存在します。
ここでは、高卒認定が就職の場でどのように見られているのかを解説していきます。
高卒認定を高卒と同等に扱う企業・自治体は全体の30%以上
文部科学省の調査によると、高卒認定を「高卒と同等」の扱いで評価している企業は32.8%、自治体では38.4%にのぼります。
企業・自治体の高卒認定取得者の扱いは以下の通りです。
| 企業 | 自治体 | |
|---|---|---|
| 高卒と同等 | 32.8% | 38.4% |
| 学歴で差はつけていない | 6.7% | 19.3% |
| 前向きに評価している割合の合計 | 39.5% | 57.7% |
「学歴で差をつけていない」と答えた企業・自治体と合わせると、企業の39.5%、自治体の57.7%が高卒認定を前向きに評価しています。
一方で「対応を決めていない」と回答した企業や自治体も一定数あるので、「高卒以上」と記載された求人に応募する際には、念のために事前に確認をとるのも手でしょう。
参考:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験合格者の企業等における扱いに関する調査」(参照 2025-6-10)
高卒認定を中卒扱いする企業・自治体は全体の3%以下
高卒認定を取得しても中卒扱いになるのではと不安に感じる方もいるかもしれませんが、実際に「中卒として扱う」と明言しているのは、企業でわずか0.6%、自治体でも2.3%にすぎません。
つまり、ほとんどの企業・自治体が高卒認定取得者を中卒と同等としては扱っていないということになります。
こうしたデータからも、高卒認定は就職活動において無意味ではなく、前向きな評価につながる制度であると言えるでしょう。
高卒認定試験に合格する勉強法3選

高卒認定試験に合格するには、自分にとって効果的な学習方法を選ぶことが重要です。
試験対策には主に「独学で取り組む」「予備校や塾に通う」「通信講座を受講する」の3つの方法があります。
それぞれの特徴やメリットを解説します。
独学で取り組む
独学は自分のペースで勉強できる点が魅力ですが、その反面、自己管理が求められるため計画的に学習を続ける強い意思が必要です。
| 独学のメリット | 独学のデメリット |
|---|---|
| 費用が安い | モチベーション管理が難しい |
| 好きな時間・場所で自由に学習できる | 学習計画や疑問点の解決に時間がかかる |
また、モチベーションの維持や勉強で行き詰ったときに自力で解決しないといけないハードルはあるものの、費用を抑えたい方や時間に制約のある方にとって、有効な方法と言えるでしょう。
自分の理解度や弱点に合った参考書や過去問を選ぶことが合格への近道となります。
予備校や塾に通う
予備校や塾に通えば、プロの講師による指導が受けられるほか、出題傾向に沿った効率的なカリキュラムに沿って勉強ができます。
| 予備校や塾に通うメリット | 予備校や塾に通うデメリット |
|---|---|
| プロ講師から指導を受けられる | 費用がかかる |
| 仲間と励まし合いながら学習できる | 通学時間の確保が必要 |
費用や通学の手間はありますが、仲間と切磋琢磨できる環境も魅力で、学習習慣が自然と身につきやすいです。客観的に自分の理解度を把握しやすい環境に身を置けるのも大きなメリットと言えます。
苦手な分野は早めに先生やクラスメイトに相談しながら、理解を深めていきましょう。
通信講座を受講する
通信講座はプロが用意したカリキュラムに沿って、自宅で自分のペースに合わせて学習できるのが最大の魅力です。通学の手間がないので、仕事との両立もしやすいです。
一方、自主的に勉強を進められない人には不向きな面もあります。
| 通信講座を受講するメリット | 通信講座を受講するデメリット |
|---|---|
| 自分のペースで学べる | 自己管理スキルが必要 |
| 自宅でプロが作成したカリキュラムを受講できる | モチベーションの維持が難しい場合がある |
教材の質やサポート体制も確認し、自分に合った講座を選びましょう。合格実績や合格者の声が多い信頼性の高い通信講座を選ぶのもおすすめです。
高卒認定は中卒扱いだけど取得する意味がある!

高卒認定を取得しただけでは、学歴は「高卒」にはなりません。
しかし、履歴書上では中卒扱いのままであっても、高卒認定には進学や就職、資格取得など、将来の選択肢を広げる力があります。
高卒認定を取得するメリットがある人は以下の通りです。
- 大学・短大・専門学校への進学を目指す人
- 高卒以上が応募条件の企業や公務員試験に挑戦したい人
- 学歴要件がある国家資格を取りたい人
- 就職時に学歴による不利を少しでも減らしたい人
「意味がない」かどうかは目指すキャリアプランに左右されるので、改めて取得が必要かどうか検討してみましょう。