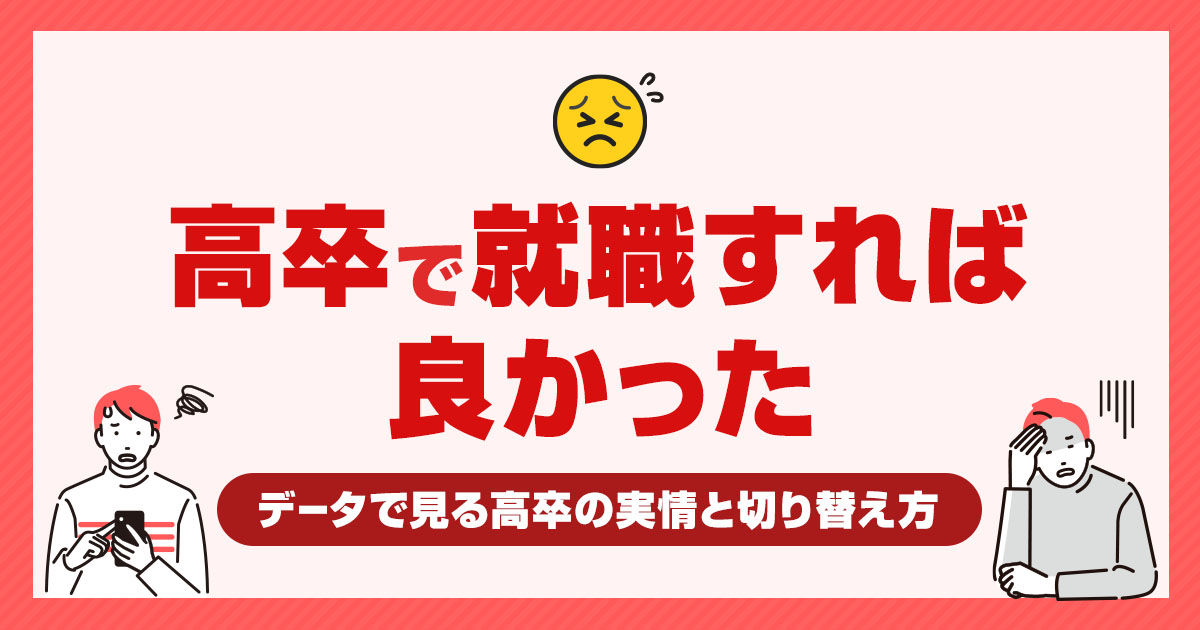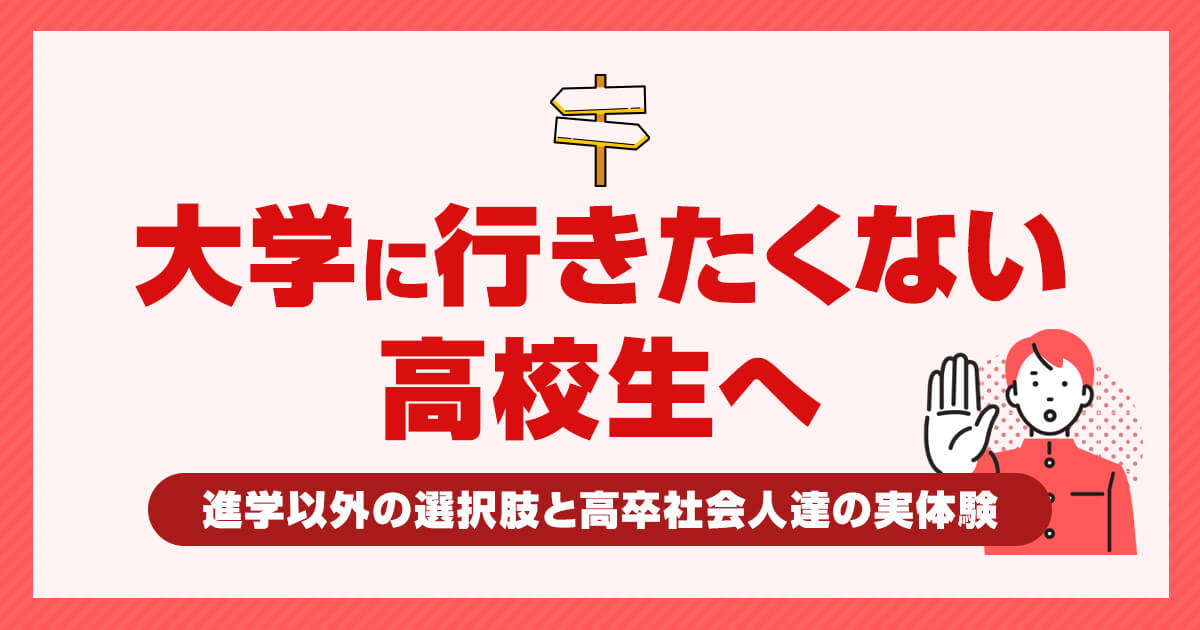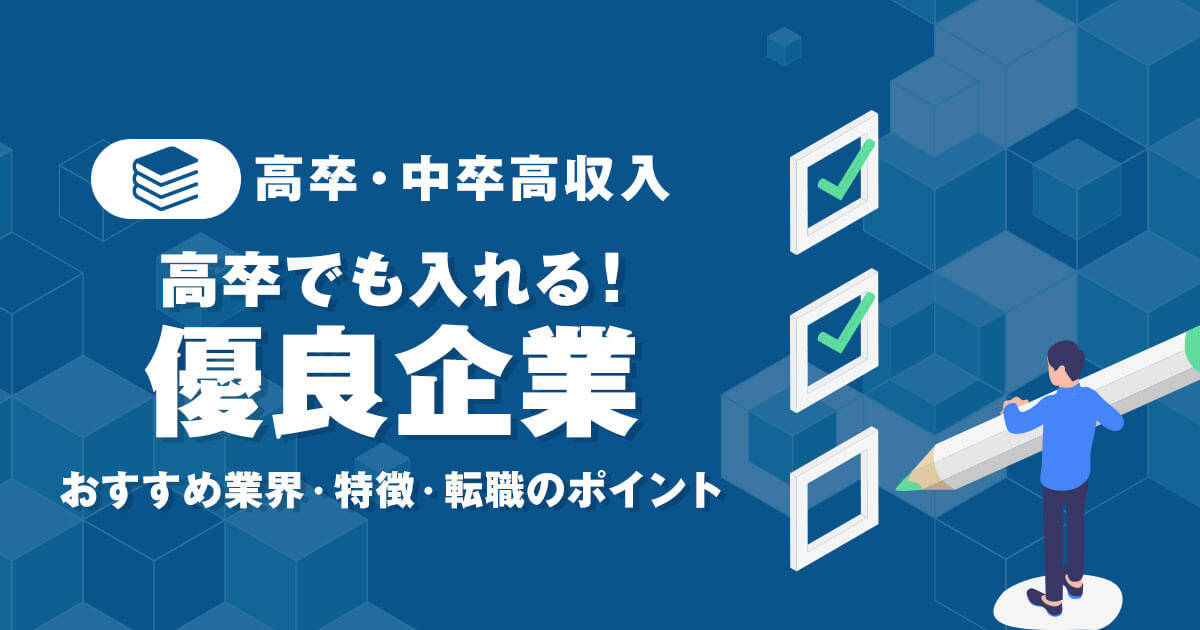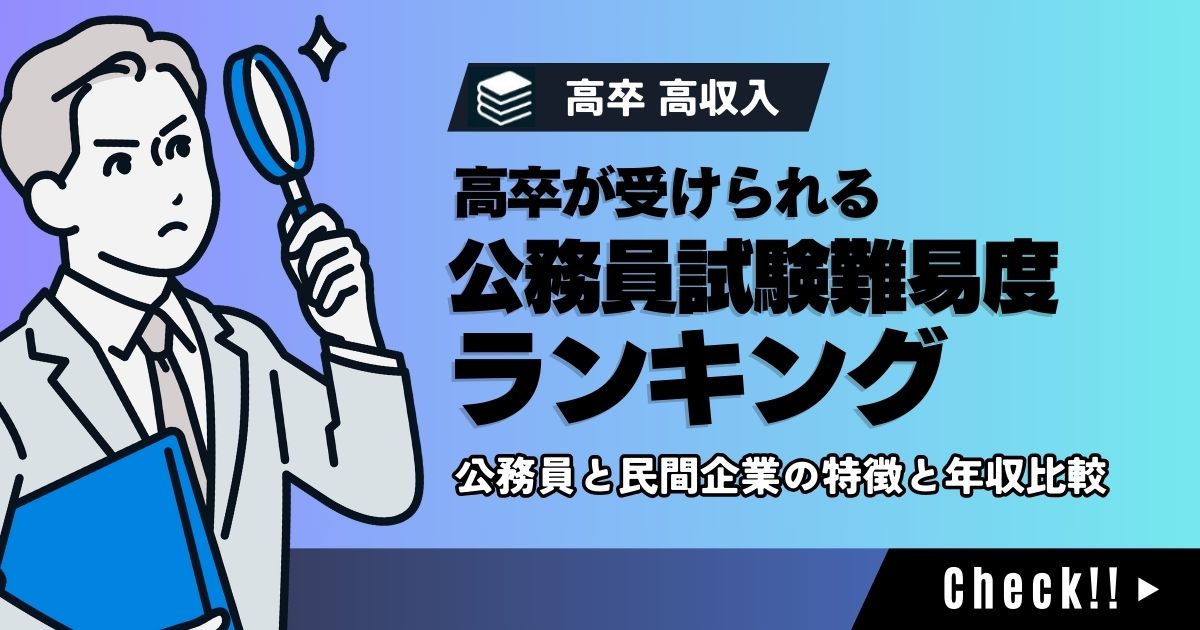高校を卒業してから進学の道を選んだものの、「高卒で就職すれば良かった」と感じている方もいるのではないでしょうか?
近年ではスキルやポテンシャルを重視する企業も増えており、学歴に縛られることなく就職しやすくなってきています。
では、大学へ進学するよりも高卒で就職したほうが良いのでしょうか?
本記事では、文科省などのデータをもとに高卒社会人の実情や高卒で就職するメリット・デメリットなどを解説します。
現状に悩んでいる方はもちろん、これからの進路を考えている高校生の方も、ぜひ参考にしてみてください。
「高卒で就職すれば良かった」と後悔している人は多い?

大卒での就職活動に苦労し、「高卒で就職すれば良かった」と後悔している人は少なくありません。
日本企業では、これまで「学歴」がかなり重視されてきました。
しかし、近年は応募者の経験やスキルが重視されるようになってきています。また、新卒はポテンシャル(将来の可能性)を見られ、高卒の応募者を「育てる」という意識で採用してくれる企業も多く、大卒よりも採用ハードルが低い場合もあります。
そして、ここ最近は「キャリアアップ転職」という選択肢も増え、スキルや経験を積んで、より良い待遇の職場へ転職するという方法もとりやすくなっています。
そのため、大学に進学せずに高卒で就職していち早くスキルを習得したり、実務経験を積んだりしたほうが良かったと後悔する大卒者は一定数いるのです。
データで見る高卒社会人の実情

「高卒社会人の就職率や年収は大卒と比べるとどの程度なのだろう」と気になる方も多いでしょう。
ここでは、データをもとに高卒社会人の実情をご紹介します。
進学せず就職する人の割合
文部科学省の調査によれば、令和6年度における高卒の大学進学率は87.3%です。令和5年度は84.0%、令和4年度は83.8%だったため、高校卒業後に進学する人の割合は年々増加傾向にあります。
一方、高卒の就職希望率は14.0%で、前年よりも0.2%減少していました。
進学を選ぶ人が増える中で、就職を選択する高卒者の割合はわずかながら減少していることがわかります。
この傾向は、より待遇の良い企業に就職するために、少しでも学歴をつけようと考える学歴重視の価値観が依然として根強いことの表れといえます。
参考:文部科学省「令和6年度学校基本調査(確定値)について公表します。 」(参照:2025-05-27)
文部科学省「令和6年3月新規高等学校卒業者の就職状況(令和6年3月末現在)に関する調査について」(参照:2025-05-27)
大学生と高校生の就職内定率はほぼ変わらない
文部科学省の調査によれば、令和6年度の高卒者の就職(内定)率は98.0%です。
一方、厚生労働省の調査で、令和6年度の大卒者の就職率は98.1%なので、高卒者と大卒者の就職内定率はほぼ変わらないことが分かります。
採用時に学歴を重視する企業があるものの、高卒だからといって就職先が決まらないというわけではありません。
ただし、就職内定率がほぼ同じであっても、業界や職種、企業、キャリアなどの選択肢において、学歴が影響を及ぼす場面も少なくありません。自分の目指す将来像や希望に合わせて見極める視点が重要です。
参考:文部科学省「令和6年3月新規高等学校卒業者の就職状況(令和6年3月末現在)に関する調査について」(参照:2025-05-27)
厚生労働省「令和6年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」(参照:2025-05-27)
高卒・大卒者の生涯年収
厚生労働省の調査によれば、令和6年度における高卒者・大卒者の平均年収と生涯年収は以下の通りです。
なお、生涯年収は「平均年収×就労年数」で計算しています。就労年数は、高卒者が18歳から60歳までの42年間、大卒者が22歳から60歳までの38年間を想定しています。
| 平均年収 | 生涯年収 | |
|---|---|---|
| 高卒 | 約347万円 | 約1億4,560万円 |
| 大卒 | 約463万円 | 約1億7,590万円 |
このデータには賞与や各種手当などが含まれていないため、実際にはもう少し金額が増える可能性がありますが、平均年収・生涯年収ともに、大卒者が高卒者を上回っています。
また、高卒はより年齢が若いうちから働き始めるので「労働時間あたりの給与」として考えると、高卒と大卒の年収差はさらに開くと言えます。
ただし、上記はあくまでも平均値に過ぎません。就職先の企業規模や業種、地域、個人のキャリアによって、実際の年収は大きく変わります。
そのため進学・就職を決める際は「学歴=収入」だけでなく、自分が望む働き方や生き方も含めて総合的に考えることが大切です。
参考:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況:学歴別」(参照 2025-05-27)
高卒社会人たちの就職理由は?

高卒で進学せずに就職した人たちの就職理由は、下記のように人によってさまざまです。
- 早く自立がしたかったから
- やってみたい仕事があったから
- 金銭的な面で進学できなかったから
- 進学することに意味を見出せなかったから
- 早い時期から経験や実績を積めるから
なぜ就職を決意したのか、高卒社会人たちの主な就職理由を詳しく見ていきましょう。
早く自立がしたかったから
高校生が進学せず就職する理由として、「早く自立したかった」という意見が挙げられます。
多くの高校生は実家で親にサポートを受けながら生活していますが、「自分の力で収入を得て生活したい」「早く社会で経験を積みたい」と考える人も少なくありません。
「安定した収入を得て自分の生活や趣味を充実させたい」「親に頼らず自分の選んだスタイルで生活を始めたい」そんな前向きな気持ちで就職を選ぶケースも見られます。
このように、早く自立することで自分の可能性を広げたいという思いが、高校卒業後の進路選択に影響を与えていることがうかがえます。
やってみたい仕事があったから
高校生の時点でやりたい仕事が明確にある場合、高卒で就職を選ぶ人もいます。
特に、職人や芸能関連などの技能職をはじめとした、長期的に現場でスキルを身につける必要のある職業は、できるだけ早いうちから実務経験を積み重ねたほうが有利なケースが珍しくありません。
「自分の目指す業界や職種では大学進学が有利にならない」「若いうちから経験を積むキャリアプランが有効」といったように、高校を卒業してすぐに就職するのが適しているパターンはいくつかあります。
そのため、大学進学が遠回りになり得る仕事を目指している人は、あえて大学進学を選ばないケースが多いです。
金銭的な面で進学できなかったから
経済的な理由から、やむを得ず高卒での就職を選択する人もいます。
進学するには多大な費用がかかります。大学や専門学校への進学にかかる学費(初年度納付金)の目安は、以下の通りです。
- 国立大学:約81.7万円
- 私立文系大学:約116.7万円
- 私立理系大学:約154.4万円
- 専門学校:約125.5万円
高額な学費は、進学を希望する高校生やその家族にとって大きな負担になります。また、返済義務のある奨学金制度を活用した場合は、卒業後に返済をしなければならないケースが多く、長期的な経済的負担となってしまう可能性もあります。
さらに、大学や専門学校の学費が年々値上がりしていることもあり、高卒での就職を選ぶ人は少なくないのです。
進学することに意味を見出せなかったから
特に大学進学の必要性を感じなかったため、高卒で就職を選ぶ人もいます。
たとえば、「進学してまで学びたいことがない」「単純にもう学校で勉強はしたくない」といった理由から、大学進学に意味を見出していないケースはよくあります。
大学進学には費用と時間がかかるため、「目的もないのに進学するなら就職したほうが良い」「費用や時間を無駄にしたくない」と考える人がいるのは自然です。
また、今すぐ大学へ進学せずとも、本当に学びたいことを見つけてから大学へ入学するのも不可能ではないので、高校在学中の現役合格にこだわらない人も一定数います。
早い時期から経験や実績を積めるから
早い時期から現場で経験や実績を積むために就職したいと考える人もいます。
同年代が大学を卒業して新入社員として研修を受けているころには、高校で就職した人は社会人5年目に入った中堅社員になります。
4年分の社会人経験や実績は大きな評価点であり、企業によっては昇給や昇進の話も舞い込んでくるタイミングです。
また、社会人5年目になればキャリアアップ転職も視野に入ってきます。大卒者と同じ年齢で数年の実務経験、スキル、実績を持っている人材は、転職市場での価値が高いです。
そのため、実力が評価される業界をしっかり選び、キャリアプランを立てたうえで早くから経験や実績を積むのは悪くない選択だと考えている人は多いのです。
高卒で就職するメリット

学歴が重視される現代社会において、高卒で就職するのは不利と考える人もいるでしょう。しかし、高卒で就職するのは、大学進学にはないメリットがあります。
ここでは、高卒で就職するメリットを5つご紹介します。
- 早くから自立できる
- 早くから社会人経験を積める
- 大学や専門学校の学費がかからない
- 就職に関するサポートが手厚い
- 高校生採用に慣れた企業が多い
早くから自立できる
高卒で就職すると、経済的・社会的に自立できる時期が早まるというメリットがあります。
安定した収入を得ることで、自分の力で生活費をまかない、自分に合った生活を送れます。また、自分の裁量でお金の使い方を考えられるようになるなど、責任感や自己管理能力も自然と身についていきます。
そして、高校卒業後すぐに就職することで、業務を通じて学びや成長の機会を大卒より多く得られるのも、メリットになります。
業界や職種によっては、大卒が就職する頃には「中堅メンバー」として業務的にも自立できるようになってくるので、若いうちから自分の裁量で動かせる仕事を任せてもらえるチャンスがあります。
早くから社会人経験を積める
高卒で就職する最大のメリットのひとつは、社会に出るタイミングが早いことです。
大卒と比べて4年早く働き始められるため、その分早くスキルや実務経験を積むことができ、若いうちからキャリアを築いていくチャンスが広がります。
特に実力主義の業界・職種は、学歴よりも現場での成果や経験が重視される傾向があります。
若いうちから経験を重ねておけば、大卒の同年代が新卒として入社する頃には、昇進や昇給で差を広げられる可能性もあります。
また、早くからスキルや実績を積んでおくことで、転職市場でも高く評価されやすくなります。キャリアアップ転職を目指す際にも、年齢に対して豊富な経験があることで、選択肢の幅が広がるのは大きな強みです。
大学や専門学校の学費がかからない
高卒で就職すれば、大学や専門学校への進学費用、教材代などがかかりません。
大学や専門学校に進学する場合、入学金や授業料、教材費などを含め、初年度だけでも80万~150万円程度が必要になります。卒業までにかかる総額は、数百万円にのぼることも珍しくありません。
さらに学生の間は、安定した収入を得ることが難しく、生活費も含めて経済的な負担は大きくなります。たとえ奨学金を利用しても、卒業後に何年もかけて返済を続けなければならないケースがほとんどです。
その点、高卒で就職した場合、こうした学費の負担をおさえ、早くから収入を得られるメリットがあります。
就職に関するサポートが手厚い
高卒での就職は、「学校からの支援を受けながら進められる」という大きな強みがあります。
大学生が基本的に自分で企業を探し、選考対策を行うのに対し、高校生の就職活動は、学校の先生や進路指導の担当者がしっかりとサポートしてくれます。
たとえば、就職支援が充実している学校なら、下記のような支援を受けられる可能性があります。
- 履歴書作成や面接対策の時間を作ってくれる
- 企業との連絡に先生が入ってくれる
- 希望の業界・職種研究を手伝ってくれる
- 就職に必要な資格取得のサポートをしてくれる
特に、事務作業や企業への連絡などのサポートを受けられれば、自分は履歴書や面接の対策に集中でき、スムーズに就職活動を進められます。
高校生採用に慣れた企業が多い
高卒採用に積極的な企業は、「新人を育てる体制」が整っていることが多く、働きながら着実に成長できる環境があります。
こうした企業では、高校を卒業したばかりの新入社員を即戦力としてではなく、長期的にじっくり育てていく方針が一般的です。そのため、新人研修や先輩社員からの実地指導(OJT)など、育成プログラムがしっかりと用意されています。
- OJTとは
- 職場の上司や先輩が、実際の業務を通じて仕事に必要な知識・技術・仕事の進め方などを指導する職業教育のこと。
知識や技術だけでなく、仕事に対する考え方や意識といった心構え、ビジネスマナーなどを丁寧に教えてくれる企業もあります。
高卒を採用している企業は、未経験入社でもイチから学びながら働ける環境が整っているので、効率良くスキルアップできる可能性が高いです。
高卒で就職するデメリット
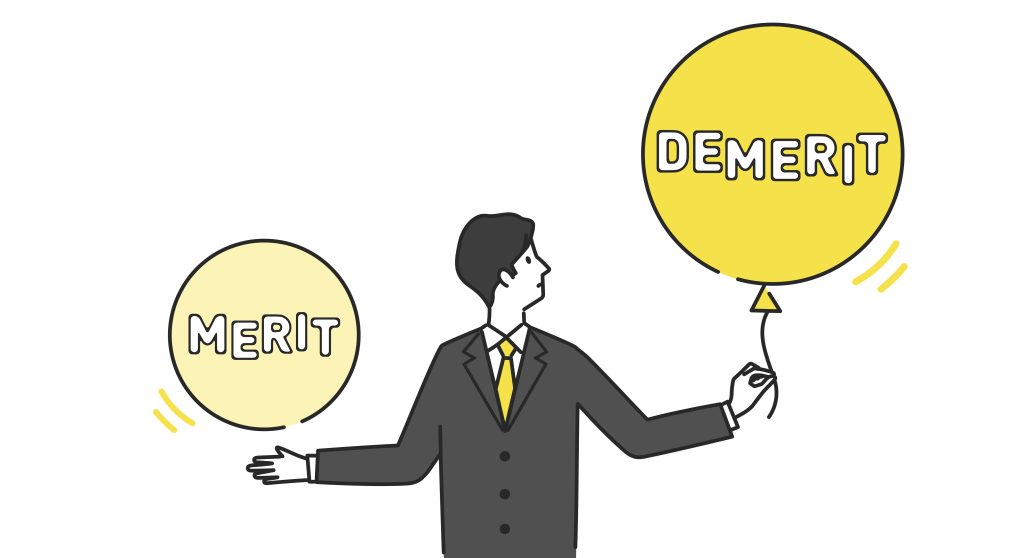
高卒で進学せずに就職するメリットは多いですが、デメリットもあります。
ここでは、高卒で就職するデメリットを4つご紹介します。
- 応募できる求人の選択肢が狭まりやすい
- キャリアアップしにくい場合がある
- 生涯労働時間が長くなる
- 学歴コンプレックスを持ってしまうことがある
応募できる求人の選択肢が狭まりやすい
高卒で就職する場合、応募できる求人の選択肢が狭まりやすい点はデメリットです。
たとえば、「大卒以上」といった学歴制限が設けられている求人は、高卒だと応募できなかったり、書類選考で不利になったりする可能性が高いです。
特に、研究職や技術職など専門的な知識や技術が求められる仕事では、学歴だけでなく、一定以上の学歴がないと取得が難しい資格を求められるなど、高卒が応募可能な求人が少ない傾向にあります。
また、学歴によって応募できる職種が異なるケースもあり、たとえば大卒は総合職・一般職のどちらの求人にも応募できる一方で、高卒は一般職に限られるといったことも実際に見られます。
このように、高卒での就職は求人の選択肢が狭まりやすいため、希望の業界・職種によっては就職しづらいケースもあります。
キャリアアップしにくい場合がある
学歴を重視する企業に就職した場合、高卒は大卒よりもキャリアアップしにくい可能性があります。
学歴重視の企業では、管理職への登用に一定以上の学歴が基準とされていて、昇進の面でも大卒が有利になりやすいのが実情です。
さらになかには大卒を管理職、 高卒を現場担当といった形で、学歴によって役職や業務内容に差を設けている企業も存在します。
そのため、高卒で就職する場合、企業によっては長期的なキャリア形成で不利になることも考えられます。
キャリアアップを目指すのであれば、業界や職種を慎重に選ぶとともに、スキルや資格を身につけ、学歴によるハンデを補う努力が重要です。
生涯労働時間が長くなる
高卒での就職は、大卒者よりも生涯労働時間が長くなります。そのため、大卒と比べて若いうちから自由な時間が少なくなる点はデメリットと言えるでしょう
社会人になると、1日の大半を仕事に充てることが一般的で、長期休暇も取りづらく、時間の自由が制限されがちです。
一方で、進学すると、大学生の間は学業以外の時間を比較的自由に使えます。春休みや夏休みなどの長期休暇もあり、気軽に旅行や短期留学に行くことも可能です。
もっとも、大学進学のために返済義務のある奨学金を借りていた場合、言ってみれば未来のお金で時間を買ったようなものなので、メリットとなるかデメリットとなるかは捉え方にもよります。
学歴コンプレックスを持ってしまうことがある
高校時代にどれだけ優秀であっても、大学へ進学しなければ最終学歴は「高卒」となります。一方、大学時代に成績が振るわなかったとしても、卒業すれば最終学歴は「大卒」です。
学歴社会の現代においては、学歴が評価基準の一つになるケースが多いので、実力以上に学歴に目が向けられる場面も少なくありません。そのため、高卒で就職した人の中には、学歴にコンプレックスを感じる人もいるでしょう。
一度そうしたコンプレックスを抱くと、払しょくするには時間がかかることもありますが、努力の原動力に変えられれば、それがむしろ大きなメリットになる可能性も十分にあります。
高卒で就職したほうが良いのはどんなケース?

高卒での就職はメリットもデメリットもあるため、「高卒で就職して正解」と言えるかどうかは、人によって異なります。
高卒で就職したほうが良い例としては、以下のようなケースが想定されます。
- 学歴よりも技術や経験が重視される企業や業界へ就職する場合
- 実力主義の企業や業界へ就職する場合
- 高卒枠採用のある公務員を目指す場合
- キャリアアップ転職を前提とした就職をする場合
- 高額な学費や奨学金返済を避けたい場合
上記のように、高卒での就職が有利になる状況やメリット・デメリットを理解しておくと、希望のキャリアプランに合った適切な進路選択がしやすくなります。
高卒で就職して上手くいったAさんの事例

では、実際に高卒で就職して上手くいったAさんの事例を見てみましょう。
Aさんは、少しでも早く社会人になり、スキルにものを言わせて実力勝負の世界で活躍したいと考えていました。1社にずっと勤め続けるつもりはなく、段階を踏んでより高度なスキルを身につけられるように、転職を前提としていたそうです。
最初の就職先から、将来を見据えてスキル磨きと資格取得に集中し、4年後に同年代の大卒が入社してきたタイミングでキャリアプランを再設計。すでに経済的に自立していたため、貯蓄も十分にあり、迷わず転職を決意できたそうです。
そして、スキルや資格、実務経験がある状態だったので、転職市場での価値も20代という年齢を見ても高く、無事にキャリアアップ転職を成功させました。その結果、高卒の平均を大きく上回る年収アップにもつながっています。
このAさんのように自身のキャリアプランがはっきりしている場合、今何をすべきかが明確なので、時間を有効活用でき、高卒での就職が上手くいきやすくなります。
高卒者が就職しやすい5つの業種もチェック

ここでは高卒者が就職しやすい業種を5つご紹介します。
- 建設業・土木業
- 公務員
- 医療・介護・福祉業
- エンジニア・IT関連業
- ナイト系スタッフ
高卒者が特に就職しやすいのは、「学歴不問の業種」や「経験・スキル・資格などが重視される業種」です。詳しくチェックしてみましょう。
建設業・土木業
建設業・土木業は肉体労働がメインの職種が多く、若さや体力が重視されます。そのため、高卒から就職しやすく、経験を積んでスキルや資格を取得することで、現場の監督、管理職といったキャリアアップも目指せます。
建設業・土木業が高卒者におすすめの理由は、以下の通りです。
- 現場での経験が重視される
- 資格取得による昇進がしやすい
- 体力が重要なので若いうちから活躍しやすい
学歴不問で募集している未経験歓迎の求人も多く、働きながら技術を習得し、実力次第で昇進できる可能性があります。
体力に自信がある人や、ものづくりに興味がある人に向いている業種です。
公務員
公務員も高卒の就職先としておすすめです。
公務員になるには公務員試験に合格する必要がありますが、基本的に学歴不問で受験可能です。高卒程度の学力があれば合格できる試験もあり、高卒が目指しやすいのもポイントと言えます。
公務員が高卒者におすすめの理由は、以下の通りです。
- ほとんどの公務員試験は学歴不問で、努力次第で合格できる
- 景気の影響を受けにくく、収入が安定している
- 福利厚生が充実している
- リストラのリスクが低く、定年まで働きやすい
高卒の就職において、収入の安定性や福利厚生の充実度は重要な要素です。公務員になれれば定年まで働きやすく、学歴に左右されずに安定した生活を送れるのは大きな魅力でしょう。
医療・介護・福祉業
医療・介護・福祉業は、日本の高齢化社会の進行に伴い、今後も高いニーズが見込まれています。
医療・介護・福祉業が高卒者におすすめの理由は、以下の通りです。
- 未経験者でも採用されやすい
- 働きながら資格取得やキャリアアップが可能
- 実務経験を積んで専門職への転職を目指せる
特に介護・福祉業は学歴不問の求人も多く、高卒も就職しやすいです。業界全体で未経験者を積極的に採用しており、資格取得支援の制度を設けている企業もたくさんあります。
働きながら資格取得やキャリアアップを目指せる点も魅力です。また、資格を取得することで、医療事務、介護福祉士、ケアマネージャー、社会福祉士などの専門職への転職も可能になります。
誰かの役に立ちたい人や専門職に就きたい人に向いている業種と言えます。
エンジニア・IT関連業
エンジニア・IT関連業は専門知識やスキルを必要とするものの、IT人材の需要が高く、学歴・経験は不問の求人が多いです。
エンジニア・IT関連業が高卒者におすすめの理由は、以下の通りです。
- 学歴よりも知識やスキルが重視される
- 充実した研修制度がある企業が多い
- 働きながらスキルアップを目指せる
エンジニア・IT関連業は、学歴よりも知識やスキルが重視される業界なので、人材育成に力を入れている企業が目立ちます。高卒や未経験者を歓迎している企業も豊富で、やる気があれば仕事を着実に覚えていける環境が整っていると言えるでしょう。
また、実務経験を積みながらスキルや資格を取得しやすく、学歴に関係なく仕事の幅を広げてキャリアアップを目指せます。
IT技術に興味がある人、常に学び続ける努力ができる人に向いている業種です。
ナイト系スタッフ
高卒・未経験で高収入を目指すのであれば、ナイト系スタッフという選択肢もあります。
ナイト系スタッフが高卒者におすすめの理由は、以下の通りです。
- 学歴・経験は不問で、やる気や人柄が評価されやすい
- コミュニケーション能力のように、学歴や資格で評価されないスキルが重視される
- 学歴に関係なく早期から昇給や昇進が可能
ナイト系は高卒で就職する人の割合が比較的大きい業界なので、高卒からチャレンジしやすい業界です。
実力主義のため、評価の基準は学歴や経験ではなく、やる気や人柄、そして入社後の実績にあります。成果を出せば学歴に関係なくスピード昇給・昇進を目指せるため、同年代よりも高収入を得られる可能性も大いにあります。
すぐに成果を出して稼ぎたい人やコミュニケーション能力に自信がある人に向いている業界です。
高卒の就職に関するよくある質問

最後に、高卒の就職に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。
「高卒で就職すれば良かった」と感じている方も、今まさに高卒で就職すべきかお悩みの方も、ぜひ参考にしてみてください。
企業側はどんなメリットがあって高卒者を採用するの?
企業が高卒者を採用するメリットは、「長期的な人材育成ができる」「組織活性化につながる」といった点があります。
高卒は大卒よりも4年早く社会人経験を積むため、企業は若いうちから自社の戦力になるように育成をして、自社にとって長期的な戦力になってくれることを期待しています。
また、若い高卒の新入社員が入社すると、既存社員への刺激にもなるので、職場全体の活性化につながる可能性も高いです。
このような理由から、高卒者を採用する企業は多い傾向にあるのです。
高卒の就職先選びの注意点は?
高卒で就職する際は、就職先の特性をよく理解することが重要です。
たとえば、学歴を重視する業界・企業を選ぶと、昇給や昇進で不利になるケースがあり、キャリア形成に限界が出やすいです。
一方、学歴不問の業界・企業に就職すると、高卒も昇給・昇進できる可能性が高いですが、実力主義の傾向が強く、大卒と同じ基準で人事評価が下されます。
安易な選択は将来的に悩みを抱えてしまう恐れがあるので、志望業界・職種・企業の特性をしっかり理解したうえで慎重に進路を見極めましょう。
高卒でキャリアプランを組み立てるときの注意点は?
キャリアプランを組むときは、具体性を盛り込んで明確に考えることが大切です。
「最終的にどうなりたいか」だけではなく、「転職はするのか」「何歳までにどんなスキルを習得するのか」「資格取得はいつするのか」などを具体的に決めておくと、そのプランを実現させるために最適な選択肢が見つかりやすくなります。
キャリアプランを具体的に考えないまま就職した場合、キャリアアップの最短ルートを進めず、知らず知らずのうちにその先の選択肢が狭まってしまう可能性があるので注意しましょう。
高卒での就職にはメリットもデメリットもある

「高卒で就職すれば良かった」と後悔している人もいるかもしれませんが、高卒での就職にはメリットもあればデメリットもあります。
高卒で就職するメリット
- 早くから自立できる
- 早くから社会人経験を積める
- 大学や専門学校の学費がかからない
- 就職に関するサポートが手厚い
- 高校生採用に慣れた企業が多い
高卒で就職するデメリット
- 高卒での就職の求人は選択肢が狭まりやすい
- キャリアアップしにくい場合がある
- 生涯労働時間が長くなる
- 学歴コンプレックスを持ってしまうことがある
高卒で就職するのが正解かどうかは、希望の業種や企業の特性、そして自身のキャリアプランなどによります。
キャリアプランは再設計していくことも可能なので、どの選択を選んだとしても「今できること」に目を向けて、自分にとって最適な選択をしましょう。