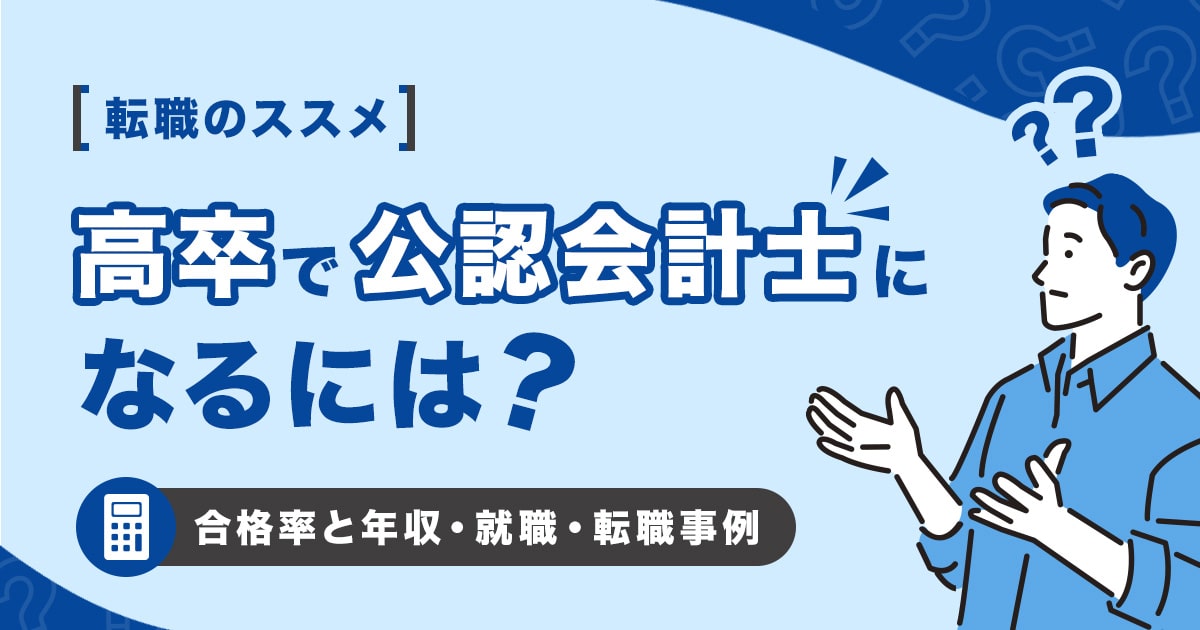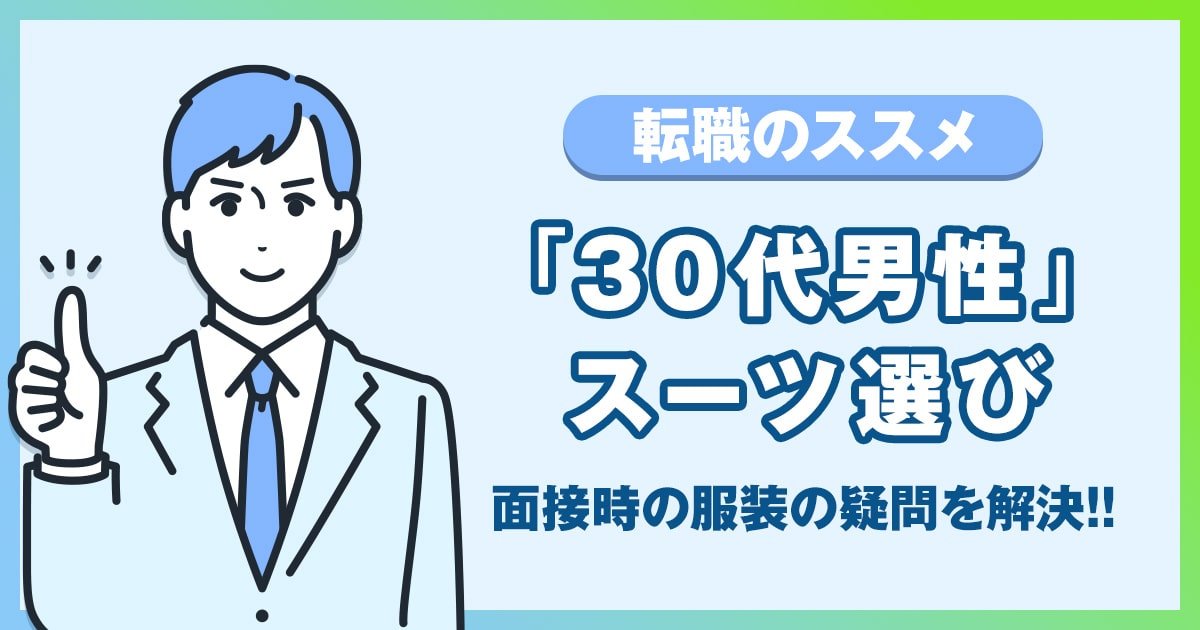-
高卒が公認会計士試験に挑戦するのは無理?
-
30代高卒が公認会計士試験に合格しても実際に就職はできる?
公認会計士は学歴不問で挑戦できる国家資格ですが、高卒の方にとっては試験の難易度や就職のハードルが気になるところではないでしょうか。
本記事では、高卒の公認会計士の割合や試験の合格率、30代からの試験対策や、公認会計士を目指すメリットや試験合格後のキャリアについても解説します。
「学歴がないと厳しいのでは?」と不安に感じている方でも、しっかり準備と努力をすれば合格は不可能ではありません。
今から高収入を目指したい方や、公認会計士の仕事に関心がある方はぜひご参考ください。
30代高卒も公認会計士になれる

公認会計士は高卒や30代からでもなれる職業です。
- 公認会計士とは?
- 会計や税務に関する専門知識とスキルを活かして、企業の財務諸表の監査や税務相談などを行う職業です。
中でも公認会計士のメイン業務である監査は、独占業務(国家資格である公認会計士の有資格者しか関われない業務)であり、非常に難易度の高い仕事でもあります。
公認会計士になるためには、公認会計士試験に合格する必要がありますが、この試験は学歴や年齢、国籍を問わず誰でも受験できます。
実際、高卒で公認会計士試験に合格して活躍している人や、30代から資格取得を目指してキャリアチェンジに成功している例もあります。
ここからは、高卒者や30代の公認会計士の割合や合格率などを解説し、学歴や年齢がどの程度影響するのかを見ていきましょう。
高卒の公認会計士の割合
公認会計試験の高卒の合格者は、全体の約6.4%程度というデータが出ています。この割合から推測すると、公認会計士の約20人に1人ほどは高卒であると考えられます。
令和6年の公認会計士試験における学歴別の合格率と合格者構成比は以下です。
| 合格者学歴 | 合格率 | 合格者構成比 |
|---|---|---|
| 高校卒業 | 4.5% | 6.4% |
| 大学在学中(短大含む) | 8.8% | 37.7% |
| 大学卒業(短大含む) | 7.7% | 46.6% |
| 大学院在学中 | 8.0% | 0.9% |
| 大学院修了 | 5.6% | 3.7% |
参照元:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験 合格者調」(参照 2025-3-27)
合格者の多くは大学生もしくは大卒者ですが、これは公認会計士試験の一部科目免除が受けられる大学があることや、大学在学中に試験対策を進める人が多いことが理由として挙げられるでしょう。
また、高卒者の合格率が著しく低いわけではないことがわかります。
このように高卒者の合格率がゼロではない以上、努力次第で合格を目指せる資格と言えます。
30代の公認会計士の合格率
続いて、公認会計士試験に合格している30代の割合も見てみましょう。
令和6年の公認会計士試験における30代の合格率は以下の通りです。
| 年齢層 | 合格率 |
|---|---|
| 20歳以上25歳未満 | 9.8% |
| 25歳以上30歳未満 | 7.8% |
| 30歳以上35歳未満 | 5.1% |
| 35歳以上40歳未満 | 3.3% |
| 40歳以上45歳未満 | 1.2% |
| 45歳以上50歳未満 | 0.4% |
参照元:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験 合格者調」(参照 2025-3-27)
この表からわかるように、30代で公認会計士試験に合格している人はいます。
30代から公認会計士を目指すことは決して遅くはありません。合格者の中には社会人経験を積んだ後に挑戦した人も多く、公認会計士は30代以降でも十分に活躍できる職業です。
資格取得後のキャリアパスも計画しながら、着実に準備を進めることが成功の鍵となります。
公認会計士は学歴不問で活躍できる仕事

公認会計士に必要な国家資格は、学歴に関係なく資格を取得できます。
高卒や社会人でも挑戦できるので、実際に高卒や30代以上で合格する人もおり、年齢や学歴に関係なく活躍できる職業です。
資格取得後は監査法人や会計事務所、一般企業の経理・財務部門など、幅広い分野での就職が可能です。特に、学歴よりも実務経験やスキルが重視されるため、高卒でも十分にキャリアを築けます。
公認会計士の平均年収は746万円
公認会計士の平均年収は約746万円であり、日本の平均年収460万円と比較すると、約1.6倍の水準にあります。
このことから、公認会計士は高収入を得やすい職業の一つと言えます。特に、監査法人や大手企業の財務部門に就職すれば、年収1,000万円を超えるケースも少なくありません。
また、キャリアを積むことで収入がさらに向上する可能性があります。例えば、経験を積んでパートナー(経営層)になれば、年収2,000万円以上を得ることも可能です。さらに、独立して会計事務所を開業すれば、収入の上限はさらに広がります。
学歴を問わず挑戦できる国家資格であるため、高卒や社会人からでもキャリアアップの手段として有効です。公認会計士は努力次第で収入を大きく伸ばせる魅力的な職業です。
参考:
e-State政府統計の総合窓口「令和6年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(参照 2025-3-27)
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」(参照 2025-3-27)
公認会計士試験は30代高卒に不利なのか?

ここまで、30代高卒の方も公認会計士になれることについて解説しました。
ここでは、公認会計士試験は30代高卒にとって不利なのかを解説します。公認会計士試験の受験を考えている方は参考にしてください。
大卒より合格までの学習時間が長くなる可能性はある
公認会計士の試験問題には、大学の経済学部や法学部の履修範囲も含まれています。そのため、経済学部や法学部出身の大卒者は基礎知識がある状態で公認会計士の勉強を始められるのです。
基礎知識を学ぶ機会がない多数の高卒者は、その分だけ学習時間が長くなる傾向にあります。
そして、これは一概には言えませんが、勉強が苦手だったという高卒者は、学習に対する意欲や吸収力が大卒者と異なるケースも考えられます。「何時間もずっと勉強をするのに抵抗がある」「高校で習った範囲も含めて経済や法律の知識がまったくない」ような人にとって、公認会計士の試験勉強のハードルはかなり高いです。
このような理由から、大卒者と比較すると高卒者が公認会計士試験の学習時間が長くなる可能性があります。
高卒だと公認会計士の試験科目免除を受けづらい
高卒の場合、公認会計士の試験科目免除が受けづらい点にも注意が必要です。
公認会計士の試験は、過去2年間の間に短答式試験に合格した人や、一定の条件を満たした学歴・経歴の人は、試験内容を一部免除されるシステムがあります。
具体的には、商学・法律学関連における博士学位取得者は短答式試験を全科目免除、法科大学院修了者は短答式試験を一部科目免除など、商学・法律系の分野を大学院で学んだ人に対して試験科目が免除されます。
高卒だとこういった免除制度は利用しづらく、原則として全科目の勉強をしなければいけません。
とは言え、試験科目の免除を受けられる人は全受験者の中でも限られているので、免除を受けられないことをハンデに感じることはないでしょう。
ちなみに、税理士の資格を持っている人なども一部の科目が免除されるので、先に税理士の資格を取得している場合は、試験免除の申請を忘れずにするようにしてください。
強い意志で独学できれば学歴や年齢は関係ない
高卒者は、大卒者よりも公認会計士試験において不利になるケースがあります。とは言え、強い意志を持って頑張り続けられるなら、大卒者との差をなくすことは可能です。
公認会計士試験の基礎知識の土台が大卒者よりも不足しているケースがないとは言えませんが、大学の講義で学べる知識量と公認会計士の試験に合格するために必要な知識量はまったく違います。
基本的な大卒者と比べてもスタートラインにそこまで大きな差があるわけでもないので、最終的には学歴や年齢などは関係なく、努力し続けられる人が合格を掴み取れます。
公認会計士に向いている30代高卒の4つの特徴

30代高卒で公認会計士試験に合格できても、公認会計士としてしっかり働けるか不安な方もいるのではないでしょうか。
ここでは、公認会計士に向いている人の特徴を解説します。
数字が好きで長時間集中して取り組める
公認会計士の仕事は、細かく数字をチェックしたり計算したりすることが欠かせません。そもそも数字が苦手な人には不向きな職業なので、長時間集中して数字のチェックや計算に取り組める人ではないと、公認会計士を続けるのは難しいでしょう。
また、公認会計士は書類の作成やチェックなどといった地道な作業が多く、基本的にミスは許されません。作業の正確性も求められることから、細かい作業にコツコツと取り組める人や慎重な人は、公認会計士として活躍できる可能性が高いです。
正義感が強くやり遂げる力がある
公認会計士には、中立的に考えられる正義感の強さが求められます。企業の不正を見つけたらしっかりと指摘ができる勇気や責任感がある人は、公認会計士として適性があります。
また、難しい監査やイレギュラーな対応を求められるケースがあっても、最後まで投げ出さずにやり遂げる意志の強さや対応力も必須の職業です。
仕事のために学び続けられる
公認会計士は難関資格であり、膨大な試験範囲を勉強する必要があります。そして、試験に合格すれば勉強を終われるというわけではありません。
公認会計士試験に合格後も、仕事のために勉強し続けることが必要不可欠です。会計に関する法律は常に改定を繰り返しており、改定されるたびに新しい知識を学び直さなければなりません。
将来的にもずっと学び続ける意欲がある人でないと、公認会計士として働き続けるのは難しいでしょう。
コミュニケーションをとることが得意である
公認会計士は数字と向き合う仕事であると同時に、人と関わることも多い仕事です。企業へのヒアリングやアドバイスなどが業務に含まれており、同じ職場内だけではなくさまざまな立場の人と話す機会が多いので、コミュニケーション能力は必須です。
また、独立開業した場合は、集客のために営業力も求められます。コミュニケーションが得意だと、公認会計士として活躍できるチャンスが広がります。
30代高卒が公認会計士になる5つのメリット

30代高卒が公認会計士の資格を取得することには、下記のように多くのメリットがあります。
- 平均年収が600万円以上にアップする可能性がある
- 不景気による煽りを受けにくい
- 社会的な信用を得られる
- 需要が高く有資格者のみの独占業務もある
- いろいろな企業や人とつながりが持てる
特に、収入の向上や社会的信用の獲得、安定した需要などは魅力を感じる人が多いのではないでしょうか。
30代高卒が公認会計士になることで得られる5つのメリットについて詳しく解説します。
平均年収が600万円以上アップする可能性がある
公認会計士の平均年収と高卒者全体の平均年収は以下の通りです。
- 参考
- 【公認会計士の平均年収】
・中小企業(企業規模5~9人):約562万円
・大企業(企業規模1,000人以上):約1,044万円
【高卒の平均年収】
・約433万円
全業界・職種における高卒者全体の平均月収は約28.9万円なので、年間賞与3か月分と仮定すると、平均年収は約433万円です。公認会計士として大企業に勤められれば年収が600万円以上高くなる可能性があります。
公認会計士になるまでは非常に難易度が高いものの、年収が大きく上がる可能性が高いので、努力する価値はあるでしょう。
参考:
e-State政府統計の総合窓口 「令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 企業規模5~9人」(参照 2025-3-27)
e-State政府統計の総合窓口「令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」(参照 2025-3-27)
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(参照 2025-3-27)
不景気による煽りを受けにくい
公認会計士は、景気の影響を受けにくい職業の一つです。
公認会計士が携わる監査業務や税務業務は、企業の経営状況に関わらず法律で実施することが義務付けられているため、景気が悪化しても業務が大幅に減ることはありません。
むしろ、不況時に企業の経営が悪化すると、税務対策や財務改善の専門知識を持つ公認会計士の需要はむしろ高まります。
また、公認会計士は難関国家資格の一つであり、誰もが簡単に取得できるものではありません。そのため、有資格者の数が限られており、景気が悪化しても職を失うリスクは低いです。
さらに、独立開業すれば、企業だけでなく個人事業主や資産家の顧問業務も担うことができ、幅広い収入源を確保できるので、臨機応変に動ければ収入を安定させやすいと言えます。
社会的な信用を得られる
公認会計士は高度な専門知識と実務経験が求められる難関資格を取得する必要があるので、学歴に関係なく高い社会的信用を得ることができます。
特に、財務や税務の分野では公認会計士の意見が重視されるため、企業経営や金融機関との取引といった場において信頼されやすいです。
また、公認会計士は有資格者しか担当できない「独占業務」を持つ国家資格であり、監査やコンサルティング業務を通じて重要な意思決定に関わる機会も多いです。そのため、企業の経営者や投資家からの評価も高い職業と言えるでしょう。
さらに、公認会計士としてのキャリアを積めば、独立開業や経営幹部としての道も開けます。
需要が高く就職先の選択肢が幅広い
公認会計士は、幅広い選択肢の中から自分らしい働き方を選べるのも大きな魅力です。
公認会計士の資格は「三大国家資格」と呼ばれるほどに高難易度の資格であり、資格を持っているだけで希少価値が高く、優秀な人材だとみなされます。
また、公認会計士が携われる監査業務は、公認会計士の有資格者しか担当できない独占業務です。専門職でもあるため、資格を取得できれば全国どこでも活躍できる可能性が高くなります。
そんな資格を持っているからこそ、公認会計士は需要が高く、監査法人だけではなく民間企業への転職や独立などさまざまな進路があります。
公認会計士はなり手が少ないからこそ人手不足の傾向があるため、就職や転職に困りにくいというメリットがあるのです。
いろいろな企業や人とつながりが持てる
公認会計士は大企業とのつながりを持てることも魅力の一つです。
高卒で特定の企業に勤める場合は、関わることができる企業や人は限定されがちです。しかし、公認会計士になると大企業や社外の多様な職種の人と関わりを持てるので、人脈づくりにも役立ちます。
後に独立したり転職をしたりするときにも、幅広い業界の人脈はかなり重要になります。有益な経験を積みながら多くの人とのつながりを持ちたい人にとって、公認会計士はぴったりな仕事です。
30代高卒が公認会計士になる3つのデメリット
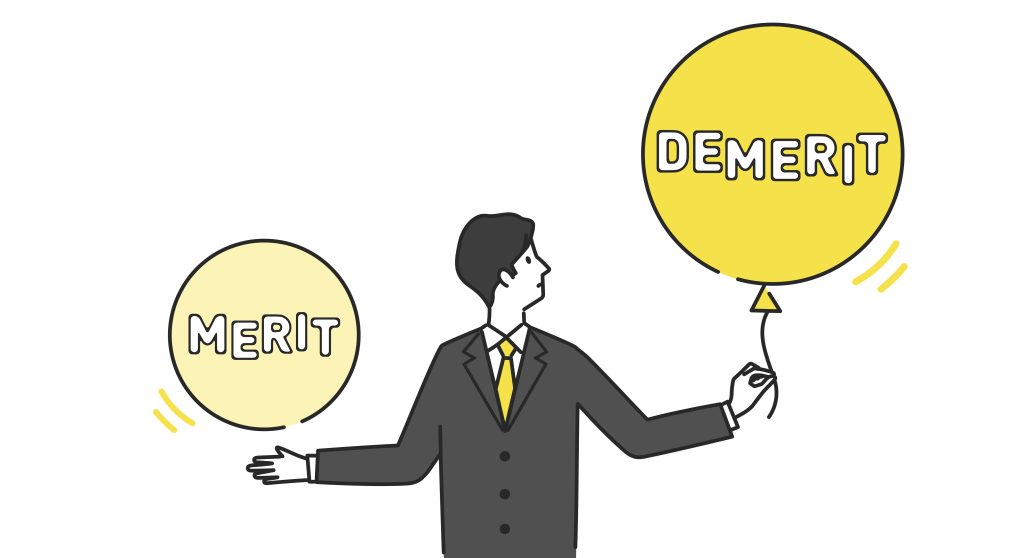
30代高卒で公認会計士になると大きなメリットがあることがわかりました。しかし、30代高卒から公認会計士を目指す場合、デメリットもあります。
- 資格取得の難易度が高い
- 30代高卒以上は就職が厳しい可能性がある
- 市場の変化などで将来的に需要が低くなる可能性がある
メリットだけではなくデメリットについても理解して、公認会計士を目指すかを今一度考えてみましょう。
資格取得の難易度が高い
公認会計士は、合格までに3,500時間以上の勉強時間が必要だとも言われています。2〜3年で合格する目標を立てたとしても、毎日3〜5時間以上勉強しなければならない計算です。
そのため、資格の勉強に長期間費やせる忍耐力や経済的な余裕があり、また勉強そのものがある程度得意でないと、公認会計士に合格することは難しいでしょう。
高卒に限った話ではありませんが、試験勉強に費やせる時間的・経済的余裕がないのであれば、まずは試験勉強に集中できる環境を整備する必要があります。
30代高卒以上は就職が厳しい可能性がある
公認会計士合格の平均年齢は24〜25歳です。そのため、30代で合格した場合は20代と比べて就職が厳しくなるケースもないとは言えません。
転職者のキャリア形成や研修のしやすさなどを考えて、同じような条件であればより若い人材を採用する企業が多いのは事実です。
年齢を重ねていくにつれて就職が厳しくなる可能性が高まったり、記憶力が衰えたりするので、公認会計士試験を受けるならできるだけ早い段階での挑戦・合格を目指しましょう。
ただし、公認会計士の資格取得には年齢制限はありません。就職活動の対策をしっかりすれば30代高卒の方も公認会計士として働ける可能性はあるため、スタートが遅い場合でも諦めずに挑戦してみてください。
参考:公認会計士・監査審査会「過去の試験結果等」(参照 2023-12-25)
市場の変化などで将来的に需要が低くなる可能性がある
現在、公認会計士の需要は非常に高いですが、将来的に市場の変化や技術の発達によって需要が減少するおそれがあります。実は公認会計士はAIの発展などで仕事がなくなるかもしれないと言われている職業の一つでもあるのです。
公認会計士試験に合格するまでに費やす時間は膨大です。
そのため、「何年も勉強しているうちに環境が変わる可能性がある」「公認会計士でも一生安泰な職業ではない」ということを理解し、将来的に公認会計士を取り巻く状況が変わった場合にも上手く立ち回れるように準備しておく必要もあります。
高校卒業から年齢を重ねて一念発起して人生を一発逆転させたいと考えている方は、特に忘れてはならない点と言えます。
公認会計士の主な業務内容

30代高卒の方も公認会計士を目指せることについてお話してきましたが、そもそも公認会計士の業務内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは、公認会計士の基本的な業務内容を解説します。公認会計士の具体的なイメージをつかむ意味でも参考にしてみてください。
監査業務
公認会計士の監査業務とは、企業が作成した財務諸表が法令に則った内容か、数値が正確かといった点をチェックする仕事です。監査業務は公認会計士の有資格者しかできない独占業務に定められています。
投資家にとって、各企業が出す貸借対照表・損益計算書・利益処分計算書・附属明細表などの財務諸表は、投資の大事な判断材料です。正確性が欠けていると投資家が損失を被るだけではなく、企業側も信頼喪失や株価暴落、利害関係者との関係悪化などのおそれがあります。そういったデメリットを回避するために公認会計士が監査業務を行うことで、企業の経営活動の正当性を保証しているのです。
上場企業のほか、学校法人・社会福祉法人・医療法人・独立行政法人などでも、法令で監査が義務づけられています。
税務業務
税務業務とは、企業や個人に代わって法人税や所得税、消費税などの各種税務にかかわる書類を作成したり、税務処理をしたりする仕事です。また、企業から税務に関する相談を受けてアドバイスすることも税務業務に含まれています。
公認会計士は所定の研修を受ければ税理士の登録も可能になるため、就職先で税務業務を担当する人も多いです。
コンサルティング
公認会計士が行うコンサルティングとは、経営戦略や経営計画、組織再編といった企業の経営全般にわたる悩みや課題を解決に導けるようにアドバイスする仕事です。
特に上場企業は、従業員や顧客、株主をはじめ多数の利害関係者が関わっています。それらの利害関係者と良好な関係を築くために、監査や会計のプロである公認会計士に経営のアドバイスを求める企業は少なくありません。
公認会計士試験の内容は2種類

ここでは、公認会計士試験の概要を解説します。
公認会計士試験では、短答式試験と論文式試験の両方に合格する必要があります。試験範囲が膨大で、なおかつ論文式の試験もあるので、独学だけで合格するのはかなり難しい試験です。
また、明確な合格点はなく、「総点数に対して一定の点数比率を満たす、かつ答案提出者内での相対評価」で合否が決まるのが特徴です。
ここでは、短答式試験と論文式試験のそれぞれの概要を解説します。
短答式試験
公認会計士試験の短答式試験では、監査や会計などの基本的な専門知識を幅広く理解しているかどうかを問われます。
短答式試験に合格しないとその先の論文式試験は受けられません。しかし、短答式試験に合格すると、以後2年間は短答式試験が免除されて論文式試験から受験できるシステムがあります。
| 実施時期 | 第1回:12月上旬~中旬 第2回:5月下旬 |
| 試験形式 | マークシート形式 |
| 試験科目 | ・財務会計論 ・管理会計論 ・監査論企業法 |
| 合否 | 総点数の70%以上が目安 |
参照元:公認会計士・監査審査会「公認会計士試験に関するQ&A」(参照 2023-12-25)
合格点は総点数の70%以上が目安で、公認会計士・監査審査会が「相当」と認めた得点比率となります。1科目でも満点の40%に満たない場合や、答案提出者の下位33%の人の得点比率に満たない場合は不合格となる可能性があります。
論文式試験
公認会計士試験における論文式試験は、監査や会計などの専門知識の理解に加え、実践的な思考力や判断力、応用力が問われる試験です。また、試験は3日間にわたって行われます。
| 実施時期 | 8月下旬に3日間 |
| 試験形式 | 論述形式の筆記試験 |
| 試験科目 | 【必須科目】 ・会計学(財務会計論・管理会計論) ・監査論企業法租税法 【選択科目(いずれか1つ)】 ・経営学経済学民法統計学 |
| 合否 | 総点数の52%以上が目安 |
参照元:公認会計士・監査審査会「公認会計士試験に関するQ&A」(参照 2023-12-25)
論文式試験の合格基準は総点数の52%以上が目安となっており、短答式試験と同じく審査会が「相当」と認めた得点比率を満たしている必要があります。また、1科目でも得点比率が40%に満たない科目があった場合は、不合格となる可能性が高いです。
30代高卒で公認会計士を目指す方法

30代高卒で公認会計士を目指すには、独学で勉強する方法と、資格専門学校に通う方法があります。
ここではそれぞれの方法について、メリットとデメリットに触れながら解説していきます。
独学で資格取得を目指す
独学は自分のペースで勉強できる点や、資格専門学校に通うよりも学習費用を抑えられ、経済的な不安を感じずに勉強できる点が魅力です。
ただし、公認会計士試験は合格までの勉強時間の目安が約3,500時間と言われており、なおかつ学習範囲も広範囲にわたるため、一人での勉強だとモチベーション維持が大変です。わからない部分があっても有識者に質問できず、勉強の効率が落ちてしまう可能性も出てきます。
一人でやってみて独学では難しいと感じたら、通信教育を始めるのも一つの方法です。通信教育なら「自分のペースで学べる」「学習費用を抑えられる」という独学のメリットを得ながら、「わからない問題を解決することが難しい」というデメリットを補えます。
資格専門学校で資格取得を目指す
公認会計士の資格取得を目的にした専門学校は全国にあります。
公認会計士試験は長期にわたる学習が必要ですが、資格専門学校に通えば生徒同士の交流や講師による授業によってモチベーションを維持しやすくなります。また、わからない問題はすぐに講師に聞くことができるのも大きなメリットです。
ただし、受講料がかかるため、経済的に余裕がないと入学が難しい傾向にあります。通学と仕事の両立も難しくなるので、時には現職を退職しなければいけない場合も出てきます。
可能な限り今の環境で通いやすい学校を探すようにしましょう。
また、基本的には生徒数が多く、合格者を多く輩出している専門学校がおすすめです。
公認会計士の合否基準は絶対評価ではなく相対評価であり、資格専門学校に通っている間から自分の相対的な立ち位置を見極めることが重要だからです。生徒数が極端に少ないと母数が少なくなり、自分の立ち位置を知るのが難しくなるおそれがあります。
公認会計士を目指す方法別のメリット・デメリットまとめ
公認会計士試験に挑戦する各方法のメリットとデメリットは下記の通りです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 独学 | ・自分のペースで学べる ・学習費用を抑えられる ・通信教育と併用しやすい | ・モチベーション管理が大変 ・わからない問題を解決しづらい |
| 資格専門学校 | ・モチベーションを維持しやすい ・学校に通うことで仲間ができる ・わからない部分を講師に質問できる | ・独学よりも費用がかかる ・通学と仕事との両立が難しい |
どちらにもメリット・デメリットはあります。相当の学習時間と学び続ける努力が必要なのはどちらも変わらないので、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
30代高卒が公認会計士になるための準備

30代高卒が公認会計士を目指すために準備しておくべきことをまとめました。
やみくもに勉強を始めるのではなく、まずはしっかりと環境を整えることが大切です。
公認会計士試験について情報収集する
まずは、資格試験の勉強に必要な期間や勉強方法、資格取得後の就職先のリサーチなど、公認会計士になるための全体像を把握しましょう。全体像がわかれば、公認会計士試験に挑戦するための具体的な計画を立てやすくなります。
とりあえず資格専門学校に入学したり参考書を買ったりするのではなく、公認会計士試験について情報収集をして、いつまでに試験に合格するか、合格後にどこに就職して最終的にどうなりたいのかといった目標を立て、目標から逆算して今何をするべきかを見極めてください。
自分に合う参考書を選ぶ
試験勉強をする際は最初から難しいテキストを選ぶと理解しづらく、挫折するリスクが高まります。独学なら初心者向けのテキストから少しずつステップアップできるように、段階を踏んで勉強しましょう。
簿記や会計の初心者向けのテキストなども売っているので、まずはどんなテキストがあるのかを調べて、自分の理解度に合ったものを選ぶことがコツです。
ライフスタイルに合う勉強方法やペースを見つける
ライフスタイルや自分の性格などによって効率の良い勉強方法は変わるので、自分なりの勉強方法をできるだけ早く見つけることが重要です。
公認会計士試験は長期にわたる学習となり、自分に合った勉強方法でないとモチベーションを維持できず、いずれ挫折してしまうリスクがあります。
数ヶ月ではなく長期間勉強を続けていくと考えて、自分にとって独学がいいのか、専門学校がいいのかなどを判断することが大切です。
息抜きの方法を見つける
公認会計士試験は難関資格であり、たゆまぬ努力が必要です。しかし、勉強のみの生活ではモチベーション維持が難しくなっていくのも事実です。
適度に気分転換できる趣味やストレス発散方法を見つけることも、合格まで走り続けるうえで大切です。
とは言え、気分転換やストレス発散に時間をかけすぎては本末転倒なため、あくまでも勉強のモチベーションを保つためのものと割り切って短時間で楽しめるような方法を見つけると良いでしょう。
生活費や勉強代のためにお金を貯める
公認会計士試験の勉強に集中するために仕事をやめて無職やフリーターになるなら、生活費や通学資金などをあらかじめ貯める必要があります。お金が足りないまま公認会計士試験の勉強に専念すると、すぐに勉強を続けられなくなったり、心配のあまり勉強に手が付かなくなったりしかねません。
現時点でお金の心配があるなら、短期間で高収入を目指せる仕事やアルバイトに転職することも有効です。
特に、ナイト系の仕事なら学歴を問わず頑張り次第ですぐに稼げるチャンスがあるほか、シフトを自由に入れて短期間・短時間だけ働けるアルバイトの求人も豊富なので、公認会計士試験の勉強との両立も可能です。
ナイト系の仕事は「短期間でお金を貯めて公認会計士試験に専念したい」「アルバイトと勉強を両立したい」という方にぴったりと言えます。
就職面接の対策も入念に行う
公認会計士になるためには、資格取得がゴールではありません。合格しても就職できないと意味がないため、資格取得後は就職面接の対策もしっかりと行う必要があります。
特に、公認会計士試験の勉強に専念した結果フリーターや無職になった期間があると、なぜ空白期間があるのかを面接にて高確率で問われます。
30代高卒の方は空白期間がネックになりやすいので、「受験のために無職やフリーターになった」など、理由を明確に説明できるよう準備しておくことがポイントです。
また、面接のマナーも事前にしっかり押さえて落ち着いて面接に望んでください。
公認会計士試験に合格したあとの流れ

公認会計士試験に合格しても、すぐに資格を取得できるわけではありません。
公認会計士試験に合格した後の流れは以下の通りです。
- 公認会計士試験に合格した後、就職活動を始める
- 合計2年以上の実務経験を積む
- 実務補習所に3年間通学する(※実務要件を満たしている場合は期間を短縮できる)
- 実務補習所の卒業試験に相当する修了考査に合格する
- 公認会計士登録の要件を満たしていることを示す書類を提出し、登録審査会の審査を受ける
公認会計士になるには、公認会計士名簿への登録(開業登録)および日本公認会計士協会への入会が義務付けられています。
公認会計士名簿への登録には、一定期間の間実務経験を積み、実務補習所へ通学したりした後に修了考査で合格しなければいけません。
実務補習所の修了考査は合格率が約70%とされており、不合格の場合はさらに1年間通学することになります。また、公認会計士の登録には約15万円の費用がかかり、登録後の年会費も約13万円が必要です。
こうした要件をクリアすることで、正式に公認会計士として活動できるようになります。
30代高卒の公認会計士の就職先4選

公認会計士試験に合格したとして、そもそも30代高卒で就職先が見つかるのかと疑問が生じている方もいるでしょう。
結論から言えば、30代高卒から公認会計士になった場合でも就職先を見つけることは可能です。代表的な就職先をご紹介していきます。
①9割は監査法人に就職
監査法人とは、第三者として企業の会計監査を行う機関です。設立には5名以上の公認会計士が社員として在籍していることが求められます。
監査法人の社員は全員が出資者かつ業務執行権を持っているので、一人ひとりが株式会社の取締役・役員クラスといった立ち位置であることが特徴です。
また、監査法人は新人の公認会計士の養成にも関わることができる組織でもあります。そのため、公認会計士試験の合格者の9割近くは、まずは監査法人に入って実務経験を積みます。
監査法人によって規模は異なりますが、大手監査法人と中堅や中小の監査法人は働くうえで下記の違いがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 大手監査法人 | ・大手顧客に対して複数の公認会計士が協力して業務にあたることができる | ・英語力が必要なことが多い ・分業体制の傾向にあるので、監査業務の全体に関わりづらい |
| 中堅や中小の監査法人 | ・いろいろな業界の監査に関わる機会が多く、幅広い経験を積める | ・大手監査法人と比べると給料が低い傾向にある |
監査法人に就職する際には、給料と経験のどちらを重視するか考えるのがポイントです。
ちなみに、4大監査法人(BIG4)として知られる大手監査法人の「有限責任あずさ監査法人」「有限責任監査法人トーマツ」「EY新日本有限責任監査法人」「PwCあらた監査法人」は、公認会計士の就職先として特に有名ですが、未経験から就職するのはかなり難しいです。しっかりと実務経験を積んでから転職活動で狙ってみるのも手です。
②民間企業の経理・財務部門に就職
民間企業に就職し、企業内会計士(インハウス会計士)として活躍する道もあります。
企業内会計士は自社の日々の売上や仕入れの管理、税金の計算、決算書の作成といった業務を行うことが多いです。また、社員の給与や保険の管理・計算といった業務を担当する場合もあります。
企業内会計士は経理実務に幅広く携われるのでやりがいを感じやすく、また入社する企業によっては充実した福利厚生と安定性があるのがメリットです。
上場企業や他にまだ会計の専門家が在籍していないことが多いベンチャー企業の場合は多様な会計業務を行う必要があるため、特に公認会計士が重宝されやすいです。
③会計事務所に就職
会計事務所に就職する場合は、顧客である企業や個人に代わって税務申告や経理処理といった業務を行います。定期的に顧客のもとへ訪問し、会計データをチェックしたり、月次・年次の会計処理を担当したりするほか、経験を積めば経営コンサルティングを任される場合もあります。
会計事務所は、監査法人ではなかなか経験を積みにくい会計実務や税務申告の業務を自分で経験できるので、その後のキャリアに幅を持たせられるのがメリットです。
ちなみに、「会計事務所」には「会計士事務所」「税理士事務所」があり、公認会計士が所属していない税理士事務所の場合は監査業務ができないので注意しましょう。
参考:SMC税理士法人「「会計事務所」「会計士事務所」「税理士事務所」「税理士法人」いろいろ呼び名があるけど、どう違うの?」(参照 2023-12-25)
④経験を積んで開業登録後に「独立」も可能
実務経験を積んで公認会計士として開業登録をすれば、独立することも可能です。
独立すると自分で仕事を選べるようになるので、税務業務やコンサルティング業務など、自分の得意分野だけに集中できるメリットがあります。また、自分の裁量で仕事を受注できるのでワークライフバランスを整えやすくなったり、経営が軌道に乗れば収入がアップしたりするといった可能性も出てきます。
ただし、開業したものの営業力不足や実力不足などで思うように仕事がとれず、再度就職し直すケースもないとは言えません。また、大企業の監査は有名監査法人が担当することが多いので、大きな案件に携わる機会が減ってしまうといったデメリットもあります。
そのため独立開業は、自由に仕事を選びたい人や、経営知識が豊富な人、顧客獲得のために努力できる人でないと後悔してしまうケースがあるという点には注意しましょう。
30代高卒でも努力次第で公認会計士になれる!

公認会計士は学歴不問で挑戦できる国家資格であり、30代高卒でも努力次第で取得が可能です。
試験の難易度は高く、大卒者に比べて合格までの学習時間が長くなる傾向がありますが、正しい勉強方法を選び、計画的に取り組めば合格は十分に目指せます。
公認会計士になることで、平均年収を大きくアップさせられる可能性があるほか、不景気の影響を受けにくく、社会的信用も高まります。また、監査業務や税務、コンサルティングなど幅広い仕事に携わることができ、キャリアの選択肢が広がるのもメリットです。
さらに、独立開業すれば自分のペースで仕事ができるため、将来的なキャリアの自由度も高まるでしょう。
おさらいとして、これから公認会計士試験を目指す方は下記のポイントを意識して勉強するのがおすすめです。
- 公認会計士試験について情報収集する
- 自分に合う参考書を選ぶ
- ライフスタイルに合う勉強方法やペースを見つける
- 息抜きの方法を見つける
- 生活費や勉強代のためにお金を貯める
- 就職面接の対策も入念に行う
30代高卒からでも、確実な努力と計画的な学習を積み重ねれば、公認会計士としての道を切り開くことができるので、諦めずに挑戦していきましょう。