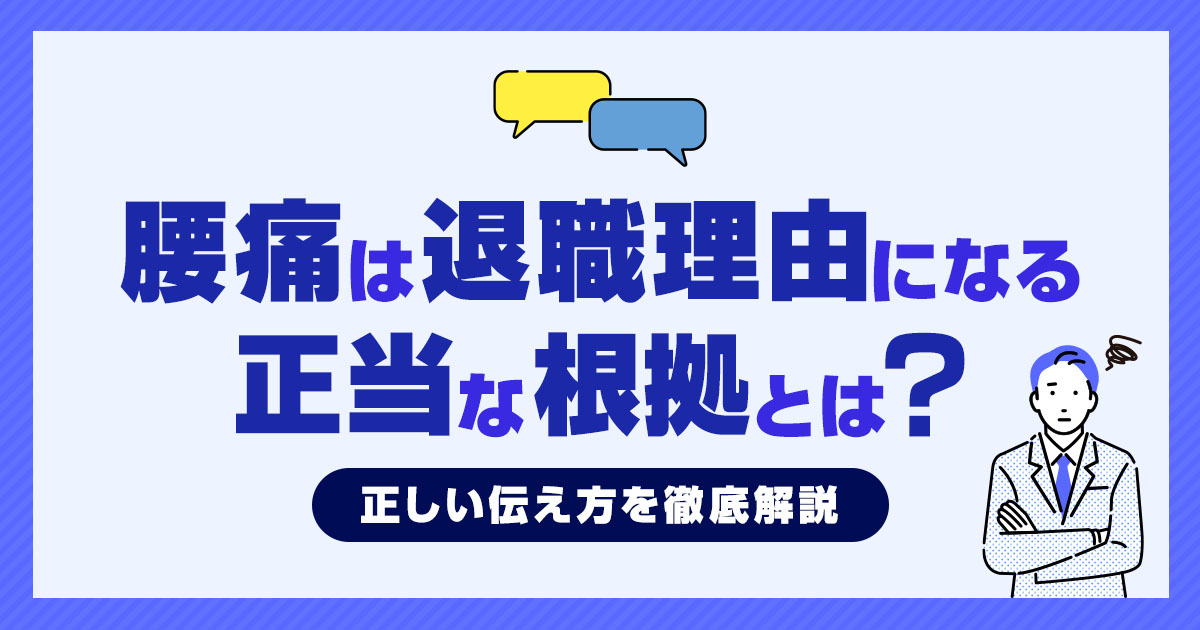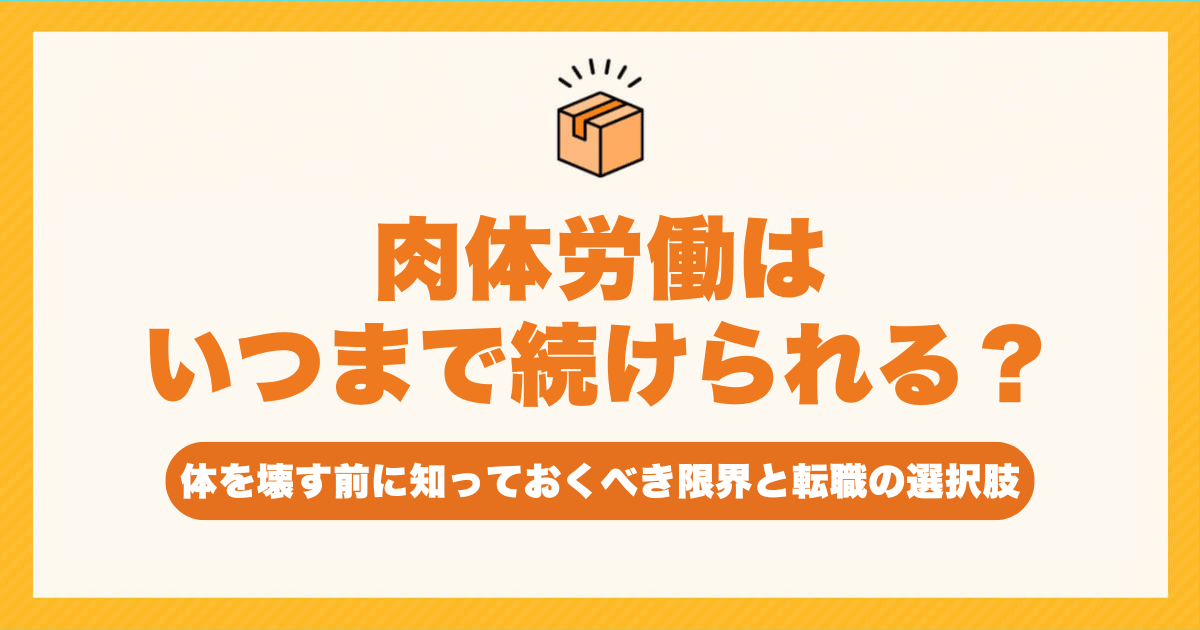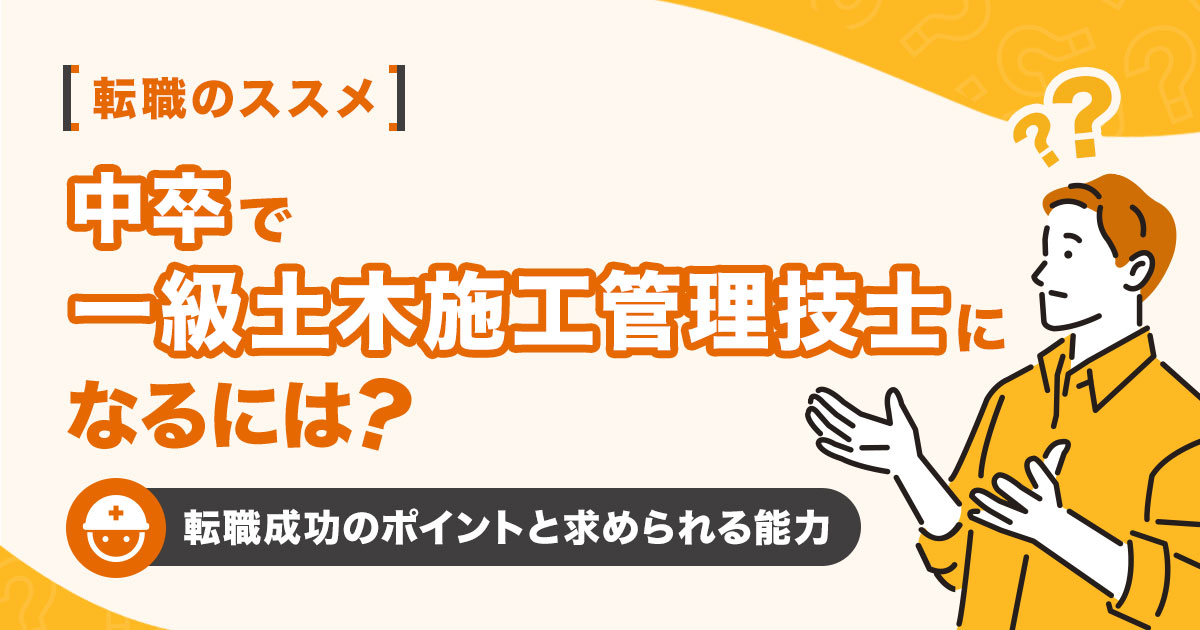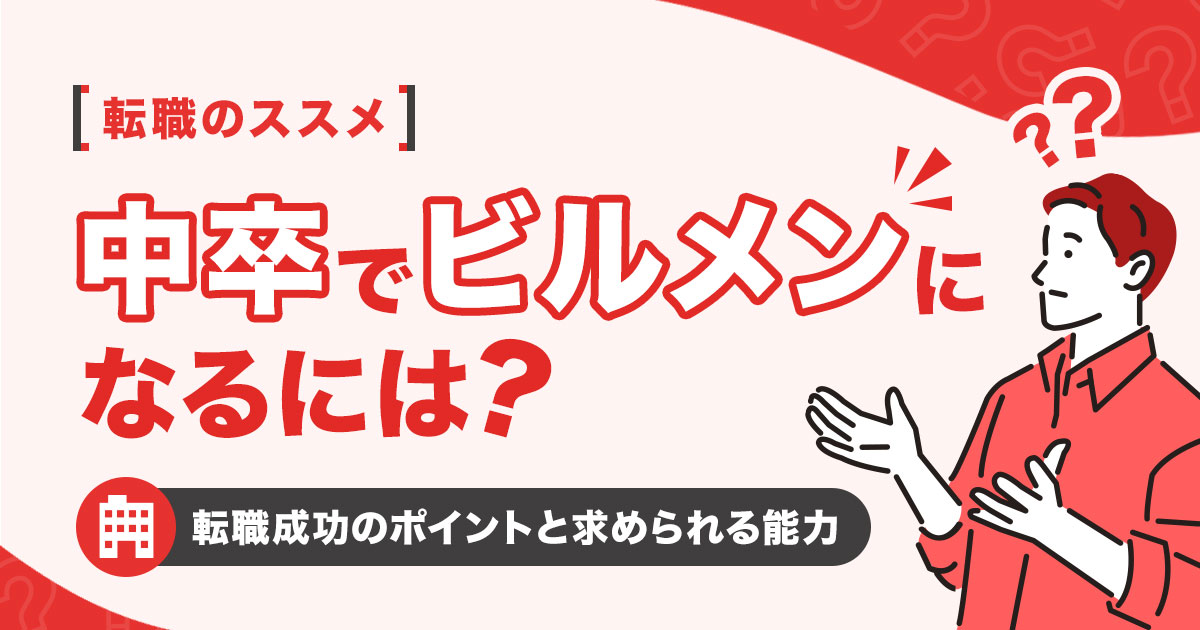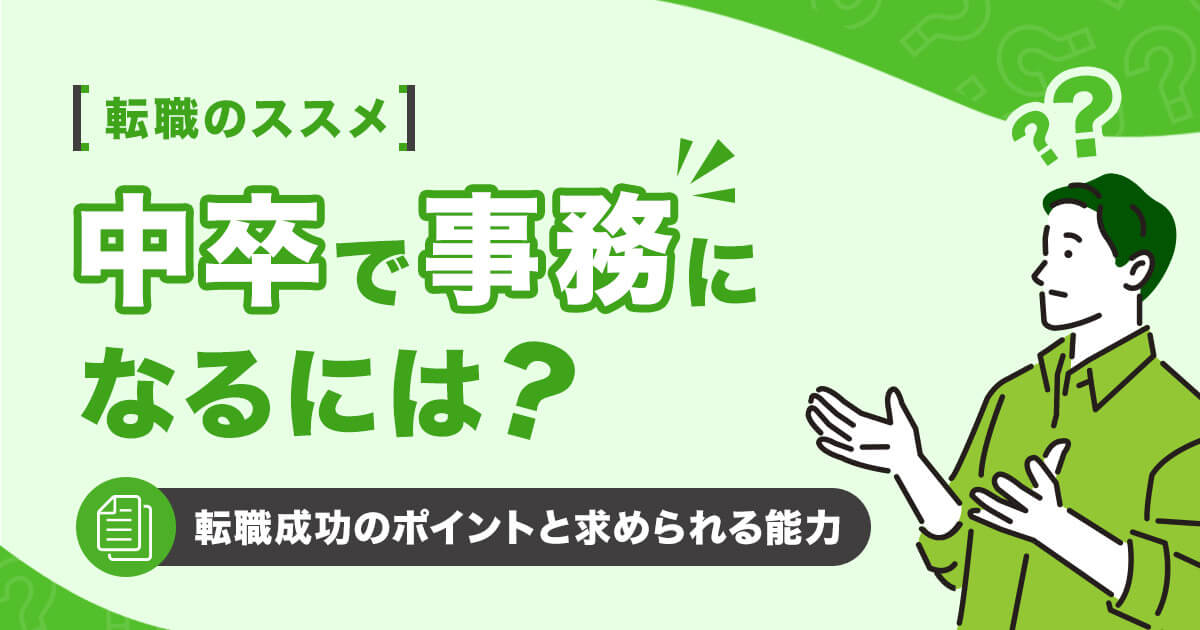-
腰痛は退職理由として認められる?
-
腰痛を理由に退職するときはどのように伝えればいいの?
慢性的な腰痛があると、仕事を続けるのがつらくなり、退職を考えるのも自然なことです。
結論からいうと、腰痛は退職理由として正当に認められます。体調や健康上の理由は、会社側も無視できない正当な事情だからです。
本記事では、腰痛が退職理由になる根拠や退職の伝え方、注意点などを解説します。
さらに、腰への負担が少ないおすすめの転職先についてもご紹介します。今後のキャリアを考える上で、ぜひ参考にしてください。
腰痛が退職理由として認められる理由
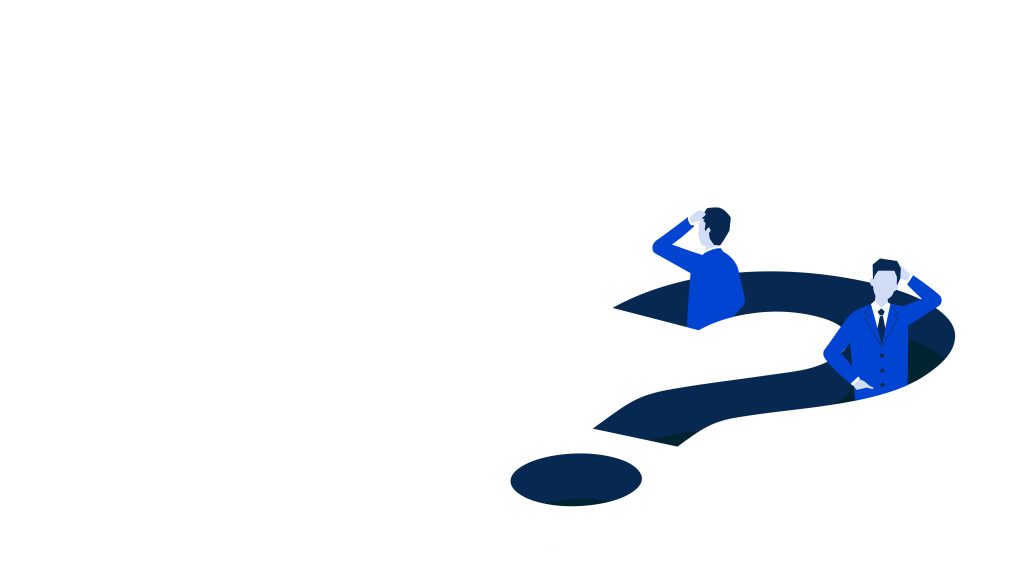
腰痛を理由に退職することに引け目を感じる方もいるかもしれませんが、腰痛は退職理由として認められます。
ここでは、その正当な根拠について解説します。
日本で腰痛に悩む人は約2,800万人
慢性的な腰痛で仕事を続けるのが困難な場合、健康上の正当な理由として退職が認められます。
日本全国で腰痛に悩む人は約2,800万人にのぼり、決して「自分だけの悩み」ではありません。腰痛に悩む人の年代は20代から50代まで幅広く、若い世代でも発症する身近な症状です。
また、腰痛は「職業病」の代表例ともいわれています。特に、介護職や看護職といった重いものを持つ頻度が高い仕事や、デスクワークや長距離ドライバーといった長時間同じ姿勢を保つ仕事は、腰痛を発症しやすい傾向にあります。
こうした環境で働き続けると治療に専念できず、退職を決意するケースも少なくありません。
参考:四国こどもとおとなの医療センター「腰を守るために、腰痛の予防と治療」(参照 2025-08-05)
健康経営トータルサービス「vol.40悩んでいる人も多い「腰痛」」(参照 2025-08-05)
医師から生活・就労継続困難と診断が下る場合がある
腰痛の症状によっては、医師から「生活や仕事を続けるのが難しい」と診断される場合があります。
腰痛を我慢した状態で仕事を続けると、適切な治療を受けていたとしても症状が悪化する可能性も考えられます。腰痛が悪化すれば、仕事において集中力やパフォーマンス力が低下し、思うように業務が進められなくなるでしょう。
また、腰痛の悪化により心身の負担も増大し、日常生活を送ることもままならなくなるかもしれません。
このように、腰痛が原因で心身ともに支障をきたした結果、医師から仕事を続けるのが困難という診断が下り、そのまま退職を決断するパターンも少なくないのです。
参考:健康創造都市KOBE推進会議「腰痛がもたらす影響とその対策とは!」(参照 2025-08-05)
労働基準法・安全配慮義務の観点からも正当性がある
腰痛を理由に退職するのは、労働基準法や安全配慮義務の観点からも正当です。
仕事が原因で腰痛を発症し、労働環境の改善が難しい場合は退職理由として正当に認められます。たとえば、以下のような状況が挙げられるでしょう。
- 特定の業務を担える人材が限られていることから、他の部署への異動が難しい
- 「自分の体に合ったデスクや椅子に変える」「腰の負担が少ない業務への配置転換」といった要望が通らない
腰痛の根本的な原因を解消するのが難しい職場環境の場合、上司や同僚に相談したとしても適切な解決策を見出せない可能性があります。
現状のまま働き続けると体を壊す可能性があるため、改善が見込めない場合は早急に退職を検討しましょう。
腰痛を理由に退職する前に確認すべきポイント

腰痛の原因が仕事だった場合、発症の経緯によっては労災認定が受けられるケースもあります。
せっかく積み上げてきたキャリアを無駄にしないためにも、退職を決める前に以下の3つを確認しておきましょう。
会社に診断書を提出して症状を理解してもらえるかどうか確認する
腰痛が慢性的に続いている場合は、病院で診察を受け、医師から診断書をもらうのがおすすめです。診断書があれば、退職理由の裏付けになるだけでなく、会社に腰痛の深刻さを理解してもらいやすくなります。
退職がスムーズに進みやすくなるだけでなく、退職を選ばなくても「腰に負担の少ない部署に異動」などの配慮を受けられる可能性があります。
退職を決意している方もそうでない方も、まずは病院で医師に腰痛の症状を診てもらい、会社に診断書を提出するのが得策です。
ただし、すべての会社が必ずしも適切に対応してくれるとは限りません。
提出後の反応を見て、次のステップを考えましょう。
腰痛が労災認定の対象か確認する
腰痛が仕事由来のものであれば、労災認定を受けられる可能性があります。
厚生労働省は腰痛を次の2種類に分け、認定要件を定めています。
| 災害性の原因による腰痛 | 負傷などによる腰痛で、次の①、②の要件をどちらも満たすもの ①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること ②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること |
| 災害性の原因によらない腰痛 | 突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの |
参考:厚生労働省「腰痛の労災認定」(参照 2025-08-06)
腰痛が労災として認定されると、治療費を負担してもらえる「療養(補償)給付」や腰痛の治療・療養を理由に仕事を休んだときに賃金が補償される「休業(補償)給付」などが受けられる可能性があります。
ただし、腰痛が労災認定されるかどうかは、会社の判断に委ねられます。
厚生労働省が定める認定要件を満たしているのにもかかわらず会社が認めない場合は、「労災隠し」という違反行為に該当するので、労働基準監督署や労働局に相談しましょう。
会社の安全配慮義務違反を確認する
腰痛が労災として認定された場合、会社に安全配慮義務違反があれば、損害賠償を請求できる可能性があります。
- 安全配慮義務とは
- 従業員が安全かつ健康に働けるように、会社が職場環境の整備や安全管理など必要な配慮をする義務を指します。厚生労働省が定める「職場における腰痛予防対策指針」に準じて腰痛予防の対策を実施していなければ、会社に対する安全配慮義務違反が認められる傾向にあります。
▼「職場における腰痛予防対策指針」に記載されている対策例
・機械による作業の自動化や台車などの道具を使用して作業者の負担を減らす
・腰に過度の負担がかかる作業は極力一人で行わない
・6カ月以内に1回、医師による腰痛の健康診断を実施する
・上司や同僚からのサポートを受けながら腰痛で休みやすくする環境づくりを行う
参考:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(参照 2025-08-26)
会社の安全配慮義務違反が認められた場合、退職する前に損害賠償を請求できないか検討することも一つの手です。
腰痛を理由にした退職の正しい伝え方

腰痛を理由に退職する場合、会社への伝え方はとても重要です。
退職の意思は、できるだけ直接会って伝えるのが基本ですが、体調的に出社が厳しい場合はメールや電話でも問題ありません。
医師に腰痛の診断書を発行してもらうとよりスムーズに退職しやすくなりますが、診断書がなくても可能です。
また、今後も同じ業界に携わりたいのであれば、なるべく円満に退職するのが得策です。会社に対して感謝の気持ちを伝えることで、より円満に退職しやすくなります。
ここでは、対面・メール・電話の3つのパターンについて、腰痛を理由にした退職の正しい伝え方をご紹介します。
対面で伝える場合
対面で伝える場合、誠実な態度で退職の意思を伝えることが大切です。上司に時間を設けてもらい、落ち着いた場所で話をするようにしましょう。
- 例文
- お忙しいところ申し訳ございません。
このたび、持病である腰痛の悪化により、医師から就労継続困難と診断され、業務を継続することが難しくなりました。誠に恐れ入りますが、○月○日をもって退職させていただきたく思っております。
ご迷惑をおかけする形になり、申し訳ございません。
対面で伝える際は、相手の立場に配慮しつつ、丁寧な言葉遣いを心がけて申し出ることを意識しましょう。直接会って誠意ある姿勢で伝えることで、円満退職につながります。
メールで伝える場合
健康上の理由によりやむを得ずメールで伝える場合、誠意が伝わるような文面を心掛ける必要があります。
- メール例文
- 件名:退職に関するご相談(自分の名前)
本文:
○○さん(上司の名前)
お世話になっております。○○(自分の名前)です。
突然のご連絡となり恐縮ですが、退職についてご相談させていただきたくご連絡いたしました。
このたび、持病である腰痛の悪化により、今後の業務の継続が難しい状況となっております。そのため誠に勝手ながら、○月○日を目途に退職をお願いできればと考えております。
本来であれば直接お伝えすべきところですが、体調の都合により難しいため、メールにてご連絡差し上げましたことをお詫び申し上げます。
今後の手続き等について、ご相談させていただければ幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
メールで伝える際は、丁寧な文章を心がけつつ、退職の意思が固いことを記載することが大切です。
電話で伝える場合
電話で伝える場合、業務に支障のない時間帯を選んで電話をかける必要があります。
- 例文
- お疲れ様です。○○(自分の名前)です。今、お時間よろしいでしょうか?
突然のお電話で失礼いたします。実は持病の腰痛が悪化し、医師から仕事を続けるのは難しいと診断されました。そのため、治療に専念するために○月○日をもって退職させていただきたいと考えております。
本来なら直接お伝えすべきところ、このような形になり申し訳ございません。ご理解いただけますと幸いです。
電話で伝える際は、落ち着いた口調で丁寧に話すのが退職の意思を上手く伝えるコツです。また、就業時間内に連絡し、話を長引かさないように簡潔に伝えましょう。
腰痛を理由に退職するまでの過ごし方

腰痛を理由に退職すると決めたあと、退職するまでに心がけるべきポイントがいくつかあります。
ここでは、腰痛を理由に退職するまでの過ごし方を5つご紹介します。
退職の意思はできるだけ早く伝える
退職をする際は、後任者の決定や業務の引き継ぎなど、さまざまな作業が伴います。そのため、退職を決意したらできるだけ早く会社に意思を伝えましょう。
余裕を持って後任者への引き継ぎを行えるように、1ヶ月半~3ヶ月前までには伝えるのがおすすめです。
また、退職を切り出すタイミングとして繁忙期は避けるのが無難です。円満退社を希望している場合、できるだけ会社に迷惑がかからない時期を選びましょう。
ただし腰痛の悪化状況によっては、繁忙期と重なってしまう可能性もあります。自分ではコントロールできない部分ではあるので、繁忙期に退職せざるを得ない状況を気に病む必要はありません。
これ以上腰痛を悪化させないように工夫する
腰痛を理由に退職する際、これ以上悪化させないように体を労わりながら業務に取り組むことが大切です。
たとえば、介護職や倉庫作業員など重いものを運ぶ業務が多い仕事の場合、中腰やひねった動作といった不自然な動きを避け、腰に負担をかけないフォームで行うことを意識しましょう。
また、デスクワークや長距離ドライバーなど長時間座り続ける仕事の場合、作業中の姿勢を見直したり、ストレッチを習慣づけたりするのがおすすめです。
腰に負担がかかる働き方を続けてしまうと、日常生活に支障が出るほど悪化してしまい、今後のキャリアに影響が出るかもしれません。
自分の体を第一に考えながら仕事を行いましょう。
参考:くすりと健康の情報局「腰痛の予防」(参照 2025-08-06)
腰痛の原因となる業務内容を記録する
腰痛は、退職したからといってすぐに症状が良くなるとは限りません。一時的に良くなったとしても、腰痛の原因を根本的に解決しなければ、すぐにぶり返してしまう恐れがあります。
そのため、退職する前に腰痛の原因になった業務や症状を記録しておくのがおすすめです。
どんな場面で腰が痛くなるのか記録しておくことで、自分に合った対策が明確になるのはもちろん、医師や上司に腰痛の症状をわかりやすく説明できるメリットもあります。
腰痛と長く付き合っていく意味でも、腰痛の原因となった業務を知っておくことが大切です。
腰痛の原因となる業務を減らせないか上司へ相談する
腰痛の原因となる業務を把握できている場合、その業務を減らせないか上司に相談してみましょう。
先述したとおり、退職する際はこれ以上腰痛を悪化させないように体を労わることが大切です。腰痛の原因となる業務を減らせないか上司と交渉して受け入れてもらえれば、腰の負担を軽減できる可能性があります。
また、上司に腰の負担がかかる業務を根気強く伝えることで、会社が安全配慮義務について考えるきっかけにつながります。
作業内容・体制の見直しや機械や補助機器の導入など、労働環境の改善に対して前向きに取り組んでもらえるかもしれません。
会社に「仕事のせいで重度の腰痛を患っている従業員がいる」という事実を知ってもらうためにも、退職する前に一度上司に相談してみてください。
有給休暇を活用して症状の治療をする
退職する前に、残りの有給休暇を使って腰痛の治療に充てるのもおすすめです。
退職前は、業務の引継ぎや担当範囲の縮小などにより仕事量が減る傾向にあるため、有給休暇をまとめて取りやすくなります。この期間は、腰痛の治療に専念する絶好のチャンスといっても過言ではありません。
仕事を休んで適切な治療を受けることで、腰痛の症状が緩和される可能性があります。有給休暇を活用して、次のステップに進む際の不安材料を解消しましょう。
また、有給休暇をまとめて取得できれば、自分の人生を振り返る時間を作れます。
「腰痛を患うまでは体のケアに無頓着だったかもしれない」「腰痛予防のために軽い運動を始めてみようかな」など、今後の人生をポジティブに過ごすためのアイデアが思い浮かぶかもしれません。
腰痛の人におすすめの転職先一覧

腰痛の人が転職する場合、できるだけ腰に負担のかからない業種・職種を選びたいものです。
ここでは、腰痛の人におすすめの転職先をご紹介します。ぜひ仕事探しの参考にしてみてください。
建設・製造業の経験者向け
前職が建設・製造業だった人に向けて、腰痛持ちでも知識やスキルを活かして働きやすい仕事をご紹介します。
| 職業 | 特徴 |
|---|---|
| 施工管理技士 | 建設現場の作業進行を管理・監督する。現場経験を活かせる。体力よりも調整力・管理能力が求められる。 |
| 品質管理 | 製品の品質検査・記録・改善提案などを行う。製造現場の経験をもとにリスクマネジメントスキルやコミュニケーション能力が求められる。 |
| 製造管理・生産技術 | 製造工程の効率化・人員管理などを行う。コミュニケーション能力や協調性が求められる。 |
運送・倉庫業の経験者向け
運送・倉庫業で働いたことのある人に向けて、なるべく腰の負担を減らしつつ、経験を活かして働ける仕事をまとめました。
| 職業 | 特徴 |
|---|---|
| 配車オペレーター | 主にタクシーの配送ルートやドライバーの割り振りを担当する。コミュニケーション能力や協調性が求められる。 |
| 物流管理・倉庫管理 | 在庫や品質、配送、納品スケジュールなどの管理業務を行う。現場経験が大きな武器になる。 |
| 受発注事務 | 商品の注文・納品・在庫管理をPC上で行う。正確さが求められる。 |
| 軽作業スタッフ(小物中心) | 仕分けや組立・加工などを行う。座ってできる検品や梱包業務が多く、体の負担が少ない傾向にある。柔軟な働き方ができる職場が多い。 |
修理・設備保守系の経験者向け
修理・設備保守系の仕事に就いていた腰痛持ちの人におすすめの仕事をご紹介します。
| 職業 | 特徴 |
|---|---|
| アフターサービススタッフ | お客様が購入した家電や建物、自動車などの定期点検、メンテナンス、説明対応などを行う。修理専門のコミュニケーション能力が求められる。 |
| 設備管理 | ビルや施設内の機械設備の点検・メンテナンスなどを行う。専門知識が求められる。 |
| 技術営業 | 機械や工具の説明・提案などを行う。営業力が求められるが、経験や技術知識を活かせる。 |
| テクニカルサポート | IT製品に関する問い合わせ対応やトラブル対応を行う。操作方法や故障時の対応など技術面でサポートするため、高度な知識の習得が求められる。 |
未経験から転職を検討している人向け
腰痛持ちの人が未経験からでもチャレンジしやすい仕事を解説します。
| 職業 | 特徴 |
|---|---|
| 一般事務・営業事務 | 書類作成・管理、電話対応、パソコン作業などを行う。自分のデスクや椅子があるため、腰痛対策がしやすい。 |
| データ入力 | 書類やアンケートなどの入力を行う。在宅ワークOKの求人も多く、周囲を気にせず定期的に席を立ちやすい。 |
| Webライター | クライアントの依頼を受けて、Web上に掲載する記事の執筆を行う。フリーランスの働き方も選べて、長時間の座りっぱなしを防ぎやすい。 |
腰痛で退職して転職する際のよくある疑問

腰痛を理由に退職した場合、転職活動をどのように行うべきか悩むところです。
最後に、腰痛を理由に退職した場合の転職活動でよくある疑問を2つご紹介します。
転職の面接で腰痛で退職したことを伝える?
腰痛が完治していない場合は、面接時に伝えておくのが無難です。
伝えないまま採用されてしまうと、入社後に万が一業務への影響があった場合、会社に迷惑をかけてしまいます。実際に、面接時に虚偽があったと判断され、解雇処分を受けた人も存在します。
- 参考
- ▼面接で腰痛持ちであることを伝えるときの例文
前職は腰に負担のかかる業務が多かったため、休職期間に治療を行い、退職いたしました。
現在は医師からも仕事復帰の許可を得ておりますが、検診のために1カ月に一度半休をいただけますと幸いです。
また、腰痛が完治している場合は、「現在は回復しており、業務に支障はありません」と一言添えておくと、企業から不安材料ととらえられる心配が少なくなるでしょう。
履歴書にはどのように記載すればいいの?
履歴書の職務経歴欄に、「病気療養のため退職」と記載するのが一般的です。
また、腰の状態に応じて、健康状況欄には以下のように書くのがおすすめです。
- 腰痛が完治している場合:良好(現在は回復しており、業務に支障はありません)
- 腰痛が完治していない場合:持病の検診で、1ヶ月に一度半休を希望いたします
なお、「一身上の都合」と記載すると、企業から前職を退職した背景への理解が得にくくなるため、あまり好ましくないとされています。
「体調不良を理由に退職した事実を伝えてしまうと、採用されにくくなるかも……」と不安を抱える方もいるかもしれません。
しかし、採用面接に進めば、遅かれ早かれ腰痛について直接話さなければいけないので、履歴書の段階から記載しておくのが得策です。
腰痛は退職理由になる!続けられる仕事を探してみよう

腰痛は、退職理由として認められます。
腰痛を患っている人は日本全国に約2,800万人いるといわれているほど、多くの人が腰痛に悩んでいます。腰痛が悪化すると、心身の健康に悪影響を及ぼすため、日常生活を送ることもままならなくなるかもしれません。
よって、腰痛を理由に退職するケースも珍しくないのです。今の仕事をこれ以上続けるのが難しいと感じたときは、医師から診断書を発行してもらったうえで、所定の手順に沿って退職の手続きを進めていきましょう。
また、転職先を探す際は、腰痛を発症した原因をなるべく避けられるような仕事を選ぶのがポイントです。本記事を参考にしつつ、自分にとって腰の負担が少ない仕事を探してみてください。